
大河コラムについて思ふ事~『光る君へ』第37回
10月上旬になりました。空が高くなりそろそろ秋の気配が濃くなる頃だと思いますが、皆様健やかにお過ごしでしょうか。
暑さがだいぶ収まってきましたが、水分をよく取って皆様健康には充分お気を付けください。さて、光る君へ第37回。
今週も『武将ジャパン』大河ドラマコラムについて書かせていただきます。
太字が何かを見たさんの言質です。
御手隙の方に読んでいただければと思います。それでは。
・初めに
>道長と中宮の心を奪われた源倫子。
>一条天皇の心を奪われた清少納言
敦成親王の五十日の祝で道長卿とまひろさんは阿吽の呼吸で歌を交わします。
左衛門の内侍から二人の仲の噂を聞き半信半疑の赤染衛門は道長卿の嫡妻である倫子さまのためにまひろさんに「左大臣さまと貴女は、どういうお仲なの?」と問い質し「そういう事も分からなくはないけれど、お方さま(倫子さま)だけは傷つけないでくださいね」と釘を刺します。
一方、中宮・彰子さまはまひろさんから内密に白居易の『新楽府』のご進講を受けます。
『道長の心を奪われた源倫子』ならば妾でもないまひろさんが左大臣と藤壺の女房に飽き足らず、召人の関係になっているかもしれないという疑惑の意味になるでしょうが、『道長と中宮の心を奪われた』では彰子さまの「(漢籍を)密かに学んで帝を驚かせ申し上げたい」という自分の意志を無視してさもまひろさんが操っていると言っている様に感じます。
また『一条天皇の心を奪われた清少納言』ではききょうさんが一条帝を好きで心をまひろさんに奪われたと言っている様に見えます。
『枕草子』でかつての登華殿の栄華や皇后・定子さまの在りし日の姿を描き、繋ぎ止めた一条帝の御心がまひろさんが道長卿の命で『源氏物語』を書いた事で藤壺に向き、彰子さまの懐妊に繋がります。そのためききょうさんは「物語を読んでみたい」と藤原伊周卿に申し出ます。

>源倫子が孫の敦成を抱いて、目を細めています。
寛弘5年(1008年)。
中宮・彰子さまは土御門殿に里下がりし、9月11日に皇子を出産しました。
そして11月。
敦成親王と名付けられた若宮の五十日の儀が無事に執り行なわれました。
>源倫子が孫の敦成を抱いて、目を細めています>そんな母と我が子を見ている中宮彰子。
>歴史劇の魅力とは、この祖母と孫の背景にある要素を読み解くことにあると思えます。
『祖母と孫の背景にある要素』とは具体的にどの様な要素でしょうか。
出産が今よりもずっと母子共に命がけの行為であった平安時代、無事出産してからも子供に関する様々な儀式が行われました。
平安時代の貴族社会では、生まれたばかりの赤子のへその緒を切る『臍の儀』に始まり、初めて乳を含ませる『乳付(ちつけ)の儀』、初めて沐浴する『湯殿の儀』、お食い初めに当たる『五十日の儀』や『百日の儀』などの儀式は細かい規則や手順に沿って行われました。
特に天皇の后が生んだ親王については外戚である母方の実家が大きな権力を持ちました。
一通りの儀式を終えると、乳児は実の母親ではなく乳母に育てられます。
律令制度では、『凡親王及子者皆給乳母』とあり、親王とその子に乳母を支給する事を規定していました。
・親王に三人、子に二人
・所養子は年13歳以上
・乳母が亡くなっても、乳母を替えることはできない
・乳母の考叙者は宮人に準ずる
天皇や院、摂政、関白の乳母及びその一族は特別な優遇を受け、破格の昇進をしたり政治的に大きい力を振るう事もありました。
敦成親王の場合、彰子さまの里下がりが終わり宮中に戻るところでまだ乳母の選定がされておらず祖母の倫子さまが世話をしていたのでしょう。
・赤染衛門の懸念?
>彰子が内裏に戻る前に帝へのお土産を作りたいと言い出しました。
寛弘5年(1008年)11月、彰子さまは内裏に戻る事になりました。
親王を抱く母・倫子さまに「母上、内裏へ戻ります前に、帝へのお土産を作りとうございます」と打ち明けます。
彰子さまは「藤式部の物語を美しい冊子にして帝に差し上げようと思います」と言い、倫子さまは複雑そうな表情ながらも「帝もお喜びでしょう」と答えます。
しかし側で会話を聞いていた赤染衛門は、親王の五十五日の祝の夜にまひろさんに「左大臣さまと貴女は、どういうお仲なの?」と問い質した事を思い出していました。
「そういう事も分からなくはないけれど、お方さま(倫子さま)だけは傷つけないでくださいね」とまひろさんに釘を刺した赤染衛門。
彼女は彰子さまと倫子さまのやり取りを聞きながら複雑な気持ちでいました。
猫の小鞠は円座に座り、そんな人々の様子を眺めています。



>彰子が内裏に戻る前に帝へのお土産を作りたいと言い出しました。
>彼女の提案を聞いて、嬉しそうな赤染衛門。
彰子さまが「藤式部の物語を美しい冊子にして帝に差し上げようと思います」と提案した際、倫子さまは『藤式部』の名に複雑そうな表情ながらも「帝もお喜びでしょう」と答えます。
しかし、側で親子の会話を聞いていた赤染衛門は倫子さまが道長卿の女性関係で傷つく事を恐れ、まひろさんに「そういう事(道長卿の召人になる事)も分からなくはないけれど、お方さまだけは傷つけないでくださいね」と釘を刺した事を思い出して倫子さまを心配して見ています。
『紫式部日記「御冊子づくり」』には『中宮様(藤原彰子)が内裏へ還御なさる時期が近づいたけれど、女房たちは行事がいろいろと続いてくつろぐ暇もないのに、中宮様は物語の御冊子をおつくりになられるという。』とあります。
入らせたまふべきことも近うなりぬれど、人びとはうちつぎつつ心のどかならぬに、御前には御冊子作りいとなませたまふとて


>と、ここで思い出したいのが『鎌倉殿の13人』での政子です。
>政子は頼朝と亀の関係を察知すると、屋敷ごと破壊しました。
>あれは、りく(牧の方)が教えた上方由来の「後妻打ち」ではあったものの、坂東の蛮勇ぶりは頼朝の想像をはるかに凌駕。
>倫子の嫉妬を不健康とみるか?
>いや、政子がヤバい、やりすぎだとみるか?
>さて、皆さんはどちらでしょう。
『後妻打ち』とは、前妻が後妻に嫉妬をしその恨みを晴らすために、親しい女性を集め集団となって後妻の家を襲うという風習です。
『亀の前事件』は北条政子さんが出産直後に『源頼朝公が政子さんの懐妊中も亀の前を寵愛していた』という報告を受け、りくさんの提案で彼女の兄・牧宗親公により亀の前さんの住む邸を破壊する事になりました。『鎌倉殿の13人』に於いては軽く破壊するつもりが居合わせた義経公・弁慶主従により邸は徹底破壊されてしまいました。
牧宗親公は頼朝公により髻を切り落とされる辱めを罰として受け、この件を知った北条時政は大いに怒り、伊豆に帰ってしまいます。


ちなみに最古の後妻打ちの記述は『権記』寛弘7年(1010年)2月18日条『祭主大中臣輔親の前妻(藤原教通の乳母)が、教通の随身や下女など30人ばかりで後妻のいた鴨院の西対を襲撃させ、内財雑物が損壊された』というものです。
道長卿とまひろさん(紫式部)が恋仲であるという噂は十四世紀に成立した系図集『尊卑分脈』の『歌人 上東門院女房 紫式部是也 源氏物語作者……御堂関白道長妾云々』という一文によるものです。
ドラマ設定は後の世に書かれた史料による創作であり、後妻打ちの様な記録に残るエピソードは史料にない創作として挟みづらいと思います。
また、『光る君へ』時系列では、寛弘5年(1008年)11月、敦成親王が誕生し、道長卿は外祖父となりました。また皇后定子さまの遺児・敦康親王は彰子さまの許で養育されており、道長卿も醜聞で失脚する事は避けたい時期だと思います。
それを踏まえて倫子さまは個人の恨みで左大臣家の恥になる事は得策ではないと考えるでしょう。
倫子さまをよく知る赤染衛門は「そういう事(道長卿の召人になる事)も分からなくはないけれど」と言いつつも醜聞を避ける様釘を指したのでしょう。

・母親失格? そんなことはない?
>道長との性的な関係は途切れたにせよ、物語でここまで中宮との関係を深めたら、倫子もまひろにコンプレックスを刺激されることでしょう。
道長卿との仲はともかく、彰子さまがまひろさんの物語を所望したり漢籍のご進講を受ける事が倫子さまのコンプレックスになるのでしょうか。
彰子さまがまひろさんに力を借りて自立する事は嫡妻としての嫉妬の対象になるでしょうか。
彰子さまは中宮であり倫子さまから見れば帝の中宮という目上の方です。
何見氏は道長卿と彰子さまの人格を同一視しているのでしょうか。
>しかし倫子には、そう落ち込まないで欲しいのです。
>中宮の土産作りのために、紙はじめ材料を手配することだって、母としてできる素晴らしいことではないですか。
>猫の手配だって倫子の素晴らしい気遣いです
猫の手配とは何でしょうか。
猫の小鞠は土御門殿で飼われている倫子さまの愛猫です。
彰子さまは現在出産と産褥のため、実家である土御門殿に里下がりし藤壺の女房も彰子さまに付いて土御門殿に滞在しています。
小鞠にとって土御門殿は我が家であり、いつもの様に人々の集まる場所で自分の場所に陣取っているだけではないでしょうか。
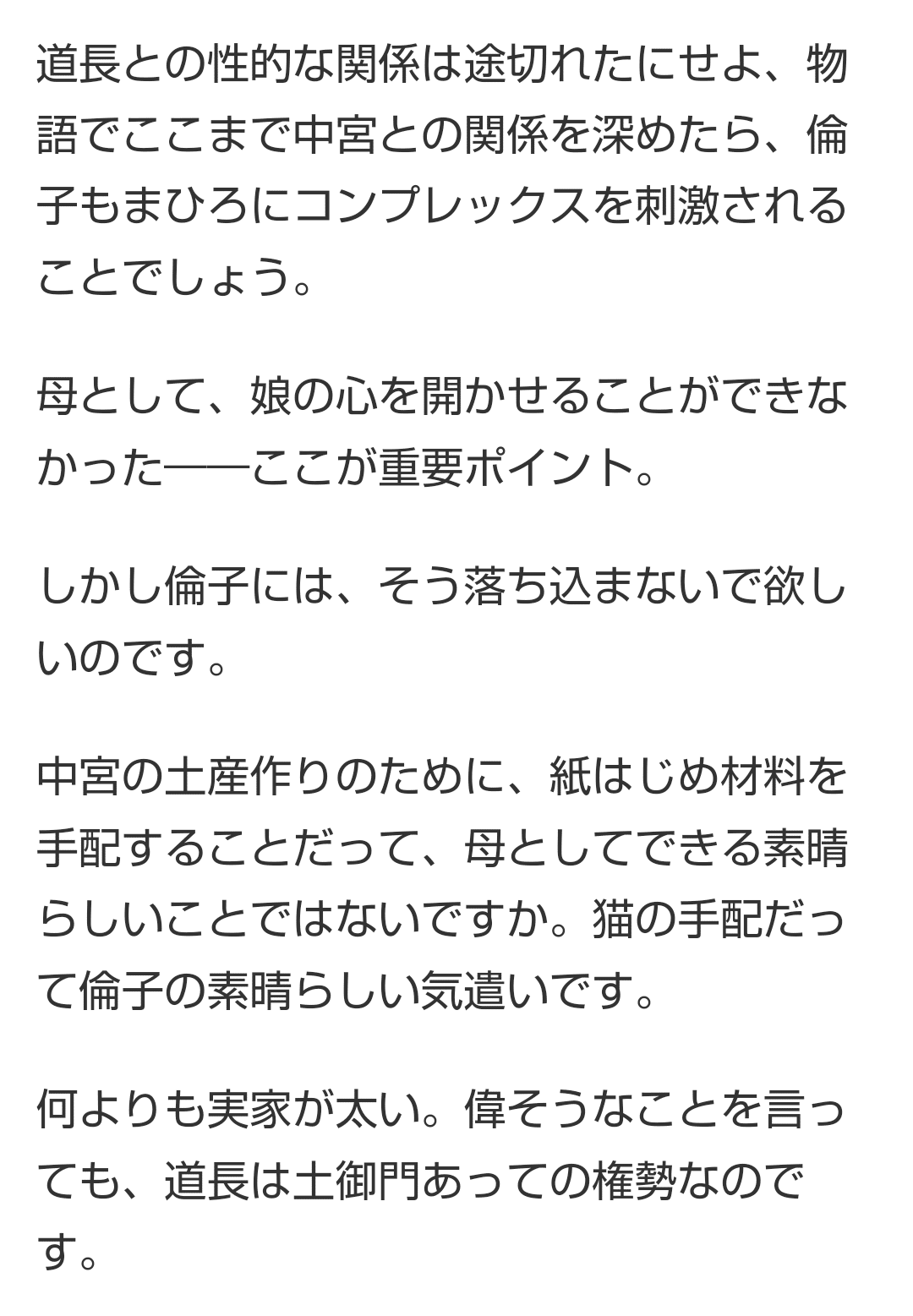
>なお、猫好き大河ファンに良い知らせがあります。(中略)
>来年は今年以上に猫がうろつく大河ドラマとなることでしょう。
>猫への愛情は江戸っ子並、そんな森下佳子先生ですので、ぬかりなく出すと予測されます。
なぜここでまだ放送どころか情報も十分に揃っていない『べらぼう』の話ですか。
来年大河の話がしたいなら別の記事を立てるか自身のnoteで書いてください。
自分が猫が見たいためだけに来年の大河を持ち出し関係無い話をするのは如何かと思います。

・お堅い中宮サロンの共同作業?
>かくして、豪華な冊子作りが始まります。
早速、彰子さまの傍らには冊子に使うための料紙が用意され並べられました。
左衛門の内侍が「流石左大臣さま、このような美しい紙をこんなに沢山」と感心しています。
彰子さまは色の付いた料紙を手に取り、まひろさんに「光る君が見つけた若草のような娘の巻は若草色がよいであろうか、藤壺の色の藤色がよかろうか」と尋ねます。
まひろさんは「中宮さまのお好みでどちらでも」と答え、彰子さまは若草色を選びました。
宮の宣旨が料紙の1枚を手に取り「このような美しい紙に書かれた文を貰いたい」と惚れ惚れとして言い、他の女房たちの驚いた視線を感じたのか少し決まり悪そうに微笑みます。



>確かに色彩パレットが東アジアらしく、見ていて目に心地よいのです。
>時代劇は伝統色を用いているかどうかも重要です
日本の色彩感覚は春夏秋冬の区別がはっきりしているため、昔から四季折々の植物や自然現象と連動して、季節の変化を感じ取ってきたのだそうです。
日本人は昔から四季折々の植物を通して『色』を感じていたため植物由来の色名が多く、女房装束の襲色目にも反映されました。
中国の伝統色名には鉱物に由来するものが多いそうです。
また、古代中国の陰陽五行説に由来した『五色』があります。
万物は「陰・陽」の二気、「木・火・土・金・水」の五行で成り立ち、五行を色で表したものが五色です。
五色は「青・赤・黄・白・黒」の5色となっており、「木=青、火=赤、土=黄、金=白、水=黒」を表し、魔除けの意味があります。
五色は日本にも渡り、現代でも相撲の土俵の上の房や鯉のぼりの吹流しや七夕の五色の短冊に反映されています。
>宮の宣旨は紙を手にして「このような美しい紙に書かれた文をもらいたい」と語っています。
(中略)
>ただ、こういう色好みの話題は苦手なのか、他の女房は硬い顔をしています。
>そこが定子サロンとの違いなのでしょう。
宮の宣旨は冊子に使う料紙を手に取り、「このような美しい紙に書かれた文を、もらいたいものでございます」と惚れ惚れした様に呟きます。
この時点で宮の宣旨は『美しい紙に書かれた文をもらいたい』と言っており、恋文かどうかは分かりません。
職務に忠実な女房筆頭である宮の宣旨が美しい料紙を見てうっとりしている事に皆驚いたのでしょう。
視線に気付いた宮の宣旨は決まり悪げに笑みを浮かべつつ彰子さまを見遣ります。
宮の宣旨のお茶目な一面が見られる場面です。


>まひろの弟・藤原惟規が、中将の君を追いかけた斎院サロンこと選子内親王に仕えた女房も明るく機転が利いてため、「中宮のサロンって、ノリの悪い非リア陰キャじゃね?」と比較されてしまっていたそうです。
『機転が利いてため』ではなく『機転が利いていたため』だと思います。
紫式部の弟・惟規さまは賀茂斎院・選子内親王に仕える中将の君と恋仲でした。
『紫式部日記』によると、『中将の君が他の人に書き送った文を惟規さまに見せられ、自分(中将の君)だけが情緒深く、総じて世間の人は、思慮も分別もないと思っている様に見えた』と腹を立てている紫式部の記述があります。
また、『斎院はとても風雅な心がおありで御所はとても世離れして神々しい感じのため、自然とそのように風雅を好む環境となる』ともあります。
藤壺の女房については『競い合いなさる女御や后がいないため、藤壺には比較する方も無く殿方も女性たちも競い合わない。彰子さまは好色めいたことは、ひどく軽薄なことだとお思いなので仕える人もめったなことでは人前に出るような事はしない』『女房は、気がおけないままに、殿方が立ち寄って話しかけるので、中宮方の女房は引きこもりがちである、あるいは配慮がないなどとも批判する』『上臈や中臈くらいの女房たちは、あまりにも引きこもり上品ぶってばかりいる』と評していますが『人はみな各人各様で、そうひどく優劣があるわけではありません。』ともあります。

・美しい紙に、美しい字で、美しいだけでない物語を?
>まひろの手元が大写しになり「源氏のものかたり」と記しています。
まひろさんは『三蹟』といわれる能書家である藤原行成卿宛てに清書を依頼する文をしたためました。
そこへ道長卿と倫子さまが赤染衛門と左大臣家の家人を伴い藤壺を訪れました。
家人が携えた箱には筆・墨・紙・硯など文房四宝が入っています。
倫子さまが「殿からのご褒美である、皆で分けよ」と言いました。
彰子さまは父に礼を述べ、まひろさんの方を向きながら「紙は藤式部に」と言い、倫子さまの表情が固まります。
道長卿も「筆や硯も入り用であろう」と言います。
まひろさんは礼を言い、道長卿は「いや、大したものでは」と答えます。
倫子さまが「帝がお喜びくださる冊子となるよう、頼みますよ」と笑みを浮かべ女房たちを激励します。
笑顔の倫子さまとは裏腹に、赤染衛門は硬い表情のままでした。




そして彰子さまや女房たちによる冊子づくりが始まりました。
行成卿他、何人かの能書家が帝に献上する物語各巻の清書依頼を承りました。
依頼文を受け取った行成卿は微笑みながら、仮綴じされた金銀の砂子や箔を散らした藤色の料紙に清書を始めました。
美しい文字で『いづれの御時にか…』と第一帖『桐壺』の物語が写されていきます。
完成した清書が藤壺に届き、まひろさんが目を通して検品します。
彰子さまや女房達がそれを赤い糸で綴じていき、仮綴じをしていた余白を裁ち落として製本します。
そして、宮の宣旨が表紙と裏表紙を付け、まひろさんが表題を糊で貼りました。
やがて全巻が仕上がり、冊子が畳の上に並べられました。
彰子さまは嬉しそうに笑い、まひろさんも一礼します。
「帝に献上する『源氏の物語』の冊子はこうして完成した。」と語りが入ります。











帝に献上する『源氏の物語』の冊子の完成後、まひろさんは里下がりの許可を貰うため、彰子さまの御座所を訪れました。
まひろさんが「里に下がりたい」と申し出ます。
敦成親王を抱く彰子さまが「冊子も出来上がり、これから内裏に戻ると言う時に何故か?」と尋ね、まひろさんは「久しぶりに老いた父と娘の顔を見て来とうございます」と答えます。
彰子さまはまひろさんに娘がいた事を思い出しました。
まひろさんの娘・賢子さんは10歳になっていました。
彰子さまは「自分の事だけを思い、ひと時でも側を離れられるのは困ると思っていたが、それは間違いであった」とまひろさんに詫びます。
さらに彰子さまは「娘も寂しい思いをしているに違いない。絹と米と菓子を土産として持って行くが良い」と勧め、手配をしました。
まひろさんは「ありがたき幸せにございます」と礼をいいます。
彰子さまが「内裏に戻る時は一緒に参れ」と言い、まひろさんは「それまでには必ず戻ります」と答えます。


>すると、道長と倫子がやってきて、文房四宝を褒美として賜ります。
>中宮がうやうやしくお礼を言うと「いや、たいしたものでは」と道長はあっさり返答するのですが……いやいや、かなりお高いものでしょう。
まず『文房四宝』がどういったものであるか説明した方が読者には理解しやすいと思います。
また、倫子さまが「殿からのご褒美である、皆で分けよ」と言いますが、彰子さまが「紙は藤式部に」と言い道長卿も「筆や硯も入り用であろう」とまひろさんを贔屓し、倫子さまの表情が固まった場面は無視でしょうか。
女房たちが出揃う中、あからさまなまひろさん贔屓の道長卿・彰子さまに対し藤壺全体の調和作りに苦心する倫子さまの対比が伺える場面です。
『文房四宝』とは文人が書斎で用いる道具のうち、筆・硯・紙・墨の事を言い、唐代にその名が初めて登場しました。
これらの道具は、中国の学者や文人たちに重宝され、日本を含む東アジア文化圏にも広まります。
実用的なもの以上の価値を持ち、所有者の教養や地位の象徴とも見なされました。
美しい色彩や装飾の入った料紙だけでなく、高価な文房具を褒美や激励の品として贈る事は左大臣家にとって権威や藤壺の繁栄を誇示する意味もあったのではないでしょうか。
『『紫式部日記』御冊子づくり』には、『殿(藤原道長卿)は、「どのような子持ちが、この冷たい時節にこんなことをなさるのか」と中宮さま(藤原彰子さま)に申し上げなさるものの、上質の薄様紙(うすようがみ)、筆、墨などを何度か持っておいでになる。』とあります。



>行成は文を受け取り、目を通し、硯に墨を擦り、筆を手にします。
>彼のような能書家に書写の依頼がされているのです。
>バイオリンの響きとともに数文字書きつける。>日本書道史における最大の達人ですから、ほんの短い場面のようで、どれだけ気を配ったことでしょうか。
>この場面がなっていないとなると、それはもう日本文化への冒涜となりかねません。
『硯に墨を擦り』とありますが『硯で墨を擦り』が適切かと思います。
行成卿が書写していたのは『源氏物語』第一帖「桐壺」の冒頭です。
『日本文化への冒涜』と言うなら、三蹟と謳われた行成卿が創作の中でも『源氏物語』を書写しているという国宝級の価値に気付いて頂けると良いのですが。
まひろさんは行成卿宛てに帝に献上するための物語の清書を依頼する文を送りました。
史料では誰がしたのかは不明ですが、皇子を出産した直後の中宮が帝へのお土産として自らてを加えた装丁本で、中宮が天皇に献上する品と聞き当代随一の能書家がこぞって依頼を承ったのではないでしょうか。
風俗考証担当・佐多芳彦氏によると、行成卿が清書のために承ったものは5枚ほどの料紙を紙縒り(こより)で仮綴じしている状態のものだそうです。
行成卿は依頼を受け、原本を見ながら『いづれの御時にか』と『源氏物語』第一帖「桐壺」の冒頭を写し取っています。




>こうして出来上がってきた紙をチェックするまひろ。
>自分の物語を最高の能書家が手分けして書くのですからまさに感無量でしょう。
>中宮と女房たちは、皆丁寧な手つきで本を仕上げてゆきます。
中宮彰子が、藤式部(まひろさん)ら女房とともに帝に献上するための『源氏物語』を豪華な冊子に仕立て、表紙や料紙の美しさにも目を奪われる印象的な場面であるのに端折り過ぎではないでしょうか。
風俗考証担当・佐多芳彦氏によると、『源氏物語』の冊子は『粘葉装(でっちょうそう)』という装丁で、1枚の料紙を二つに折り、折り目の外側に糊をつけて貼り重ね、表紙を加えて冊子にする方法なのだそうです。
表紙に使われている料紙は『金銀の砂子(すなご)や、さまざまな形に切った金箔(きんぱく)・銀箔(ぎんぱく)が蒔き落とされた特注品』という設定だそうです。
・小少将の君が紙縒りを使って、5枚ほどの料紙を仮綴じする。
・まひろさんが行成卿他能書家宛てに物語の書写を依頼する文を添える。
・物語が書写され、返却された仮綴じの料紙をまひろさんが検品。
・仮綴じした料紙をさらに重ね、合わせ赤い紐で綴じ、一纏めにしていく。(彰子さま、左衛門の内侍、馬中将の君)
・大納言の君が仮綴じをしていた余白を断ち切る。
・宮の宣旨が表紙と裏表紙を付ける。
・まひろさんが文書の題名を記した『題簽(だいせん)』を刷毛と挟む道具を使って表紙の所定の場所に貼る。
『『紫式部日記』御冊子づくり』には『私(紫式部)は夜が明けると真っ先に御前に上がって差し向かいで伺候し、色とりどりの紙を選び整え、物語のもとの本を添えては、あちらこちらに書写を依頼する手紙を書いて配る。また一方では、書写したものを綴じ集めて整理するのを仕事にして日を送る。』とあります。














・まひろ、久しぶりの帰省?
>藤原為時邸に届けられた白い米を見て、乙丸、いと、きぬは大喜び。
まひろさんは多くの土産を持って牛車で帰宅しました。
滅多に見ない米俵の白米に「白い米だ!」と大喜びの福丸さんをいとさんが「触るんじゃないよ」と叱ります。
きぬさんも「こんな白い米初めて見た!」と驚いています。
その様子を微笑みを浮かべ、まひろさんと為時公が見ていました。
為時公は「お前の働きのおかげで何とか家の者らが食べて行ける。ありがたい事だ」と言います。
まひろさんは、賢子さんを父に任せきりにしていた事を済まないと思っていました。



そこへ「姫さまのお帰りにございます」と乙丸の声がして水仙を手にした賢子さんが帰宅し、為時公に帰宅の挨拶をします。
賢子さんにまひろさんが「しばらく帰れずにいた」と謝罪し、為時公は「背丈も随分と伸びたであろう」と賢子さんの成長をまひろさんに見せます。
賢子さんは固い表情と大人びた口調でまひろさんに「お帰りなさいませ、母上。内裏でのお仕事、ご苦労様にございます」と言い、いとさんの許へ走り寄り「水仙をあげる」と水仙を渡しています。
為時公は「照れておるのだ」と言うが、まひろさんは「気難しいところが自分に似ている」と思っています。
まひろさんが乙丸に「賢子さんが世話になっているのね。ありがとう」と礼を言います。
久々にまひろさんを見て感極まって涙ぐむ乙丸に為時公が「泣くでない」と笑い、まひろさんは「乙丸って泣いた顔と笑った顔が同じなの」と言いました。
その時向こうからいとさんの「たまには贅沢もいいわね」という声が聞こえました。
福丸さんが相槌を打ち、いとさんに「あんたは帰るのでしょう?!」と言われ、「それはない」と言った表情の福丸さんに賢子さんも笑います。




まひろさんは久々に我が家に上がり室内を見渡します。
まひろさんは心の中で「何だか、この家がみすぼらしく思えた」と言い、部屋の片隅に置いた母ちやはさまの形見の琵琶に目を遣ります。

食事の刻限になりました。
為時公、まひろさん、惟規さま、賢子さんの前に漆器の器に白米を高盛りにした御膳が並べられました。
惟規さまが豪華な御膳に驚き、まひろさんと目を合わせます。
まひろさんは得意満面という様子で微笑みます。
反面、賢子さんは正面を向いて黙ったままで為時公がため息をつきます。




>藤原為時邸に届けられた白い米を見て、乙丸、いと、きぬは大喜び。
土御門殿とまひろさんの邸である堤中納言邸(現廬山寺)は道を挟んだ徒歩で帰れる範囲の距離です。
しかし彰子さまが手配した土産があるため、まひろさんは牛車での帰宅となりました。
滅多に見ない白米に「白い米だ!」と大喜びしたのは福丸さんで、いとさんが「触るんじゃないよ」と叱り、きぬさんも「こんな白い米初めて見た!」と驚いています。




>水仙を手にして、母に少し戸惑った顔を見せています。
>一通りの挨拶をしつつ、水仙はいとに渡してしまう。
>母には渡しませんでした。
>まひろにしても、ジッと静かに娘を見つめるだけで、涙ぐんだり、頬を触れるようなことすらしない。
(中略)
>まひろはどこかクールな性格に思えるのです。笑みすら浮かべません。
まひろさんは久しく里下がりができておらず、賢子さんを為時公に任せきりにしていました。
賢子さんは固い表情で再会した母に「お帰りなさいませ、母上。内裏でのお仕事、ご苦労様にございます」と言い、いとさんに水仙をあげました。
まひろさんが「気難しいところが自分に似ている」と評する様にいつも世話をしてくれる家族には普段通り接する事ができるものの、久しぶりに帰ってきたまひろさんにどう接していいか計りかねているのではないでしょうか。

>まひろはしみじみと家の中を見て周り、「みすぼらしく見える……」と感じています。
>それこそ『源氏物語』ならば卑しいものの粗末な家とみなされそうな家でしょう。
紫式部は『『紫式部日記』里下がりしての述懐』の中で、久々に里下がりした実家について『見所もなきふるさとの木立ちを見るにも、ものむつかしう思ひ乱れて(見所もない実家の庭の木立ちを見るにつけても、なんとも気がふさぎ込んで思い乱れて)』『あらぬ世に来たる心地ぞ、ここにてしもうちまさり、ものあはれなりける。(別世界に来たような心地がして、実家に帰って一層強く感じられ、しみじみと悲しいのだった。)』と述懐しています。
華やかな宮中での上級貴族との交流や藤壺での生活にだんだん慣れ、ためしに物語を手に取って見ても感動が無く不安を話せる旧友とも疎遠になり、実家に帰っても別世界にいる様な感覚が一層強く感じられるとあり、作中のまひろさんも慣れ親しんだ実家や家族なのに所在なげで家も華やかな宮中と比べてしまい「みすぼらしく見える……」と感じたのではないでしょうか。

>夜は豪華な食事となりました。
>ただし、平安時代ですのでシンプルといえばそうかもしれません。
>私の感覚ですが、日本料理の再現を見て「おぉ、豪華だな」と思えるのは、織田信長のおもてなし御膳あたりから。
平安時代に於ける食事はどの様なものでまひろさんが里下がりした日の食事がどの様に豪華なのか具体的に史料などを提示しながら解説してはいかがでしょうか。
何見氏の食事の好みは聞いていません。
平安時代の食事の主菜は魚がメインで蒸す・煮る・焼くという調理法で食べる前にしょうゆの原型である醤(ひしほ)、塩、味醤、酢、酒、わさびなどを浸けて食べました。
ヤマドリやハトなどの鳥類や獣肉が食され、海から遠い京の都では干物や乾物が流通していた様です。
平安時代の人々にとって米は重要な主食であり、ご馳走として扱われていました。
農業技術や収穫量の関係から米は値段が高く高級品とされ、平安中期に編纂された『和名類聚抄』という文献によると、当時の貴族の食生活では米を食べられる事は裕福の象徴だった様です。
参考までにこちらは作中に出てきた中宮彰子さまのお食事です。

見ない白米に福丸さんやきぬさんが驚き喜んだのは普段雑穀が主食である庶民が手を出せない食べ物であり、中宮直々に貴族しか食べられない様な白米を俵で手配してくれるほどまひろさんが信頼されている証拠でもあるでしょう。
粳米(うるちまい)を保存が効くように蒸したものを『強飯』といい、十分な水を加えて炊いたものを『姫飯』といいました。
客人を饗す際、強飯は高く盛り付けするのが行儀でした。
『光る君へ』作中の比較ですが、宣孝公存命の頃は椀に軽く盛られたご飯がまひろさんが実家に帰ってきた時には所謂『高盛り』になり、惟規さまが驚きまひろさんが得意げに微笑んでいました。
作中では彰子さまが菓子を土産として持たせており、食卓に上がったかもしれません。


>さらには、見た瞬間に美味しそうだ!と思えるとなると、『べらぼう』の時代あたりに食べられていた揚げたて天ぷらあたりからではないでしょうか。
>日本食は江戸っ子ファストフードである江戸前寿司、天ぷらが代表扱いとなる、変わった料理といえます。
『天ぷら』はポルトガル語の「テンポーラ(temporas)」/四季に行う斎日」が語源という説が有力なのだそうです。
日本に天ぷらの調理法が伝わったのは、戦国時代。
鉄砲の伝来とともに『南蛮料理』としてポルトガルから伝わりました。
日本では油は大変貴重なもので、油を大量に使う天ぷらは高級品でした。
江戸時代初期、油の生産量が増え天ぷらは江戸の庶民の味として立ち食い屋台で売られ、徐々に広まっていきました。
前述の通り、平安時代は『蒸す・煮る・焼く』という調理法で、食べる前に調味料を付ける食べ方でした。
天ぷらは平安時代の日本に存在しません。
寿司の起源は、東南アジアの『なれずし(熟れ鮓)』とされています。
手に入りにくい魚を長期保存するための方法として編み出した発酵食品で、米など穀類を炊いたものと魚を一緒に漬け込み、乳酸発酵によって魚を保存していました。
熟れ鮓は、奈良時代頃に日本に伝わったとされています。
甘酢で味付けしたご飯に鮎や鮒などの川魚や鮑や鯛などの海産物を乗せ寝かせたもので、保存食として食べられていました。
これらは貢物として朝廷に献上され、貴族も食べていました。
『延喜式』延長5年(927年)には、各国が鮨を税として納める規定があり、『伊勢の鯛鮨、近江・筑紫の鮒鮨、若狭のアワビの甘鮨、讃岐の鯖鮨』などが朝廷に献上されていました。

・酒癖が悪いまひろ?
まひろさんは酒を注ぎながら、「藤壺の女房の皆様はやんごとなき姫様方だが、揃ってあまりにも奥ゆかしすぎます」と言いその酒を口に含みます。
惟規さまが「皆可愛いけど」と言うと、まひろさんは「すごいいびきをかいたり、寝言を言ったりするのよ」と笑います。
為時公が「お前とて寝言を言っているやも知れぬぞ」と言い、まひろさんが「そうかも知れませぬ」と答え、今度は使用人たちが笑います。
しかし、ほろ酔い気分で楽しそうなまひろさんとは対象的に、賢子さんは黙ったまま料理を口に運んでいました。

なおもほろ酔いのまひろさんの話は続き、「親王さま五十日の儀の時は道長が無礼講だと仰せになったら本当に無礼講になってしまって。殿方たちがすっかり酔っぱらって、自分に絡んで来た方もいたのよ」と笑いながら敦成親王の五十日の儀の事を話します。
まひろさんが「あ…、あの生真面目な大納言実資さままで、女房の袖の中に手を入れたりなさってたまげました」と言うと、いとさんが「それは左大臣さまも同じですか?」と尋ねます。
まひろさんは「左大臣さまはそうでもなかった」と言いながら瓶子の酒を手酌しています。
賢子さんは食後に母の話をあまり興味なさそうに聞いています。
まひろさんはさらに「お菓子も料理も食べきれないくらい並んでおり、そのお菓子は女房たちが食べつくし、殿方はお酒で…ハハハハ…」とその宴が実に盛大であったかを話し続けます。
為時公は「我々のような貧しき者には縁のない話だ」と言います。
まひろさんは酔いが回り「お菓子は中宮さまからのお土産でいただいて参りましたよ。皆食べたでしょう。賢子も食べたかしら?」と尋ねます。
しかし賢子さんは返事をせず、つまらなそうにしています。
「姉上、飲み過ぎだよ」と惟規さまがまひろさんの飲み過ぎを窘めますが、まひろさんは「お酒は殿方だけの楽しみではありませんよ」と上機嫌です。
まひろさんは今度は「中宮さまの出産に立ち会えるなんて、これまでで一番胸が熱くなった」と話し始めますが、延々と宮中の話ばかり聞かされ賢子さんはさらに不満げです。
為時公が「もうよい、そのくらいにしておけ」と止めます。
まひろさんはまだ話し足りなさそうでしたが、嬉しそうです。
しかし、賢子さんは黙ったままでした。
そんな賢子さんの様子をきぬさんが見守っていました。








>さらには親王五十日の宴は本当に無礼講になってしまったと言い出します。
>殿方は酔っ払ってきて絡んでくると笑い、あの生真面目な実資によるセクハラまで明かすまひろ。
まひろさんは酔って敦成親王の五十日の儀の無礼講の話をします。
まひろさんは「あの生真面目な大納言実資さままで、女房の袖の中に手を入れたりなさってたまげました」と言います。
宴では、実資卿が大納言の君の手を取り袖口から覗く袿の枚数を数え色を観察していました。
これはセクハラ行為ではなく、装束が勅令を破って華美になっていないかと枚数を数えていたのだそうです。
国の秩序や財政に気を配る真面目さに加え、祝歌を求められても自作をひけらかさず古来の祝歌を詠み上げるなどの実資卿の態度に紫式部は好感を持ち、自ら実資卿に「話しかけてみたところ、当世風に気取っている人よりも断然、ご立派だった」と評価しています。
『『紫式部日記』十一月一日 誕生五十日の祝儀』には、『下座の東の柱下に、右大将(藤原実資)は寄りかかって、女房たちの衣装の褄(つま)や袖口の色や枚数を数えていらっしゃるご様子は、ほかの人とは格段に違っている。』とあります。
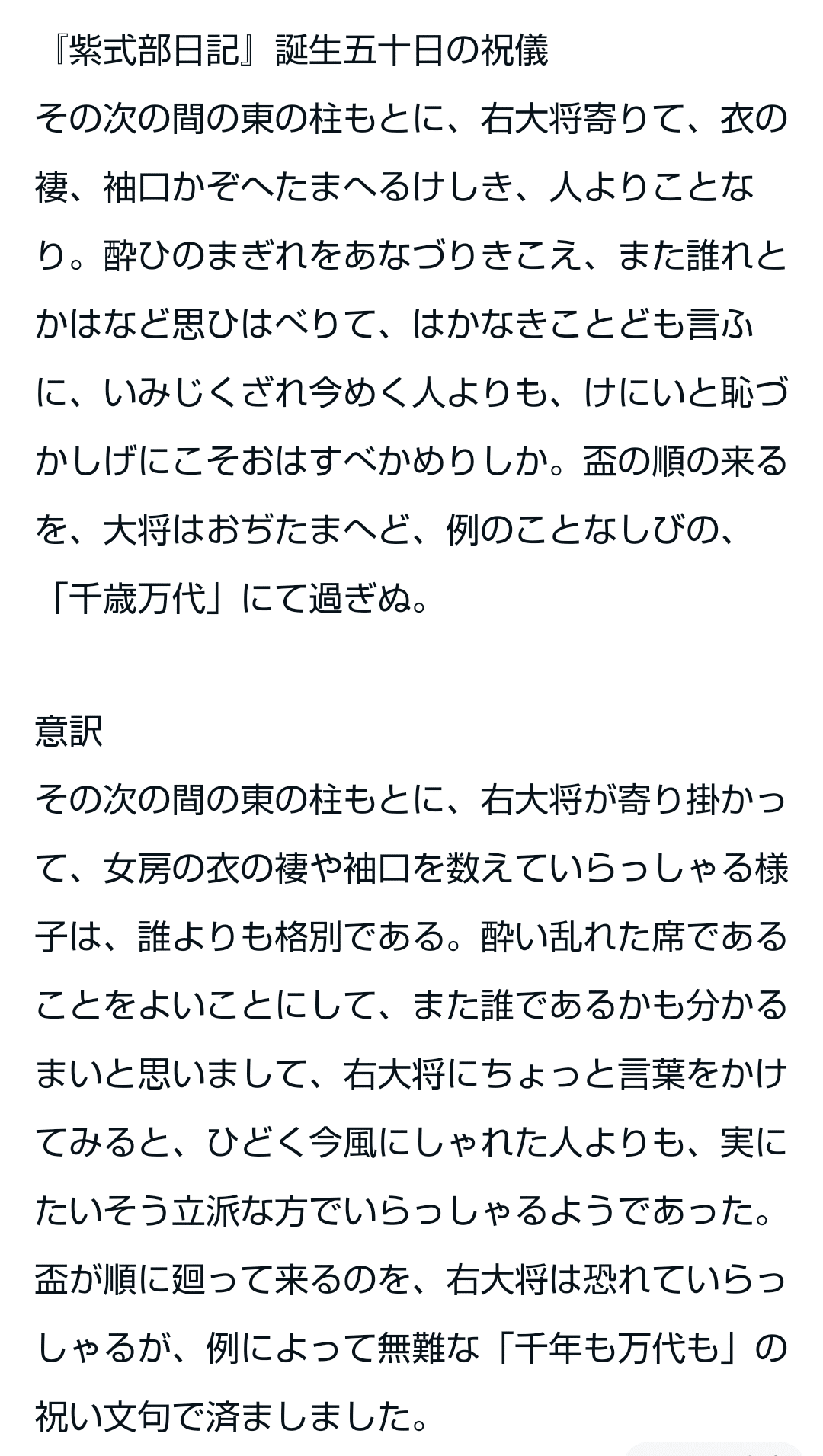

五島美術館所蔵

>理詰めの面倒臭さを残しながら、酔っ払いらしく話題がすっ飛ぶので、周りはとにかく相手にしにくい。
>実にのたちの悪い酔い方をしています。
>可愛げもありません。
>そして酔うと、日頃は下劣だと押し殺している本音も漏れてしまう。
>とにかく彼女の醜さが露呈してしまう場面ですね。
まひろさんを『理詰めで面倒臭い』と何見氏は評していますが、どの様なところが『理詰めで面倒臭い』のでしょうか。具体的に提示してください。
職場から実家に戻り、本人は緊張から開放され大いに酒を飲み煌びやかな宮中での出来事を日記の様に家族に話しているのでしょう。
取立てて誰かに何かを言い含めたり意見をする『理詰め』の状態ではないと思います。
しばらく家を空け、家族に娘を預け単身赴任で宮仕えしたまひろさん。
受領層の娘だったまひろさんは、いつしか男性の学ぶものとされる漢籍の知識を買われ中宮彰子さまに『新楽府』のご進講を行い、自分の書いた『光る君の物語』は宮中で評判になり、豪華な装丁の写本として帝に献上されるまでになりました。
久々に帰ってきた実家までみすぼらしく見え白米や豪華な料理に家族は驚きます。
宮中で豪奢な生活に慣れたまひろさんは酒に強かに酔い宮中の様子を語りますが、宮中での贅沢自慢になってしまい、今まで通り質素な暮らしをする家族とは無意識のうちに話が噛み合わなくなっていたのでしょう。
それでもいとさんは話を聞き、官吏経験者である為時公や惟規さまはまひろさんを窘めます。
しかし、まひろさんが「気難しいところが自分に似ている」と評する様に賢子さんは母にどこか他人行儀になり、食後の会話もつまらなそうにしていました。
まひろさんは宮仕えでは一応の成功を収めていますが人の心は移ろい、家族とも距離感が分からなくなっているのではないでしょうか。

・罪と罰?
>道長が、廊下で赤染衛門を呼び止め、藤式部の行き先を尋ねます。
その頃、土御門殿では道長卿がまひろさんを探し「藤式部の姿が見えぬがいかがした?」と赤染衛門に尋ねています。
赤染衛門は道長卿を警戒しながらも、「里に下がりました」と笑顔で答えます。
道長卿は「何故だ?中宮様もご承知なのか?」とさらに尋ねます。
赤染衛門は「娘もいるので、内裏に戻る前に里下がりをしたいらしいです」と答え、道長卿はつまらなさそうに視線を外し「そうか」と答えました。



夜半。
起き出した賢子さんは母が机に向かっているのを見かけました。
紙に『罪』としたため、まひろさんは心の中で「罪…」と呟きました。
次にまひろさんは『罰』と書き、心の中で「罰…」と呟きます。
賢子さんは遠くから母を見つめていた後、部屋に戻っていきました。



まひろさんが里下がりをし、彰子さまは宮の宣旨を呼び、「藤式部に戻って来るよう文を書いてくれ」と頼みます。
彰子さまは「藤式部がおらぬと心細い」と不安げです。
まひろさんは土御門殿の使者から彰子さまの文を受け取って目を通し、そばに来た父為時にも見せます。
為時公は「帰ってきたばかりというのにもうお召しか。よほど中宮さまに気に入られておるのだな。左大臣さまにも良くしていただいておるのであろう」と言います。
まひろさんは返事をしませんでした。
為時公は「お前が幸せなら答えずともよい」と言い、まひろさんは賢子さんの話題を持ち出しました。
為時公は「あの子にも、その内お前の立場は分かる」と答えます。


>そして、心細いから式部に戻るよう文を書いてくれ、と宮の宣旨に頼みます。
>為時の家に、その文が届きます。
>中宮は真面目なので、皇后定子が清少納言に送ったような、ひねりのある文ではありません。
彰子さまは「藤式部がおらぬと心細い」と宮の宣旨にまひろさんに戻って来る様にと文を書くよう頼みました。
『『紫式部日記』里下がりしての述懐』には「中宮様が雪を御覧になって、よりによってあなたが里に退出したことを、ひどく残念がっていらっしゃいます」と、他(藤壺)の女房たちから文が届き、倫子さまからも「わたしが引き止めた里下がりなので、格別に急いで退出して、『早く帰参します』と言ったのも嘘で、長く里にいるようですね」と文が届いたため慌てて帰ったとあります。


・親の堕落が許せない潔癖な娘?
>賢子が戻ってきました。
賢子さんが戻って来て為時公とまひろさんの前を一礼して通り過ぎようとします。
為時公が呼び止め、まひろさんが土御門殿に戻る事を伝えると、賢子さんは「一体何しに帰ってこられたのですか?」と冷めた表情で尋ねます。
まひろさんが目を伏せ為時公が驚いた表情をしますが、賢子さんは構わず「内裏や土御門殿での暮らしを自慢するため?いとや乙丸も、変な顔をしておりました」と問います。
まひろさんは「賢子の顔が見たいと思って帰ってきたのよ」と答えますが、賢子さんはにべもなく、「母上はここより、あちらにおられる方が楽しいのでしょう?」と言います。
為時公が「おまえの母は働いて、この家を支えてくれておるのだぞ」と賢子さんを窘めましたが、賢子さんはそれにも反発します。
賢子さんが「では何故昨日のようなお話をするのですか?お菓子をたらふく食べたとか」と母を問い詰め、まひろさんは返答に窮しています。
賢子は尚も「母上が嫡妻ではなかったから、私はこんな貧しい家で暮らさなけれはならないのでしょう?」と母に問いました。





ついに為時公が「黙らぬか」と賢子さんを叱りました。
まひろさんは「私は、宮仕えをしながら高貴な方々とつながりを持って、賢子の役に立てたいと思っているのよ」と弁解します。
しかし賢子さんは「嘘つき。母上なんか大嫌い!」と泣きそうな表情で飛び出して行ってしまい、後を乙丸が追いかけます。
まひろさんは「すっかり嫌われてしまいました」と言い、為時公は「おまえがいない間、あの子の友は、書物であった。おまえによく似ておる」と打ち明けます。
門を出た先の道で1人涙する賢子さんを、少し離れた場所から乙丸が見守っていました。



>民の窮状を思いやるわけでもなく、食べきれないほどの飲食物を自慢する。
>口先だけか、身につけた教養が活かせていない! という心境なのでしょう。
>実は、母と娘の怒るポイントは一致しています。
>まひろは酔態を晒し、人の悪口をぬけぬけと語っているわけで、母親である以前に人としても醜悪だと指摘しておきましょう
幼くして母を失い父が官吏として働くも散位し無職になってしまい、貧しい中育ったまひろさんや、まだ10歳の子供で父は早くに亡くなり妾の立場だった母が才能を認められ早くに出仕し、祖父や使用人たちと貧しい中暮らしてきた賢子さんは似た者親子で書物を友として生きてきたのでしょう。
当時、女性の学ぶものではなかった漢籍を身に付け、内密とはいえ中宮彰子さまに『新楽府』のご進講を行い、『光る君の物語』が宮中で認められた事はまひろさんにとって誇らしい事だったでしょう。
しかし、賢子さんにとってまだ幼く母の愛情を欲した時期にまひろさんが出仕した事は、いくら大人の目を気にして我慢してきたとしても寂しかったのではないでしょうか。
まひろさんにしても収入の少ない家計を助けるためや自分を伝手として父や弟の待遇面を有利にするためもあったのではないでしょうか。
そのためにいつしか贅沢に慣れ久しぶりに帰ってきた実家でハメを外し酒の力も借りて宮中の仕事や高級貴族の事などを語り続け、賢子さんは手の届かない自慢話をされている様にしか感じられなかったのでしょう。
賢子さんから見たまひろさんは執筆活動の傍ら自分と遊んでくれる母ではなく、嫌いな己の才能や身分の高い貴族との繋がりを誇る女流作家だったのかもしれません。
しかし、赤の他人である何見氏がそれぞれの思いや家庭事情や当時の時代背景を考慮せず『民の窮状を思いやれ』『身につけた教養は口先だけ』『母親である以前に人としても醜悪』と一家の稼ぎ頭であるまひろさんを一方的に人格否定するのは如何かと思います。
>それこそ「ワーキングマザーの試練」ならば、まず母親は泣くなり、表情にはっきりと出したほうが良さそうだ。
>しかし、まひろは冷静に受け止めているうえに、それを踏み台にして物語を執筆しそうなふてぶてしさすらある。
働く女性として人から良く思われなかったり、子供を家族に預け後ろ髪を引かれる思いで働いている母親が子供の気持ちに添えず否定されてしまったからといってなぜ泣き出したり、(自分の不満を)表情にはっきりと出さなければいけないのでしょうか。
「私は頑張っているのに子供に認めてもらえないから泣いちゃう」と被害者仕草しなければいけないのでしょうか。
まひろさんは母として賢子さんに向き合う前に「すっかり嫌われてしまいました」と自覚しています。
そのうえで自分の不義を『罪』として作品に昇華しようとしているのではないでしょうか。

・『 源氏の物語』は帝のお気に入りになる?
>まひろが出仕し、中宮も、内裏の藤壺に戻りました。
寛弘5年(1008年)11月。
彰子さまは敦成親王と共に内裏に戻りました。
お側にはまひろさんが控えています。
そこへ敦康親王がやって来ます。
彰子さまが長期間の留守を敦康親王に詫びました。
敦康親王は「弟は?」と尋ね、乳母になった宰相の君が抱いていた敦成親王を見せます。
彰子さまは「かわいがってやってくださいませ」と言い、敦康親王は「中宮さまが私を可愛がってくださるのなら、私も敦成を可愛がります」と答えます。
彰子さまは「もちろん。敦康さまは大事な敦康さまでございます」と言い、まひろさんが笑顔でその様子を見ています。

そこへ宮の宣旨が、帝のお渡りを告げます。
皆が一礼する中、帝がお出ましになり「朕も敦康も寂しかったぞ」とお声をかけられました。
彰子さまは「畏れ多きお言葉、勿体無く存じます」と答え、「主上、こちらを献上します」と皆で製本した『光る君の物語』を帝に献上します。
帝はその1冊をお手に取って、「おお…これは美しいのう」と感嘆の声を上げられ、物語をお読みになりました。
「『源氏の物語』か」と仰る帝に、彰子さまは「33帖ございます。後で清涼殿に届けさせます」と答えました。
帝はまひろさんに「これはそなたの思い付きか?」とお尋ねになります。
まひろさんは「滅相も無い事、中宮さまがお上のためにこの様な設えにしたいと仰せになり、表紙も料紙も自らお選びになり、また御手ずからお綴じになりました」と答えました。
帝は彰子さまに「礼を言うぞ」と仰いました。
さらに帝は「33帖は大作である」と仰り、まひろさんは「まだ続きがございます」と答えます。
彰子さまが振り返り「これで終わりではないの?」と驚き問います。
まひろさんは「光る君の一生はまだ終わってはおりませぬ」と言います。
彰子さまが「これからどうなるのだ?」と尋ね、まひろさんは「今色々と考えております」と答えます。
帝は「それは楽しみである、大いに励め」と仰り、藤壺で物語の朗読会を開く事を提案なさいました。







後日、藤壺を会場に帝と彰子さま、公卿たちや女房が揃い、『源氏の物語』の朗読会が行われました。
宰相の君が第25帖「螢」を読み上げます。
『日本紀』などはほんの一面に過ぎない
という源氏の君の台詞を聞いた藤原斉信卿が「今、日本紀より物語を持ちあげたのか?」と藤原公任卿に尋ねます。
当代一の文化人である公任卿は「帝がお読みになると分かっていて、よく書けたものだ」と半ば呆れています。
行成が斉信卿と公任卿を声が大きいと窘め、帝は「何か気になることがあるのか?」と行成卿にお尋ねになります。
行成卿は、「『源氏の物語』には時折はっとさせられると申しておりました」とその場を取り繕います。
帝は全くお気になさらぬ様子で、「女ならではの物の見方に、漢籍の素養も加わっているゆえか、これまでにない物語になっておる。藤式部は日本紀にも精通しておるゆえ」とまひろさんを評価されました。
帝が一目置かれた事で、まひろさんの『源氏の物語』は評判を呼び、彰子さまの藤壺を華やかなものにして行きました。






>まひろが出仕し、中宮も、内裏の藤壺に戻りました。
>するとそこへ敦康親王が嬉しそうにやってきます。
寛弘5年(1008年)11月17日。
中宮・彰子さまが敦成親王とともに内裏に戻りました。
『紫式部日記』寛弘5年(1008年)11月17日条によると『中宮様(藤原彰子)が内裏(だいり)にお帰りになるのは11月17日である。戌の剋(いぬのこく/午後7時~午後9時ごろ)と聞いていたけれど、だんだんと伸びて夜も更(ふ)けてしまった。』とあります。

ちなみに、内裏に向かう牛車に馬の中将の君と相乗りになった紫式部は『嫌な人と乗り合わせたと思われているのはまあ何と大袈裟な事かと、ますますこのような宮仕えが鬱陶しく思われました』と馬の中将の君に露骨に嫌がられた様を記述しています。

>しかし、中宮が33帖で終わりだと思っていた物語が、実はまだ続くことが判明します。
>構想中だと語るまひろですが、ここが重要でしょう。
帝は献上された『光る君の物語』を手に取り「33帖は大作である」と仰います。
まひろさんは「まだ続きがございます」と答えます。
彰子さまが「これで終わりではないの?」と尋ね、まひろさんは「光る君の一生はまだ終わってはおりませぬ」と言います。
帝に献上された写本は第1帖「桐壺」から第33帖「藤裏葉」までです。
『源氏物語』は3部構成の読み物とする考え方がよく取られ、「藤裏葉」はその第一部の最後を飾る巻なのだそうです。
「藤裏葉」は、源氏の君39歳から始まります。
夕霧と雲井雁が結ばれ、明石の姫君(明石の中宮)の入内によって紫の上と明石の上が和解します。
秋になり、源氏の君は『四十の賀』を控えて准太上天皇となります。
11月、六条院へ冷泉帝と朱雀院が揃って行幸なさり、華やかな宴が行われ、源氏の君は栄華の絶頂に立ちます。

詞 菊亭季宣
京都国立博物館所蔵

>帝の発案で、物語を読み上げる会が藤壺で開催されることになりました。
>そして作者の「物語論」が語られ、『日本紀』より上であるという部分が読み上げられます。
『作者の「物語論」』『『日本紀』より上であるという部分』とはどの巻のどこの部分でしょうか。
該当部分を提示して解説してください。
一条帝の発案により藤壺で『光る君の物語』の読書会が開催され、帝と彰子さまを始め女房や公卿が揃いました。
宰相の君が第25帖「螢」を朗読していきます。
「物語」に至上の価値があるという主張が、源氏の君の口を借りて展開されていきます。

>藤原斉信が、このぶっ飛んだ理論に驚き、藤原公任へ動揺を語る。
>公任は困惑しながらも「帝が読むとわかっていて、よくそんなことを書けるな」と返しています。
『『日本紀』などはほんの一面に過ぎない』という源氏の君の台詞を聞いた藤原斉信卿が「今、日本紀より物語を持ちあげたのか?」と藤原公任卿に尋ねます。
公任卿は「帝がお読みになると分かっていて、よく書けたものだ」と半ば呆れています。
平安時代の基礎知識として当時の貴族が『物語』に対する考え方が分かる斉信卿と公任卿のやり取りです。
>この理論は確かに吹っ飛んでいるでしょう。
>東アジアにおいて、物語や小説は「一段落ちるくだらないものだ」という意識は強固なもの。
>一流の書物は歴史書や思想書であると考えられていたのです。
そんなくだらないものを上に置くというのは、あまりに大胆で驚くべきことなのです。
平安時代の物語は『虚事(そらごと)』として、女性の読み物でした。
その対局なのが男性が嗜んだ漢籍や『日本書紀』などの史籍でした。
こうした背景から源氏の君は物語を読む玉鬘を「あな、むつかし。女こそ、ものうるさがらず、人に欺かれむと生まれたるものなれ(あぁ、困ったことだ。女性こそ人に騙されるために生まれてきたのか……)」と誂うのです。

>ただし、この一件で「日本紀の御局」という嫌味たらしいニックネームを、左衛門の内侍につけられることになるのですが、まひろには余裕があるようにみえます。
『『紫式部日記』日本紀の御局』には一条帝がおつきの方に『源氏物語』を読ませていらっしゃった時に「この者(紫式部)は、『日本書紀』を読んだのだろう。本当に学才があるようだ。」と仰ったのを小耳に挟んだ左衛門の内侍が「(紫式部は)たいそう学才がある。」と殿上人などに言いふらし、『日本紀の御局』とあだ名を付けたという記述があります。
『紫式部日記』もその様な所で学才はひけらかさないとあり、まひろさんに余裕があっても不思議ではないと思います。


・中関白家の焦燥?
>そのころ清少納言は、定子の残した脩子内親王に仕えていました。
一方その頃、定子さまの娘・脩子内親王に仕えているききょうさん(清少納言)は『源氏の物語』を読んでいます。
その奥の間では脩子内親王も菓子を口にしつつ『源氏の物語』を読んでいました。


藤原伊周卿は、叔母の高階光子さまから「このままでは敦康親王は左大臣に追いやられてしまう」と詰められています。
伊周卿は「帝の第一皇子、しかも皇后定子が残した唯一の皇子である。帝のお気持ちが揺らぐことはない」と言います。
しかし伊周卿の北の方・幾子さまの兄・源方理(みなもとの かたまさ)卿は、「最近は帝も左大臣には逆らえないと聞いている」と反論します。
幾子さまは方理卿に「余計な心配をなさいますな。帝のお計らいで殿の位も元に戻されている、今はお静かに」と兄を制します。
伊周卿も幾子さまに賛成し、「事を急いては過ちを犯す」と言い宥めます。
しかし、光子さまは「このままじっとしてはいられない」と不満を洩らし、「分かりました故、もうお黙りを」と伊周卿に窘められます。
伊周卿は部屋に籠るとたくさんの形代に小刀で傷つけ、道長卿を呪う呪詛を行います。





>定子の母方にあたる高階光子が「敦康親王が追いやられるのではないか」と危惧して伊周に訴えているのでした。
高階光子さまは伊周卿・定子さま・隆家卿の母・貴子さまの妹で、伊周卿の母方の伯母です。

>源方理は「帝は左大臣に逆らえぬ」と焦っているようです。
>彼は伊周の嫡妻である幾子の兄です。
源 方理(みなもとのかたまさ)卿は伊周卿の嫡妻・幾子さまの兄です。
方理卿は「最近は帝も左大臣には逆らえないと聞いている」とあくまで伝聞の形を取っています。
方理卿は長徳2年(996年)の長徳の変で伊周卿の義兄弟であったために連座により昇殿を許されていないので、人伝てに『帝も左大臣には逆らえない』と知ったのでしょう。

・盗賊が藤壺に侵入した?
>内裏の藤壺で、女房たちが寝静まっています。
大晦日の夜。
藤壺の女房たちは寝静まり、まひろさんが自分の局で『『源氏物語』第34帖「若菜」』の執筆を続けています。
三の宮はまだ幼く、ただ私ひとりを頼みとしたので
その時悲鳴が聞こえ、まひろさんは真っ暗な廊下に出ました。
中宮さまの所ではと思ったまひろさんが廊下を小走りして行ったので、女房たちが「今走って行ったの藤式部?」「そのようね」と囁き合っています。
戸を開けたまひろさんは、二人の女房が下着姿で震えうずくまっているのを発見しました。
事情を聞けば「男どもに刀で脅かされた」との事でした。
「何事だ!」と彰子さまが言い、宮の宣旨も駆けつけて来ました。
「中宮様はお出ましになりませぬ様に」とまひろさんが注意を促します。
しかし彰子さまは「しばし待つ様に」と言って奥へ戻ります。



屋外では、追儺の儀式のために内裏を巡っていた方相氏の面をつけた2人の男が「鬼やらへー!退散なさしめたまえー!」と叫んでいます。
そこへ何人かの男たちが走り出て来て、奪った女房の衣を捨てて逃げました。
面を付けた男の1は衣を確かめると自分の面を上へめくり上げました。
そして、就寝中だった道長卿は百舌彦さんに起こされ「藤壺に盗人が押し入りました」と報告されました。
道長卿は藤壺の彰子さまを訪ねて「無事で何より」と述べ、彰子さまは「大事ありませぬ。藤式部が駆けつけてくれました」と答えます。



>ちょうどこの日は惟規が宿直でいたはずなのに、この日に限って早めに退出していて「アイツ、頼りになんないわ!」と呆れたということが『紫式部日記』には記載されています。
『『紫式部日記』十二月三十日の夜、追儺の儀の後』には、『大晦日の夜、追儺の儀式が早く終わり局で他の女房と寛いていたところ、彰子さまの部屋の方で大声や女房の泣き騒ぐ声が聞こえ恐る恐る駆けつけると、裸になった女房が二人うずくまっていた。
盗人が入った事が分かるも大晦日のために中宮付きの侍も滝口の武者も皆退出し、弟・惟規さまがいるからと「兵部丞(ひょうぶのじょう)という蔵人を呼びなさい」と命じたがすでに退出していた。情けない事この上ない。』という記述があります。
>すると、盗賊が置いていった衣服を拾い上げた“謎の若武者”の顔が一瞬、あらわになりました。
『紫式部日記』の盗賊侵入事件や惟規さまの退出を知っているのなら、この事件が大晦日の夜、追儺の儀の後に起きたと分かるはずですがなぜ『追儺』や女房の衣を拾った謎の男が何をしていたのかについて説明しないのでしょうか。
『追儺』とは、大晦日(旧暦12月30日)に疫鬼や疫神を払う儀式です。
中国で宮中で行われる辟邪(不吉な兆しや悪しきものを退ける事)の行事として立春の前日である大晦日に行われていた儀式が日本に渡り宮中で年中行事として行われるようになりました。
平安時代「追儺」は宮中総出の行事でした。
まず紫宸殿の前庭で陰陽師が鬼に対して供物を捧げ祭文を読み上げました。
儺人(なじん)たちは桃と葦でつくられた弓と矢を持ち、黒い衣を着て4つ目の四角い面を付け右手に戈、左手に大きな楯を持った鬼を駆逐する役目の方相氏とそれに従う侲子たちは『鬼遣らい』と言いながら鬼たちを払い出すため内裏を回りました。
これが現代では2月3日の節分となりますが、京都の平安神宮や吉田神社では古来の『追儺』が再現されています。
盗賊が捨てた衣を拾った二人の男は『鬼遣らい、退散なさしめたまえ』と言い内裏を廻っていた面を付けた方相氏と侲子だったのでしょう。

『都年中行事画帖』(1928年)

・道長から吹いてくる冷たい風?
>道長はまひろに語りかけ「中宮を助けようと駆けたのは本当か」と確認しています。
道長卿はまひろさんの許へ行き、「お前ひとりが中宮様を助けようと駆けつけたのはまことか、他の女房たちは何をしていたのだ」と詰問します。
まひろは「御立派なのは中宮さまで、衣を剥ぎ取られた女房たちに自ら袿をお持ちくださいました」と答えました。
まひろさんは「上に立つお方の威厳と慈悲に満ち溢れておいでで、胸打たれました」と話します。
道長卿は「お前もよくやってくれた、これからも中宮さまと敦成親王さまをよろしく頼む、敦成親王さまは次の東宮となられるお方故」と言い、まひろさんは「次の…」と言いかけます。
唖然とするまひろさんを余所に、道長卿は「警護が手薄なのを知っていて忍び込んだという事は、ただの賊ではないやも知れぬな。これよりは後宮の警護を一層厳重にする。ご苦労であった」と告げて去っていきました。
まひろさんは複雑な思いを浮かべ彼を見送ります。

>この瞬間、まひろの書く物語の意味も彼女の中では変わってしまったことでしょう。結局は政治権力の道具であったのか、と彼女は理解したのかもしれません
当初は「入内するも、帝のお渡りもお召しもなく、寂しく暮らす中宮を慰めるために物語を書いてほしい」と言っていた道長卿でしたが、真の目的は『一条帝に『枕草子』を超える書物を献上し、亡き藤原定子さまに囚われる帝の心を動かす事』だと分かり、まひろさんは道長卿の本心と政治的意味を知った上で「自分らしい物語を書きたい」「帝がお読みになるものを書いてみとうございます」と執筆活動に臨んでいます。
出仕し、物語を書く事が勤めとなったものの周りの喧騒に耐えられなくなり里下がりを申し出た時も、道長卿ははっきりと本心を述べ「最後の賭けなのだ!」と懇願しています。
しかし、内裏に入った賊の対応でまひろさんと対話する道長卿は「敦成親王さまは次の東宮となられるお方故」と言い、まひろさんを戸惑わせています。
『人の心は移りやすい』という様にいつしか栄華を極め驕りも見え、まひろさんに本心を隠しておけない道長卿は、敦康親王と敦成親王どちらが後継者になるのかという政治問題に野望を見せ始めたのではないでしょうか。
かつて、道長卿の兄・道兼卿が「俺達の影は皆同じ方を向いている。一族の闇だ」と言っていましたが、道長卿も自らの栄華の陰でそれを避ける事は出来ないのかもしれません。



・波乱の予兆?
>そしてあの謎の若武者が、決定的でしょう。
>彼はまるで直秀が蘇ったように思える。
>直秀が忍び込んだ時、若い頃の道長は救い出そうとしました。
>それが今はまるで害虫が忍び込んだように考えている。
>一方でまひろはどうか?
>あの謎の若武者は、直秀の再来として、二人の心を映す鏡になるのかもしれません。
伊藤 健太郎さん演じる双寿丸は公式HP人物紹介に於いて『賢子を盗人から救ったことで、その屋敷に出入りするようになり、まひろ(紫式部)とも知り合う。武者としての生き方に独自の考えを持っており、興味を持った賢子はひかれていく。』と設定があります。
また、藤原隆家卿と親交のある武者・平 為賢公の人物紹介には、『為賢のもとで、双寿丸は武術の研鑽(けんさん)に打ち込んでいる。』とあります。
公式に書いてある事を調べず勝手に人物設定を改変し『こうなるに違いない』で物語を進めたがるのは如何なものかと思います。



・東宮の座を巡る争いが生じる?
>寛弘6年(1009年)、年があけると帝は伊周を正二位にとしました。
年が明け、寛弘6年(1009年)正月7日。
伊周卿は帝から正二位の位を賜り、道長卿と同じ官位となりました。
「年が明けると一条天皇は伊周に正二位の位を授けた」と語りが入ります。
伊周卿が帝に礼を述べ、帝は「大臣に准じる地位の者としてこれからも頼む」とお声をかけられました。
伊周卿は「私は第一の皇子におわす敦康親王さまの後見」と強調し、道長卿の方を見ながら「左大臣さまは第二の皇子敦成親王様のご後見であられます。くれぐれもよしなにお願い申し上げます」と述べます。
右大臣・藤原顕光卿と藤原公季卿が道長卿の方に視線を送ります。




藤原道綱卿は「伊周の正二位は帝1人ではお決めになれないだろう。左大臣はよく許したね」と藤原実資に話しかけます。
実資卿は「伊周の不満がこれ以上募らぬ様、位を上げてやったのだろう」と答えます。
道綱卿が「それってなんで?」と尋ね、実資卿は「上に立つ者のゆとりであろう」と答えます。
それを聞いて道綱卿は「ゆとりかあ…」と呟きます。
二人は並んで座ります。
実資卿は「されどお上の敦康親王さまを次の東宮にというご意志は相当お強い」と言い、道綱卿が「大好きだった皇后定子さまのお子だもんね」と相槌を打ちます。




藤原公任卿は藤原隆家卿に「伊周殿がここまで盛り返すとは思ってもおらなんだ」と言います。
しかし、隆家卿は「私は兄とは一切関わりございませぬ」と言います。
「まことか?」と疑う公任卿に、隆家卿は「とうの昔に兄は見限りました。左大臣さまを煽るようなことを申す兄に、最早まともな心はありませぬ」と答えます。
公任卿は「俺も斉信も行成も道長を支えるつもりだ。そなたもその心があるか?」と敢えて意志を隆家卿に尋ねました。
「勿論です」と隆家卿が答えます。
そこで公任卿は「伊周殿に何か動きがあれば知らせよ」と隆家卿に命じ、隆家卿もそれを受け入れていました。



>寛弘6年(1009年)、年があけると帝は伊周を正二位にとしました。
>ついに道長と並んだ。
>これで東宮が誰になるかによって、情勢は大きく変わります。
>帝は一体何を考えているのか?
>パワーバランスを取ろうとしているのかもしれません。
寛弘6年(1009年)正月7日。伊周卿は帝から正二位の位を賜り、道長卿と同じ官位となりました。
帝の仰る様に正二位は『大臣に准じる地位』であり、敦康親王の後見として権力を拮抗させようとのお考えかもしれません。
「伊周の正二位は帝1人ではお決めになれない」と藤原道綱卿は訝しがりますが実資卿は「伊周の不満がこれ以上募らぬ様、位を上げてやったのだろう」と言い、「上に立つ者のゆとりであろう」とも評価しています。
『権記』寛弘6年(1009年) 正月七日条には、『帥(そち/藤原伊周)が加階された。』とあります。

>それにしても、これは隣国の宋あたりからすれば「何をしているんだ君たちは!」と驚愕しそうな話でして。
>中国でも、兄弟のうち器量や母の身分差で決めていたこともあります。
(中略)
>しかし、それでは兄弟同士が無駄に争ってろくなことがありません。デメリットが大きい。
>ゆえに、よほどのことがない限り、基本的には長男を皇太子にして、弟はそれを補佐させることが定着していきました。
仮に中国の宋に於いて長男を皇太子にして、弟はそれを補佐させる事が通例だとしても、朝貢国や植民地でもない他国の後継者争いに「何をしているんだ君たちは!」と口を出す事は越権行為や他国への干渉であり、中国を例に出すのは無粋ではないでしょうか。
第一皇子の敦康親王の母・定子さまはすでに亡くなり母方である中関白家も政変により力を失い、今は中宮・彰子さまが養育しています。
彰子さまが生んだ第二皇子・敦成親王には道長卿が付いており、一条帝は伊周卿の位を上げる事で敦康親王の後ろ盾の中関白家を強くしようとしたのではないでしょうか。
・清少納言、『 源氏物語』を読む?
>さらにこの日、為時は正五位下にのぼりました。
この日は為時公も正五位下の位を賜りました。
「この日為時は正五位下に昇った」と語りが入ります。
惟規さまがまひろさんを訪ねて来て「どうなっているんだろう一体。父上もまた官職を頂けるという事なのかな?」と不安を洩らしました。
しかし、まひろさんはそれほど驚いていない様子で惟規さまは「驚かないの?」と尋ねます。
まひろさん「早く仕事に戻りなさい」と言い、惟規さまは「せっかく教えに来てあげたのに」と言います。
惟規さまが「今日はおいしいお菓子はないの」と訊くので、まひろさんは「ありません」と答えます。
局に戻ったまひろさんは道長卿から贈られた扇を広げ見つめています。



そこへ足音が聞こえ、大納言の君が「藤式部、清少納言殿がお見えです」と伝えます。
局に通されたききょうさんが「お久しゅうございます。まひろ様」と挨拶します。
ききょうさんが「『光る君の物語』、読みました」とまひろさんに告げます。



>さて、邪悪なのはどちらでしょう?
>私はまひろだと思います。
>改めて考えてみてください。
>彼女は定子をモデルにするように桐壺更衣を描き、桐壺帝の愛が殺したように書き始めています。
>道長が困惑し、帝も気付き、苛立った出だしです。
>そのうえで桐壺帝の寵愛を上書きする存在として、藤壺の宮を出してきている。
>皇后定子はオワコン。
>今は中宮彰子の時代。
>そう揶揄しているような内容といえます。
何見氏は帝と定子さまの愛情を上書きするまひろさんに怒って邪悪と言っているのか、紫式部の『源氏物語』第一帖「桐壺」の内容に怒って邪悪と言っているのかどちらなのでしょうか。
史籍としての『源氏物語』とそれをモチーフにした二次創作であるドラマ内の作品としての物語が混同されているのではないでしょうか。
まず、基本的な教養として『源氏物語』第一帖「桐壺」を書いたのは誰でしょうか。
『源氏物語』を書いたのは『紫式部』でありまひろさんは『光る君へ』作中で紫式部をモチーフとしたキャラとして源氏物語を書いています。
つまりドラマは紫式部の『源氏物語』をそのまま借りた二次創作です。
紫式部には困惑する道長卿も苛立った帝も存在しません。
『桐壺』はおそらく『長恨歌』をベースに桐壺と桐壺更衣の純愛と業を唐の玄宗皇帝と楊貴妃の恋に準えて描いたと思いますが、紫式部か定子さまを否定したかどうかは分からないと思います。

>火の玉ストレート豪速球を、定子周辺にぶつけてきた、憎んでも憎みきれない、そんな炎上上等作家です。
>そのくせ涼しい顔で「ききょう様」と返してくる奴。
>邪悪に決まっているじゃないですか。
「帝のお渡りもお召しもなく、寂しく暮らす中宮を慰めるために物語を書いてほしい」と依頼を受けて『桐壺』を書いたまひろさんを頭から定子さまを下げるために『桐壺』をぶつけてきたと思い込み、事実誤認で『炎上作家』と決めつけ、混同して現実で文学作品として成立している物語にありえない解釈をするのは歴史ライターとして如何なものかと思います。
ききょうさんも「『光る君の物語』、読みました」とまひろさんに挨拶しただけで何も言っていません。

・MVP:藤原行成?
>能書家である藤原行成が筆を執り『源氏物語』を記す。
>行成の出番は長く、字が美しいことは紹介されてきました。
>その能筆を前面に押し出した瞬間、何かが当て嵌まる音が聞こえたような気がしたのです。
>書とは、東アジアにおいて天意を受け止める器のような意味合いすらあります。
>ゆえに君主は己の治世において、能書家が出るよう願うもの。
三蹟と謳われた藤原行成卿の能書家としての能力やそれを作中で表現した書道指導・根本知先生を評価するはずが個人ではなく、『東アジアでは〜』とマウントになるのでしょうか。
結局、マウントを取りたいのと、能書家を多く排出する権威を主張したいのではないですか。

※何かを見た氏は貼っておりませんでしたが、今年もNHKにお礼のメールサイトのリンクを貼っておきます。
ファンの皆様で応援の言葉や温かい感想を送ってみてはいかがでしょうか?
