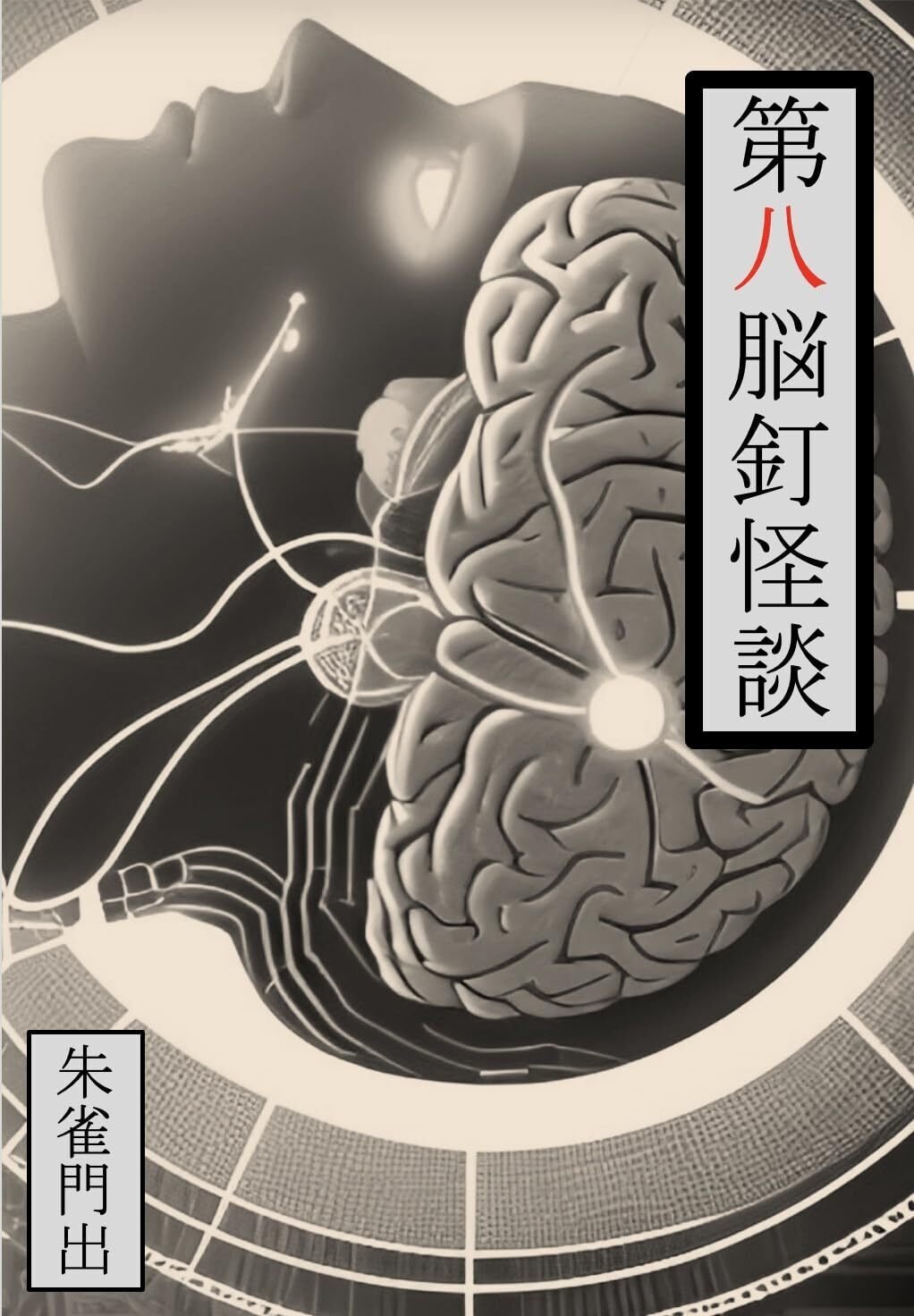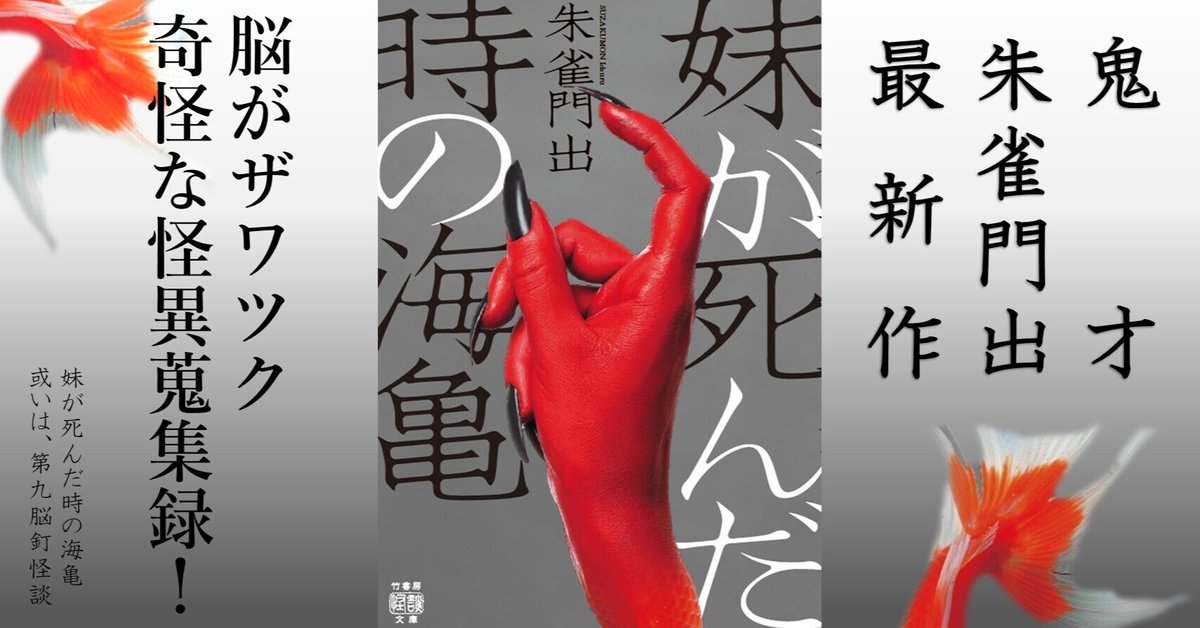
【1月29日発売】鬼才・朱雀門出待望の新刊が登場!全話に著者の怪画付き、脳がザワツク奇怪な怪異随筆集『妹が死んだ時の海亀』内容紹介&著者コメント&試し読み!
鬼才・朱雀門出が採話した奇絶怪絶な体験談の数々を描きおろしの怪画と文で綴る魅惑の闇世界。

あらすじ・内容
「人魚に殺まされるからな」
盆の海に男が三人。
「××のようにならなければいいだけ」
おまえは何を撫でている……?
怖い話、幽霊の話に収まらぬ奇怪な体験談を取材し続ける朱雀門出の最新怪異録。
◆盆に船を出してはならない禁忌を好奇心で破った男が語る不気味な海の記憶…「妹が死んだ時の海亀」
◆夜の散歩で見かけた焚き火を囲む壺のようなもの。壺はぶつぶつと何かを喋り…「焚き火を囲む首」
◆姪がおじちゃんと呼ぶ視えない人。いつしか自分にも視えだしたソレが口にする不穏な言葉とは…「子供のお漬物」
◆幼い頃にさせられた異様な作業の記憶。箱にミニチュアの父母を詰めるというのだが…「報い箱」
ほか、全話に著者の怪画付き。
得体の知れない奇怪さに本能が舌なめずりをし、問答無用で惹きずりこまれる怪楽の65話収録!
平和な日常に飛び込んでくる、耳を疑う言葉たち。
思考を停止させる強烈な異物感。
「人形の材料にイヌは適してないよ」
「鬼にワザマられやすいから」
「俺の〝水なんとか〟を掘り出せ」
「子供のお漬物がへれめてる」
「オヤコタワケめ!」
「蛇が喋るまで待ってくださいね」
奇妙な言葉の裏に潜む不穏すぎる何か。
それが見えた時、恐怖は泡の如く弾けだす……
著者コメント
このたび上梓いたしました『妹が死んだ時の海亀』ですが、口に出したり、SNS で表記するには長いかと思います。遠慮なく「海亀」なり、「妹死海亀」なり、あるいはもっと呼びやすかったり書きやすい名称をご自由にお使い下さい。
また、従来の「脳釘怪談」シリーズをご愛読下さり、『第九脳釘怪談』はまだかとありがたいお声を頂戴しております。朱雀門出が採話した怪談をまとめた書籍は「脳釘怪談」ではないのか、との疑問もよくわかります。
本作『妹が死んだ時の海亀』も「これまで聞いたことのない怪談」を選んでお伝えする脳釘怪談の方針は継承しておりますので、実質的には『第九脳釘怪談』です。ただ、今回から自作のイラストを加えたり新しい試みもありますし、ナンバーが付いていると途中から手に取るような感じがして新規読者には良くないなど販売戦略上の理由もあって、あえて脳釘怪談とは明記しておりません。
短編集でよくあるように、表題作として収録作の一つを書籍のタイトルにしているのだとお考え下さい。そこにシリーズ名を書いていないだけなのです。
ご希望の方には、お目にかかったときなどに「実質、第九脳釘怪談です」と但し書きをお入れいたします。是非、お声がけください。
私の書く怪談集は報告書ではなく、随筆です。見聞きした出来事や話の中で興味深いものを時には考えなども含めて自由に書いたものが随筆であり、本作は怪談集ですから、その中でも怪異に関する話を選んで書いております。
前述の通り、「これまで聞いたことのない怪談」と感じた、意外で奇妙な話を今回も集めておりますので、これまで上梓してきたものを愛して下さっている方々には、あの感覚をお楽しみ頂けるかと思います。また、「これまで聞いたことのない怪談」というなら試してやろうという初めてお読み下さる方々にも刺さる部分はあるかと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
試し読み
「報い箱」より抜粋
志郎さんには、小さい頃から数年に亘って非現実的な作業をさせられたという異様な記憶がある。
箱にラベルを貼って中身を入れるという簡単な作業で、月に一度くらいのペースで行っていた。就学前からしていたように思える。高校に入る前まで行っていたので、その辺りになると記憶ははっきりしている。
庭に物置小屋があった。中は十二畳ほどのスペースがある。そんなちょっとした離れくらいのサイズがある大きな物置だった。その中に作業スペースが設えてあり、そこに座ると、箱とラベル、中身が目の前に置かれるのだ。
箱は一辺が十五センチほどの立方体で、材質は骨のようなものだった。少し黄ばんだ白で、薄くてもろい感じがした。
そして、そこに入れる中身が変わっているというか、狂っていた。志郎さんの父と母なのだ…… ※続きは書籍にて

「焚き火を囲む首」 より抜粋
佐智代さんは友人と、夕食の後にウォーキングするのが日課だった。
(中略)
その時は、城跡の方へ向かった。城跡といっても立派な公園の中にあり、他にもウォーキングをしている人の姿を見かける。
ただ、二人は少し人気の少ない側道へと足を向けた。といっても、そちらにも偉人の名を冠した井戸があり、昼間なら観光客が集うので、忘れ去られて放置されたようなところではない。単に城や庭園からは離れており、石垣の陰になって暗いので、夜にわざわざ行こうとするものが少ないだけであった。それが却って、目先を変えることにもなるし、空いていて気兼ねなく歩けることにもなるので、その日は行ってみたのだった。
しばらく脇道を進むと、明かりが見えた。それは井戸があった跡を示す石碑よりも向こうにあった。
焚き火をしているようだった。
しかし、人の姿はない。人の姿はないが、焚き火を囲むように壺のようなものが置かれていた。
不思議に思って二人は近づく。と、それらは壺ではなく、人の頭部だとわかった。
ギョッとして足を止めた。生首かと思ったのだ。
「人形?」と佐智代さんは頭に浮かんだことを口にした。
「あ、ああ、人形か」と友人はホッとするような言葉を漏らした。
友人は周囲を見回していた。釣られて佐智代さんも周囲に目をやる。この火を点けたり、首を列べた人の姿はない。火を点けたまま放置するのは危険だと思える。
周囲を見回しながら焚き火に近づくが、やはり他の人影はなかった。
低い男の声が、低い位置から聞こえた。地面に置かれた頭からだ。
二人は反射的に身を屈め、足を止めた……※続きは書籍にて

「P山 二」 より抜粋
P山の麓に住んでいる松尾さんが小学校に上がる前の話だ。
当時、近所の子とよく遊んでいた。遊び場はP山だった。川は危ないので入らないようにとは注意されたものの、あとは自由に遊ぶことが許されていたものだった。お蔭でずいぶんと昆虫や野草などには詳しくなったものだという。
その日はちょっと奥まで行こうと山を三人で登っていた。三人は横並びに山道を登っていった。松尾さんはその時左端にいたのをよく憶えている。
と、隣にいるミネユキくんの姿がないのに残りの二人が気付いた。ほんの一瞬の出来事で面食らった。
「おおぉい」
という声がした。ミネユキくんの声だ。その声の方を見ると、そちらは川だった。
激しい流れの中にミネユキくんが立っていた。こちらに手招きしている。
「浅いよぉ」
ミネユキくんがそう言うように、川に沈んでいるのは彼の足首から下だった。けれど、立っているのは川の中ほどで、激しい流れからするとそんなに浅いとは思えない。いや、偶々そこだけが浅くともそこに行くまでは深いところを通らねばならないのは明らかだった。
躊躇していると、ミネユキくんは手招きしながらこちらにゆっくりと歩を進めた。相変わらず、足は深く沈んでいなかった。
けれど、二人は岸から先には進めなかった。
近づくミネユキくんの腕がよく見えた。半袖シャツから出ている腕には奇妙な模様があった。今思えば、梵字だったかもしれない。確証はないのでアラビア文字かもしれない。とにかくグニャグニャした文字だった。そんな文字が、黒い糸で縫っているかのように腕に浮かんでいた……※続きは書籍にて

著者紹介
朱雀門 出(すざくもん・いづる)
大阪府生まれ。2009年、「今昔奇怪録」で第16回日本ホラー小説大賞短編賞を受賞。
著書に受賞作を収録した『今昔奇怪録』『首ざぶとん』、実話怪談では「脳釘怪談」シリーズ。
共著に『予言怪談』『人形の怖い話』『京都怪談 神隠し』『黄泉つなぎ百物語』、「怪談五色」「怪談四十九夜」各シリーズ、など。
好評既刊