
医療人の「働き方」をデザインする
医療デザイン Key Person Interview:社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院 病院長 服部 智任
神奈川県中央部の海老名市、服部智任院長は中核病院である海老名総合病院を率いる。また県下で初めて、複数の医療法人でつくる地域医療連携推進法人を発足させたリーダーでもある。
「よい医師とは?」「働くことの意味は?」「 幸せとは?」
服部はこんな質問を自らに問いかけてきた。
デザインという言葉を好んで使い、医師の働き方改革に挑む病院長。他の業種から積極的に学ぶ好奇心の源について聞いた。
130名の医師全員と個別対話を重ねる院長
海老名総合病院がある神奈川県海老名市は、県の中央部に位置する。479床と規模が大きいだけでなく、1年間に救急車が8000台もやってくる「かなり忙しい病院」だ。
服部が病院長になったのは2015年。リーダーとして1200名を超える職員を率いつつ、エリア人口約80万人の医療を守ってきた。
医師として入職したのは30代後半だったが、当時は院長職と異なり現場での診療がメインだった。だが当時から人事制度、評価制度の設計などに積極的に関わっていたという。

「自分は『経営と現場の橋渡し役だ』『自分は全体を代表している』など傲慢にも勝手に思ってました。ただ、組織全体を良くしたいとは考えていました。ただ今から考えると、当時の経営陣にモノ申したりして、だいぶ無鉄砲だったなとも思います(笑)。」
ーーもともとマネジメント、経営への意欲が強いほうだったのですか?
「いろんなことに首を突っ込みたい、好奇心旺盛な性格だったんですよ。管理職になる前から『他人にどんな言葉で、どう伝えていくか』はいろいろ試行錯誤していました。」
服部は院長となった現在も年に二回、勤務するすべての医師との個別面談を行う。大病院のため勤務医の数は130名を超えるが、個々の職員とのコミュニケーションに膨大な時間を割いていることが分かる。
「本音を言えば全職員と話したいです。同じグループのクリニックの院長時代は、100名あまりの全職員と1対1の対話をしたこともありましたが、さすがに今は無理です。
普通の社長さんと同じはずですよ。まずみんなの話を聴かないと実態が分かりません。もちろんこちらが期待していること、期待とのギャップなども直接伝えます。その人の価値観、働く上で大切にしていることを聴けば、適材適所にもできるかもしれません。」
対話を通して、病院の方針も伝えてきた。その一つが「医師の働き方改革」への対応だ。
医師の働き方改革で問われる
「良い医師」と「働く」意味
病院経営者の多くが「医師の働き方改革」に頭を悩ませている。救急対応や当直などがある医師も、一般のサラリーマンと同様に年間の総労働時間の規制が始まる。ただ時間短縮すれば良いわけではない難易度の高いテーマだ。
ーー勤務時間を削減しながらも医療の質は守らなければならないですね?
「残業時間の削減ばかりに気を取られるのはよくないと思います。また研修医など若手の育成にとっては、あまりに短い時間しか医師として研鑽を積めないのは成長という点で影響があるとも考えています。
勤務時間が限られるなら医療も、生産性の向上が大事になります。ひとつポイントがあって、医療者が患者さんに費やした時間は必ずしも患者さんの満足度に比例しないんですよ。たとえば3分の診察でも聞きたいことが聴けた、安心した、という感想もありますよね。」
ーーあります。でも難しいですね。旧来の概念なら、患者と向き合う時間が長いほうが良いとされていました。
「そうですね。医師の『想い入れ』なのか『こだわり』なのかという論点もあります。こだわりは辞書では『ムダなこと』という意味合いもある。でも『それはこだわりだ、ムダだ』などと、こちらが勝手に決めつける訳にはいきません。
そこで当院では、まず医師と約束することとしました。
共通認識で意見交換をするために『皆さんが提供した医療サービス量=診療報酬点数(診療行為ごとに国が定めた病院の収入になるポイント)』という考え方です。診療報酬点数は、国が求める医療に対する評価指標なので、こうした言葉選びは重要ですね。」

ーー昭和と令和では働くことの考えも変わってきましたね。
「全然違いますよね。僕らはめちゃくちゃに働くのが当たり前でした(笑)。今は仕事とプライベートなどもきっちり分かれますよね。
それでも『働くことは…自分がハッピーになり、ハッピーをお裾分けすること』という価値観はずっと変わりません。よく自己犠牲などと言いますが、自分が不幸なのに人のために働けるなんておかしいと考えてきました。」
自身はモーレツに働いてきた世代なのにもかかわらず、先進的な考え方を身につけていたと言っていいだろう。「労働は自分の時間を売ること、労働はツラいこと」という枠組みでは、服部の視点には到底たどり着けない。
「単独では難しくても力を合わせれば」
地域を守る矜持
服部のリーダーシップは、1つの病院の枠におさまらない。
2019年、神奈川県内で初となる地域医療連携推進法人「さがみメディカルパートナー」が発足した。代表に就いた服部は旗振り役となり、現在、海老名総合病院のほか地域のクリニックや老人ホームなど17施設が加盟している。
「一般の方には分かりづらいかもしれませんが、地域医療連携推進法人は、大小さまざまな医療機関が参加することで地域医療の全体の質を高める効果があります。」
法人化すると医療機器や医薬品の購入、人材の交流などでメリットがある。またメンバーの施設には、海老名総合病院の患者情報が提供され、患者さんの受け入れ先になることも多い。
それぞれが独立した医療機関であることは変わらないが、地域に強力なリーダーシップをもった存在がいないと組織化は進まなかっただろう。
ーー立ち上げも大変だったでしょうけれど、持続はさらに大変なのでは。
「ここまで当院が大病院として推進的な役割を担ってきました。常日頃から皆さんから尊敬される存在でなければと、心がけています。民間同士ですから加盟している他の医療機関に経営上のメリットも示し続ける必要があります。患者さんを積極的に紹介するのもその一つですね。
いくら大きな医療法人でも、単独で草の根レベルまで質の高い医療を提供するのは難しい。私たちから地域の医療機関、患者さんへの情報発信を強化して仲間を増やしていきたいですね。院内でも院外も、大切なのはコミュニケーションです。」

デザインはいつも身近にあった
服部の言葉からは何気なく『デザイン』の単語が出てくる。
以前に服部が、日本医療デザインセンターで講演した際にもスライドに「デザイン」の文字が出てきた。医療デザインという言葉を知る前から、服部はデザインという言葉を好んで使っていたという。


ーー「医療デザインサミット」に合わせて選んだのだと思っていました。
「実は以前からデザインって言葉が身近なものだったんですよ。デザインに関する本を読むのも好きですね。」
ーーええ! デザインに造詣のある病院長は聞いたことがありません。
「そうかもしれませんね(笑)。クリエイティブ・ディレクターとして活躍する佐藤可士和さんは『外見は一番外側の中身』という言葉で表現されていました。
建築家の隈研吾さんは『更地に作るなんて大変。むしろ制約があるからこそ、その条件でデザインできる』という趣旨の話をされています。
この話も好きですね。だって医療も同じだと思うから。」
ーー医師の働き方改革も、労働時間の「制約」とも考えられるかもしれません。
「同じだと思います。時間的な制約は必要ですしね。その中でどうやって理想の医療を追求するか。従来の考え方にとらわれないデザインの発想、大事だと思いますよ。」
日本医療デザインセンターとの出会いは、病院で作る動画教材を編集する会社を探していたときだったという。「デザイン」の意味は服部が予想していたのとは異なり、課題を解決する思考法だった。彼らが企画するセミナーには知的好奇心を刺激されたと言う。
ーー今後、日本医療デザインセンターに期待することはありますか?
「プラットフォーム役でしょうか。医療の世界は狭いし、外の世界の情報を取りに行かないといけない。『デザイン』という切り口を通して、職種や業種のまったく違う人たちの話を聴けるのが貴重だと感じています。」
ーー病院長のお立場だと、病院経営の話が聴きたいのかと思っていました。
「病院長同士なら自分でいくらでもつながりをつくって情報交換できます。それよりも『外』の成功例、苦労、考え方…を学びたいですね。」
最後に服部は自信ありげに添えてくれた。
「好奇心ならありますね。デザインをどう経営に生かせるかは私次第。楽しみです。」
今よりもよくできる、よくしたい。
そんな貪欲な向上心の表れだと感じた。
取材後記
日本医療デザインセンターには海老名総合病院に伺った経験のあるスタッフが何名もいます。口をそろえて、働いている人たちがイキイキしているのに驚いたと言います。
服部先生自身が「いつも幸せに働く」を念頭に置き、実践されているからなのでしょう。経営者として優れているだけでなく、仲間への愛にあふれたすばらしいリーダーだと感じました。
(聞き手:医療デザインライター・藤原友亮)
日本医療デザインセンター桑畑より
賛助会のフォーラムでは、毎回毎回、服部先生のコメントに唸らされます。医療の知識は当然のことながら、経営やマネジメントについても博識で・・・いや、服部先生の場合は博識という言葉よりも、視点の鋭さと考察の深さを感じずにはいられません。本当にユニークで聡明な方です。
そして、その根底には人に対する優しさと、最高の組織をつくっていくことへの覚悟を感じます。
服部先生と毎月お話しできるのがいつも本当に光栄で、そして楽しみです!
服部 智任さん プロフィール
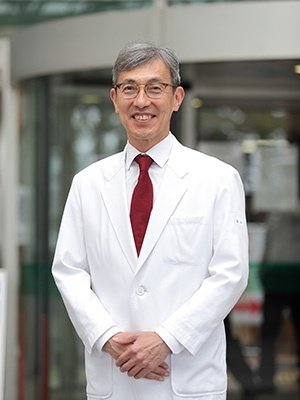
1985年、滋賀医科大学卒業。アメリカでの勤務や日本医科大学付属病院泌尿器科での勤務を経て、2000年に医療法人社団仁愛会(現:社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス)に入職する。
2008年、海老名メディカルプラザ院長。2015年より海老名総合病院病院長を勤める(現職)。2019年には地域医療連携推進法人さがみメディカルパートナーズを設立して初代の代表理事を兼任している。
