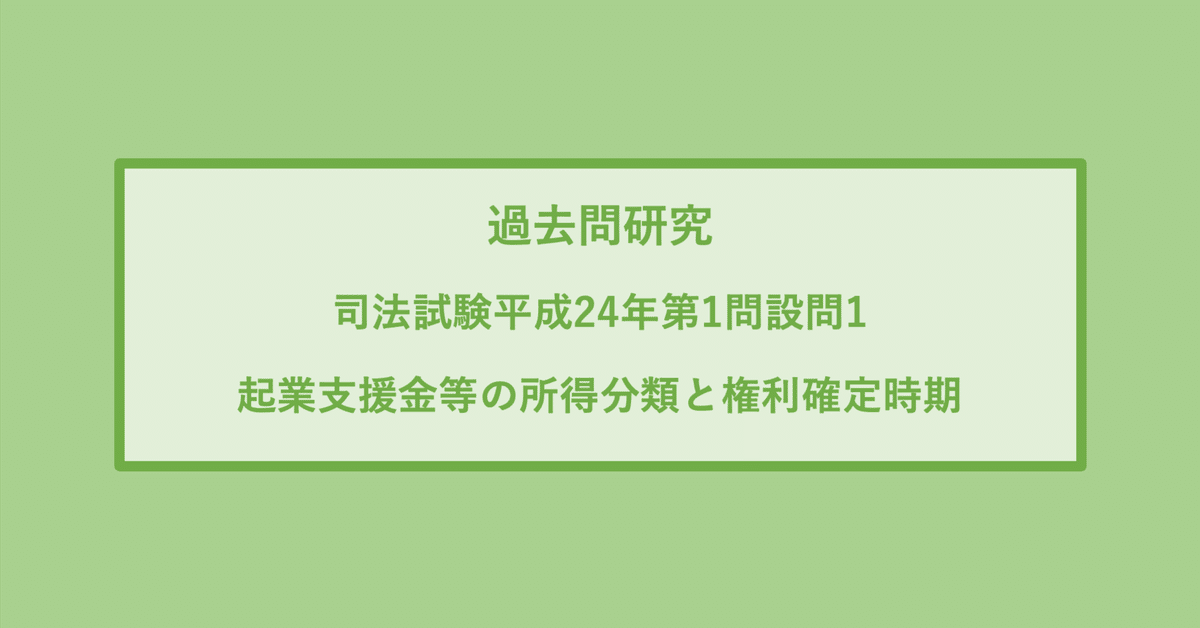
【過去問】 起業支援金等の所得分類と権利確定時期
1.問題
上場会社であるX社(暦年を事業年度とする内国法人。)は、同社の知名度を上げるとともに、同社の新規投資先発掘を目的として、X社の商号を冠した「X起業大賞」という起業企画コンペを行った。X社は、平成21年10月に、X社が大賞受賞者と起業支援のための起業支援契約を締結することなどを盛り込んだ募集要項を発表、平成22年10月に優秀者5名を決定し、うち1名を最優秀者としてX起業大賞を授与することとした。
甲(居住者)は、子供の頃から、いつかは自分が発明したロボット製品を世界中に広めたいという夢を持ち、工学系大学院修了後は、実家に住み、叔父が経営するY精密機械工場(以下「Y」という。)で働きながら、実家の物置を改装した作業場で、大学院在学中に自分が取った特許技術を応用した比較的低価格で製造可能な介護支援用ロボット「OKくん」の商品開発を続けていた。甲は、ロボット専門誌でX起業大賞のことを知り、ここが人生の正念場と考えて起業の決意を固め、平成21年末にYを退職し、その後、退職時にYから受けた退職金100万円を軍資金とし、叔父の好意でYの工場の一角と工作機械を使わせてもらい、OKくんの商品性の改良と企画書作りに専念した。甲は、平成22年3月の締切りぎりぎりにOKくん起業企画書を仕上げて応募し、同年4月から発表までの間も、父親から300万円を借金してOKくんの商品性の改良にまい進していたところ,最優秀者に選ばれた。
平成22年11月1日に行われたX起業大賞表彰式において、優秀者5名に対して、X社から奨励金として500万円が入った金一封が授与され、最優秀者甲には、この金一封に加えて、甲を宛先とし、X社代表取締役社長名義で記名押印され、「貴殿がX起業大賞に応募したOKくん起業企画書を最優秀と認め、奨励金500万円を授与するとともに、①正賞として、総額で最高5000万円までの起業支援金を授与し、②副賞として、貴殿がX社のビジネス・パートナーとなった証として、X社普通株式1000株を授与する。また、X社は、本日付けで募集要項記載の起業支援契約を貴殿と締結したことを確認する。」と記載されたX起業大賞目録が授与された。「起業支援契約」の主要な条項は下記のとおりである。
第1条(起業支援金支払条件)
X社は、甲に対し、本契約に定める条件に従って、X起業大賞目録記載の正賞として、起業支援金を支払う。ただし、X社は、OKくん起業企画書(以下「甲起業企画書」という。)の企画を実行するための費用として、本契約有効期間中に発生したものにつき、甲がX社に対してその請求書又は領収書を提出することを条件として、当該費用相当額を、本条に基づく起業支援金として、累積合計5000万円に至るまで支払うものとする。
第2条(協議及び独占販売権)
甲は、甲起業企画書の企画達成状況につき、本契約有効期間中、少なくとも1か月に1回、更にX社が希望する場合には随時、X社に報告しなければならない。X社は、甲起業企画書記載の商品につき、別途合意する売買条件で、本契約の期間満了日前でX社が指定する日(以下「独占販売契約開始日」という。)から2年間の独占販売権を甲から受ける権利を有する。
第3条(起業支援金残額の取扱い)
第1条の規定にかかわらず、①甲が独占販売契約開始日までに同条に基づいてX社に請求した起業支援金の累積合計が5000万円に満たなかった場合には、X社は甲に対し、未請求分の起業支援金残額を独占販売契約開始日に支払うものとするが、②X社が本契約の期間満了日までに独占販売契約開始日を指定しなかった場合には、甲はX社に対し、未請求分の起業支援金残額の支払を請求することはできない。
第4条(契約期間)
本契約の有効期間は、平成22年11月1日から、①X社が第2条に基づいて独占販売契約開始日を指定した場合には、X社が指定した独占販売契約開始日の前日、又は②平成23年11月1日のいずれか早い方の日までとする。
甲は、奨励金500万円で父親からの借金の返済もでき、平成22年11月にはようやく念願の新作業場を賃借し、アルバイトを雇って試作品の製作を開始した。その後のOKくん発売までの道のりは次のとおりであった。
平成22年
11月〜12月
甲は、新作業場の賃料、人件費及び機材購入費の請求書を添付して、起業支援金800万円の請求書をX社宛てに発行し、X社は即時に請求額を支払った。
平成23年
1月〜3月
甲の新作業場で製作したOKくんの試作品をX社の技術研究所に持ち込み、耐久性、安全性等のテストを行い、3月末には上々のテスト結果が得られた。
4月
X社は、平成23年7月1日を独占販売契約開始日に指定した。
1月〜6月
甲は、新作業場の賃料、人件費及び機材購入費の請求書又は領収書を添付して、起業支援金500万円の請求書を毎月1回、月初めにX社宛てに発行し、X社は甲に対し、この半年間で合計3000万円の起業支援金を支払った。
6月
甲とX社は、X社をOKくんの独占販売代理店に任命する2年間の独占販売契約を締結した。甲は、新作業場では専ら製造原価引下げのための改良作業を行うこととしていたので、独占販売契約開始日以降の製造能力を確保するために、起業を応援してくれた叔父に恩返しをしたいということもあり、Yと、取りあえず1年間の製造委託契約を締結した。
7月1日
独占販売契約開始日。X社は甲に対し、平成23年6月30日時点の起業支援金未請求額1200万円を支払った。
7月〜
X社は、独占販売契約締結後速やかに、平成23年の敬老の日を発売開始日として、OKくんの予約キャンペーンを開始したところ、OKくんは爆発的なヒット商品となった。
甲に対する副賞のX社普通株式1000株は、X社側の必要手続や甲側の証券口座開設手続等いろいろな手続に時間が掛かり、結局、平成23年4月1日にX社から甲に引き渡された。なお、甲が表彰式においてX起業大賞目録を受け取った日である平成22年11月1日におけるX社普通株式の株価は、1株2万円であったが、その後急落し、甲がX社から同社普通株式1000株の引渡しを受けた日である平成23年4月1日の終値は、1株1万円であった。しかし、OKくんが爆発的なヒット商品となったことから、同年12月末には、1株3万円まで株価が上昇した。
以上の事案について、次の設問に答えなさい。ただし、租税特別措置法は考慮しないこととする。
〔設問1〕
あなたは、甲から、次に掲げるX起業大賞の賞金・賞品は、それぞれ、所得税法上、どの年に、幾らの金額が、いかなる種類の所得として取り扱われるかについて意見を求められた。あなたの意見を、理由を明らかにして述べなさい。
(1) 奨励金
(2) 起業支援金
(3) X社普通株式1000株
2.出題趣旨
個人所得課税においては所得の種類と所得の年度帰属の判断が必ず求められることは、法科大学院における租税法学習上の基本的な事項の一つである。設問1では、その基本を理解していることを前提に、問題文に示された一連の事実関係や契約内容を分析・評価し、法律の当てはめを行い、法人から支払を受けた個人の所得課税において必要となる所得の種類や所得の年度帰属などの判断をすることが求められている。
所得の種類については、脱サラした起業者が開業準備中又は開業初期に、起業中の事業に直結し得るコンペの賞金・賞品を受け取り、コンペをきっかけとして起業者が製造する商品の販売ルートを確保できることになる可能性のある契約も締結したという状況設定の中では、一般に論じられる事業所得と雑所得の違い(事業と事業に至らない程度の業務との違い)だけではなく、事業所得と一時所得の関係、一時所得と雑所得の関係を踏まえ、事実関係を的確に評価しての判断が求められる。この問題では、所得の種類についての基本ルールの理解に加えて、法律の適用上重要と考えられる事実を選り出して評価し、当てはめを行って結論を導き出すという判断のプロセスないし判断の理由を、いかに説得力をもって論述できるかが問われている。また、設問1では、問題文の中に支払の根拠となる契約文言が契約そのものの形で織り込んであることから、その支払(起業支援金)に係る所得に対する所得税法の適用を論ずる際には、まずはその支払の私法上の性質を契約解釈によって明らかにすることが所得税法適用の前提として求められる。
所得の年度帰属については、法人から個人への支払が複数年にまたがり、かつ場合によっては契約上条件付でなされるという設定であること、また、株式は「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」に該当することから、それらの収入計上時期につき、契約の内容や株式に対する会社法の規律という私法の理解と所得税法における権利確定主義の理解という双方の理解を踏まえた分析に基づく判断が求められる。
3.採点実感等
主要な論点と求められる能力は、「出題の趣旨」に記載したとおりである。採点に当たっては、基本的なルールの説明に対しても一定の基礎点を与えたが、より多くの点数について当てはめで評価した。当てはめについては、結論によって差を付けるのではなく、問題文に記載されている契約内容の解釈とそれに基づく支払の性質の理解、株式に関する法律関係の理解、事実摘示と事実評価の適切さ、所得税法の基本ルールの当てはめにおいて法律の適用順序に誤りはなく、論証の論理性に問題はないか、という観点から見て、その結論を導き出す論証の部分にどれほどの説得力があるかという論証の質を重視した。
設問1(所得税法関係)の主たる論点である所得の種類については、それぞれの所得の種類の意義に関する基本的な理解(いわば基本ルール)に関する限り、「一応の水準」以上の答案が大部分であり、「良好」以上の答案も多かった。これに対して、事実や契約の分析とそれを踏まえた法律の当てはめの部分の論述では、問題文中に記載されている契約の内容や支払の法的性質の分析を曖昧にしたまま結論だけを述べるものや、問題文に記載されている情報のごく一部にだけ焦点を当て、事実評価を誤った結果妥当性を欠く結論に至っているものが相当数あった。出題の趣旨で言及した所得の種類以外にも給与所得、譲渡所得まで検討対象を広げている答案も多かった。そのこと自体は全く問題ないが、この問題のような脱サラ、起業という状況設定及び起業支援契約の契約内容からは、給与所得や譲渡所得に該当するという結論に至る可能性はないと言ってよいことを考えると、時間の配分を考えて検討にメリハリを付けるという判断も必要である。
なお、契約に基づく支払の所得分類の判断においては、納税者(甲)の活動の態様を観察して、事業所得を生じる事業と言える程度の活動をしているかを判断することも重要であるが、支払の根拠となる契約を解釈してその支払が何の対価であるかを分析することも同じように重要である。前者については、丁寧に書けている答案も少なくなかったが、後者の観点から契約内容の分析がしっかりできている答案は、期待していたよりも少なかった。課税対象となる取引・契約の内容やそれらの法的性質を理解することと租税法のルールを正しく理解することは、課税上の判断の基礎となる車の両輪であるから、採点においては、そのことを考慮して点数を付与した。
所得の年度帰属については、所得税法第36条第1項、第2項の基本ルールの一般的説明に関する限り、おおむね良好といえる答案が多数であった。具体的な当てはめにおいては、起業支援金については契約上支払が条件にかかっていることを指摘し、契約の内容を理解して当てはめるというプロセスがきちんと書けている答案も多かったが、株式については、合意の成立時期だけを考慮することで足りるのか、会社法に定められている株式の権利移転の手続き及び効力要件に関する規律を所得税法上の所得の実現と関連付けて考える必要はないかなどの検討も必要と思われるところ、その点まで踏み込んでよく考えられた答案はあったものの多くはなかった。
4.解答例
設問1小問⑴について
1.奨励金を何年の所得として取り扱うべきか。「その年において収入すべき金額」(所得税法36条1項)の意義が問題となる。
「その年において収入すべき金額」とは、現実の収入がなくても、その年に収入の原因たる権利が確定的に発生した金額のことと考える(権利確定主義・雑所得貸倒分不当利得返還請求事件判決)。
これは、常に現実収入のときまで課税できないとしたのでは、納税者の恣意を許し、課税の公平を維持できないので、徴税政策上の技術的見地から、収入すべき権利の確定したときをとらえて課税することとしたものである。また、同項は「収入した金額」と規定していないこととも整合する。
甲は、小問⑴の奨励金500万円は、X起業大賞に応募し、選考の結果、最優秀者に選ばれて授与されたものである。このため、平成22年11月1日に奨励金を授与された時点で、奨励金を受け取る権利は確定的に発生していると考えられる。したがって、奨励金は、平成22年分の所得として取り扱われるべきである。
2.そして、奨励金500万円の金銭の支払いにより給付されているため、収入金額は500万円とする(同項)。
3.奨励金の所得区分を検討する。甲は、X社の公募した「X起業大賞」に応募し、その「OKくん起業企画書」が優秀と認められ、奨励金を授与された。
甲は、退職金100万円と叔父からの借金300万円を使って、自己の計算と危険により、OKくんの開発に勤しんだが、「X起業大賞」への応募は、継続的に行う経済活動とはいえない。このため、事業所得(同法27条1項)にはあたらないと考える。
そして、甲とX社との間には雇用契約等の契約関係はなく、奨励金は、従属的な地位での非独立的な役務提供の対価ではないため、給与所得(同法28条1項)にもあたらない。
雑所得以外のその他の所得に該当しないところ、前述のとおり、反復継続した経済活動からの所得ではなく、かつ、労務提供の対価でもなく、さらに、資産の譲渡の対価でもないことから、一時所得(同法34条1項)に該当すると考える。
設問1小問⑵について
1.起業支援金は、何年の所得と扱うべきか。
⑴ 起業支援契約1条によると、受賞した企画に基づいて起業するための費用を補てんする性質のものであり、支払の条件として、甲からX社に対し、費用に係る請求書又は領収書を提出することとされている。このため、起業支援金を受け取る権利が確定したのは、起業支援契約を締結した平成22年11月1日ではなく、費用に係る請求書等を甲からX社に提出した日と考える。したがって、起業支援金のうち、800万円は平成22年分、3000万円は平成23年分の所得として取り扱われるべきである。
⑵ また、起業支援契約3条①と2条によると、本件のように、独占販売契約開始日がX社により指定されると、5000万円のうち独占販売契約開始日までに支払われていない部分は、同日に、支払われる。起業支援金の残額は、同日に、権利が確定的に発生するものと考える。したがって、起業支援金の残額1200万円は平成23年分の所得として取り扱われるべきである。
2.起業支援金は、いずれも金銭で支払われているので、受領した金額で評価されるべきである(同法36条1項)。
3.甲は、「X起業大賞」を受賞した、平成22年11月以降、「OKくん」の製造・販売に向けて、作業場の賃借、アルバイトの雇用、試作品の製作を開始し、量産のための製造委託契約の締結、予約キャンペーンの開始等の従事している。これら一連の開業準備行為は、自己の計算と危険において営利を目的とし対価を得て継続的に行う経済活動といえ、それに関する所得は、事業所得に区分されるべきである。そして、起業支援金は、開業準備行為を支援する目的で支給される金銭であり、その活動に関連する収入であるといえ、事業所得に区分されるべきである。
設問1小問⑶について
1.X社普通株式1000株は何年の所得と扱うべきか。
X社は、平成22年11月1日に、甲に普通株式を授与することを約束している。このため、同日、甲はX社に対し普通株式を請求する権利を有しているとも思われる。
しかし、X社の普通株式を甲に授与するためには、会社法上の手続が必要となる(会社法199条、201条など)。また、X社は上場会社であるため、その普通株式は、振替株式であり、甲の証券口座に記録されることによって、甲は、初めて、権利を取得する。このため、上述の権利が確定的に発生したと認められるのは、普通株式が、甲に引き渡された平成23年4月1日であると考える。したがって、X社普通株式1000株は平成23年分の所得と扱うべきである。
2.X社普通株式1000株の収入金額は、収入のあった日(平成23年4月1日)を、その経済的利益を享受した日として、その日の時価を基礎に算出し、1000万円となる(同法36条2項)。
3.X社普通株式1000株の所得区分であるが、奨励金と同様に支給されているため、奨励金と同じ理由から、一時所得に区分すべきであると考える(同法34条1項)。
5.ケースブック租税法〔第6版〕との関係
所得区分、収入金額の評価、収入金額の帰属年度を、複数項目に分けて尋ねる、総合問題のように思えた。別問題で勉強してきたことを前提に、シンプルに解答例を作成してみたが、それなりの分量になってしまった。小問⑴、⑵、⑶に分けて検討するのか、帰属年度、評価、所得区分に分けて検討するのか、悩んだが、採点者は、小問に従った方が、採点しやすいであろうと思い、前者の手順で検討を加えてみた。これまで検討した司法試験の問題のなかで、難しいほうの問題なのではないかと思った。
いいなと思ったら応援しよう!

