
渡米76〜88日目 映画と絆とフルブライト・プレゼンテーション
2023年11月6日(月)〜11月18日(土)
前回の更新以来、二週間ぶりの更新となる。この二週間はしつこい咳に悩まされながらも、学業に専念し、沢山の撮影経験を積み、仲間との絆をより深めることができた時間だった。
サマータイムが11月5日に終わって以来、ボストンの秋も一気に深まり、日没が1時間早くなり、夕方の4時を過ぎると薄暗く、5時にはすっかり夜になる。日本との時差もマイナス13時間から14時間に広がった。

▼「撮影監督」を引き受ける
この二週間の中でまず一番の収穫といえば、映画を撮る具体的な経験ができるようになってきたことだ。監督クラスでは、この秋学期にそれぞれの生徒が、実在する映画のワンシーンを監督することになっているが、クラスメイトの一人であるRuiに頼まれて、彼女の監督作のDP(Director of Photography・撮影監督)を引き受けた。撮影機材のシネマカメラCanon C70にはこれまでほとんど触れたことがなく、あまり馴染みがなかったのだが、撮影テストや実際の撮影を通じて、この新しいカメラにかなり馴染むことができ、体の一部のような存在になりつつある。
撮影はドキュメンタリーの撮影とは異なり、プロの俳優に加えて、監督、プロデューサー、撮影監督、録音、照明とそれなりの大所帯にな利、チームワークとコラボレーションが求められる。11月11日(土)、自宅からも程近いブルックラインのある公園の一角で撮影が行われたた。当日は天候にも恵まれ、気温は3度から5度前後とかなり肌寒いものの、紅葉に染まる公園で、
カンヌやサンダンスで数々の受賞をしたサスペンス映画「Martha Marcy May Marlene(邦題マーサ、あるいはマーシー・メイ」のワンシーンを撮影した。紅葉が一番美しい季節に、被写界深度の極めて浅いレンズを駆使してとても美しく、ミステリアスなシーンを撮影することができた。
この撮影を通じて、仲間との絆もまた一段と深まった。監督を務めたRuiは僕が撮った映像にとても感動してくれて、次に控える僕の監督作の助監督を快く引き受けてくれることになった。彼女は中国の北京フィルムアカデミー(Beijing Film Academy / 北京電影学院)という合格率1パーセントのアジア最大の最難関の映画大学を卒業した秀才。シャイな性格で普段クラスではほとんど発言しないものの、一緒に仕事をしてみるととても責任感が強く、細部にまで気を配ることができるとても思いやりに溢れた人物であることがわかってきた。

▼監督作のリハーサルに向けて
僕が実際に自分のワンシーンの監督を務めるのは12月2日(土)でまだ少し先ではあるが、来週にはサンクスギビングが控えていてアメリカはまるでお正月のようなムードになる。この時期、大学も休みとなりほどんど何も機能しなくなるため、今週中にリハーサルを行うことになった。
しかし、リハーサルに何をすればいいのか。これまで実際にプロの現場で監督を務めたことがない僕には、具体的なプランが明確に思い浮かばなかった。Ruiに相談してみてところ、彼女は自分の監督作用に彼女が準備したプランを参考に僕に送ってくれて、リハ前日には4時間近い時間を割いて、辛抱強く割いて準備に付き合ってくれた。
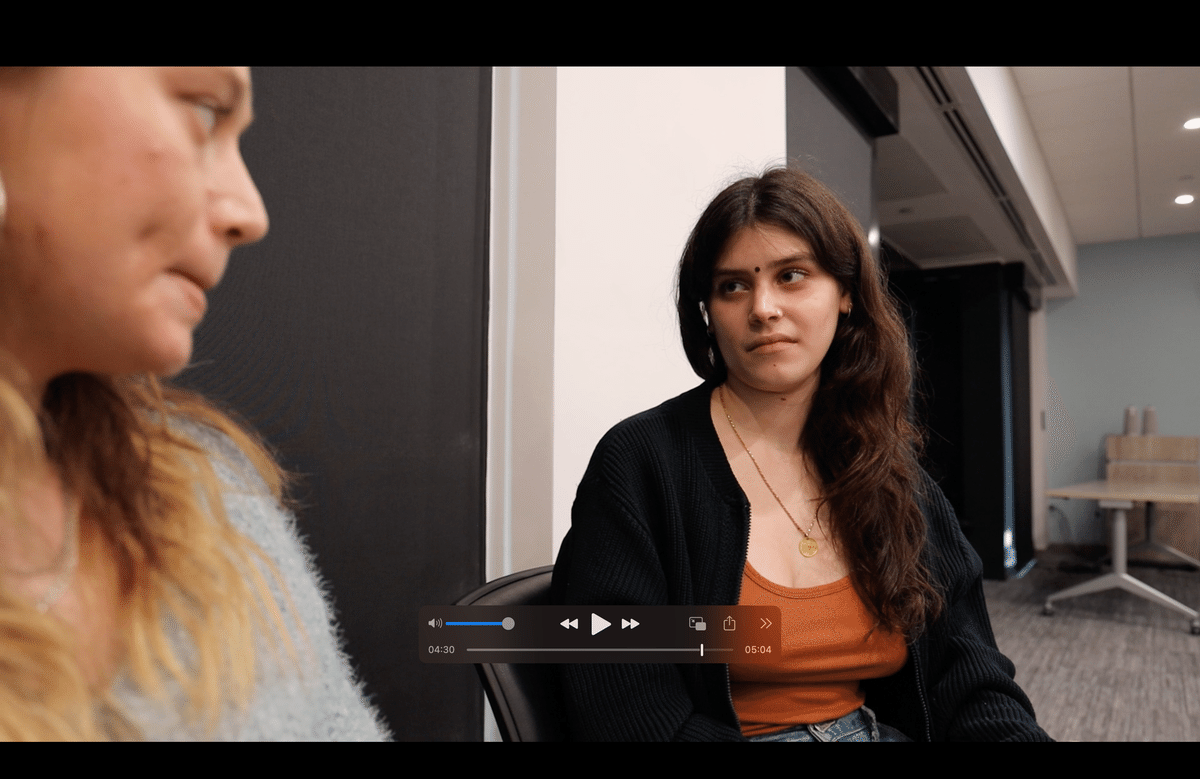
そして迎えた昨日(11/18)のリハーサル。映画「Pariah」の主役Alikeと友達Binaのキスシーンが控えているこのデリケートなシーンの撮影に向けて、出演者のMischaとKallieをエマーソンに招き、Ruiを含む主要スタッフとリハーサルを行った。ただ実際にシーンをリハーサルするだけでなく、このシーンに至る映画全体の背景やそれぞれのセリフの奥に隠された言外の意味(Subtext)などについて監督としての意図を説明しつつ、俳優たちとディスカションした。彼女たちもとても辛抱強く、監督の僕の意見に耳を傾けてくれて、その後、実際のリハーサルへと進んだ。
「やはりこの映画には、絶対にこのキスシーンが必要ね」
4時間近いリハーサルが終わりに差し掛かる頃、Bina役のKallienがそう口にした。実は主役のAlike役を引き受けてくれたMischaがエマーソン大学の俳優学科の学生ではあるものの、まだ未成年に当たる17歳であることもあり、キスシーンには法律的な規定も伴うため、キスシーンを頬に触れるだけにするかもしれないという選択肢も僕たちには残されていた。しかし、リハーサルを進める中で、やはり二人の関係性のドラマを体現するのには、キスシーンが欠かせないという結論に役者自身が達した。それはまさにその場にいた皆の共通認識だった。
僕はついにこのシーンで自分が求めている二人の関係性を俳優が見事に表現する準備が整ったことを実感することができた。リハーサルには、助監督のRuiに加えて、プロデューサー役を引き受けてくれるこになったMajaや照明役のJerryも朝早くから駆けつけてくれて、惜しみないフィードバックをくれた。皆、映画が撮りたくてここにきたのだ。ようやく具体的に映画を形にしていくときが訪れて、その作業を繰り返す中で、お互いがお互いを知り、結束が強くなりつつあるのを感じている。

▼「フルブライト・プレゼンテーション」
また、先週は一週間、大学でインターナショナルフェアが行われていて、大学からフルブライターとしてプレゼンテーションを依頼された。これまで母校で大学生向けに特別講義を何度か引き受けたことがあるものの、英語でのプレゼンテーションにはあまり自信がない。英語でパワーポイントを作るのも未経験の領域だ。
手ぶらで参加してもうまくいくはずはなく、準備を怠るわけにはいかない。毎週水曜日に留学生向けのプレゼンテーションのクラスに参加しているため、その機会を利用して、まず11月8日(水)に40分のプレゼンテーションを行った。
「タカヤのフルブライトを巡る物語には、山あり谷ありの人生そのものが含まれている。まさに映画そのものだ。だから、もっとそこをストーリーテラーとしてうまく伝えられればすごくいいプレゼンになるはず」
まだ準備を始めたばかりで結果はボロボロだったが、クラスメイトのジェリーがそう言ってくれた。ジェリーはやはり中国出身で、まだ大学を出たばかりの22歳の青年。だが、彼にはプレゼンとジョークの天才的な才能がある。子供の頃から中国の伝統楽器を習っていてテレビに出演していて、ディベートが大好きで話術にも長けているので、子役としても引っ張りだこだったのだという。
そこからジェリーとの特訓が始まった。11月10日(金)は「退役軍人の日」で祝日だったが、一緒にランチをした後で、2時間ほど時間を割いて練習に付き合ってくれた。プレゼンで与えられる時間は15分。これまでの人生で2度、フルブライト奨学金を得て米国で学ぶを得た僕としては、フルブライトがいかに人物交流や次世代リーダーの育成に重きを置いていているか。20代の頃にフルブライトに挑戦するに至った経緯や、厳しいNYUやNHKでジャーナリストとして成長した経験、30代の後半に網膜の難病が進行し一時は全てが終わったと絶望したこと、そうした中で大林監督に出会い、心の目を磨くことの大切さや映画の力に限りない可能性を感じるようになったこと。そしてエマーソンで何を学び、フルブライターとして最終的に何を目指すのかなど、一つの物語としてプレゼンするための周到な準備を進めた。
僕は難病で視力を失いつつありある種絶望的な状況にあるし、フルブライト奨学金を得るまでにも3度挑戦している。人生は楽じゃない。でもそれぞれのステージで学ぶべきことがあり、そして今に至っている。
「タカヤは人生はそのものが映画。脚本と同じように、人生の絶頂と絶望、それに負けずに立ち上がる姿を伝えられれば、絶対みんなの心を打つ。そしてジョークを忘れずに!」
ジェリーが時間を測り、動画を記録してくれて、それを見直しながら何度も練習する中で僕もこのプレゼンの流れが掴めてきて、ジョークを交える余裕さえも生まれてきた。
そして迎えた今週11月14日(火)のプレゼン。音盤当日、学食の隣になるプライベートダイニングホールで行われたプレゼンには、脚本クラス(Writing Short Subject)のオーエン、映像音響クラス(Fiction Film Direting)のデイビッドなど、今学期履修しているクラスの教授も駆けつけてくれた。
「皆さん、この写真。なんでこんなに髪が短いかわかりますか?」
(沖縄に赴任していた当時の丸坊主の僕の写真などを見せながら)
「報道の仕事では24時間365日、事件や事故が起これば、例え真夜中でも現場に駆けつけることが求められます。だから髪を洗っている時間がない。だから当時は常に髪を短くしていました」
ビターな人生の体験を含んだシリアスなプレゼンの途中途中でちょっとしたジョークを取り入れると、ドッと笑いが巻き起こる。プレゼンは20分近くに及んだが、終了後、熱い拍手のシャワーが鳴り止まなかった。
「あたなの物語に心を打たれました!」
その後、大学のキャンパスを歩いていると不意に声をかけられて、知っている人からも知らない人からも何度かそのように言われ、プレゼンが心に響くものであったことを実感した。改めて、今回のプレゼンを支えてくれたジェリーや仲間に感謝した。この経験を活かして、いつかTEDでもプレゼンしてみたい。

▼ついにナンバープレートをゲット!
10月下旬に中古でプリウスを購入したものの、その後保険への加入などが必要とあり、その手続きに時間がかかってまだ車両登録ができていなかった。車両登録を管轄するRMV(Massachusetts Registry of Motor Vehicles)は、その登録に長蛇の列ができ、登録には半日近い時間を要し、書類の不備があると突き返されるととても悪名が高く、そのための時間をなかなか見つけられずにいた。11月16日(木)、子ども達を学校に見送った足でそのまま大学から程近いハイマート駅近くにあるRMVへと向かった。僕たちが9時前に到着して間も無く、後ろには長蛇の列が出来始めたが、すぐに呼び出しがあり、(担当者の対応がとても横柄でとても気分が悪かったことを除けば、)幸いにも1時間ほどで念願のナンバープレートを手にすることが出来た。
こちらにきて間も無く3ヶ月。やはり車がないことでの生活の不便さをずっと感じてきていたので、これでようやく生活も少しは楽になり、家族で週末に出かける楽しみも増えるだろう。帰宅した次男が自らドライバーを手に、ナンバープレートを車に取り付けた。驚くほど、大きく目を見開いて。その姿を見て、僕は心から嬉しく感じた。

▼息子からの手街
次男をその夕方、強豪水泳チーム・ドルフィンズの練習に連れていき帰宅すると、ずっと用意していたという手紙を渡してくれた。
「いつも、学校に送ってくれてありがとう。
Emerson大学のおべんきょうがんばってね。
木とか、電ちゅうにぶつからないようにがんばってね」
そして、カメラの絵とともに最後にこんな言葉が書き添えられていた。
「がんばって、すごいえいが作ってね」
折紙で作った手裏剣が入った、9歳になったばかりの次男がくれた手紙。まさに僕の宝物だ。心の中で目頭が熱くなるのを感じた。

▼バークリー音楽大学とゴーストムービー映像と音響制作クラス(Foundation of Image and Sound Production)の課題で、ここ二週間ほど「音楽とボストン」をテーマに、バークリー音楽大学の学生たちを仲間とシネマカメラで記録し続けてきた。その中で、僕は一つのショートムービーのアイデアを思いついた。それはレコーディングスタジオに宿るゴーストの話だ。
多くの世界的な音楽家を輩出してきたバークリーには大小無数のレコーディングスタジオがある。夢を叶えた者もいれば、夢に敗れここを去っていった者もいる。それぞれのスタジオには人生の頂点や後悔、希望と絶望、血と涙と汗が染み込んでいて、いつしかそこにゴーストが宿るようになったという奇妙な話だ。
Foundationクラスでは、学期の最後に一つの短編映画を手がけることができ、そのアイデアを共有したところ、担当教授のデイビッドも、バークリーの仲間もとても共感してくれて、深夜にスタジオを借りて11月27日(月)の深夜に撮影をさせてもらうことになった。さらにゴーストに遭遇する俳優が歌う音楽も、仲良くなったグロリアに作曲してもらうことになった。彼女は詩が苦手だというので、僕が英語で作詞をする。
英語で歌詞を書くのも、そして、ホラー映画を撮るのも初めての経験だ。「人を怖がらせる」のには映像と音響の高い技術が要求される。Foundationクラスの最終課題にDirectingクラスで監督した短編を提出することもできたが、それではもったいない。未知の領域に挑戦する。その過程の中でこそ、僕たちは成長する。

▼来週、ニューヨークへ
来週11/23(木)はサンクスギビング(感謝祭)の祝日。それに合わせて、大学も週後半は休みとなり、街はまるでクリスマスとお正月を合わせたようなお祭りモードになる。
「サンクスギビングに、ぜひニューヨークに遊びにきなさい」
ニューヨーク大学時代の担当教授のMarciaがそう声をかけてくれて、家にも泊めてもらえることになった。MarciaはNYU時代の最大の恩師で、とても厳しく、そして愛情を持って僕たちを育ててくれた。今回の留学に際しても、フルブライトを始め、大学院に何度も惜しみなく推薦状を書いてくれて、フルブライトの奨学金の面接の前などにはzoomで模擬面接までしてくれた。まだこちらに来てから一度も会えていない。お礼も兼ねて、ニューヨークを訪れたいと思っていた矢先の申し出がとてもありがたかった。
「英語も話せないし、ニューヨークに行きたくない」
だが先週、子供達がそう言っていると妻からそう知らされた。ニューヨークでホテルに泊まるならまだしも、英語もわからない中で、Marciaの家でお世話になっても窮屈な思いをするだけだと感じているという。正直、とても悲しい気持ちになった。だが、彼らがそう感じるもの最もかもしれない。仕方がないかとも思った。
「サンクスギビングの具体的な予定は?」
今週、Marciaから短いメールが届き、僕は率直に家族の状況を共有した。するとそういったことも顧慮して、実は僕たち家族が泊まれるように、今使っていないMarciaのワンベッドルームの部屋を用意してくれていたことがわかった。
「私のマンションは、NYUにも近くて、タカヤがよくライブをしていたヴィレッジのカフェの近くにあるわよ」
「カフェ・ビバルディ!!懐かしい」
「様々な思い出の扉が開きそうね。子どもたちにニューヨークを見せてあげなさい。好きなだけ泊まっていくといいわよ」
サンクスギビングの詳細についてMarciaに電話すると、懐かしさが込み上げてきて胸が熱くなった。直接Marciaに会うのは、2011年に出張でニューヨークを訪れて以来もう12年ぶり。Marciaに出会っていなければ、今の僕はいなかった。彼女はまさに僕をジャーナリストとして最初に厳しく育ててくれた「母」のような存在だ。
サンクスギビングにあたる11月23日は、8月23日にボストンに渡米して以来、ちょうど3ヶ月の節目にあたる。ニューヨークで何を感じるのか。懐かしさと真新しさに胸が躍る。
書いたのは202311190743-1128-1228
