子育て支援金は「負担」なのか
みなさん、こんにちは!年金界の野次馬こと、公的年金保険のミカタです。久しぶりの投稿ですが、今回は子育て支援金を取り上げます。
いよいよ、子育て費用の社会化の財源として、国会でも審議がはじまり、「子育て支援金の負担は月500円」と岸田首相が国会で答弁したことで、この負担額についての報道や情報発信が目立つようになりました。
子育て支援は投資である
下のYoutubeは、国民民主党の玉木代表が情報発信をしている「たまきちゃんねる」で、子育て支援金を取り上げたものです。
このタイトルから分かる通り、玉木氏は、現役世代の負担は月500円ではすまず、もっと高くなるということを訴えています。それが、いくらになるのかということは、あとで触れるとして、動画の初めに以下のように話していることに注目して欲しいのです。
「子ども・子育て・教育・科学技術は教育国債でやったらいい。投資なので、リターンがあるから(財源は教育国債で)いい。」
子ども・子育て支援は、日本の未来のための投資であるということに異論はありません。
国民と企業が連帯して負担する支援金は、子育て世帯に給付されます。そして、子育ての社会化が進むことによって少子化に歯止めがかかれば、日本の将来の経済成長につながることが期待されます。
そうであれば、支援金は単なる「負担」ではなく、子育て世帯に「給付」されるものであり、それが将来の経済成長につながる「投資」ということになります。
それなのに、その財源が自らが主張する国債ではなく、国民から広く集める支援金になると、これを「負担」と呼ぶのが理解できません。
つぎに支援金の金額について、岸田首相が国会で答弁した「1人あたり月500円」を意味のない数字と言い、被用者保険に加入する現役世代が拠出する支援金を制度ごとに試算したものを示しています。

・協会けんぽ・・・年間12,300円
・健保組合・・・・年間17,644円
・共済組合・・・・年間19,644円
これは、被保険者1人あたりの平均なので、高所得者はこれよりも高くなるでしょうし、低所得者は逆に低くなります。
先程述べたように、子育て支援は投資ですから、これだけの投資ができることについて、もっとポジティブに考えることはできないのでしょうか。
NISAの投資枠が年間360万円に拡大されたことは歓迎されているのに、子育て支援の投資枠が年間2万円となったことについては、負担が増えると批判するのは、なんか残念ですね。
NISAでインデックス投資を年間120万円するのと同じか、それ以上の投資の意義が支援金にはあると思います。
子育て支援金は医療保険の流用ではない
次に、支援金は医療保険制度の保険料徴収のしくみを利用して徴収されることを「医療保険に上乗せ」とか「健康保険料の目的外使用」といって批判していますがこれも的外れです。
介護保険も医療保険とは別の社会保険制度ですが、医療保険料と合わせて徴収されていても、これを目的外使用と呼ばないでしょう。
厚生年金保険と合わせて徴収され、児童手当などの財源に充てられる子ども・子育て拠出金も同様です。
こども未来戦略会議でも、権丈先生は以下のような発言をして、支援金を医療保険料の上乗せとか流用と言って批判することについて釘を刺しています。
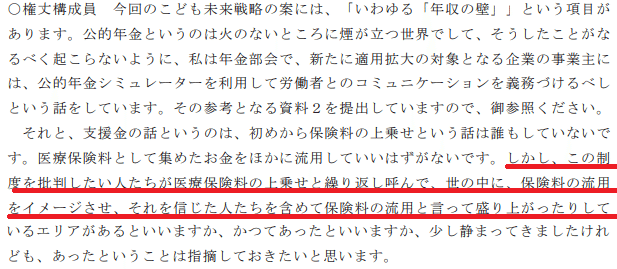
「実質的な負担なし」というまやかしができた理由
そして、もう1つ動画のホワイトボードに書かれている「『実質的な負担なし』はごまかし」という批判もこれまた的外れです。
そもそも、この「実質的な負担なし」というのは、どういう経緯で出てきたのか、見てみましょう。
こども未来戦略会議において、子育て支援の財源の議論をしている中で、経済界からは、医療保険料の徴収ルートを利用する支援金制度は企業負担が生じるため、これに対して警戒する姿勢が見られました。
財源の議論が本格的に始まった、第3回こども未来戦略会議では、経済界を代表する委員から、まず「歳出の改革」を行うべきという意見が相次ぎました。
小林 健( 日本商工会議所)
最後に、財源については、社会全体で支えることが大前提であります。第1に高齢者偏重の社会保障給付を含む徹底的な歳出の改革、第2に投資拡大や賃上げモメンタムの継続による経済の好循環実現に伴う歳入増を基本とすべきと考えます。その上で、不足する財源については、タイミングも含めてあらゆる選択肢を検討し、中小企業でも取り組んでいる賃上げ努力に水を差さず、国民の理解が得られる形で賄うこととすべきだと思料いたし ます
武田洋子 (三菱総合研究所)
2点目は、歳出改革についてです。今後、財源の議論が進められると理解しておりますが、その際には、総理の国会答弁にもございましたとおり、まずは徹底した歳出改革が大前提と考えます。特に医療・介護分野については、全世代型社会保障構築会議の報告書に記載されました歳出の適正化・効率化を進めていく必要がございます。
十倉雅和 (日本経済団体連合会)
また、対策に必要な財源については、今は日本経済のダイナミズムを取り戻す重要な時期であり、負担を求めるタイミングは慎重に考えるべきです。したがいまして、まずは政府自ら給付と負担の徹底的な見直しを通じた歳出改革等により、財源確保に最大限に取り組むべきであります。
新浪剛史 (サントリーHD)
その中で、高齢化の進展に伴って、大変今後とも増えていくと思われる社会保障費について、デジタルをもっと活用し、イノベーションや技術革新の適用などのための規制改革を含めた、医療介護分野の歳出改革をやらないといけないのではないかと思います。ぜひこの辺りをやらないと、若い世代にとって社会保障のトータルの保険料が本当に負担感になってくるのではないかという危惧を大変しております。そういう歳出改革の議論をされないまま、国民に対する追加負担を議論するのには大変違和感を覚えております。
そして、第4回の戦略会議では、下の資料の2ー①で「徹底した歳出の見直しを行うことによって公費財源の確保や保険料負担の抑制を最大限図るべきではないか」という文章が出て、

最終報告書には以下のように記されました。
歳出改革等による公費節減と社会保険負担軽減の効果を活用することによって、実質的な負担が生じることなく、少子化対策を進める。少子化対策の財源確保のための消費税を含めた新たな税負担は考えない。
一方、子育て支援の財源を検討する際のキーワードとなる「全世代型社会保障」の考え方は、社会保障制度改革国民会議の報告書に以下のように書かれています。
全世代型の社会保障への転換は、世代間の財源の取り合いをするのではなく、それぞれに必要な財源を確保することによって達成を図っていく必要があるものである。
もちろん、歳出(給付)の見直しは常に必要ですが、子育て支援の財源確保を高齢者の給付削減とセットにして行うことは、全世代型社会保障の本来の考え方から外れたものであるということです。
このような形になってしまったのは、負担増を避けたい企業側の言い分と、社会保険料が現役世代の負担となっているとキャンペーンを張っている野党(特に統一地方選で勢いのあった日本維新の会)に対して、官邸が日和ってしまった結果です。
それに対して、野党がイチャモンつけるのは、何かおかしくないかと思うのですが。。。。
社会保険料のせいで手取り収入が増えないのか?
ところで、野党が主張するように、現役世代の社会保険料の負担が重く、手取り収入が増えない原因となっているのでしょうか。
下の記事は、小黒一正教授(法政大学)が書いたもので、やはり社会保険料の負担が重いということを述べているものですが、記事で使われているグラフが面白いので紹介します。
下のグラフは、記事で使われているもので、家計調査(勤労者世帯二人以上)のデータを用いて、収入、税、社会保険料が2000年から2022年の間でどのくらい変化したかを表しています。

これを見ると、収入の伸びに対して、社会保険料の伸びが大きく上回っていて、やはり社会保険料負担の増加によって手取り収入が増えないのだなと思うかもしれません、
しかし、下のグラフを見てください。同じ家計調査のデータを使用して、それぞれの項目の実際の金額の推移を表したものです。

どうでしょうか?社会保険料はこちらのグラフでも20年間で1.4倍になっていますが、そのせいで手取り収入が増えないと言えるでしょうか。
手取り収入が増えないのは、社会保険料負担が増えているからではなく、元の給料が増えていないからです。ここでも、野党(と小黒先生)の社会保険料に対する批判が的外れであることが分かりますね。
これから子育て支援金の国会審議の動向を注目していきたいと思います。
それでは、皆さんごきげんよう!
