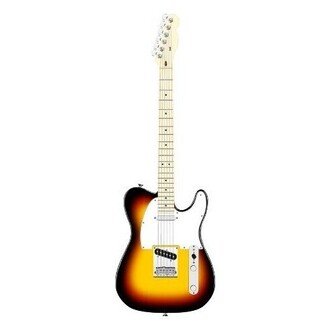「就活」は「終活」の始まり:26卒が考える「働くこと/生きること」と「死ぬこと」
はじめに
2025年1月末、筆者はとある企業に内定受諾の意を伝え——2月初旬には誓約書も提出し——、2026年4月入社の学生としての就職活動を終了した。
筆者はいわゆる「早期選考」の波に乗ることができ、内定受諾をした会社からの内定通知は12月下旬に受け取っていた。
また、別の会社からも12月下旬に内定通知をいただいており、それからおよそ1ヶ月をかけて、面談や自力での情報収集などを重ね、最終的に内定を受諾する1社を決めていった。
内定をいただいていた2社は、どちらを選んでも自分の納得のいくキャリアプランを描けそうであったため、片方に辞退の連絡を入れる際には断腸の思いであった。
正直なところ、自分自身が早期選考の波に乗れるとは思っておらず、かなり順調に就職活動が進んでいったな、というのが実感である。
文系大学院生という、周囲よりハンディがある——日本の社会システム上、とくに文系の大学院生は学位に見合った評価を受けているとは言い難い——ということを念頭に置き、2024年の1月ごろより徐々に就職活動を始めていったことが功を奏したのかもしれない。
また、就職活動にあたっては終活エージェントの方に併走していただき、自身のキャリアプランや終活軸の言語化、面接練習などさまざまな面でサポートいただいた。
その中で、「おじいちゃんになったとき、どういう生き方をしていたいか」という視点でキャリアプランや企業選びをしてはどうか——担当者が「おじいちゃん」ということばを使用したのは、筆者が、性自認・身体的特徴ともに男性であるためだと思われる——、というアドバイスをいただいた。
そのときふと感じたのが、本noteのタイトルでもある「就活」は「終活」の始まり——つまり、就活と終活には近接性がある——ということだった。
「どう生きるか」=「どう老いていくか/死ぬのか」
就職活動を始める最初のステップとして、自分の強みや弱み、興味関心のある分野などを明らかにしていく「自己分析」の存在があるだろう。
自分の考え方・感じ方・ものの見方などを深く掘り下げていく——「棚卸し」とも呼ばれるだろう——ことで、志望業界や志望職種を絞り込み、あるいは就職活動の軸や判断基準といったものを設定することができる。
自身の就職活動の方向性を見定める上で、自己分析はまさにはじめの一歩なのである。
また、中長期的なスパンで自分のライフイベントやキャリアを見通しながら、将来なりたい自己像をイメージする「キャリアデザイン」という観点からの業界・業種・会社規模などの絞り込みも、終活ノウハウのひとつとして言及されることがある。
これらの取り組みの根幹にあるのは、つまるところ「私はどう生きるか/生きたいか」という問いである。
昇進・昇給・転職・結婚・子育て・高齢になった両親への対応など、さまざまなライフイベントを念頭に置き、それらに対してどういうスタンスを取る(取りたいか)を考えていくことは、自分がこれまでの人生で(無意識に)確立してきた価値観や行動・価値判断基準といったものを整理し、言語化する機会になる。
そして、自分の生き方=キャリアの最適解を発見したり、それを実現していくための手段のひとつとして、就職という選択肢が——このほかにも、企業、海外移住など多様な選択肢もあろう——ある。
*もちろん、VUCAの時代と呼ばれる現代社会において、このタイミングで設定したキャリアプランが順調に描ける、という保証はどこにもない。
自身のキャリアプランを動態的なものだと考えた上で、状況に応じて柔軟に思考し、キャリアプランの変更などをしていく必要がある。
ところで、社会人という新たな社会的身分の「始め方」を考えるのが就活であれば、社会的存在としての自分の「終わり方」を考えるのが「終活」である。
終活とは、主に高齢者が自らの死に備える動きのことであり、このことばは、2009年の『週刊朝日』での連載記事において初めて登場したとされる[木村・安藤 2018:1]。
遺された親族が困らないよう、身辺整理や口座などの情報、延命治療の希望有無をまとめておくことが一般的な手順のようである。
こう聞くと、自らの老いを実感した高齢者だけを対象にしているようにも思えるが、終活において「死」がどう語られているのか/いないのかに着目すると、就活との類似性が見えてくる。
すなわち、終活においては「死」よりもむしろ「生」が強調される、という点である。
テキストマイニングの手法を用いてマスメディアの終活の捉え方を分析した木村由香と安藤孝敏によれば、終活に言及した記事などには、死についての考え方や価値観を掘り下げるような内容が少ない。むしろ、「今をよりよく自分らしく生きる活動」などと、「生」の側面が取り上げられる場合が多いという[木村・安藤 2018:16]。
先に提示した3つのWebページでも、終活の目的として「これからの自分として充実した人生を送る」、「残された時間を有意義に過ごす」、「残りの人生をどのように生きるかを前向きに考え、老後の生活を豊かにする」といった記述を確認できた。
身辺整理や遺言書の作成、看取られ方の希望を書くことなど、終活における諸活動の基盤には、就活と同じように「人生の棚卸し」があるはずだ。
自分の築き上げてきた人生や財産、家庭などのあり方は、程度の差はあれ自分の価値観や生き方の軸を反映した/しようとしたものであるだろう。それに気づき、「自分らしい最期」を迎えるためにどうするか・どうしてほしいかを考えていく。
そうした一連のプロセスは、この先の人生を見通し、現時点での自身のキャリアプランを設計し、それに対応した企業選択等をおこなっていく就職活動と、根源的な部分では同じなのではないか。
さらにいえば、1日1日を生きることは、いつか訪れる「死」に、確実に近づいていくということでもある。
生と死は互いに単独では成立し得ず、他方の存在があって初めて意味をもつ。その点で、就活はある程度終活に重なるのではないか。
終わりに
就活は、「この先のキャリアプランをどうしていくか」を考える営みであり、終活は、「どういう最期を迎えたいか=残された生をどうしていくか」を考える営みである。
両者とも、「生」が強調される——これから先を考える就活と、残された時間を考える終活、という違いはあるにせよ——という点では共通点をもつ。
さらに、自身の描いたキャリアプランを達成すべく、1日1日を生きていくことは、とりもなおさず1日1日死に近づいていくということである。
生きることと死ぬことは互いに切り離せず、したがって、就活と終活も切り離すことができないのではないか、というのが筆者の考えである。
参照文献
木村由香・安藤孝敏 2018「マス・メディアにおける終活のとらえ方とその変遷——テキストマイニングによる新聞記事の内容分析——」『技術マネジメント研究』17: 1-19.
いいなと思ったら応援しよう!