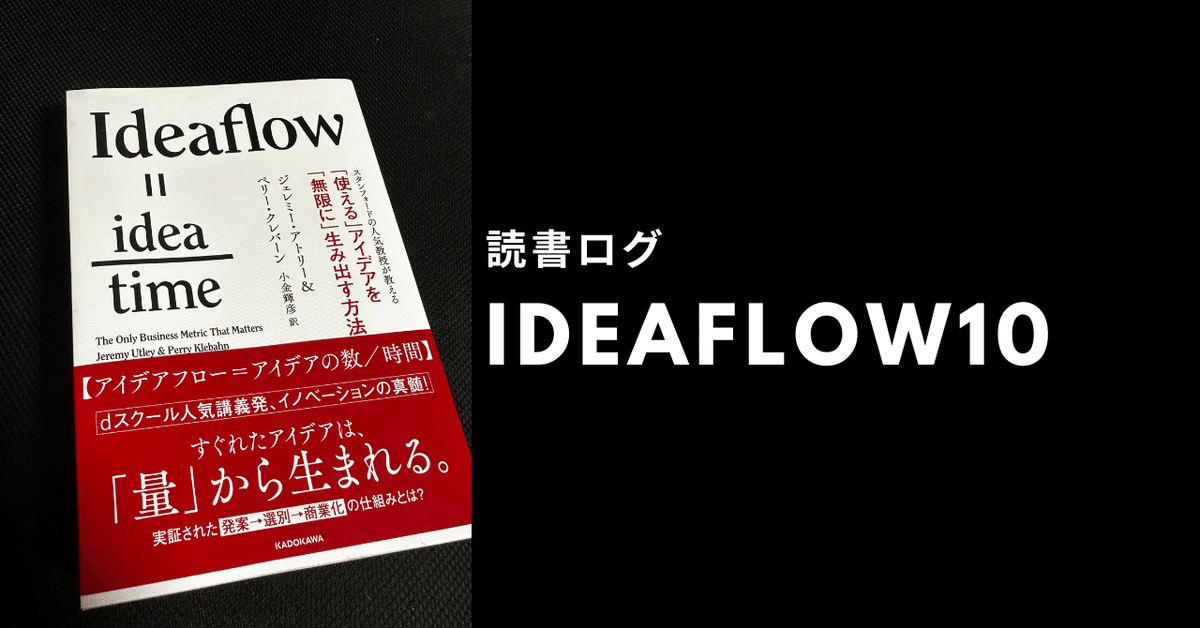
Ideaflow part10 【読書ログ】
前回を振り返る
いいアイディアを選択するのはシリコンバレーの優秀な集団でも難しい
選出するという意識を止める
早くテストすることが新しい示唆,洞察を得るのに有効
うまくいってもテストをやめずに多くのシチュエーションを検証するべき
四章四節|実験のポートフォリオを構築する
優秀なものを選出することはやめた方がいい.物事は可能な限りデータに決めさせた方がいい.テストと修正を繰り返し,成功する方向を明確に示してから進むべきだ.
ではどのようなテストをするべきだろうか?
本書では以下のように述べていた.
膨大に出したアイディアを一つ一つテストするのが一番いい
無理な時は多様性を孕むようにアイディアを選び取りテストを行う
実施に関与しない人間の意見を取り入れる
「これは興奮するアイディアか?」という基準は入れた方がいい
とりあえずテストする前に誰かが興味を示すかを見てからテストを行うといい
実施に関与しない人の解決策のアイディアを取り入れることのメリットとして多様性が挙げられる.
アイディアには多様性が必要不可欠なのだろう.この本では多様性という言葉が多く見られる.多様性があるからこそ可能性の探求ができ,新規性のあるアイディアが生まれる確率が高まるのだろう.
これは興奮するアイディアだろうか?この評価基準を置くことの意味としては,実行するにあたって,それに際する人間の熱意がなければ成功することなどあり得ないからだ.と書いてある.全くその通りであると感じる.
自分にしても,興奮すること以外で力を注ぐことができなかった.
誰かが興味を示すかをテストする前にテストする.というのはテストする対象を絞る有効な方法であると感じる.確かに誰にも興味すら持たれないアイディアは有効である可能性は少ないように感じる.
いいアイディアとは拒否反応と熱狂が同時に存在する.と誰かが言っていた
今回はこの辺にしよう
