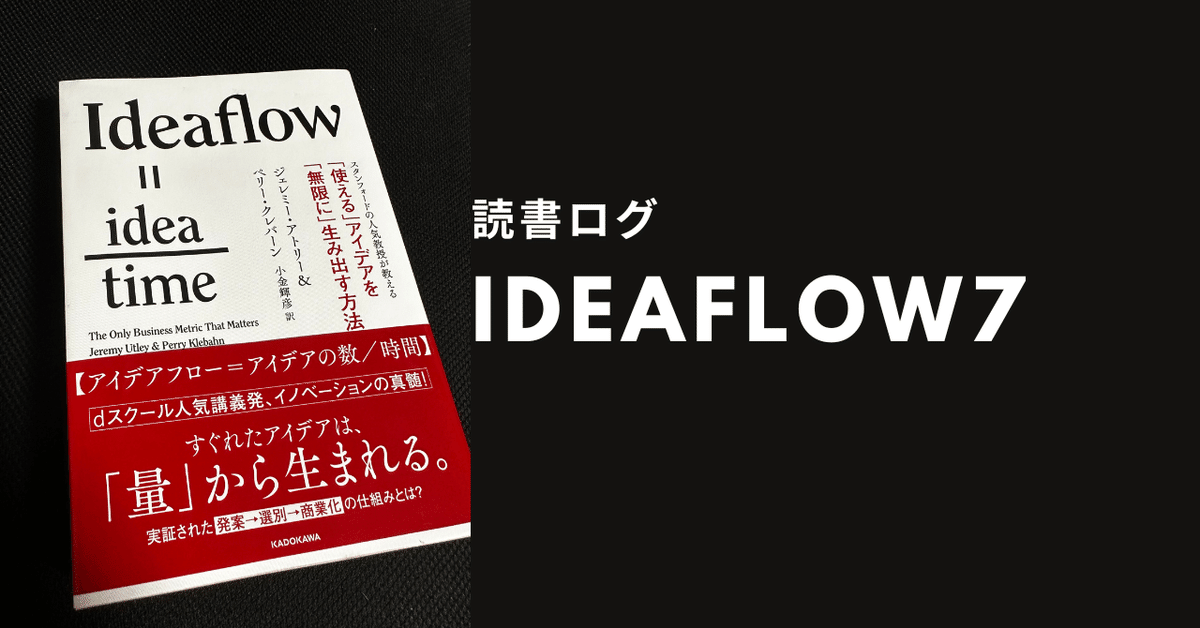
Ideaflow part7(読書ログ)
前回を振り返る
前回の内容は第一部二章五,六,七節に当たる
出したアイディアは定期的に見直せ
一週間に一日アイディアを実践したり,整理するためだけの時間をとれ
失敗を恐れずやれ
第三章|問題をアイディアで満たす
一般にアイディアを出すといえばブレインストーミングだ.一般のブレインストーミングにおける良いアイディアは
実行が容易く
絶対に失敗しないもの
「”ゴルゴディアスの結び目を両断するアイディア”が最適」らしいが,これは消極的なアイディアを思いつくための疲れるだけで効果のない方法だ.と書いてある.
ではなぜ多くの企業でブレインストーミングが行われているか?
これは急にアイディアが必要となり,失敗することが目に見えている時,集団で失敗する方がいいという,リスクに関するマインドセットの現れである.
ではどうすればいいアイディアを出すことができるのだろうか?
最高の結果を出すには,イノベーション・サンドイッチを使うべきだ.
innovation・sandwichとは?
まずは思わぬ発見や,知識の共有によるメリットを全て享受するために,メンバーを招集する.そしてそこで議論した内容を席に帰って考えさせる.
最後にもう一度集まってそれぞれの考えを共有し,さらに大きなアイディアを出させる.
グループ作業を打ち切る理由としては認知的閉鎖を避けるためだ.
認知的閉鎖は実行可能な案が一つ以上出ている時に判断を遅らせて新たな可能性を考え続けていると,ますます落ち着かなくなるというものだ.
そのため,新しい可能性を追求し続けるためには,一人で熟慮する時間も必要である.
だが実際,それほど多くのアイディアが必要なのだろうか???
いいアイディアが一つあれば十分ではないのか???
第三章一節|アイディア比率「2000:1」の法則
心理学者のディーン・キース・サイモントンが提唱した「イコール・オッズの法則」は,誰かの想像的な成功の数は,創造物の総数と相関が強いと述べている.
サイモントンの研究や著者(ジェレミー)の経験において勝者を際立たせているのは「量」である.世界に通用する創造者は平均よりも多くの可能性を定期的に生み出している.
要は成功している奴はいっぱい出しているから,お前もいっぱいだせ.とのことである.そしてその相関は確実に存在するとのことだ.
じゃあどのくらいの数のアイディアを出せばいいのか?
ジェレミーたちの経験では約2000必要だと言っている.
これを「アイディア比率」と呼んでいるらしい.
事例を上げていくと
玩具メーカー:4000もの製品アイディア,200の試作,1ダースの製品,成功数=2つか3つ
タコベル・タコスのインサイト・ラボ:一ヶ月に50種のコンセプトの設計を書いている.実際に市場に出すのは年間10やそこら
ダイソン:パック不要の掃除機のために5127の試作機を作った.
エジソン:バッテリーの実験を数千回
より良いアイディアを生み出すにはより多くのアイディアを生み出すしかなく,出したアイディアは無為ではなく,次のアイディアを引き出すための燃料となる.
エジソンは失敗した試みを成果として捉えていた.うまくいかないことに悩むのではなく,それが勝利に向かう前進だと捉えていたのだ.
第三章二節|なぜ人はあまりにも早く辞めてしまうのか
典型的なブレストでは数個のアイディアしか生み出さず,実現可能な選択肢が出てくるとアイディアをどう遂行するか,という議論になってしまう.
その原因のいくつかを挙げる.
プレッシャー
量と質の相関関係がわかっていない人たちは最初の良いアイディアを超えることに固執するのは完璧主義だとみなす傾向がある.収束への衝動とも呼ぶべき傾向である.
これは実感する,いいアイディアが浮かんできたらすぐそれをやりたくなっちゃう.ガチャガチャ次の可能性を議論していたら「もういいだろうがッ!」と言いたくなる気持ちはすごいわかる.だがいいものを作ろうとすればアイディアを膨大に出す必要があるらしい.
クリエイティブ・クリフ(創造性の崖)
心理学者のルーカスとノルドグレンが明らかにした「クリエイティブ・クリフ・イリュージョン」という認知バイアスがアイディア出しをやめてしまう要因となる.
人間は創造性を発揮すると,”何かを消耗している”という勘違いを起こすと書いてある.忍耐や意志力と違って,創造性は使っていても摩耗しないらしい.だから考え続けろ!とのことだ
奇抜で前例のないアイディアは明白なアイディアを出し切った後でやってくるのだ.
アンカリング・バイアス
人は決定を下す時,最初の基準点であるアンカーに固執する傾向がある.
例えば物体の大きさを推定するように指示した時,最初の推定値が全くの見当違いであっても,その後の値は最初の値の近くに集まってしまう.という現象がある.
”最初のアンカーが形成されるのを,系統立てて防ぐプロセスが必要である.”
…どうやって?
アインシュテルング効果
一つ解決策が浮かぶと,それを無視して別の解決策を見出すことが難しくなる現象だ.言葉探しゲームですでに見つけた言葉が何度も繰り返し目につくように.
あらゆる可能性をくまなく探るためには他の人の力を借りる必要がある.
今日はここらでやめにしよう.
2日も書くのをやめてしまった.
明日は朝早く起きて必ず書こうと思う.
