幕間:日常の誰そ彼、決意の彼は誰
目を覚ましたわたしを出迎えたのは、視界に大写しになった恐るべき強面二つだった。
起こそうとした頭をとっさに降ろしたため、後頭部を床に強打する。悶絶するわたしをオロオロと心配するのはノートンさんの部下二人。
「目ぇ、覚めたか。」
危うく深い眠りにつくところだ。本人は西に面した窓の向こう。吹き込むそよ風に乗って、とげとげしたタバコの香りが部屋の中に漂う。
「お前、何をした?」
「声を聞きました。」
彼の質問にわたしは答える。そうだ、わたしは声を聞いた。何故ならそれこそがわたしの取り柄であり、その為に邪魔をしていた無粋な鏡はわたしがぶち割ってやった。
ノートンさんも感じているのだろうか。わたしたちを取り巻く空気の、取り返しのつかない変容を。
「……どんな声やった。」
「悲しい声でした。とても。幸せにも救いにも繋がらない、悲しい、ただ悲しいだけのお話。」
わたしはうつむいて答える。西日はもうだいぶ落ちて、ほとんどが木々の間に隠れてしまった。照明も無い暗い部屋の中、わたしには立ち上がる気力も無い。
「どう感じた。」
「腹が立ちました。」
怒りなら、ある。
振り返って返すと、ノートンさんの手にはすでに最近流行りの《スマートホン》が握られていた。確か、なんとかごーとかいうゲームを遊ぶための錬金術製の小さな板の筈だが、彼はそれを顔の側面に当てている。
「あ、もしもーし。毎度やっしゃあ。いつもニコニコノートン金融でおますけど〜。……そないにツレへんこと言わんとって〜なぁ!」
気でも違ったのだろうかと戦慄するわたしに構わず、ここにはいない誰かと会話でもするかのように、先ほどまでとは打って変わった明るい声でしゃべくりだす。しまいには笑い出した。こういう……タイプの怖さを醸し出す人ではなかった筈だが。わたしは眠りネズミのぬいぐるみを抱きしめ、這いずって少しでも距離を稼ごうと苦心する。
「――ワイら、七人の仲でっしゃろ。」
刃物のような呟きはその場の誰にも届く事はなく、ただ遠く離れた一人の男の認識を小さく揺らす。
***
――おや、またお会いしましたね。本日は具合もよろしいようで、何よりです。
こんにちは、帽子屋さん。この間はごめんなさい。また、お話をいいかしら。
――もちろんですよ、耳のいいお嬢さん。さて、どんなお話をご所望でしょう。
ジルティアさんに聞いたわ。あなたはこの世界において、最も力ある過去の一つだって。
――おやおや、力をご所望ですか?あなたのようなお嬢さんが。
いいえ、力は要らないわ。でも知恵を貸して欲しいの。
――ははは、そうでしょうとも。わたしはあの目つきの悪いウサギの彼では無いし、今が三月かどうかもあやふやだ。それにあなたはどうやら、すでに力を持っている。必要なのはそう、知恵……というより視点かと。

この窓はなあに?帽子屋さん。
――どうです、おもしろいですか。時の流れている数多の板の……世界の流れを見ているのです。世界の外からね。
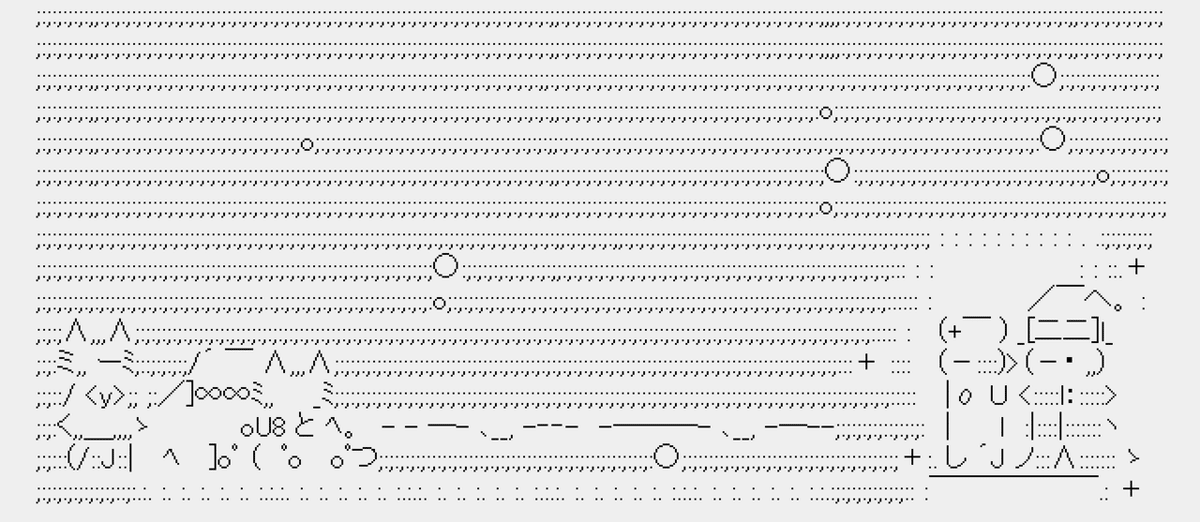
……これは、今起こっている事?
――そうとも言えるし、違うとも言える。2012年の太古の昔に繰り広げられた過去とも言えるし、これから起こる未来の出来事として語る事も出来ましょう。外から見た世界は、かくも自由で柔らかい。
世界を、外から。
――そう。世界を俯瞰してご覧なさい。第四の壁をすら透かして。あなたの世界の住民にはそれが出来る。界を超え、時を超えた繋がりを手にしたあなたがたにとって、それこそがむしろ自然な事。
そうすれば、何が問題かきっとよくわかるでしょう。あとはあなたのお力を存分に振るえばよろしい。あなたの世界の内に根ざした、内から世界を語り動かす力をね。
ありがとう、帽子屋さん。
――お安いご用です。次は是非、お友だちも連れていらっしゃい。
「……ありがとう。」
わたしはカップを置く。机の上の眠りネズミのぬいぐるみをひと撫で。
なるほど。
これではっきりした。この怒りの矛先が。振り上げた拳を、どこにいかようにして叩きつければ良いのかが。
***
「いきなり出せって言われてもな〜」
「お掃除とか、なさらないんです?」
「過去は振り返らない主義でな。前シリーズのグッズなんて犬も食わねぇ。」
工房の隅に山と積み上げられた特撮ヒーローショー用の衣装、小道具。我らがダシガライダーショーチームの演出担当、エンキドゥ氏は義足をコツコツと床に鳴らしてぼんやりそれを見上げている。自ら進んで探しものをする気はなさそうだった。
諦めて山に挑む。散らかっているものを片付けるのは好きだ。ただ、その際に要となるのは「如何に捨てるか」であり、胡乱なものばかりが転がり物品の要不要の判断が全くつかない錬金術師のアトリエに秩序をもたらす事は至難のわざだ。加えて今のわたしには、じっくり趣味のお掃除に耽溺している暇はなかった。
必要なのはただ一つ。一本のベルト。
「なんで今更あんなモンを。ガチなヤツはショーじゃ使えないって、散々文句垂れやがったのはお前らだぞ?あんなモン使ってお前……」
エンキドゥさんは間違いなく我が劇団のエポックメイカーであったが、正当な評価を得るまでには多少の紆余曲折があった。自身の錬金術スキルを惜しみなくつぎ込んだ「ガチなヤツ」を携えて劇団の門を叩いた当初は、客席演者の境なく、テロもかくやという混乱を引き起こしたものだ。街から何度も怒られた。
「お前さぁ……」
しかし、彼の特撮にかける情熱と知識は確かなものであり、(いい歳して)周囲からの視線や評価を(たまに迷惑をも)顧みない自由な姿勢には、個人的に学ぶところが多かった。「子供じみた」と評する向きも理解はできる。しかし、硬直し行き詰まった体制に風穴を開け得るのは常にそうした若さであり、実際我らがヒーローショーも……
「……お前、自分が何をやろうとしてるのか、本当にわかっているのか?」
かがめていた上体を起こして振り返ると、そこに立っていたのはエンキドゥさんでは無かった。
頰の傷、細身の黒いローブ、床板に悪そうな尖った義足。姿形はそのままに、しかしそれ以外の全てが何か別の者――"モノ"に置き換えられてしまったかのようだ。静かな眼差しはどこか高みから見下ろすようで、視線に晒された自分が何かちっぽけな……盤上の駒の一つにでもなってしまったかのように感じる。
わたしは立ち上がってまっすぐに視線を返す。
「やめとけ。まだ引っ込みはきく。《鏡》を割っちまったのは、まぁ、また立てれば済むことだけどな。これ以上は『勢い余って』じゃ済まない。明確にケンカを売る行いだ。世界に望まれたハッピーエンドに。」
「素敵なお話だと思いましたけど、」
臆する事は何もない。
「わたしの方が上手にできるから。」
目の前の誰かが噴き出して笑う。たちまち、"目の前に居ない何者か"からの無数の視線がわたしを貫く。ぐるぐると空気が渦巻く音。否定、拒絶、懐疑と排斥。世界の非寛容にはじめて晒され、わたしの全身の毛が逆立つ。だが、それがなんだというのか。
「ちょっと手伝ってあげようと思って。」
「ああ、笑った笑った。その面の皮の厚さは大したもんだ。成る程、お前にはわかっているんだろうさ。自分のしようとしている事を……既にしてしまった事についても。」
何を、当然のことを言っているんだろう。答えず、じっと見つめる。
「お前が割っちまった《鏡》が、何を隔てていたのか。何をパラレルの向こうの出来事として、この世界との接続を絶っていたのか。」
あれは、あの教会の過去だ。神父さんの過去。あんないびつな教会が、どうして今存在しているのかという答え。
「原因が語られたなら、物語は結果へと向かわざるを得ない。時の流れを意識させる"過去ネタ"は、お話を前進させる弾みを付けるのにうってつけだ。あの《鏡》によって保留され続けてきたお前らの日常は……」
気持ちよさそうに語っていた誰かさんが、わたしの顔を見て声を詰まらせる。何かついているだろうかと、自分の頬に手を当てて仰天する。
「うえへっ」
変な声が出た。涙だった。
あれおかしいなとか、そんなつもりじゃとか、口にしようとした言葉が形になる前に、意思に反してスキップしはじめた横隔膜が押し出す空気が断続的に喉を高く鳴らす。たちまち、胸が潰れるほどのさみしさを自覚して、わたしは感情に逆らうのをあきらめた。
一年。わたしがあの教会にお世話になると決まった時に、神父さんから提示された期限だ。ここは近く取り壊される、終わってゆくだけの場所であると。だからわたしは、あの借金取りから自由の身となるために、働いてお金を稼ぐ必要があると。
一年?時の流れなんていい加減なものだ。……いや、もしかしたら、優しくて柔らかいこの世界は、「もっとこの日常を続けていたい」という誰かの願いを叶えてくれていたのかもしれない。「この日常を終わらせたくない」という、わたしの願いを。
「えっ……と、大丈夫か?」
先ほどまでの超然とした様子とは打って変わった誰かさんの狼狽ぶりに、おかしくなったわたしは泣きながら笑った。
「んだよ」
毒づきながら、少しホッとした様子だった。
いいひとだと思った。この誰かさんは、「誰かさんでしかなくなってしまった」あとになっても、わたしのように、日常からはみ出しかかってしまった人々に対して、こうしてお節介を焼いているに違いなかった。
「大丈夫です。」
相変わらずぴょんぴょこ跳ねる横隔膜に難儀しながら、わたしは言葉を絞り出す。
「全部わかってます。それでも、」
「うん。いや、わかったよ。」
それを遮った誰かさんに、万物を見下すような様子はすでにない。参ったような苦笑いに細められた目はどこか寂しげでもあった。
「よくわかった。お前が"わかってる"って事。覚悟の上だってことは。なら、俺から言うことはもう何もないよ。……"それでも"か。みんな決まってそう言うんだよ。背を向けて行っちまう奴らは。」
そう言いながらわたしの横に立った誰かさんは、うずたかい山に手を差し込んで一本のベルトを引き出した。
「何が正しいかなんて知るかよ。どうあるべきかなんてクソ食らえだ。ただ、失うモノを自覚しながら"それでも"と一歩を踏み出す、お前らに俺は敬意を表す。」
それをわたしに差し出す。変身ベルト、そして《ゼクター》。ダシガライダーシステムの要。
「もってけ。こいつで、お前の最高のハッピーエンドを、世界の横面に叩きつけてやれ。……あー、鼻かんでからな。」
