
30年のまとめ。そして、未来へ。【Web30年史】エピローグ
デジタルデザインの未来をWeb30年史から考える。今回は最終回のエピローグです。
今までのnoteの中であった出来事を振り返り、得られた気づきをまとめていきたいと思います。
振り返ってみて
30年の歴史と20年のFOURDIGITを振り返ってみて、結構変わったなぁ、という感じ。まぁ、当たり前ですよね。
30年を切り取ると、
例えば日本の1930年と1960年では、全ての価値観が変わるレベルで違うわけだから、そりゃあ1990年から2020年だって大きく違います。
まさに日本が席巻したバブル時代の終わりからの30年なわけです。失われた30年といわれた30年。
テクノロジーは明らかに進化したし、インターネットはいろいろなものを変えていきました。昔は海外でタクシー拾うのも大変だったし、翻訳がこんなに簡単にできるとも思いませんでした。ニュースはスマホでいつでも手に入り、どこにいてもFacebookやInstagramをチェックできるし、海外でもSlackでプロジェクトの会話もしながら同じニュースも見れます。

ただ、テクノロジーが進化した結果、いったい何が良くなったんだろう、という気持ちもあります。
結果的にスーパー企業を生み出して一部のハイパーテック企業にデジタル世界は牛耳られているようにも感じます。スタートアップやユニコーンもなんだかんだで出口はテックジャイアントになっちゃうし、なんだかなぁという気持ちもあります。
まぁ、とはいえ、歴史をどこでスライスしても、常に良し悪しはある。

この振り返りは、20周年を迎えるFOURDIGITが今後の道筋をよりクリアにするためのものでした。
FOURDIGITは事業をやるチームです。事業は押せば成長するボタンのようなものはなくって、試行錯誤の連続です。CREATIVE SURVEYの事業パートナーであるSansanの寺田さんも「薄皮一枚一枚を積み上げるようにやる」と言ってました。
デジタルデザインの仕事はチーム戦なので、個人個人の集まったチームの化学反応で差がつきます。
チームで戦うリーダーとしては、情熱と意志を一番持っていたいのと同時に、実行においては誰しもが前に立っていくチームでありたいと思います。これは事業の内容や、やる仕事に関わらずそうですね。
デジタルデザインの仕事は振り返ったように、異常なスピードでスキルと仕事の意味あいが変わっていきます。テクニカルスキルもそうですし、ビジネスに対するデザインの関わりも変わってきているので、成長の余白も大きくなりました。
デジタルデザインに関わるデザイナーは、あらゆるビジネスリーダーと一緒に、本当に必要な体験はなんだろうと考えることができます。
それはとても幸せなことだなぁと感じます。
さて、30年のWWWの歴史の中で、気がついた大事なものに触れたいと思います。
技術的バックボーンに向き合うこと
WWWが生まれ、インターネットが普及し、パソコンが普及し、モバイルが普及し、といったハードウェアの進化。その中での、OSやブラウザ、アプリなどのソフトウェア。これらは完全に技術に依存します。できないものはできませんし、できるものはやればできます。
また、デザイン!デザイン!といっても機能の差が大きいと、スペックが圧倒的なものが勝ちやすくなります。
ある程度の普及と浸透、スペックの差が人間にとって小さくなってくると、デザインの影響が強くなっていきます。

携帯が普及してない国に、進んでいる国の携帯を持ち込んだら、技術的イノベーションとして驚きがあるでしょう。技術的にコモディティ化すると、競争が激しくなり、デザインが重要性を発揮していきます。
生産がグローバル化することで、コモディティ化までのスピードが早くなりました。それもあって、デザインの重要性が早期に顕在化しやすくなりました。
本当の意味でのデザインは、差別化でもなく、イノベーションでもなく、その時にある技術を最大化して「良いものをつくる意志」なんだと、ジョナサン・アイブも語っています。

しかし、毎日の地道な活動を見る限りでは全てがそうもいきません。
全ての制作に「良いものじゃなければ作らない」が許容されるわけではなく、オペレーション上で必要とされ実行される日常のデザインボリュームが多いのも現実です。
「良いもの」をつくる活動も単に最終的な形をつくるだけでなく、良い体験をつくり、良いプロダクトをつくり、良いタッチポイントをつくり、良いビジネスをつくることでもあります。
結果的に「良いものをつくる意志」と経済活動を両立させなければなりません。
ジョン・マエダの言う「インクルーシブデザイン」のように境界や垣根がなくデザインを考えることができる力はこれからも必要で、その価値はさらに高まっていくと思います。だからこそ手触りを持って技術的な今が分かっていなければならない。手触りから遠ざかり過ぎてしまうとレガシーな世界の中にしか出口が見えなくなります。

今ほどWeb標準技術が進んでいなければ、Webアプリケーションがここまでビジネスとして普及することはなかったし、Webを通じたコミュニティもできなかったはずです。
デバイスはどうなるのか、OSはどうなるのか、Flashがなぜ流行したのか、衰退したのか、フロント技術はどうなるのか、バックエンドは、テックソリューションは、解析技術は、認証は、AIは、ノーコードは……。
GAFAMのようなプレイヤーが先進的なのは、技術をさらに進歩させる力があり制約を超えることができるからです。言語や標準化に対して影響力を持とうとする動きはそこから来ています。もっといいものをつくって提供するためには今の技術的な制約を越えて解決しようということです。
デジタルデザインにおいて、目の前の技術的な動きがどうなっているのか、どういう変遷があるのか、どういった先を見据えているのかを肌で感じていることは非常に重要だと感じます。
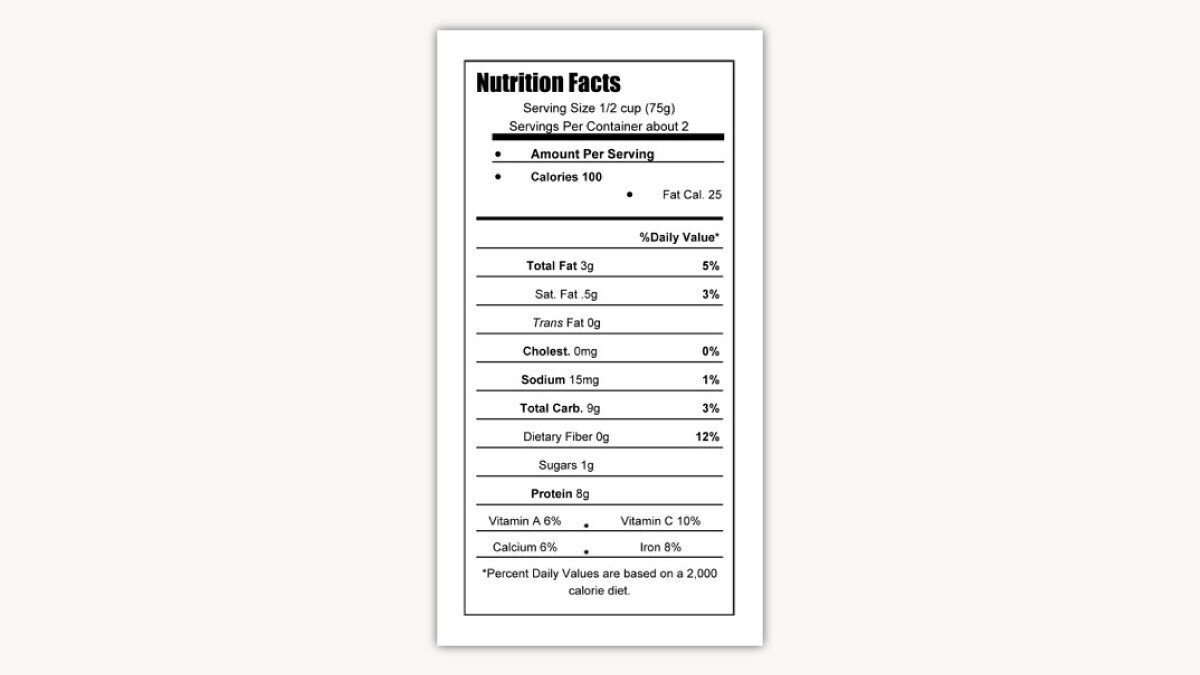
テックリテラシーの欠如は致命的になるかもしれません。
これからの時代はどのサービスにどんな技術が使われているか、ますます分からなくなります。
どんなテクノロジーで動いているのか分からないものは、製造工程が分からない食品のようなものです。食品は遺伝子組み換えやアレルギー表示、生産地区、などの表示基準がありますが、テックサービスにはそういう表示はありません。
全体のリテラシーが高まった先にはどういう技術がどう使われているのかを開示する責任が、サービスサイドにもっと強く求められる可能性もあります。これを易しく説明するための技術のニーズが高まるかもしれませんね。
人々の生活の変化に向き合うこと
人の生活についても、技術の変化と同じように肌で感じている重要性があると思います。
社会は常に変化していて、いいなーと思うことも、素敵だなーと思うことも、全てが一人一人の感覚的な概念に左右されています。
震災があったときに僕たちの心は、どこかで傷ついていて、どこかで怒っていました。寄付をしたり、自分にできることをやろうとか、そういう行動になりました。きっと9・11でのアメリカ国民の気持ちは、目の当たりにしていない日本の僕にはどこかで分からないのも現実です。

新型コロナも、病気にかかるのが怖いという気持ちもそうだし、自粛生活の中でデリバリーばかりでなく店でラーメン食いたいなとか、居酒屋いきたいなとか、満員電車もうやだなとか、日常にある気持ちもあります。
僕の下の娘はこのコロナ禍の真っ最中2020年4月に中学に入学しましたが、夏休みぐらいまでは本当に入学したのかすら、はっきりと自覚していなかったように思えます。体育祭がなくなり、遠足がなくなり、マスクで顔を覆ったクラスメイト全員に初めて会ったのは7月でした。SNSは大人の僕たちにとって、情報収集だったり、宣伝とか、連絡の手段だったりするかもしれません。
SNSばっかりやって、と大人は言うけど、若い彼女にとっては唯一友達と話せる場所だったりします。
コロナ禍で赤字企業がたくさん出てくるでしょう。尋常じゃない四半期の各社の決算数字を見ると、これからリストラにあったとしても働き場がないかもしれません。
第二波、第三波と情勢はなかなかよくなりません。
働きたくてもできない人たちの気持ちはどうなるんでしょう。
全員助けたくても無理だと嘆く政府の方もいると思います。
社会は、あくまでも、気持ちを持った人、ひとりひとりの集合体です。

倫理的な観点を持つことも変わらず大事だと感じます。
日本もコンプガチャ問題、ブラックハットSEO問題、キュレーション問題、いろいろな問題が起こり、それを是正しようとしてきました。インターネットにはもっとずる賢く掠め取った人たちもいると思いますが、そういう問題は常に淘汰されていきました。大事なものになればなるほど、クリーンな世界にできる限り近づいていこうと言う大きな意志があるように思えます。
簡単に手にしようとすれば、簡単に失ってしまう。
会社かどうかではなく、個人個人が持つべき倫理感でもあります。

FOURDIGITは、今まで20年、いろいろな人たちに関わってきました。
人の生活、活動、気持ちに対して想像力や共感力を持つことは、この20年の中だけでなく社会の一員として、変わらない重要なものだと身に染みて感じます。
マーケットの変化に向き合うこと
技術の動き、人の動き、最後はマーケットの動きです。
アメリカで起こったドットコムバブルで、インターネット企業が大きく市場価値があることを認められました。
ヒストリーで書き漏れたけど、ネットスケープの上場の話は衝撃だったらしいですね。創業1.4年で30億ドルの企業価値。市場は新経済と旧経済に分けられたらしい。
大航海時代さながらに、企業をスピーディーに大きくするためにベンチャーキャピタルからお金を集めて、最終的にバイアウトするためのエコシステムが発展しました。
日本でもスタートアップがマザーズ市場に続々と上場していきます。お金が集まる場所が変わると人の活動もそこに集まります。

今の自分たちの業界や類似する業界の動向、誰がどんな勝負をしていて、どんなニーズがあるのか、を感じることは、ビジネスを舵取りする上で重要です。企業体だけでなく、一人一人が経済活動をする上でも重要だと思います。
さて、僕たちのデジタルデザイン業界の未来はどうでしょう。
ネットが普及していくにつれて、各企業のファーストWebが立ち上がり、ネットビジネスも組み上がりました。初期はWebデザインそのものに価値があり、Webサイトがあること自体が価値だった時期がありました。
その後、Webデザインは一般化し、高度化し、インタラクティブであることや、いわゆるインパクトが求められ、それに対する熱量とユーザーの期待とビジネスメリットに同期していました。Webサイトがあることだけでなく、中身がリッチであることに価値が移ります。
モバイルの普及とリーマンショックによって、今度はリッチからリターンに価値の比重が移り始めます。デジタルマーケティングの世界の中でKPIドリブンで施策が走り始めると、クリエイティブのインパクトより数字的効果や定量的な結果が求められます。
モバイルの普及と何もかもがネットに接続してくることで、相手は椅子に座ってパソコンの前にいなくなります。スクリーンの体験だけでなくスクリーンを持った人たちになることで、Webコンテンツ・Webアプリケーション・デジタルプロダクトの品質は、サービス全体の体験品質に比重が移り始めます。

広告としてのデザイン、ブランディングとしてのデザイン、イノベーションとしてのデザイン、UXとしてのデザイン、といった形で企業側のニーズが分散したり、変化していく中で、必要とされるものが広義かつビジネスにおける根幹に近づいていきました。
今も昔もそうですが、広義かつビジネスの根幹に近い領域でデザインを提供できるかどうかに価値が顕著になっているように思えます。
この領域での戦いは境界を超えて発生して、コンサル会社・広告代理店・SIer・デザインプロダクション、あらゆる角度でひしめき合うんだろうなと思います。次の5年ぐらいで状況は様変わりしそうです。

その時々で、リーマンショックがあったり、震災があったり、経済が揺れうごきます。
ネットベンチャーが強かったりもするし、金融業界がデジタルに投資したり、海外への進出が盛んになったりと、市場のホットトピックは動いていきました。
大きな経済の流れは、これから起こりうることや、今実際何が起こっているのかを理解するためには重要なことだと思います。方向性の舵をとるうえで、大きな潮目はとても重要です。
業界が成長しているのにもかかわらず競争力を失ってしまった会社もあれば、サービス投資をして失敗して傾いた会社もあれば、海外進出して撤退した会社もあります。手を打つ、カードを切ることによって、リスクを取ることはとても重要ですが、大きなうねりを読み間違えると、渦に巻き込まれて時には沈むことすらある、これは今までの歴史が語っています。
逆に大事じゃないこと
技術的バックボーン、人の生活の変化、マーケットの動き、これらを肌で感じることが大事だと思っておりますが、これに反することというか、こういうのはやめといた方がいいな、と感じるものもあります。
× 特定技術に比重を起きすぎること
これはまず危険。Flash技術に依存した価値提供や、特定の広告技術に特化したり、特定の表現技術に特化したり、特定のプラットフォームに依存したり、そういったこと自体は価値があくまでも一時的になります。今の流れで考えると長くても4-5年でしょうか。これからはもっと短くなるかもしれません。組織として定義するのであれば一時的なチーム構築しかできなくなります。
× 著しいレバレッジが効くこと
これも注意が必要そうです。あまりにも儲かるビジネスは一時的であり長くは続きません。必ず競争相手が来て淘汰されていきます。ビジネスの世界ではWin-Winといいますけれど、提供する価値と提供される価値が一致しないものは長く続きませんし、倫理観を守れないことが起こりやすくなってしまいます。
× 栄華を求めること
これは実質的なものを求められるここ数年は、特に気をつけるべきかもしれません。賞を取ったり、本を出したり、テレビに出たり、チヤホヤされたり。僕が知っているすごい人は「勲章が後から着いてきた」人ばかりです。どんな勲章も時間が立つと華々しさは薄れます。常にうまくいくわけじゃないので、結局、向き合って積み上げて、信頼されるしかないと思います。
これから変わりそうなこと
コロナ禍のあとの世界の経済予測、きちっとした部分は別の方にお任せしたいですが、ざっくりいうと不況になる。企業の活動は、より実質的になり、うわついた話は後回しになることが増えるでしょう。効果や成果にも厳しくなる反面、思い切ったデジタル投資も加速する可能性があります。
人の生活では、コロナ禍で抑圧されていることに対して、より戻しはくると思います。
コロナが落ち着いたらカラオケ行きたいとか、居酒屋でグデグデになりたいとか、みんなでとにかく集まりたいとか。そりゃそうですよね。どこかでこういった抑圧が噴出するタイミングがありそうです。
働くスタイルも少し変わりそうですね。
そもそも毎日満員電車に乗りたくなかったとか、そもそももっと家族と過ごしたかったとか、そういうものは変わっていく力が生まれました。そもそも無駄な移動があったからオンラインでも良いだけです。そもそも必要なら今でもオンラインじゃだめです。
今回のことで新しい生活様式として残っていくのは、「本当はそうすべきだったけど、今までなんか躊躇して出来なかったよね」ということで、それ以外の"今は我慢しておいた方がいいこと"は一時的なもので定着はしないはずです。
そうして残っていくのは、本当に必要なもの、プリミティブな欲求に近いもの、なんだと思います。それぞれの事情で「Must」があると思いますが、それぞれの「Must」はもっと真剣に取り組む必要があり、本気でやるべき「Must」になるはずです。
つまり、本当に大事なことなのか?という問いが顕著になっていくと思っています。僕たちも例外ではなく、FOURDIGITがクライアントやユーザーにとっての本当に大事なのか?価値があるのか?そういう感覚が強く必要になりそうです。
おわりに
歴史を振り返ると、ネットビジネスやデジタルの世界は華々しいようで競争が激しく浮き沈みも大きい。技術はすぐに変わり、振り返ると10年ごとの世界は全然違った光景です。
変わることを前提に考えると、次を生む活動と、今を作る活動を同時に行うことが必要になります。今と未来を同じぐらい作り続ける。成長企業はみんなそうしているし、言い訳抜きで向き合っていかねばと感じます。
もし、今のままで大丈夫だ、と言ってる企業があったら、その時点であぶないかもしれません。今のことを捨てて勝負をする、と言っている企業があったら、それも危ないかもしれません。
---
未来に向けて歴史を振り返るということですので、FOURDIGITのこれからについてですが、「We connect」というテーマを定めました。
「つなぐ」というテーマで、これを3年間のテーマとしました。
人のつながりを大事にして、その人のつながりの中で仕事や生活があります。理念である「関わる人すべての幸せを追求する」ということには、人のつながりが大事だし、会社・チームの力はそのままつながりの力だと思っています。
We connectのテーマでどんなことをやっていくかは、FOURDIGIT 20thサイトに詳しく記載したので、ぜひご覧ください!
---
さて、このシリーズもイントロも含めて全19回。本当に長くなりました。
お付き合いいただいた方には感謝いたします。
どんどんシェアしてください。w
イントロの回でも書きましたが、これが何か関わる人の参考になればと嬉しいです。
とりわけデジタルデザインの歴史はさらっとしたものが多くて、きちんと振り返れるものが少なかったので、初期のインターネットを知らない方や勉強する方にも時代背景を知ってもらえたらいいな、と思っています。
書くべき項目は他にもあったかもしれません。実際いろいろ書き漏れていると思います。内容に対する間違いや見解違いなどがあれば、むしろ大歓迎ですので、ぜひご指摘ください。
それでは、これまで読んでいただいてありがとうございました! 引き続き、20期からのFOURDIGITも今後ともよろしくお願いいたします。
FOURDIGIT 代表 田口 亮
