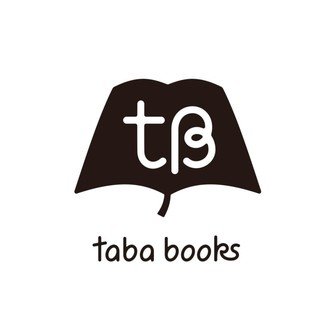無職の父と、田舎の未来について。/さのかずや 第9回・文化のための「食っていく」コストと、プラットフォームについて。(仕事文脈vol.9)
早いもので、仕事をやめて大学院に来て1年半。大学院もあと半年。
労働していた2年間の残業代で貯めたわずかな貯金は底をつき、一生懸命にスネにかじりついて暮らしている25歳、さのかずやと申します。
◯スネをかじりながらやってること
親のスネ以外にかじりつくためには、大学院を卒業し、無事に労働しなくてはならない。
大学院を卒業するための、そしてなにより自分のための修士研究として、ぼくは「オホーツク島」というウェブサイトをつくった。いまはこのウェブサイトを作っていくことに全力を注いでいる。「オホーツク」というのは、ぼくの故郷である北海道オホーツク海側地域のことだ。

このサイトのコンセプトは「オホーツクにまつわる新しい活動を、うながし、つくり、つたえる」。実際には「オホーツク島」という島は存在しないが、あえて「島」としている。なぜ「島」なのか?詳しくはウェブサイト内のコンテンツ「島のものがたり」を見て頂けたらと思う。
なぜぼくがこのメディアを作ったのか?すごく簡単にいうと、「おもしろい地域」というのは、見せ方の工夫で作り上げることが可能なのではないか?と考えたからだ。アメリカの社会学者、リチャード・フロリダは、こちらも簡単にいうと「おもしろい地域におもしろい人が集まる」と言っている。日本国内でよく話題になる、「地方創生」で注目されているような地域をみると、おもしろい人達がいる、とメディアに取り上げられることでおもしろい人たちが集まり続けている。フロリダの言説はある程度信憑性があると言えるだろう。
一見割と普通の、よくあるウェブサイトだけれど、ぼくのやりたいことはもっと深いところにあって…などと、このウェブサイトについては無限に語ってしまうので、おそらく半年後までには完成しているであろう論文を読んで頂くとして、今回は「ごはんと仕事」についてこの取り組みの中で感じたことを書いてみようと思う。

◯「食っていく」こと、スネをかじること、文化をつくること
お読みいただきありがとうございます。サポートいただけましたら、記事制作やライターさんへのお礼に使わせていただきます!