
#11 『ハーブの基礎知識と活用術』
キッチンにずらりと列んだハーブの小瓶たち。
プランターで生のハーブを苗から育てている方も結構多くいらっしゃいます。
ハーブは単なるインテリアとしてもお洒落ですが上手に扱うことで、いつものシンプルな家庭料理がまるで本格レストランで食べているかのような奥深い味わいや風味に簡単に変身させることのできる魔法のスパイスなのです。

ただ、ひとたび使いみちや使用量を誤ると、せっかくの料理が食べられないほど不味くなってしまうこともありえる諸刃の剣ともいえます。
今回はハーブに関する基礎知識と僕が個人的におすすめする定番ハーブの具体的な活用術について、できるだけ詳しく解説していきたいと思います。
① 形態の違いについて
まず基礎知識として知っておくべきなのは同じ名前のハーブでも様々な異なる形態で販売されているということです。
さらにハーブはその形態によって味や香りが全く変わってしまうものであるということも覚えておいてください。
では具体的にどのような違いがあるのでしょうか。
【ドライ or フレッシュ】
スーパーの調味料コーナーに小瓶やパッケージで列んでいるハーブやスパイス類は全て乾燥したドライタイプの商品です。

乾燥していますので傷みにくく常温で長期保存が可能です。中に水が入って濡れてしまっていたり、湿気の多い場所などでなければパッケージに表示されている期限を過ぎても1年程度なら問題なく使用できます。
ただ、購入時よりは色がくすんできたり、風味が著しく劣化したりはしますので、いつまでも購入時同様に扱えるというわけではありませんのでご注意ください。

ドライタイプのハーブに対し、葉野菜の列んでいる保冷棚コーナーに透明のプラパックなどで陳列されているのがフレッシュタイプのハーブです。

要は生の葉っぱの状態です。
スーパーの他、ホームセンター等で鉢植えの状態で売られていたり、自宅で栽培したい人のために種や苗でも販売されていたりします。

スーパーで購入してきたフレッシュハーブは持ち帰った後にやさしく水洗いし、軽く水気を振り落としてから縦長のガラス瓶の中に茎の切り口が下(瓶の底側)になるように立てて入れて蓋をし、冷蔵庫の野菜室など冷風が直接当たらない位置に保管しておけば1週間~10日ほどは問題なく使えます(※もし、保管中に変色してきた部分があれば取り除いてください)。

鉢植えで買った場合は毎日、土を湿らせる程度の水をあげ、たまに太陽光にあててやるなど、ちゃんと管理していれば数ヶ月は維持できるかと思います。プランターで購入するメリットは何より摘みたてのフレッシュな香りを楽しめることですね。
しかしながら菜園か大きな鉢植えなどで、それなりに本格的に取り組まない限り、ドライハーブのように半年~1年という長期間を維持することは困難ですので、基本的にフレッシュハーブを買うときは他の生鮮野菜と同じように近日中の料理で使いたい用途が決まったときに購入し、短期間で使い切ってしまうのがベストでしょう。

なお、フレッシュタイプとドライタイプでは味や香りはまったく異なります。
フレッシュタイプは良く言えば瑞々しい香り、悪く言えば少し青臭い印象があるのに対し、ドライタイプは香りがエグめで、やや薬品ぽい独特のクセを感じるものが多いです。ちなみに日本食で多用されている大葉(シソ)や木の芽(山椒の若芽)なんかも立派なフレッシュハーブの一種なんですよ。

フレッシュハーブは料理の仕上げに飾りとして使うことで料理が引き立ちますがドライハーブはあまり素敵な飾りとしては使えません。

とはいえ、ドライもフレッシュもそれぞれに適した使いみちや相性の良い取り合わせがありますので、どちらか一方のほうが優れているといったものではありません。
ここで覚えておいて頂きたいのは『バジル』や『オレガノ』など全く同じ名前のハーブであっても、フレッシュタイプなのかドライタイプなのかで味や香りが大きく異なるという認識です。

【ホール or パウダー】
ほとんどのドライハーブは葉を茎から外しただけの元の形状に近い状態で売られている『ホール』と呼ばれる粗めの原型タイプと、葉を機械で細かく粉砕した『パウダー』と呼ばれる粉末タイプの2パターンで売られています。
料理に香りなどを移した後からタイミングを見計らって取り除きたい場合や形状を生かして料理を魅力的に演出したい場合などにはホールタイプの使用が向いており、ハーブの姿形は前面に出さず、料理の仕上げに風味や香りだけを手軽に加えたい場合や素材の細かい隙間などに均一に刷り込みたいような場合にはパウダータイプがおすすめです。

【単体 or 混合】
ハーブは基本的に単体で売られていますが、中には複数の相性の良いもの同士をバランスよく混合することで美味しさや香りの相乗効果を生み出す定番ブレンドも多く存在します。
そこで、これら定番の配合を予め施して販売されているのが混合タイプの商品です。この記事は料理中心なのであまり深入りはしませんがハーブティーの世界では特にブレンドが盛んです。

混合系の料理用ハーブ(※一部、香辛料も含む)として特に有名なのは以下のような名称のものです。
[エルブドプロヴァンス]
タイム、ローズマリー、セージ、バジル
[ガラムマサラ]
黒コショウ、コリアンダー、シナモン、カルダモン、クローブ、クミン
[チリパウダー]
唐辛子、オレガノ、クミン、ディル、ガーリック、クローブ、オールスパイス
[ケイジャン]
カイエンヌペッパー、チリパウダー、クミン、パプリカ、オニオンソルト
[七味唐辛子]
唐辛子、山椒、陳皮、青海苔、ゴマ、麻の実、けしの実
[スパイスシュガー]
砂糖、シナモン、カルダモン、ペパーミント
[クレイジーソルト]
岩塩、ペッパー、オニオン、ガーリック、セロリ、タイム、オレガノ
[シーズニングスパイス(魚用、肉用など)]
魚や肉の調理に最適な混合スパイス
② ハーブの種類
あらゆる種類を徹底的に羅列しだすとキリがありませんので、ここではスーパーやネットなどでも入手しやすく、かつ一般的に料理用として広く使われているハーブに限定して、どのような種類のものがあるかをざっとご紹介しておきます。
[料理に使われる主なハーブ]※カッコ内は別名。五十音順。
・ イタリアンパセリ(パースレー、オランダ芹)
・ エストラゴン(タラゴン)
・ オレガノ(オリガン、ワイルドマジョラム)
・ 木の芽(コノメ、サンショウ、ハジカミ)
・ クレソン(ウォータークレス、オランダガラシ、ミズガラシ)
・ サラダバーネット
・ シソ(大葉)
・ シブレット(チャイブ、西洋あさつき)
・ スイートバジル(バジル、バジリコ、めぼうき)
・ スペアミント(緑ハッカ、オランダハッカ)
・ セイヨウタンポポ(ダンディリオン)
・ セージ(サルビア)
・ セルバチコ(セルバーチコ)
・ セルフィーユ(チャービル、フレンチパセリ)
・ ソレル(スイバ、オゼイユ )
・ タイム
・ ディル(ジール、イノンド)
・ ナスタチウム(キンレンカ、ノウゼンハレン)
・ パクチー(コリアンダー、香菜、コエンドロ)
・ パセリ(オランダせり、オランダみつば)
・ フェンネル(ういきょう)
・ ペパーミント(西洋ハッカ)
・ ホースラディッシュ(西洋わさび)
・ マーシュ(コーンサラダ、ノヂシャ、ラムズレタス)
・ マジョラム(マージョラム、まよらな)
・ ミツバ
・ ルッコラ(ルーコラ、ロケットサラダ、アルグラ)
・ レモングラス(レモンソウ、レモンガヤ、セイラ、タクライ)
・ レモンバーベナ(ベルベーヌ)
・ レモンバーム(メリッサ、セイヨウヤマハッカ、ビーバーム)
・ ローズマリー(まんねんろう、迷迭香)
・ ローリエ(ローレル、ベイリーフ、月桂樹)
いくつか名前や香りを知っているハーブはありましたでしょうか?

③ おすすめハーブと活用術
それでは数あるフレッシュタイプとドライタイプの中でも、僕がこれまでの経験上から『特に扱いやすく多用途に使えると思っているベストハーブ』をそれぞれの部門から3種類づつ厳選し、それらのハーブの特徴について活用術と共に詳しく解説していきたいと思います。
なお、パセリ(およびイタリアンパセリ)については便利で使い勝手も良いのですが日常的に使われていて身近すぎるということで、このランキング上では割愛しています。
かといって特にマニアックなものを選別したわけではなく、どこでも入手しやすく少しだけクセや特徴のあるハーブ初心者向けのラインナップですのでご安心ください。
[僕のおすすめフレッシュハーブ 3選]
1. バジル
フレッシュハーブの中で僕が個人的に最もおすすめするのは『バジル』です。スイートバジルやバジリコという名称で売られていることもあります。科目としては大葉(シソ)の仲間に属しますが味や香りは全く異なります。

とにかく手でちぎって散らすというのが基本の使い方で特にトマトとの相性が抜群に良いハーブです。
冷やした生トマトスライスの上に少量の塩コショウとバジルをちぎってちらし、エキストラバージンオリーブオイルを回しかければ即席でイタリアンなトマトサラダになりますし、そこへモッツァレラというチーズを加えればカプレーゼというイタリアで人気の定番前菜にもなります。

ボウルに細かく刻んだミニトマトと塩とハチミツを合わせ、ちぎったバジルを散らしてあえておき、トーストしたバゲットの上にニンニクの断面を軽くこすりつけてからのせ、オリーブオイルをたらせば小洒落た軽食のブルスケッタに。

市販のトマトソースやミートソースを鍋であたためる際、ちぎったバジルを混ぜ込んだり、仕上げに散らすだけでも一気に本格的な味わいに変化します。パスタに葉を飾ることで彩りも良くなり、そのまま一緒に食べれば最高にフレッシュな香りが口いっぱいに広がりますよ。

大量に安く手に入ったときはバジル、アンチョビ、ニンニク、粉チーズ、松の実、オリーブオイルを適当にミキサーに放り込んで回すだけでジェノバ風ペースト(別名ジェノベーゼソース)が簡単に作れます。ジェノバ風ペーストはパスタはもちろんですが肉料理、魚料理、前菜など非常に幅広く使える万能型のソースです。

さらに忘れてはいけないのがピッツァです。ピザ生地を自宅で用意して焼くのはなかなか難しいかもしれませんが、食パンにピザソースを塗ってトマトスライスをのせ、たっぷりのシュレッドチーズをかけてトーストし、仕上げにバジルの葉とオリーブオイルをかければ、あの大人気のピッツァ・マルゲリータが忙しい朝の食卓にでも手軽に用意できてしまいます。

これらの簡単かつ多様な使い勝手と老若男女問わず親しまれやすいクセの少ない爽やかな風味と味わい。それが数あるフレッシュハーブの中からバジルをおすすめする理由です。
2. ローズマリー
いかにもハーブらしい特有の強い芳香を持ちつつ、かつ多くの日本人が抵抗なく受け入れやすいと思うのが『ローズマリー』です。

厳しい気候にもある程度の耐性があるため、路肩の植え込みや公園の片隅など日本の街中でも意外とあちこちに植えられて茂っていたりしますので目にしたことがある人も多いのでないでしょうか。
ワサワサとモサい感じになっていることが多く、あまり見た目に美しくはありませんが時期によっては薄紫色の小さな花をつけたりもします。

ただ、都会の道端に生えてるようなものは車の排ガスや工業粉塵、犬猫の糞尿をかぶっていたりして不衛生ですのでしっかり洗うとしても食用にはおすすめしません。スーパーで食用として販売されているものか、ご自宅で栽培されたものをご使用ください。

ローズマリーはやや太くて硬い茎枝に細かい楕円形の葉が付いており、枝のまま料理の風味付けや仕上げの飾りに使ったり、細かい葉の部分だけをこそぎとって料理に散らしたり、さらに葉を包丁で細かく刻んで混ぜ込んだり、刷り込むなどして使われます。

加熱したり細かく刻めば味はあまり気にならなくなりますが生のままかじると、やや刺激的なほろ苦さがあるのでバジルのように生食向きのハーブとはいえません。

ローズマリーは特に鶏肉や豚肉、ジャガイモとの相性が良いことで知られています。
ジャガイモを皮付きのまま素揚げか軽く下茹でしてからフライパンでニンニクやローズマリーの葉と一緒にこんがりソテーし、塩コショウとバターで仕上げるローズマリーポテトや、さらにそこへウインナーやベーコンを加えたジャーマンポテト、もちろん鶏肉を合わせても間違いありません。

骨付き鶏モモ肉や手羽元などに刻んだローズマリーとおろしニンニク、塩コショウをたっぷり刷り込んでからオーブンやフライパンでじっくり焼きあげるハーブチキンのローストもおすすめです。クリスマスパーティーなどの際、豪快に丸焼きに挑戦するような機会があればチキンのお腹の中にもローズマリーを詰めて焼きあげることでカットした時に何ともいえない芳香が部屋中に広がって歓声があがります。

しっかりめに塩コショウをまぶした豚フィレ肉とローズマリーの枝、適量のオリーブオイルを厚手のビニール袋に放り込み、できるだけ中の空気を抜いてから口を固く縛り、沸騰したお湯の中に入れて蓋をします。あとは火を止めて約1時間放置しておくだけで作れる豚フィレ肉の自家製ハムもおすすめです。ここでもローズマリーの風味が非常に良い仕事をしてくれます。

また、以前に他の記事でパンの焼き方をご紹介しましたが均一の厚さに広げたパン生地に指で窪みを付け、そこへ小房にちぎったローズマリーの葉を差し込んでから焼くことで簡単に作れるローズマリー風味のフォカッチャは全国のイタリア料理店における定番メニューとなっています。

潰したニンニクとローズマリーの枝を弱火でじっくり煮込んでから冷ましたオリーブオイルをローズマリーごと煮沸消毒した瓶の中に移しておけばローズマリー風味のガーリックハーブオイルができます。パスタや料理の仕上げに使ったり、パンに付けたり、サラダやピザにかけたり、マリネに使ったり…手軽で多用途に役立ちます。1ヶ月程度は日もちします。

ローズマリーの魅力はなんといっても、その甘く上品な独特の芳香です。グラスに少量の水を入れて数本の枝を差し、書斎のデスク脇にでも飾っておけば疲れた時にリラックス効果も期待できる天然の癒やし芳香剤としても活躍してくれます。

3. セルフィーユ
なんとも美しい名称の『セルフィーユ』。これはフランス語での呼び名でチャービルやフレンチパセリとも呼ばれます。名前だけでなく、まるでレース模様のような繊細な見た目もたまらなく美しいハーブです。

また、セルフィーユは名前や見た目を裏切らない上品で甘くまろやかな香りが特徴で世界のグルメ通の間では『美食家のパセリ』とも称されています。
一般的にはケーキやデザートの上に飾ってあることが多いため、スイーツ好きな方は幾度となく見かけられていることかと思います。

ああ、あの葉っぱのことね!と認識された方も多いのではないでしょうか。
実はこのセルフィーユに似たものにイタリアンパセリというフレッシュハーブがあります。形状だけだと初心者には見分けがつかないくらい良く似ているのですがイタリアンパセリはいわゆる青臭い『パセリの匂い』がするので料理には向いているものの、デザート系には不向きです。

その点、セルフィーユは肉や魚料理はもちろん、前菜やスープ、チーズやデザートまで幅広い料理の香り付けや彩りに使えるため、飲食店の現場でも非常に重宝されています。独特な風味と味わいで個性が強いので人によっては単体で食べるのは少し苦手な方もおられるかもしれません。
デメリットはあまり日持ちしないことです。それこそ葉も薄く繊細で柔らかいため、とても痛みやすいのです。水分と冷気に気を使いながら保管していれば大方1週間ほどは使えるかと思いますが保存方法がずさんだと最悪1~2日で使えない状態になってしまうかもしれません。
僕のおすすめするメインの使い方は飾り用です。日常の食卓では仕上がりの見栄えなんてそれほど気にされないかもしれませんが、パーティー料理やおもてなし料理を作るとき、ブログやSNSに手作り料理の写真をアップするときなど、ここぞという勝負時にはセルフィーユをポンと加えてやるだけで地味な料理でも一気に見栄えをゴージャスにグレードアップできます。

食べるのであれば単体ではなく、セルフィーユの柔らかい葉だけを茎からちぎりとり、ルッコラやベビーリーフ、トレヴィスなど他の葉野菜と混ぜ合わせてハーブサラダにするのがおすすめです。サラダに肉気も加えたければ生ハムとの相性が特に良いかと思います。ドレッシングはお好みで。

あとは基本的にパセリと同じ感覚で扱えば良いので細かく刻んで魚のマリネに漬け込んだり、カルパッチョにちぎって載せたり、オムレツの中に混ぜ込んでヘルシーなハーブオムレツにしたりといった使い方もおすすめです。

[僕のおすすめドライハーブ 3選]
続いて僕のおすすめするドライハーブについてのご紹介です。
フレッシュハーブの枠でおすすめしていたバジルやローズマリーのドライハーブもありますが、こちらは残念ながらおすすめ圏外です。
というのもバジルはなぜかドライタイプになると強烈な発酵臭のようなエグい香りが前面に出てきてしまいます。フレッシュハーブの代用としては全く使い物にならず、正直ドライしかないなら使わない方がマシです。バジルはフレッシュタイプとドライタイプで風味が大きく異なるハーブの典型的な例といえるでしょう。
ドライローズマリーはフレッシュに比べて香りのインパクトが弱く、ホールタイプだと乾燥した細長い葉がガサガサとして口あたりが悪いため、おすすめしません。パウダータイプもありますがフレッシュのローズマリーの良さはほとんど失われてしまっています。
そんなドライハーブの中でも僕が特に気に入って愛用しているものは以下です。
1. オレガノ
イタリア料理や煮込み料理によく用いられるハーブのひとつで特にトマトソースとの相性が抜群なのが『オレガノ』です。
地中海料理にもよく使われる香り高いハーブで、いつもの料理になにか少しアクセントをプラスしたいというときに最適なハーブです。肉や魚などの臭み消しにも重宝する他、グリルや炒め物などにも幅広く用いられています。

ドライオレガノの風味を『鉛筆のような匂い』と表現する方も多く、たしかに言われてみればそんな気がしないでもありませんが初めて食べたときは違和感しかなくても慣れてくると病みつきになるような独特の芳香があります。

まず、もっとも手っ取り早い使い方はトマトソースパスタや市販のピザなどに適量を振りかけるというものです。瞬時に風味が一変しますので例えば最初の半分は普通に食べてから、残り半分になったところでドライオレガノを振りかけて風味の変化を楽しむといったような食べ方もおすすめです。個人的にはナスを具材にしたトマトソースパスタとオレガノの相性は最強だと思っています。

他記事でレシピを紹介しているカポナータやチキンのトマト煮、ミートソースやビーフシチューなどトマトソースでグツグツと素材を煮込むような料理に煮込みの過程で適量のドライオレガノを加えると味わいに一口では言い表せないような不思議な深みを出すことができます。
また、魚介系のマリネなどにもひとクセつけることができるのでおすすめです。軽く塩コショウしたイワシのフィレに白ワインビネガーかレモン汁とオレガノをまぶし、エキストラバージンオリーブオイルを振りかけてラップし、数時間おけばイワシのオレガノ風味マリネの完成です。

パン生地に混ぜ込んで焼いたり、オーブンで焼いたトマトの上にオレガノを振りかけるだけでも簡単な前菜になります。また舌平目などを使った白身魚のムニエルを焼く際の衣に加えたりしてもいいですね。

2. ローリエ
『ローリエ』は別名ベイリーフやローレルとも呼ばれるハーブで清涼感のある芳香が特徴的な月桂樹の葉です。葉の形そのままで乾燥させただけのホールタイプが主流で『ザ・木の葉』といったシンプルな形状をしています。
摘みたての生の葉を使うと苦味が強く感じられますが乾燥させることで苦味がやわらぎ、心地よくも強い香りを放つようになります。つまり、ドライにしたほうが使い勝手の良くなるハーブです。

乾燥した硬い葉っぱなので口あたりは悪く、食べても全く美味しくはないので充分に香りを抽出した後は取り除くか、よけて食べ残す人がほとんどです。もちろん食べたからといって特に害などはありません。なお、パウダータイプのローリエもありますが煮込んでいると苦味が出てくるため、僕は使いません。

煮込み系の料理へ数枚放り込むというのが基本の使い方です。香りが強いハーブですので4人前くらいの煮込み料理で使う葉の数は1~2枚で充分です。半分に折ったり崩して使うと香りは強く立ちますが、あとで取り除きにくくなるので口に入ると気になる人は葉を崩さずにそのまま使いましょう。
誰でもすぐにローリエの効果を実感できるのはカレーです。カレーを作る際、最初に具を炒め、その次に水を入れて煮込み始めるタイミングでローリエの葉を1~2枚投入します。そのまま仕上げても構いませんが最終的にローリエを取り除きたいのであればルーを入れる直前のほうが簡単に見つけやすいです。

他にミートソースやビーフシチュー、クリームシチュー、ポトフなど洋食系の煮込み料理なら大概プラスに作用するはずです。

また僕がお店でパスタ用のクリームソースを仕込んでおく際には牛乳にローリエを入れて一度だけ沸かしたものを生クリームと1:1で割ったものをベースとして使ったりもします。牛乳の生臭さが消え、こってりしていながらも爽やかな風味になります。冷製クリームパスタにも使いやすい上品な味わいです。

別記事でレシピを紹介している自家製ピクルスを作る際のピクルス液にもローリエを加えることで野菜にほどよい香りが移って本格的な仕上がりとなります。
またローリエには、米びつの中に数枚入れておくと虫を寄せ付けにくくなるといった意外な防虫効果もあったりします。

3. タイム
『タイム』はヨーロッパをはじめ、世界でもっとも人気のあるハーブです。フレッシュも悪くないですが、ドライタイプのタイムの方が甘い香りが強く、家庭でも手軽に扱いやすいのでおすすめです。
ホールはローズマリーに似た細長い楕円系をしていますが、ローズマリーよりも一粒のサイズが細かいため、料理と一緒に加熱してしまえば口あたりは気にならなくなり、違和感なく食べることができます。

加熱せずに仕上げに振りかけるだけという使い方をする場合は多少チクチクとした食感が残りますのでパウダータイプを選んだ方がベターです。
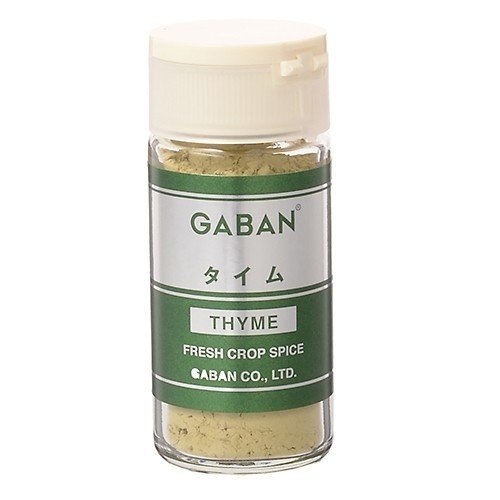
使い方として最も一般的なのは肉料理や魚料理の臭み消しです。特に生魚を焼く前に軽くまぶしてから使うことで魚自体の旨味は逃さず、特有の生臭さだけがびっくりするほど消えてなくなります。

ラムなど少しクセのある肉もドライタイムとオリーブオイルをまぶしてラップをはり、一晩寝かせてから焼けば普段は独特の風味が苦手だという方でも食べれるようになったりします。

魚や肉の他、野菜のグリルやマリネからパスタ、スープまで何にでも使えるタイムですが、僕が是非とも試していただきたいのがドライタイムとドライオレガノ、ドライパセリ、ガーリックパウダー、塩、粉チーズ、パン粉、適量のエキストラバージンオリーブオイルを均一にブレンドしたペルシャードと呼ばれる香草パン粉です。

塩加減はパン粉のまま食べて美味しいと思える濃度です。ハーブ類やガーリックパウダーの配合バランスはお好みで。パン粉の中に液体のオリーブオイルを入れるとベチャベチャになってしまうのでは?と思われがちですが適量の油であればすぐにパン粉が吸い込んでしまうので特に問題はありません。
ペルシャードは帆立や牡蠣やムール貝やはまぐりなどの貝類に載せてオーブンで香草パン粉焼きにしたり、グラタンやピザなどの上に掛けて焼いたり、フライパンで軽く炒ってパスタやサラダにかけたり、魚介類や羊肉や豚肉や野菜などにのせて焼いても抜群に美味しいです。カツやフライやコロッケの衣として使っても一味違う個性的な風味に仕上がるのでおすすめです。

適当に材料を混ぜるだけなので簡単ですし、ポリ袋などに入れて冷凍庫で保管しておけば凍ったままで使え、1年くらい日持ちしますので、いつでも手軽にハーブを活かした料理を楽しむことができますよ。
これまで『使い方も良く分からないし難しそうだし、香草とか苦手な感じがするから…』と何となく敬遠してきたような方にこそ、この記事をきっかけにハーブのもつ魅力と思っている以上にかんたんな活用術について知っていただきたいです。
ハーブを知ることできっと料理の世界が何倍にも広がるに違いありません。
④ 要点まとめ
・ ハーブは料理を変身させる魔法のスパイス。
・ 同名ハーブでも異なる形態で販売されている。
・ ドライ / フレッシュ
・ ホール / パウダー
・ 単体 / 混合
・ それぞれ特徴があり用途に応じて使い分ける。
・ 料理に使われている主なハーブは約30種類。
・ 僕のおすすめフレッシュハーブ 3選
(①バジル ②ローズマリー ③セルフィーユ)
・ 僕のおすすめドライハーブ 3選
(①オレガノ ②ローリエ ③タイム)
※内容にご意見ご質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。
いいなと思ったら応援しよう!



