
佇む彼女は遠い存在でした④
蓮加と初めて体を交えたあの日から約2ヶ月。
すっかり、羽織ものがないと肌寒い季節になった。
しかし、そんな今日でも俺の隣には冷えた心を温めてくれる存在がいる。

『ん、なに?』
木の葉が落ちて寂しくなった木々の下を歩く蓮加。無言で蓮加を見つめ続ける俺の視線に気がついた様子。
「ううん、なんでも。」
『なに、辛気臭いよ笑』
「今日はそういう日なんだよ」
『へぇ〜笑あ、飲む?』
彼女は手に持っていたスターバックスのホットコーヒーを俺に促してくる。俺は彼女にそっと微笑んでそのコーヒーを受け取り、一口飲んだ。
ほんのりと広がるコーヒーが身に沁みてどんどん体が温まっていく。
「美味い。はい、ありがと」
『んふ、どーいたしましてー』
今日は、学校帰りに2人で待ち合わせをして、ただ街をぶらぶらするだけのデートだ。
たったそれだけなのに。こんなこと、圭介とか賀喜ともしたことがあるのに
この上ない高揚感を感じる。
それだけ俺は蓮加に対して特別で愛おしい気持ちを抱いているのだと改めて今、実感する。
「…もうだいぶ暗くなってきたな」
時刻は午後19:01。冬に入りかけたこの時期だからか、日の入りも早い。
『そろそろ帰らなきゃ。こんなことしてるってお母様にでもバレたら………ってごめん。折角のデートなのにお母様の話とか、、嫌だよね』
蓮加はあの家出以降、俺とは別れたと家族に告げて無事和解したらしい。だから本当は今も付き合ってるなんて知られたらただじゃすまされない。
「そんなことないよ。まぁ、蓮加が怪しまれる前に早く帰ろう。ほら、爺を呼んで」
『うん、ごめんね。もっと一緒にいたかったのに』
彼女はおもむろに携帯を取り出して爺に連絡したかと思うと、
もはやこれ俺たちを見張ってたんじゃないか?というレベルの早さで蓮加の元にいつもの黒塗りの車がやってきた。
爺だけは、俺たちの仲を認めてくれている。
「…もうちょい別れを楽しみたかったんだけどな」
彼女の爺が仕事が出来すぎるのがかえって俺にとっては不都合だった。そのくらい蓮加との時間が惜しい。
『じゃあね…ってそんなしょげた顔しないでよ笑また会えるから。ね?』
「分かってるよ…じゃあな」
『んふ、可愛い。ほら、こっちきて』
「なんだよっ───────」
彼女は、車の中から身を乗り出して俺にキスをする。
軽く、優しいキスだった。
「……」
『また今度ね?じゃ、また』
「……」

俺の返事も聞かぬまま、彼女の車はそのまま走り去っていく。
車の中からキスをされるのはあのパーティー以降2度目のこと。
「あいつ、車から乗り出しキスが好きなのかなぁ…」
俺はそんなことを呟きながら、彼女の最後に見た表情を思い出して家に帰っていった。
───────────────────
──────────────
───────

『グッバイっ‼︎君の、運命の人は僕じゃない』
『辛いけど否めない』
『でも離れ難いのさ──────』
2学期中間テストが終わった11月の下旬。
俺は放課後に圭介と、

何故か賀喜と一緒にカラオケ店にきている。
特にこの3人で放課後を過ごしていることに恋のベクトルが交わるような暗喩的な意味はない。
ただただ幼馴染という縁で自然とカラオケに行く流れになっただけだ。
『はい来たー‼︎自己最高96点‼︎』
「無駄に歌が上手いのは何でなんだよ」
『ん〜まぁこれが才能ってやつ?』
「相変わらず鼻につくな賀喜は」
今は賀喜が髭男のPretenderで高得点を取って喜んでいる模様。

『凄いでしょ‼︎』
無邪気に笑う賀喜は、いつにも増して可愛く見える。
まぁ決してそんなこと直接伝えたりなんかしないけど。
「あ〜はいはい、凄い凄い」
『ん、馬鹿にしてるでしょ』
「してないよ。じゃあ俺も歌っちゃおうかな〜…同じくpretenderいっちゃいますか」
『どうせ私より低いんだから歌わない方がいいよ笑』
1番人を馬鹿にしてるのは賀喜じゃねぇか。なんて言おうとしたけどグッと飲み込んで、賀喜を睨みつけながらマイクを握る。
「君とのラブストーリー」
「それは予想通り───────」
──────────────
──────────────
──────────────
画面に表示された点数は83点。
あまりの落差に賀喜は爆笑する。
『ほぉら‼︎やっぱダメじゃん笑』
「…こんなつもりは…」
『やっぱ私って凄いでしょ?』
「はいはいすごいすごい」
『ん、馬鹿にしてるでしょ。ねぇ圭介、こいつ殴っていい?』
「ん〜?どうぞご自由に〜。乃木女の女の子を彼女に持ちながら、幼馴染と遊び散らかす○○君には制裁を与えなければ‼︎」
『…ん…?』
「…関係ねぇだろ今それは…」
おい、圭介。ここで蓮加の名を出すな‼︎
ほら、賀喜を見てみろ。
うるさかった賀喜の勢いがみるみるうちに落ち着いていく。
『………』
「じゃ、俺のおはこいっきまーす‼︎‼︎‼︎」
ここで、圭介が入れたであろう残酷な天使のテーゼが流れ出す。
気まずくなった空気を吹っ飛ばすように圭介が意気揚々と歌い出した。
いつも空気を読めない圭介だけど今日限りは助かった。
賀喜は、少し前から蓮加の名前を出すと如実に機嫌が悪くなる傾向がある。
今日に限った話じゃない。あの日だって、あの、蓮加と賀喜が俺の家を訪ねてきた次の日も。
──────────────
「…あ、そのキーホルダー‼︎そのキャラクター蓮加も好きなんだよ」
『蓮加…ちゃん、ね…』
「か、賀喜?」
『ごめん、用事思い出した。先行くね』
──────────────
蓮加の名を出した途端に、賀喜はその場をすぐに去っていった。
あの日を回想しながら今の賀喜の動揺と重ねて考えてみるが、結局この理由は俺には分からん。
賀喜が蓮加を妬んだり、恨んだりする理由なんてないはずだし。
ふと、視線を移すと
カラオケの選曲機を見てはいるがどこか焦点があっていない賀喜の姿があった。

そんな彼女を、俺は見て見ぬ振りをした。
───────────────────
──────────────
───────
「じゃあな〜○○も、遥香も〜‼︎」
帰り道、地区が微妙に違う圭介はそう叫びながら手を振って帰っていった。
そして、郊外の住宅街を賀喜と2人で自転車を押しながら歩く。
『今日は楽しかったね』
「うん、楽しかったな」
『また行こうね』
「おう、行こう行こう」
『でもさ…今度は2人で行こうよ』
「ん?2人?なんで?」
『いや、だって圭介アニソンしか歌わないし‼︎たまには邦楽オンリーのカラオケもありかなぁって』
「うわ〜なるほどねぇ。ありよりのありだな」
『そ、そうでしょ。じゃあ約束ね笑』
「おう」
これだけ話しても数10メートルしか進んでいない。
家まではあと200メートルくらい。
『あ、そういえばさ』
「ん?」
『蓮加ちゃん、元気?』
「え、あ、蓮加?」
蓮加と最後に会ったのは先週か。2人で公園でちょっと話したっけ。
それだけでも蓮加を間近で感じられて楽しかったなぁ。
でも、賀喜から蓮加の話題を持ち出すなんて珍しい。なんの風の吹き回しだ?
「元気だけど…どうした?」
『ううん、別に。まだ付き合ってるの?』
「もちろん」
『○○は、蓮加ちゃんのこと好きなんだ?』
「何言わせるんだよ。まぁでも…ちょっと時間を空けるとまたすぐに会いたくなるくらいには好きかな」
『…そっか…』
賀喜の横顔が夕焼けにさらされる。オレンジ色に染まる彼女の横顔はどこか儚げだった。
『ねぇ、○○』
「ん?」
賀喜は突然、自転車を押して歩く足を止めた。俺は彼女の方を振り返る。

『私のこと遥香、って呼ばなくなったのっていつからだっけ』
いつも笑っている彼女のいつになく真剣な顔はその言葉の重みを深めている。
そういえば、そうだ。
俺は今賀喜のことを遥香と呼ばなくなっている。
でもそれは彼女である蓮加への配慮、というわけではない。蓮加と付き合う前から賀喜のことは賀喜と呼んでいた。
でも、保育園の頃も小学校の頃も俺はずっと遥香、と呼んでいたことは記憶にある。
じゃあ、いつから呼ばなくなったんだろう。
「え、いつからだろう。でも昔は呼んでたよな、○○〜遥香〜って」
『今も呼んでよ』
「え?」
思わず、賀喜の目を見た。
正直、呼び方なんてどうでもよくね。って思った。呼び方で仲の良さなんて測れないって。
でも、賀喜のその目を見ると
俺が遥香、と呼ぶことに随分とこだわりを持っているのだと悟らざるをえなかった。
しかし、本心としては蓮加からの疑いを買わないためにも今さら遥香呼びに戻したくはない。
「何で今さら?」
『今更…とかじゃなくて…その…あの…昔は呼んでたじゃん…?だったら戻してもいいのかなって思っただけ』
「ほぉ〜ん。まぁ別にいいけどさ、ほら、蓮加に詮索されても困るなって」
『…また蓮加ちゃん……』
「え?」
賀喜は俯いた。
賀喜の足が止まる。
俺はまた、何が何だか分からなかった。
あの日と一緒だ。
「どうしたんだよ賀喜」
賀喜のリュックについたキーホルダーを“蓮加も好きなやつだ”と言った瞬間に、俺から離れていった、あの日。
『……』
「賀喜?」
『…もう、何で何にも気づいてくれないの』
「何が───────」
───────
──────────────
───────────────────
──────────────
───────
『好きなんじゃん。○○のことが』
震えた声で放たれたその言葉。
思わず俺の足も、止まった。
いや、周りの時間も止まったように感じる。
すぐそこを通る車も街路樹も淡く光る街灯もぼやけてただの背景に成り下がり、賀喜の姿しか認識できなくなっていた。
「…今…なん…」
『…○○のことずっと好きだった』
「……」
『でも今の○○には蓮加ちゃんがいる』
『それは、分かってる』
『でもね…でもね、好きな人が、好きな人の話するの辛いの。○○の幸せそうな顔見たら1人だけ寂しくて虚しくなる』
『特に、蓮加ちゃんのことは蓮加って呼んで幼馴染の私のことは賀喜って呼ぶの…それが1番辛かった。私の方が○○のこと知ってるのに。私の方が○○のことずっと好きな自信があるのに…っ』
「……」
『やっと2人きりになれて、漫画の話でいつもみたいに盛り上がれるかと思ったら、蓮加ちゃん、蓮加ちゃん…蓮加ちゃんのことばっかり…。』
『私のことなんかこれっぽっちも意識してないって突き付けられてるみたいだった』
『…こんなに○○のこと好きなのは私だけなんだって……』

『…ごめん、っ迷惑だよね。忘れて』
うっすらと頬に垂れた涙が夕日に照らされてきらりと光を取り入れた。
俺はそんな賀喜の突然の告白に何も言えなかった。
正直、俺は賀喜のことを女の子として意識したことはない。
ただただ気の合う異性の友達って感じで他の男友達と同じ感覚。
だから賀喜には何でも言えたし蓮加のことも話せたしもはや男友達よりも気楽な存在だった。
俺がそんな調子だから賀喜もてっきり同じ気持ちだと思っていたんだ。
「賀喜…ごめん」
「ずっと気持ちに気づけなくて」
『…やめてよ…謝られるのが1番グサってくるから笑』
見て分かる。賀喜の作り笑い。
『…いいよ、無理に私のこと、傷つけないようにしなくていいからね』
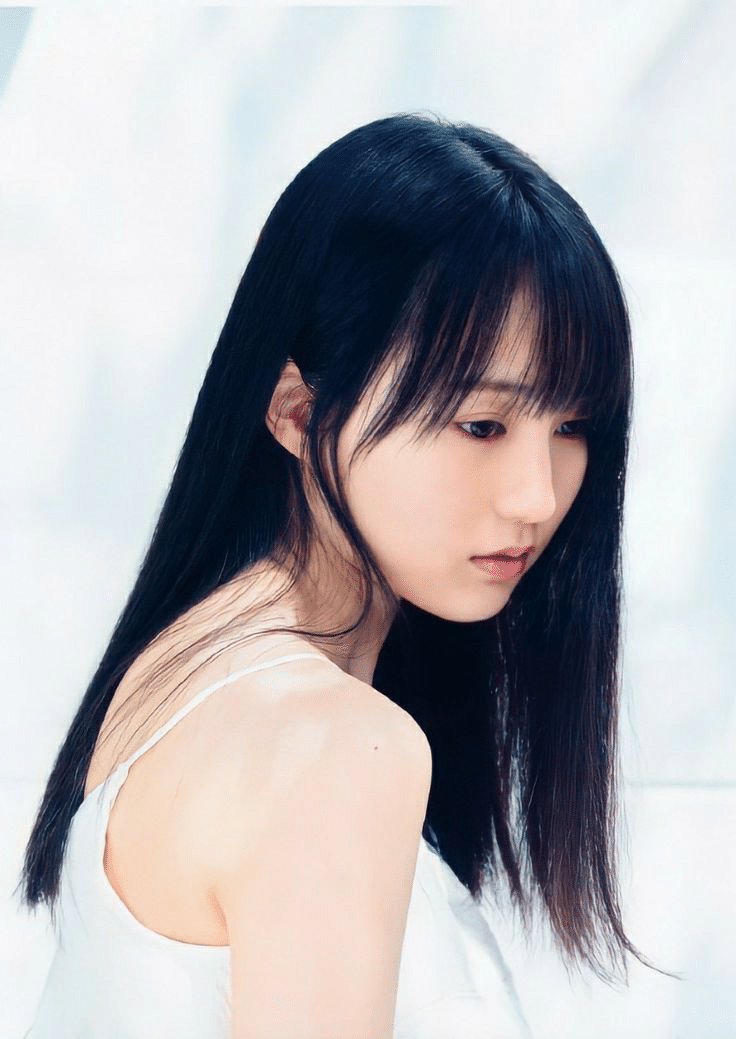
『蓮加ちゃんと仲良くするんだよ。私が認めた男なんだから』
街灯のオレンジ色の光が暗くなった空の下、賀喜の顔を照らした。
賀喜はそう言い切った後“じゃあね”とだけ告げて勢いよく自転車を漕ぎ始めると、あっという間に見えなくなっていく。
さっきまで楽しんでいた会話が嘘のようだった。
急に変わった、賀喜との関係性。いや急だと思っているのは俺だけなのかもしれない。
俺は1人取り残された夜の歩道を自転車を引きながらとぼとぼと歩いて帰った。
───────────────────
家に帰ると、いつも通り母と弟が能天気な声で俺を迎えてくれる。
“兄ちゃんおかえりー”
“ご飯まだだから、先お風呂入ってしまいなさい”
何も知らない2人。
当然なのだが、今、繊細になっている俺の心には何もかもがうるさく、耳障りに聞こえてしまう。
「あぁーうん、ちょっと休んでから入るよ」
俺はなおざりに返事をして、リビングのソファに座り込んだ。
賀喜…
普通は女の子に告白されたら嬉しいはずなのに、やはり心の底から喜べない自分がいる。
決して、賀喜のことは嫌いじゃない。もはや好きだ。大好きだ。
でもそれが交際する、ということに発展するものかどうかと言われればそれは違う気がする。
俗に言う、“like”の方。
なら振ればいい。お前は女として見れないって、幼馴染なんだって。
しかし、長年の彼女との関係性がそうさせることを難しくさせていた。
仲がいいからこそ、彼女をこれ以上傷つけたくない。
…もう、俺はどこまで情けない男なんだ…
“ヴゥー、ヴゥー”
ここで突然、携帯のバイブ音が鳴る。
俺はすかさずカバンの中から携帯を取り出す。まさか賀喜じゃ……
【蓮加】
え、蓮加?急にどうした。
「はいもしもし」
俺はさっきまでの動揺を表さないように冷静に電話に出る。
『あ、もしもし○○?』
「うんどうした?」
『急にごめんね。今私、○○の家の近くの駅にいるんだけど』
「え、あ、うん」
『電車の乗り方が分かんなくて……』
「え?」
『着いてきてくれない?』
なんだそのお嬢様な呼び出し理由。まぁ、行かない理由はないんですけど。
「あぁいいよ。どこ行けばいい?」
『西口?』
「分かった、すぐ行くよ」
俺は自分でもありえないくらいのスピードで蓮加の元へと向かった。
───────────────────
「蓮加!いたいた」
『本当に来てくれたんだ。ありがとう。勝手な理由でごめんね』
「それはいいんだよ。…えっと、駅すぐそこだから。てか爺の車呼べないの?」
『今日爺寝込んでていないの』
「そういうことか、じゃあ早く帰ってあげないとだな」
そうして俺たちはそのままちょうどよくやってきた電車に乗り合わせた。
「電車初めて?」
『うん。さっき来る時に友達と乗ったけど』
「そっかそっか」
『ねぇ…眠い』
「いいよ、肩使って」
蓮加は俺の肩に遠慮もなく寄りかかってきた。
その小さな頭が可愛らしくてたまらない。

…可愛い、可愛すぎる。
やはり、この感情は賀喜には抱かない。
やっぱり明日、ちゃんと伝えよう。ごめん、って。俺は蓮加のことが好きなんだって。
俺は蓮加のその頭を撫でようとした、
その時だった。
“逃げろぉぉおお‼︎‼︎‼︎‼︎”
と、隣の車両から大勢の人が走り逃げてきたのは。
俺は全く状況が理解できなかった。
しかし、隣の車両に目を向けるとその理由は明白だった。
スーツ姿に、血まみれの包丁を手にした男が立っていたのだ。
そしてその奥には刺されたのであろう被害者が血を流しながら倒れているのが見える。
「れ、蓮加…‼︎逃げるぞ‼︎」
『…ん…なぁに……』
蓮加が寝ていて逃げるのが遅れた。
目の前には狂気的な瞳をした男が1人、
その視線は蓮加に向けられている。
『きゃああぁぁぁぁああぁぁあ‼︎‼︎‼︎‼︎‼︎』
蓮加がその男に向かって叫ぶと同時に男は包丁を振りかぶった。
俺は咄嗟に蓮加を覆うようにしてその男に背中を向ける。
その瞬間だった。
途方もない痛みが全身に降り注いだのは。
『っっっ○○っっっ‼︎‼︎‼︎‼︎‼︎‼︎』
そんな声が、聞こえ、た、気が……し、
───────to be continued
