
コミュニケーションデザインのプロセスとわたしの5箇条
こんにちは。
GMOペパボ株式会社のハンドメイドマーケットサービス「minne」でデザイナーをしております、sziaoreoです。
こちらの記事では、サービスやプロダクトで新しい機能・概念をリリースしたりアップデートするときなどに行っているコミュニケーションデザインのプロセスと、わたしが個人的に大切にしている5箇条についてご紹介します。
コミュニケーションデザインのプロセス
1. 目的・課題を整理する
一番の目的は何で、抱えている課題は何かを整理します。
手段先行になっていないか、中長期的な視点も踏まえられているかなどを確認し、必要であればチームメンバーと一緒にチューニングを行います。
この機能や概念を取り込むことで1〜3年後、自分たちのサービスやプロダクトはどのような状態になるんだろう?
ユーザーはどんな風に喜んでくれるんだろう?
2. ユーザーニーズと課題を掘り下げる
視野を広げてみたり、多角的な視点を提供することでこぼれ落ちているものがないかを考えます。
見落とされた課題はないか?
ユーザーの行動パターンやニーズを深く理解するためのリサーチやデータ分析は行われたのだろうか?(具体的なものがなければ、なぜその課題を捉えたのだろうか?)
複数の課題が絡み合っている可能性はないか?(もし複数あった場合、どう考えれば整理でき、優先順位をつけられるか?)
1、2については、プロジェクトの状況や進め方によって行き来する場合があります。初めに目的や課題の仮説を整理することで、調査や掘り下げの指針を定めやすくなる一方、ユーザーニーズや課題の掘り下げから得られた知見によって目的を再定義することもあります。
3. 新しいアイデアの影響範囲を考える
新しいアイデアはどのようなコンテキストにより成立し、ターゲットのインサイトを満たすのかを考えます。
理想の姿は目的のところで描けているはずので、ここでは主に「避けなければならない姿」を言語化してリスクヘッジ的な思考を行います。
このリリースによってどこまでの範囲に影響が及ぶか?
世間一般的にはそのアイデアに対してどのようなことが求められるか?逆にどのような状態になると価値を失うのか?
将来的に何かしらの縛りやマイナスな制約として働いてしまう可能性はないか?
このステップから「新しいアイデアのメインターゲットにならないユーザーはどう感じるだろうか?」という点も気をつけて見るようにしています。
新しいアイデアを待望していたユーザーに対してはさほど心配はありませんが、「どちらでもない」ユーザーがそれを肯定的に捉えてくれるか、逆に行ってしまうかは設計や伝え方に大きく依存するためです。
コムデにおいては「誰にでも満遍なくプラスになる」というより、「このターゲットに圧倒的なプラスを提供する」という考え方が大切ですが、できるだけ誰に対しても「マイナスにはならない」と感じてもらえる状態を整えることも大切です。
4. 今ある仕組みと矛盾していないかを考える
既存の概念と矛盾したりハチあうものがないか洗い出します。特にブランド、利用規約、機能などの重要なものにおいては矛盾が起こると後で大変なのでチームの協力も仰いで念入りに調査しておきましょう。
ブランドインシデントに繋がったり、機能に対するユーザーの学習に混乱を与えたりする可能性はないか?
倫理的な問題に抵触したり、アクセシビリティ上のリスクはないか?
よく見落とされがちな観点としては、「新しいアイデアの提供方法によって今まであった概念、サービスが歩んできた歴史、ユーザーのあり方などを不必要に否定する構図になっていないか?」というポイントがあります。

5. 不足しているものを洗い出す
新しいアイデアを取り入れて自分たちのサービスやマーケットを活性化するにあたり、不足している前提、概念・機能などを洗い出します。
新しいアイデアの価値を最大化するには、ユーザーにどんな前提認識やコンテキストが必要だろうか?
新しいアイデアの実現にあたり、他に必要なものはあるだろうか?それは土台として不可欠なものか、それとも後付けでも良いものか?
6. 他の例や参考を探す
選択肢のバリエーションを広げる参考として他のプロダクトやサービス例を集めます。ここで大切なのは、「これの真似をすればいい」とは考えず、あくまでそれらを「参考」として見ること。
競合が最適解を持っているとも限りません。自分たち独自の目的と課題に対する解法を考えます。
7. ブランドとの調和を考える
サービスやプロダクトのブランドと照らし合わせ、その新しいアイデアを取り入れる時にどのような姿が最適か、またはブランド価値を最大化できるのかを考えます。
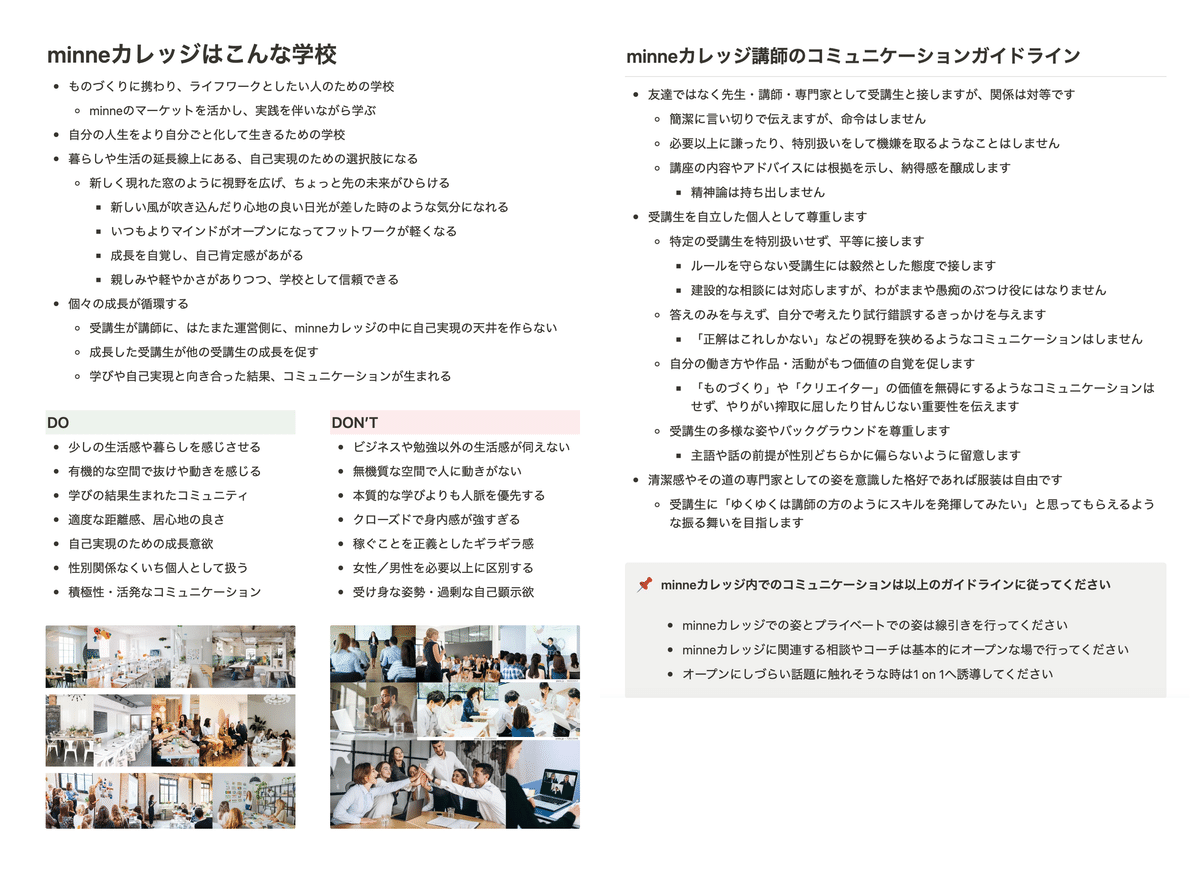
8. チームに共有し、形にする
目的・課題・ターゲット・要件がまとまったら言語化してチームメンバーに共有します。もちろん完璧に揃っている必要はありません。わからないところ、自信がないところ、たくさん意見が欲しいところはそのままお伝えしてチームみんなで考えましょう。
また可能であれば新しいアイデアを形にするプロトタイプを作成し、ユーザーにテストしたり関係者にレビューをもらうのも良いでしょう。
9. 言葉・メッセージを磨く
新しいアイデアにより生まれる言葉について精査します。
検証過程で内輪で使われていた言葉をそのままユーザーコミュニケーションでも流用するのはあまりおすすめしません。想定される言葉の使用シーンを洗い出して一番課題を達成でき、多様な場面で違和感を生まないものを選びます。
世間一般的な常識に逆らいすぎたラベリングになっていないか?
コミュニケーション速度を保てるか?
UI設計の際に文字数で首を締めるものになっていないか?どうしても長くなる場合はどのような省略を許容するか?
既存の概念や機能のラベリングと不和を起こしそうなものはないか?

加えて、新しいアイデアをユーザーに伝える際のメッセージを詰めます。
ただ「〇〇機能が追加されます」ではなく、ユーザーに起こすメリットは何なのかを具体的に想像させることが重要です。
このメッセージはUIのラベリング、販促、プレスリリース、CSなどのライティングの大元になるものです。固まったら、なるべく早い段階で関係者に共有しましょう。
10. 活用される仕組みを考える
新しいアイデアが永く機能し、価値を発揮するためのモメンタム施策・開発を考えます。
モメンタムはUI/UXに組み込んでしまうのが一番効果的で効率的ですが、事前に見積もりに入れておかないと後付けが難しくなるケースが多いため、なるべく早い段階で検討してチームに共有すると良いです。
さらにどの数値にどのような変化が起きるかを整理しておき、どのような方法でユーザーからの評価やフィードバックを収集するかも決めておきます。
以上を全て網羅できたらとても良いですが、私もプロセスを完璧に踏めているわけではありません。状況やその時の優先順位を踏まえてできることから少しずつ手をつけるのがいいと思います。
わたしの5箇条
「プロセス」について書いておいてなんですが、コミュニケーションデザインではその時の課題や状況に応じてやるべきことや優先順位が大きく変化するので、手順に固執する必要も実はありません。
そんな中でも「ここだけは常に守らねば」という気持ちでわたしが自分に課しているコミュニケーションデザイン5箇条をもっておまとめとさせていただきます。
❶手段先行にならないこと
例えば「この機能をつけたい」からスタートしている話は注意深く見る。
課題を深掘りすれば、解決する選択肢は他にも出てくる可能性が高い。
「自分たちが出したい機能を出す」のではなく「課題を解決する」「ユーザーのインサイトを満たす」ように導く。
❷自分たちにとっての最適解を導くこと
機能・概念やUIUX、ビジュアルにもトレンドはある。でもそれが自分たちにとっての最適解とは限らない。
なぜなら自分たちには独自の目的と目指す世界があって、それに向かう道のりは他のサービスやプロダクトと全く同じということはおそらくない。
トレンドにのること、ミートすることで得られるメリットももちろんあるが、それをゴールとしないこと。
❸その延長線、余白まで見ること
機能や概念を追加するとき、「そのターゲットにだけ変化が起きる」という状況は基本的にあり得ない。
新しいアイデアがもたらす中長期的な影響はもちろん、そのアイデアを外から目撃するユーザーはどう感じるのか、プロダクト・サービス・マーケット全体に対して悪い方向に力が働かないかも俯瞰的に考える。
❹機能・概念を価値に変えること
新しいアイデアはそのまま伝えても伝わらない。
「これの何があなたの人生や生活や気分をどう変えるのか」自分たちから提案し、変換し、視覚化・言語化して伝えて初めてやっとユーザーにとって意味を成す。
❺価値を言語化・視覚化できない時は設計を見直すこと
うまく言語化・視覚化できない時は大体設計のどこかに歪みがあったり定義が曖昧なままになっている。それをなぁなぁに放置しない。
自分たちがどんなに価値を感じていようとも、相手の立場に立って仕組みをうまく言語化・視覚化できないままで提供しても伝わらないし、それをわざわざ汲み取りにきてくれるほどユーザーは人生暇じゃない。
終わりに
コミュニケーションデザイナーは、サービスやプロダクトの中長期的な理想の姿を見据え、価値を設計し、言葉やビジュアルで伝えることで、ユーザーの感情や行動をポジティブに動かす役割を担います。
そして新しいアイデアを成功に導くだけでなく、その価値が定着し続けるための仕組みづくりも重要な仕事です。
設計を考える際は、サービスやプロダクトを愛する気持ちと、ユーザーの厳しい視点を行き来することが大切です。思い入れが強すぎると、「価値が伝わって当たり前」と判断が濁ってしまう可能性があるためです。
そして良い設計ほど違和感なく受け入れられ、気付かれません。つまりいい仕事をすればするほど目立ちません。
地道なブラッシュアップや懐疑的な視点を要し、時には孤独や負荷を感じることもあります。しかし、ブランドの根幹を支えるやりがいのある仕事でもあります。
「根っこから、設計から、きちんと取り組みたい」と感じた時から、コミュニケーションデザインは始まっています。チームと協力しながら、ユーザーに愛されるサービス・プロダクトを作り上げていきましょう!
