
鎌倉街道「八橋宿」へ行ってみた。
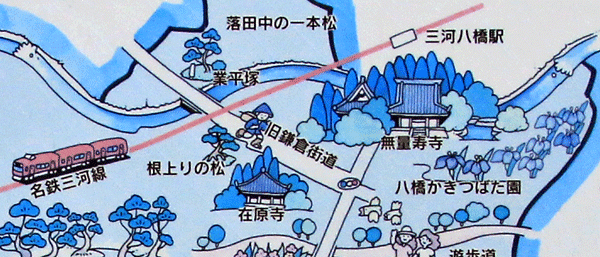
『伊勢物語』で有名な鎌倉街道・八橋宿(野路宿)へ。
無量寿寺から「落田中の一本松」へ鎌倉街道を往く。
途中、在原寺、根上りの松、業平塚がある。
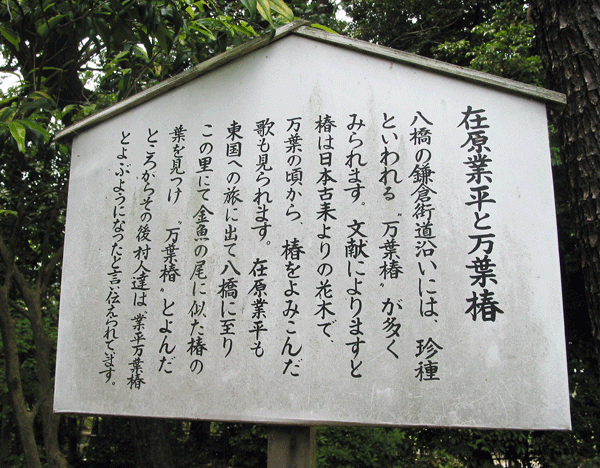
カキツバタも、ツバキ(業平万葉椿)も咲いていないが・・・。
※万葉椿:葉の先が金魚の尾のように裂けていて、葉は細長く、よじれているのが特徴。葉の形から「金魚椿」と言うが、在原業平が、八橋を訪れた時に 見つけ、「万葉椿」と名付けたので「業平万葉椿」ともいう。別の伝承では、弘法大師が云々。
■『池鯉鮒のむかし話』「金魚椿」
今から千年もむかしのこと。ある旅の僧が、東海道を通られた時の話です。とちゅう八橋のあたりで、一軒の農家によられ、昼食をとられました。家の人たちは、たいへん親切にもてなしたので、旅の僧はじゅうぶん疲れをいやすことができました。
その家を去る時、旅の僧は家人に、
「親切にしていただいてありがとう。お礼に何かおいて行きたいが持ち合わせがないので弁当につかったこのはしを地にさしておくから大切にするように、きっとめずらしい木になるから。」
といって立ち去られました。
家の人は、言われたことをよく守り、朝夕、水をやり、心をこめて育てました。
木はだんだん大きくなり、やがて先が三つにわれた葉をつける椿の木になりました。葉が金魚の尾のようなので、村人たちは、この木を「金魚椿」と言うようになりました。
後に、旅の僧は弘法大師とわかり、村人たちは、弘法さまを信仰するようになりました。
金魚椿は、現在、八橋町薬師の鎌倉街道沿いにあり、これをさし木にして、だいじに育てる人もあります。別名に、この椿は、万葉椿ともいわれています。
https://www.city.chiryu.aichi.jp/kanko_bunka_sports/bunka/2/1451813677770.html
1.無量寿寺
八橋山無量寿寺(愛知県知立市八橋町寺内)は、臨済宗妙心寺派の寺院。
慶雲元年(704年)、慶雲寺(愛知県豊田市駒場町)として創建され、弘仁12年(822年)、密円が現在地に移転させ、真言宗の無量寺(明治以降は無量寿寺)として整備したとされる。
寺宝に秘仏・十一面観世音菩薩立像(本尊。在原業平の持仏とも、在原業平が彫ったとも。木造。高さ30cm)、在原業平立像(木造。高さ48cm)、父・阿保親王の位牌などがある。
そういえば、松平初代親氏の弟(時宗の僧)が八橋にいたというが、ここではないようだ。
ここから先は
7,795字
/
22画像
¥ 100
期間限定!Amazon Payで支払うと抽選で
Amazonギフトカード5,000円分が当たる
Amazonギフトカード5,000円分が当たる
記事は日本史関連記事や闘病日記。掲示板は写真中心のメンバーシップを設置しています。家族になって支えて欲しいな。
