
山田八蔵重英
『どうする家康』第20回について、「大岡弥四郎なる人物が初登場し、謀反を起こしたが、『あの大岡弥四郎がな』と言われても感情移入できない」という意見がSNSに載せられた。確かに「力自慢の山田八蔵、切れ者の大岡弥四郎」と簡単に紹介されていただけである。本多正信程でなくても大岡弥四郎の切れ者ぶりを少し紹介するとか、足助城戦で山田八蔵が巨石を敵に投げつける場面とかを入れた方がよかったのかもしれない。
■山田八蔵重英
山田八蔵重英(?-1588)については、以前、調べたのであるが、ファイルが見つからない。水色のファイルは1冊しかないので、すぐに見つかると思っていたのであるが・・・(泣)。
山田
今の呈譜に、山田太郎重泰が男・七郎重基が後胤なりといふ。
重英(しげふさ) 八蔵
東照宮に仕へ奉り、天正3年、大賀弥四郎某逆心の時、重英、小谷甚左衛門某、倉地平左衛門某等とこれに与し、密に武田勝頼に通じ、その兵を岡崎城に引き入れんとす。時に重英、志を変じ、事の始末を三郎信康君に告げ奉りしにより、逆徒、遂に誅に伏し、勝頼も謀を失ひて兵を退けしかば、御感の仰せを蒙り、新恩の地を賜ふ。
16年、岡崎に於いて口論し、某がため害せられ、その采地を公収せらる。
https://dl.ndl.go.jp/pid/1082719/1/406
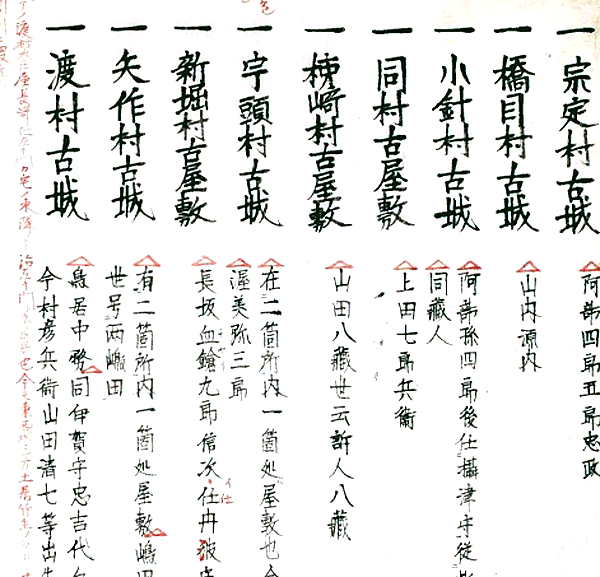
一、柿崎村古屋敷 山田八蔵。世に云ふ「訴人八蔵」。
一、宇頭村古城 二箇所在り。内一箇所、屋敷也。
今に伝へ、「芳阿弥屋敷」と云ふ。
渥美弥三郎。
(注)宇頭村(愛知県岡崎市宇頭町)には、古城と古屋敷がある。古城は、渥美弥三郎の「渥美館」(別名「宇頭城」)であり、古屋敷は芳阿弥長者の「芳阿弥長者屋敷」(愛知県岡崎市宇頭町字長者屋敷)である。
山田八蔵重英は、徳川家康の重臣・鳥居久兵衛の家来で、「三河一向一揆」では、一揆衆の1員として、倉地平右衛門、小谷甚左衛門らと共に佐々木の上宮寺に篭った。許され、後に岡崎城主・松平信康に仕えた。
天正3年(1575年)の「大岡弥四郎事件」(「信康家臣一揆」「岡崎クーデター」)では、罪悪感を感じ、改心し、松平信康に大岡弥四郎の謀叛を密告した。
■大河ドラマ『どうする家康』山田八蔵役・米本学仁コメント
――山田八蔵の人物像、役づくり
沢山あるのですが、山田八蔵として一歩目を歩む上で大切にしていたのは「不安と迷い」でした。お話を頂いてから先ず八蔵の足跡を辿るために、愛知県に向かいました。山田八蔵の塚と云われている場所を訪ねてみたら、こんもりと土が盛られていて、一本の道が二つに別れる場所でした。そこで、手を合わせ、八蔵の塚をじっと眺め、一つ一つの呼吸を噛み締めながら佇んでいると、この道で良いのか、何をするべきか、八蔵は常に迷っていたんじゃないかな、そんなことを感じました。優柔不断と言えばそうなのですが、最後まで不安の中に居て、迷いながらも進んだ八蔵。大岡弥四郎、仲間たちの凄惨な死に様は、決して忘れられるものではなく、その上で自分の命を燃やすべき場所を心の奥底で求めていたのではないでしょうか。
八蔵だけでなく築山殿、そして徳川信康さん縁の地にも足を運びました。築山殿の人物像には諸説ありあまりいい描かれ方をしていないこともあります。けれど八柱神社で出会えた「築山御前首塚」の石碑に書かれていた「…されど生害に値するほどの罪悪であっただろうか…」この一文から石碑を建てた人達の想い、築山殿に向けられる眼差しに触れることが出来きた気がします。それが山田八蔵を生きる上で一つのコンパスとなりました。八蔵が常に抱いていた不安や迷い、その苦悩に寄り添って下さる築山殿の人となりを感じました。
――徳川と弥四郎らの間で揺れ動く思い
終わらない戦乱の世。失われていくことが当たり前の命。ドクドクと脈打つ深い悲しみ、荒くなる息。そんな不条理をぶち壊したい。切なる想いを共にする弥四郎。色んな想いが巡る中「死にたくない」「生きて帰りたい」「会いたい」そんなシンプルだけど強い欲求が真ん中にありました。弥四郎や他の仲間たち。そして彼らの家族たちとも過ごしたこれまでの日々を何度も思い返すことで八蔵の苦しさ、後ろめたさがより深く大きくなっていくのを感じました。クーデターを実行するその夜、弥四郎と目線を交わしたり、仲間たちと進む中も心の中でずっとずっと謝っていました。「すまぬ、すまぬ…」と。
特に印象に残っているのは武田勝頼軍との戦に敗れ、怪我を負い城に戻って来るシーンです。たった一つしかない命を軽んじられること。またそんな状況に八蔵自身も慣れて麻痺していた部分もあったと思います。誰にも分け隔てなく手当てして下さるお方様。戦乱の世の不条理が五徳さんの台詞に現れる中、烈火の如く怒る瀬名さんの言葉たちに涙が流れました。最後まで迷いながらも裏切りを決めていた八蔵にとってその姿は驚きそのものであり、自分の命と心に温度を取り戻しました。そして瀬名さん、信康様をはじめ沢山の人達の命を愛おしく大切に感じてしまいました。迷いながら、不安と共にまた一つ裏切りを重ねる山田八蔵が生まれた瞬間でした。
――瀬名役・有村架純とのシーン
身分や立場の上下が決して覆らない時代に分け隔てなく接してくれる瀬名さんの存在は違和感。ただ命の価値があまりにも低い戦乱の世を生きる者にとって、それが当たり前で何の疑いも持ち得ない八蔵たちが現状を打破するには力によるクーデターしかないと思い込んでいました。そんな中、山田八蔵はこれで良いのかと迷い続け、疑問を捨てられません。
そして瀬名さんも同じ苦悩を生きられたのだと思います。同じ問いと真正面から向き合い続けてある決意に至った瀬名。「八蔵、頼みがある」と真っ直ぐこちらを見る瀬名には正直、恐さを感じました。誠実で真っ直ぐで腹が決まったその姿は強さそのもので、暴力よりも強力な力を感じました。何かを変える人は優しさと怖さを同時に持つ人なのかもしれません。
有村架純さんはとても不思議な方でした。飄々と淡々としているようで、一度動き出すと感覚の塊がそこにあるようでした。合間にお話させて頂いた際もとってもおもしろくて忌憚のない方で、接していてしみじみ好奇心が湧いてくるような。
ある日、前室で待機している間、有村さんと古川琴音さんと3人で話していたのですが、ふと有村さんが居なくなって、不意に戻られた時に「これどうぞ」とデコポンを僕と古川さんに下さいました。それが本当に本当にうれしくて大袈裟でなく頬擦りしながら泣けてきました。家に帰っても何度も手に取り惜しみながらも大切にそのデコポンを頂戴しました。甘さも酸味もギュッと詰まった最高に美味しいデコポンでした。劇中でも貝殻に詰まった軟膏、それを包んでいる手拭いを頂戴しました。身体が痺れるくらい嬉しかったです。劇中に下さいました軟膏と手拭い、撮影の合間に頂いたデコポン、どちらも山田八蔵、米本学仁にとって格別なものとなりました。
忠節が認められた山田八蔵は、「訴人八蔵(そにんはちぞう)」と呼ばれ、三河国碧海郡柿崎(愛知県安城市柿碕町)にて500石加増されている。
山田八藏は御加恩ありて、祿千石を賜はり、返忠の功を賞せられしとぞ。
天正3年、大岡弥四郎逆心之訴人仕、此の節、柿崎村、上地、土呂村にて500石御増加有之。渥美弥三郎と申す者と喧嘩致し、相果て候。子孫、鳥居家に之有る由。
山田八蔵には、柿崎五百石、褒美として下さる。後、大浜、上地を下され候。
・三河国碧海郡柿崎村(愛知県安城市柿碕町)
・三河国碧海郡大浜郷(愛知県碧南市浜寺町一帯):信康を一時期幽閉
・三河国額田郡土呂村(愛知県岡崎市福岡町):土呂村+上地村=福岡町
・三河国額田郡上地村(愛知県岡崎市福岡町)
天正16年(1588年)、「渥美館」(上掲『三河国二葉松』の「宇頭村古城」。愛知県岡崎市宇頭町)の渥美弥三郎と喧嘩になり、殺害された。柿碕町の「山田八蔵の塚」が墓だという。
所領は没収されたが、翌・天正17年(1589年)に養子・山田重次(小笠原時忠の次男)が仇を討った。「3ヶ所怪我をするも、討ち取った」という話を徳川家康が聞いて感激し、翌・天正18年(1590年)、300石を与えた。この後、山田重次は次々と戦功をあげて所領を増やし、子孫は徳川家の旗本となった。
■Reco説:結局「岡崎クーデター」とは何だったのか? 全く新しい視点で考えてみた。
これまで「大岡弥四郎事件」は、
・一味の単独犯行か、黒幕に武田勝頼がいるのか?
・瀬名・信康母子は関与しているのか?
という視点で考察されてきた。
私は、「クーデターを起こすのは不平不満があるからだ」とし、「岡崎の三河武士と、浜松の三河武士の差」を記事にしたが、今回は、今まで誰も触れてこなかった全く新しい視点から考えてみたい。
ここから先は
¥ 500
記事は日本史関連記事や闘病日記。掲示板は写真中心のメンバーシップを設置しています。家族になって支えて欲しいな。
