
【木工技術】大入れ 【大工道具】鑿

【木工技術】大入れ
『鎌倉殿の13人』(第39回)の北条政子は政治に興味が出てきたのか、八田知家に横に置く棚を作らせていた。源実朝が使っている棚は黒漆に金金具という美術品であるが、北条政子にしたら「そこまでしなくても・・・」と八田知家に頼んだのであろう。
八田知家は、同じサイズの角材を使う「枘継ぎ/枘接ぎ(ほぞつぎ)」ではなく、異なるサイズの角材を用意し、小さなサイズの角材を、大きなサイズの角材にあけた穴にはめる「大入れ」を採用した。
奇妙だったのは・・・
①通し穴では、汚い木口が見えてしまうので、普通は途中で止める。
②叩き鑿を叩くのに木槌は使わない。
普通は両口金槌(現在の「玄能」。当時の「玄能」は石を割る大槌をいう)の木殺し面を使う。木槌は、仮組み立てなど、木を叩く時に使う。
③叩き鑿の幅が小さすぎる。
市販の叩き鑿は、10本組、12本組、14本組であり、穴をあけるには、同じ幅の叩き鑿を使う。

※玄能/玄翁:本来は、石を割る土木作業用の大槌。南北朝時代、玄翁和尚が殺生石を割る時に用いたので、「げんのう」という。現在は、釘を打つ時に用いる両口金槌を指す。
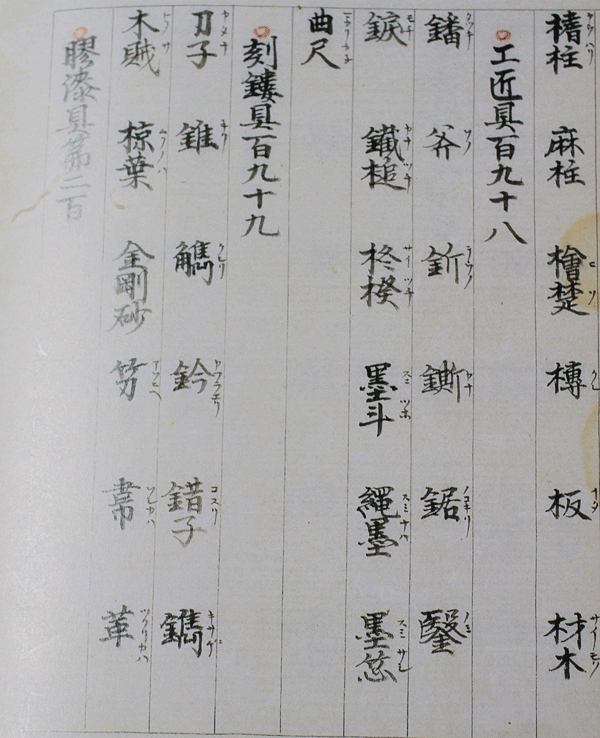
【大工道具】鑿
奈良時代、「鑿(のみ)」といえば、柄の長い「突き鑿」であった。
「冠(かつら)」を付けた柄の短い「叩き鑿」の登場は、平安時代のようである。『新撰字鏡』(昌泰年間(898-900)成立)に「鑿(ノミ)」とあるのが「突き鑿」で、「叩き鑿」は含まないとされる。『和名類聚抄』(承平5年(935年)頃成立)の工匠具に「鑿(ノミ)」とあるのが「突き鑿」で、刻鏤具に「鈐(カフラエリ)」とある彫刻鑿が「叩き鑿」だという。
なお、「のみ」の語源は、「の」が「刀」、「み」が「穴」だという。
木工鑿┬突き鑿┬薄鑿
│ ├鎬鑿
│ └鏝鑿
├叩き鑿┬追い入れ鑿
│ ├向待ち鑿
│ └丸鑿
└特殊鑿(彫刻鑿、蓮華鑿、掻き出し鑿、etc.)
いいなと思ったら応援しよう!

