
じぶんだけの地図。
これは昨晩にみた
ぼくが小学2年生だったころの
夢のお話。
キーンコーンカーンコーン
今日いちにちのおわりを告げるチャイムが鳴る。
いつもなら友達どうしでドッチボールをするのだが、この日ばかりはそんな気分にはどうしてもなれず、はやくお家へ帰りたかった。
今すぐ学校という場所から解放されたかった。
4時間目の体育の時間のこと。
ぼくはかけっこでビリになってしまった。
ぼくは幼稚園のころから足がおそい。だから今日の体育でかけっこをすると知ったときは、おなかがギュッと苦しくなった。
もっと事前に教えてくれたらよかったのに。それなら学校を休んでいたかもしれない。そもそもどうして足が遅いのに走らなくてはいけないんだろう…
おそくてもいいから全力で走ることが大事なのよ!
と先生は言う。
全力でって言われても…おそいものはおそいんだ!!
そんなことを考えながら、ぼくはトボトボとかえり道を歩いた。

家についてビリになったことをじいやんに相談してみると、考えるまもなくこう言った。
ぼ…ぼくの話を聞いていたのだろうか…。どう考えても別にいいわけがない。
「ええやん。かけっこくらい」
そりゃ、じいやんからすると体育のかけっこ“くらい”のことかもしれない。でも、ぼくにとってはそれくらいではすまされない。だって、
「なんでやと思う?」
「なんでって、ビリになって悲しくない人なんていないでしょ」
「そうか?わしは全然悲しないで」
だから!それはじいやんが学校に行ってないからで、ぼくにとっては…
「いや、ちゃうちゃう。そういう意味やのうて、もし今わしが小学生で小学校に行ってるとしても、かけっこでビリになっても悲しくも悔しくもないねん」
絶対嘘だ。
そんな人間がいるはずがない。だれだってかけっこでは1位になりたい。これは最近おぼえた言葉でたしか…強がりというやつだ。
それでもじいやんの自信たっぷりの表情は、ぼくを不安にさせる。それと同時に、またなにかぼくが知らないことを教えてくれそうな気がして、ちょっぴり期待もしてしまうのだ。
「どうでもええからやねん」
はぁ…やっぱりだ。やっぱりじいやんはテキトーなことを言っているだけだ。ちょっとだけじいやんに期待してしまった自分がはずかしくなった。
「でも、お前は悔しかったんやろ?」
「あたりまえでしょ」
「ええやん」

「ああ!すまんすまん!ちゃうねん!怒んなや!お前すごい顔なっとったぞ…」
「・・・。」
「あのな、悲しいとか、悔しいって思ったときはな、その裏っかわには理想の自分がひそんでるんやで」
「リソウノジブン?」
「せや」
いつもじいやんは、それがどういうことなのかすぐには教えてくれない。リソウノジブン…裏っかわに…どういうことなんだろう。
「あのな。さっきわしが言ったことは強がりでもなんでもなくてな、ほんまにわしはかけっこでビリになっても、これっぽっちも悲しくないねん。なんでかっていうたら、1位になることはどうでもええからやねん。わしにとってはもっと大事なことがあんねん。それは、みんなを笑わせることや。」
ん?んん?ますます意味がわからなくなってきた。
「わしがお前の立場やったら、むしろ全力でビリになりにいくで。その方がまわりは笑ってくれるかもしらんやろ?でもそれだけやったら小笑いや。わしはストイックに爆笑狙いたいから、せやな…
わしのコースだけ勝手にハードル設置したるわ。
お前だけハードル走になっとるやないかーい!つって。これでドカンや。まわりのやつら、もうかけっこどころやないで。笑いころげて走られへんくなってるすきに、わしがゴールテープきったるわ!」
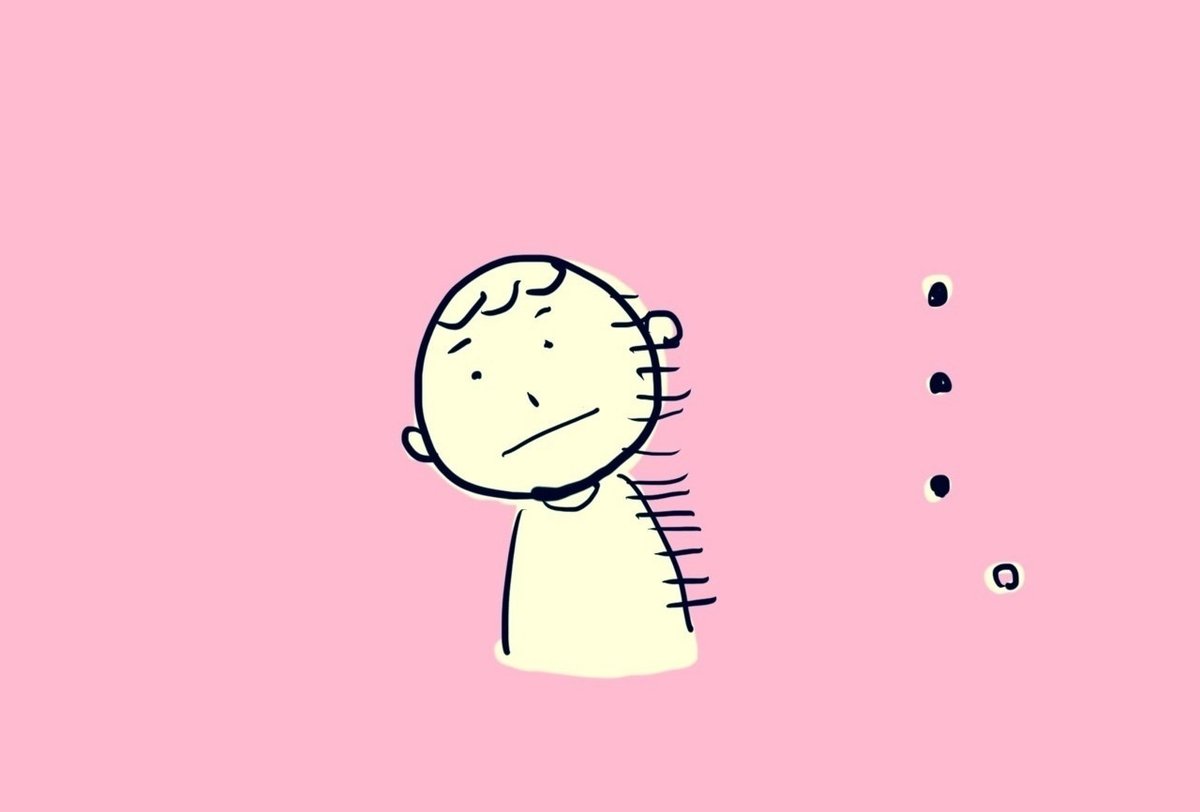
「お…お前がもうちょい歳とってたら、今ごろ笑いで腹ちぎれて救急車やったな…」
そう言ってからじいやんはひとこともしゃべらなくなった。そして「もう寝る」と言って寝室に行こうとしたので、
「いや、ちょっとまってよ!リソウノジブンについてまだなにも聞いてないよ!てかまだ5時だよ!?」
「…こういうことやがな」
「え?」
「わしの理想はおもろいやつやねん」
「どういうこと?」
「お前はもうちょい笑いの感度を磨いてこいや!」
「は?」
「ええわ…せやからな。わしはかけっこでビリになってもなんも思わへんけど、笑いがとられへんかったらめちゃめちゃ落ち込むねん」
「へー」
「へー。やあらへんがな。わしにとってはいち大事やがな。人生かかっとるがな。まぁ、そういう落ち込んだ瞬間を見逃すなっちゅーこっちゃ」
「ほー」
「お前淡々としてんなぁ…。その悲しいとか悔しいってな、理想の自分にはまだなれていない自分が味わってる感情やねんで。逆に言うたら、そこに理想の自分を探すためのヒントがあるっちゅーことやろ?もしかしたら夢とか、やりたいことを見つけることができるかもしらん。せやから、そういう感情を味わったとき、悲しんでおわりにしたらもったいないやん?」
「うーん。そうなの?」
「まぁつまりは、お前はどういうやつになりたいのかっちゅーことやな」
ぼくは想像してみることにした。どういうやつになりたいのか。そのときすぐには思い浮かばなかったけど、じいやんが教えてくれたことはなんだかうれしかった。これから悲しい悔しい出来事がおこったときにも、少しだけお土産が用意されている。そんな気がしたからだ。
「まぁ今のお前にはちょっとむずかしいかもしらんけどな。これからいっぱい泣きたくなることがおこってくるで。そのたび、しっかり自分と向き合っていくんやで。生きていくためにはそれが必要やから」
「うん」
「ほんで、お前はビリになったのがほんまに悔しかったんか?」
もちろん!と、ぼくは言いかけてとどまった。なにかがひっかかる。ぼくはほんとに悔しかったんだろうか。悔しい…というよりは、恥ずかしいのほうが近いかもしれないと思った。
「ほう。ほんならお前は別に1位になりたかったわけちゃうかもしらんな。ビリやったことが恥ずかしかっただけで。まわりからバカにされるんが嫌やったんやな」
「うん。そうかも」
「そうやってな、自分の心と話してみんねん。なんでそう思ったんでっか?それほんまでっか?言うてな。そうやってるうちに、どういうやつになりたいのかがわかってくるで」
じいやんの話は半分はなっとくできた。でも、もう半分はわかっていないことがある。
そもそもどうしてリソウノジブンを見つける必要があるんだろう。それがわからなくたって困ることはないんじゃないだろうか。
ぼくはそれを、じいやんに聞いてみることにした。
「まぁ簡単にいうたら…

「ら、楽だから?」
「ほな、今から東京のアップルストア行ってMacBookPro買ってきてもろてええ?」
「は!?」
MacBookPro?いやいや、ここは大阪だ。(ぼくの生まれは東京だけど)
「いける?」
「いや、無理だよ!!」
「なんで?」
「いやだって、行き方がわからないし。ていうか東京なんかひとりで行ったことないし。そもそも新幹線に乗ったこともないよ」
「せやな。じゃあ地図わたすわ。ここから駅まで行って、ほんでどの新幹線乗ればええんか。そこからどこで降りるのかと、降りてからアップルストアまでの道のりを全部書いた地図を」
「そういう問題じゃないよ!」
「でもあったほうが楽やろ?」
「いや、だから…」
「ないよりは、あったほうが、楽やろ?」
「ま、まぁ…」
「そういうことやねん!」
「どういうことやねん!!」
ぼくは思わず関西弁でつっこんでしまった。じいやんは、ぼくにどうしても地図があったほうが楽だということを言わせたかったらしい。
「理想の自分っていうのはな、お前が生きていくための地図やねんで?これからな、自分はなにが好きなのかとか、なにをやりたいのかとか、ほんまにわからんようになってくるで。歳をとるたびわからんようになっていくねん。そんな時、お前が進むべき道を教えてくれるのがその地図や」
「そうなの?」
「大事なこと教えといたるわ」
そう言ってじいやんはもう一度タバコに火をつけた。これはじいやんのクセだ。
なにかいまから大事なことを言おうとするとき、ゆっくりとタバコに火をつける。
それにどういう意味があるのかはわからない。多分カッコつけているのだと思う。

「さっきお前はかけっこでビリになって落ち込んでたやん?お前は陸上選手になりたいわけでもないのにやで?それはなんでかいうたら…」
「バカにされるのが嫌だったから」
「うん、せやな。じゃあなんでまわりは足が遅いやつのことをバカにするのかというと、それが学校のなかでの正解やからやねん」
「正解?」
「せや。足がはやいことが正解。テストの点数が高いことが正解。給食は残さずに食べることが正解。そう思ってへんか?」
「たしかに」
「せやろ?だからまわりは不正解のやつを笑おうとするんやで。でもな、ほんまはそんなもん正解でもなんでもないねん。ほんまはひとりひとりにとっての正解があるんや」
「どういうこと?」
「それがつまり理想ってやつやな。かけっこで1位になってモテモテになりたい!と本気で思うんやったら足がはやくなったらええ。あたまが良くなっていい大学に行きたい!思うんやったら勉強したらええ。お相撲さんになりたい!思うんやったら友達の給食もお前が食うたらええ。なんでもええねん。お前はどんなやつになりたいのか。それは人によって違うんやから。人と比べずにお前だけで考えなあかんで」
「ぼくだけで?」
「みんながやってることを正解やと思ったらあかん。これは絶対やで。学校とか、会社とか、そういうグループのなかにいると、いつのまにかグループの正解が自分の正解になってしまうねんな。さっき地図の話したけどな、みんなが進んでる道が、お前も進まなあかん道やと思ってまうねん。ちゃうで。ひとりひとりに地図があるんやで。ひとりひとりに目指すべきゴールがあるんやで。それはお前が自由に決めたらええんやで。これだけはずっと忘れたらあかんよ」
「・・・。」
「このことがな、大人になったらわからんようになってまうねん。みんなそれで苦しんでるで。自分は何が好きなんやろか。これってほんまにやりたいんことなんやろかって。そうやっているうちに道に迷ってまうねんな。自分の正解もわからんようなってまう。それはほんまにしんどいことやで。せやから、地図があったほうが楽やねん」
じいやんの言ってることはわかる。そして、それを聞いてぼくはちょっとだけホッとした。ひとりひとりに地図がある。それならまわりと違っていても当然だということだから。
でも、それでも、やっぱりぼくはまわりからバカにされるのが怖いと思った。笑われるのはやっぱり恥ずかしい。逃げ出したい。
だから今すぐ、じいやんが言ってるように、自分だけの正解を考えて、自分が本当に進みたい道を進む。ぼくにそれができるとは思えなかった。
「そらそうやん。そんな簡単なことちゃうよ」
「え、そうなの?」
「どういうやつになりたいのかなんか、そんな簡単にわかることちゃうよ。まわりからバカにされるのはだれだって嫌やで。怖くないやつなんかおらん」
「じゃあ…」
「だから、はやく地図を完成させなあかんねん。これからちょっとずついろんな経験して、いろんな感情を味わっていくなかでな。しっかり自分の心と話してみて、まっしろな紙に道を書いていくねん」

「まだわからんやろうけど、ちょっとずつ道ができあがってくるはずやから。遠回りもいっぱいすると思う。それでもちょっとずつできあがってくるはずやで。その道はほとんどの人と同じ方向なのかもしらんし、もしかしたら真逆の方向になってるかもしらん。ほんでな、その地図が完成したとたん、まわりの声なんかどうでもよくなるんやで」
「ほんとに?」
「ほんまや」
「そっか!」
「ほら言うてみ。どうでもええねん」
「ど、どうでもいいねん」
「ちゃうちゃう。どうでもええねん!」
「どうでも、ええねん」
「ほらもう一回!」

「ええやないか」
そう言ってじいやんは、またタバコに火をつけた。
基本的に記事は喫茶店で書きます。その時のコーヒー代としてありがたく頂戴いたします。
