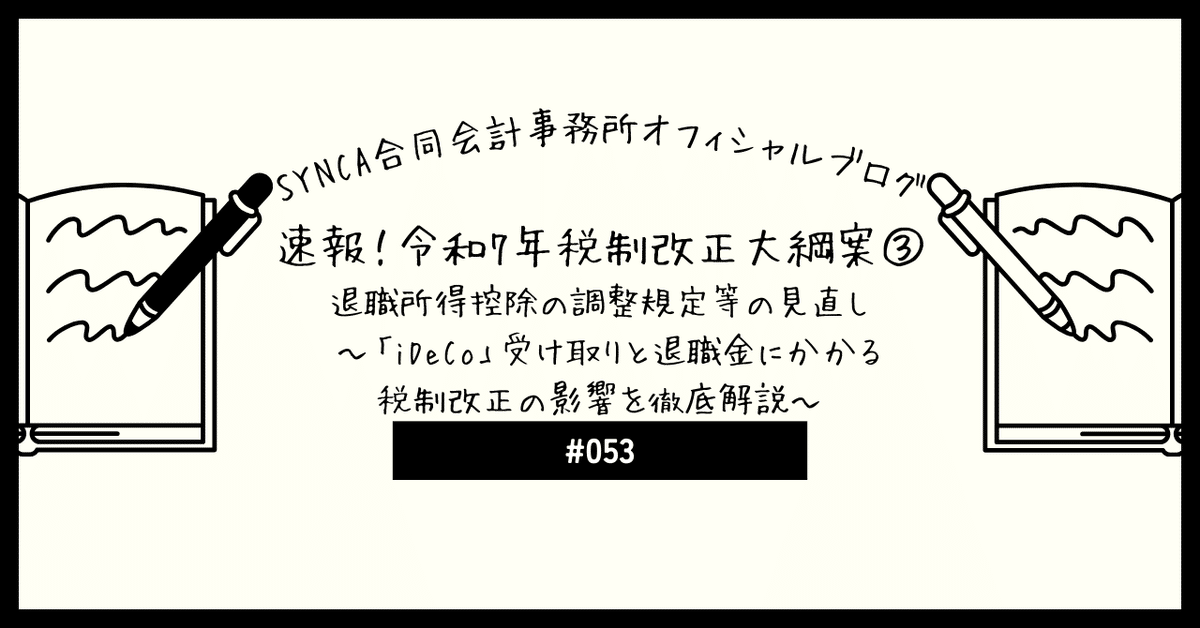
速報!令和7年税制改正大綱案③退職所得控除の調整規定等の見直し ~「iDeCo」受け取りと退職金にかかる税制改正の影響を徹底解説~
はじめに
こんにちは。SYNCA合同会計事務所 税理士の細見です。
前回の記事では、令和7年度の税制改正大綱をもとに、老後資産形成を支援するために注目されている確定拠出年金制度やiDeCo(イデコ)の見直しについて解説しました。
今回は、上記に関連して令和8年(2026年)から適用される予定である「退職所得控除の調整規定等の見直し」について解説します。
※本記事の内容は2024年12月時点の情報に基づいています。
目次
◆この記事を読んでほしい人
・「退職所得控除」や「退職金」について詳しく知りたい方
・退職所得控除が改正されることによる税負担の変化を理解したい方
・「iDeCo」の受け取り時期と退職金の受給タイミングの調整について考えている方
◆この記事を読んでわかること
・退職所得控除の調整規定等の見直し内容
・「iDeCo」の受け取り時期と退職金の受給タイミングによる税負担への影響
・改正のデメリットとそれに対する対応策
・退職所得控除の計算における注意点や今後の対応方法
退職所得控除と「5年ルール」の重要性
退職所得の特徴
退職金やiDeCoの一時金は「退職所得」として給与所得とは別枠で課税され、税制上有利。
退職所得控除を活用すると、受け取った金額の半分にしか税金がかからず、税負担が軽減。
「5年ルール」のポイント
最初の退職所得受け取りから5年以上経過すれば、2回目の受け取りにも退職所得控除が適用。
例:退職金①と退職金②の受け取り間隔を5年以上空けると、両方に控除をフル活用可能。
改正のポイント
(1) 趣旨・背景
これまで、退職金や確定拠出年金(DC)の老齢一時金を受け取る際には、退職所得控除が適用されていました。
ただし、短期間で複数回受給する場合、控除を満額利用できるケースとそうでないケースがありました。このため、不公平感が指摘されていました。
(2) 改正内容
1. 調整期間の延長
・改正前
確定拠出年金(DC)の一時金を受け取った後、5年以内に退職金を受け取ると、退職所得控除の「勤続年数の重複排除」が適用されていました。
・改正後
この調整期間が5年から10年に延長されます。
例えば、60歳でDC一時金を受け取る場合、勤め先等の退職金による退職所得控除を満額利用できる年齢が65歳から70歳に変更されます。
2. 申告書の提出義務
改正後、確定拠出年金(DC)の一時金に係る「退職所得の受給に関する申告書」の保存期間が10年(改正前7年)に延長され、また、退職所得の源泉徴収票の税務署への提出が、全ての居住者(改正前:居住者である役員)について義務化されます。
3.実務への影響
・会社員の場合
退職金の受給タイミングを自分でコントロールできないことが多く、60歳でDC一時金を受け取ると、退職金の受給時に控除をフル活用するには70歳まで待つ必要が生じます。これにより、改正前よりも税負担が増える可能性があります。
・自営業者の場合
受給タイミングを比較的自由に調整できるため、iDeCoの一時金や小規模企業共済などの受給計画を立てることで控除の適用を最大化できる可能性があります。
退職所得のシミュレーション
前提条件
会社からの退職金: 2,500万円
iDeCoの一時金: 300万円(運用歴20年:40歳開始→60歳で受け取り)
勤続年数: 35年(65歳退職を想定)
課税率(概算): 所得税10%、住民税10%(合計20%)
退職所得控除:
勤続年数35年の退職所得控除額:1,850万円(800万円+70万円×(35年-20年))
iDeCoの退職所得控除額(20年運用の場合):800万円(40万円×20年)
現行ルール(iDeCoを60歳で受け取り、5年後に退職金を受け取る場合)
iDeCoの一時金(60歳で受け取る場合)
・受け取り額:300万円
・退職所得控除(iDeCo分):800万円
・計算式: (300万円 - 800万円)×1/2 = -250万円(課税なし)
退職金(65歳で受け取る場合)
・受け取り額:2,500万円
・退職所得控除(35年勤続分):1,850万円
・計算式: (2,500万円 - 1,850万円)×1/2 = 325万円
・税金: 325万円 × 20% = 65万円
結果
・iDeCoは非課税で受け取り
・退職金にかかる税金は65万円
10年ルールが導入された場合
iDeCoと退職金が合算されるケース
iDeCoと退職金が10年以内に受け取られる場合、退職所得控除が一括で適用されます。
・iDeCoの一時金:300万円
・退職金:2,500万円
・合算金額:300万円 + 2,500万円 = 2,800万円
・退職所得控除(35年勤続分):1,850万円
・計算式: (2,800万円 - 1,850万円)×1/2 = 475万円
・税金: 475万円 × 20% = 95万円
結果
・合計税額は95万円
・現行ルールの税金65万円と比較すると、30万円の増税
10年ルール導入後の対策
分割受取(年金方式)の活用
iDeCoを一時金ではなく年金形式で分割受取すると、課税対象が小分けになり、税負担が軽減される可能性があります。
退職金の分散受取を検討
企業によっては退職金を分割で受け取る選択が可能です。
これを活用し、iDeCoとタイミングを調整すれば、課税リスクを分散できます。
他の資産形成手段を活用する
NISAなどの非課税制度を併用することで、iDeCoや退職金以外の資産を計画的に形成し、税負担を分散します。
これらの対策により、税負担を抑えながら効率的な資産受け取りが可能になります。
終わりに
退職所得控除の調整規定の見直しは、確定拠出年金(DC)の一時金や退職金の受け取りに関わる税負担に大きな影響を与えます。改正により、控除が適切に適用されることが期待されますが、受け取るタイミングや手続きの注意点を誤ると、税負担が予想以上に増加する可能性もあります。
「iDeCo」の受け取り方や退職金受給のタイミングを慎重に調整することで、税負担を最小限に抑えることができます。改正を踏まえた最適な資産運用と税金対策が求められる時代です。
SYNCA合同会計事務所では、税制改正に関するご相談や、確定申告のサポートを提供しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
