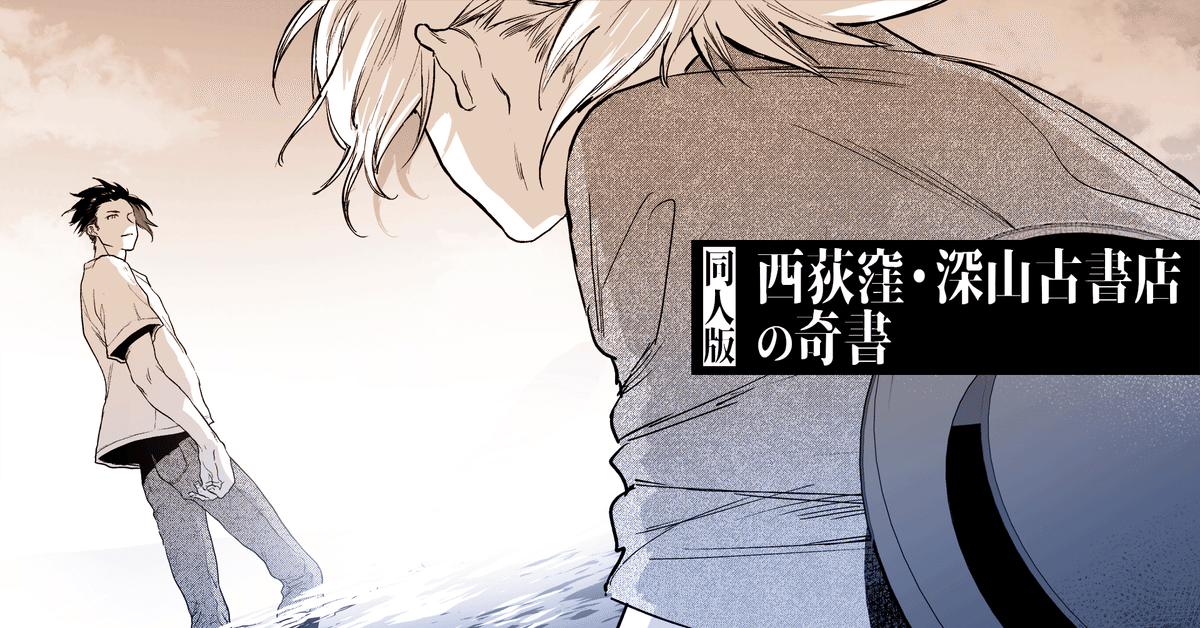
【小説】同人版 西荻窪・深山古書店の奇書|『旅行ガイド誌』の奇書
肌寒くなってきた頃、いつもと同じように深山古書店で読書を楽しんでいた凛太郎に一本木は旅行は好きかと訊ねる。一本木の発言の意図が掴めず困惑する凛太郎に、一緒にどこかへ行きたいと伝え――。

「凛太郎、旅行は好きか?」
「旅行? ボク、インドア派なんであんまりいきませんけど……」
どうしてそんなこと聞くんですか、と凛太郎はわざとらしいほど首を傾げる。予想していた通りの反応ではあったが、質問の答えにはなっていない。俺は好きかどうかを聞いたのだ。
「一緒にどこか行きたいと思ったから聞いた」
「えっ? ボクと? 一本木さんが?」
凛太郎は俺と自分を交互に指さす。だからそうだと言っているのに。とはいえ、唐突すぎたかもしれない。休日の昼下がり、冬の気配が近づく茶の間で本を読みながら出す話題としては意外なものとして受け取られたのだろう。
「え、あの、本当に?」
「嫌なら誘わないけど」
「あっ、ええと、いや、全然……アウトドアが苦手くらいで、温泉とか好きです!」
石のような肩がほぐれるし、と凛太郎は少し早口に喋る。それから、はたと何かを思いついたように立ち上がって、二階へ駆け上って行った。
深山古書店の二階から何か出てくるとしたら、それはもう奇書以外にない。温泉に関わるものか、それとも旅行に関わるものか、そういう内容の奇書があるのだろうか。小説や絵本、図鑑もあるから、図録なんかがあってもおかしくない。
ぼんやりしながら待っていたら、凛太郎が階段を駆け下りてきた。最後の二段で飛ぶのをやめろと言っているが、止める気配がない。転んだら階段に頭を打ちそうで、何となく気になっている。
「これっ、これも奇書なんです!」
手渡された奇書を見る。どこからどう見ても、旅行ガイド誌である。しかも一つのエリアを重点的に紹介するものらしく、表紙には伊豆と大きく地名が乗っている。
「……あの、何て言うか……練習、しませんか」
「練習?」
「大変お恥ずかしい話なんですけど、ボク、基本的には一人旅派なもので……誰かと行くのは初めてなんで、ご迷惑をおかけする前に予習したいというか……」
現地でいまいち足並みが合わずに微妙な空気になるのを避けたい、と絞り出すように言う凛太郎に少し笑ってしまった。今まで何度も奇書の異世界に一緒に行っているのに、今更そんなことがあるだろうか。知らない場所に二人で行って、何も問題がなかったから誘っていることに凛太郎は気付いていないらしい。
ただ、実際に行く前にお試しで行くのは良いかもしれない。その方が凛太郎も安心できるだろうしと考えて頷けば、それなら早速と書斎から奇書の異世界へ赴くことになった。
「めずらしいですよねえ。日本の、それも温泉の特集が奇書になってるなんて、ボクからすればありがたいですけど」
外出が苦手なので、と続ける凛太郎は、裸足で浜辺をさくさくと歩いていく。
奇書の外においては冬だが、この奇書は初夏を前に発行されたものらしく梅雨のじっとりとした空気はあるが過ごしやすい。俺も同じように素足になって砂浜に足をつけると、実際の浜辺とは違う、軽い砂のような感覚があった。
宿は海が見える大きなホテルで、ホテルマンは誰もいないのに部屋が誂えられていた。海の音が聞こえる、気持ちのいい部屋だった。荷物も持たずに来たから、そのあたりを歩いてみようと海まで出てきた。
同じように裸足になって、凛太郎の足跡を追う。足のサイズが違うと気付いて、足跡を踏むのではなくて少しずらして歩いた。凛太郎は海から吹いてくる風に帽子を飛ばされないよう、片手で押さえながら波打ち際まで歩いていく。
「海、あんまりいったことないんすよね。夏と言えばクーラーとアイスと本ですよ」
「冬もそうだろ」
「わかります? 冬はストーブとアイスと本ですね、干し芋を焙ってもいい」
茶の間にあるストーブによくアルミホイルが乗っているが、あれは干し芋を焙ったあとのものだったか。火傷するからすぐ片付けろと言っているが、凛太郎は無精だから都度変えずにそのまま何度も使っているのだろう。
凛太郎は波に濡れないよう、一歩引いて立ち止まっている。俺はなんだか物足りない気がして、裾を上げて濡れた砂を踏んだ。足が少し沈むような感覚と、足の裏にぴったりと細やかな砂が張り付く感触が気持ちいい。
「一本木さんって、泳げます?」
「一通りは……」
波が来た。冷たさに体が驚いて震えたが、すぐに慣れた。足の裏の砂が波に攫われていく。
「ボク、泳げないんすよ。一本木さんが波に攫われたら助けられないんで気を付けてくださいね」
あんまり遠くにいかないでくれ、と言いたいのはわかる。ただ、何となくもう一歩前に踏み出した。凛太郎を振り返ると、きょとんと目を丸くしている。話を聞いていたのかと言いたそうな目に少し笑ってしまった。
「奇書の中で溺れるとどうなる?」
「溺れたことないからわかりませんけど……えっ、あの、ダメですよ! 一本木さん、ちょっと!」
引き留めるのを知らんぷりで、大股に二歩進んだ。ちょうどこちらに来た波とぶつかって、顔まで飛沫が飛んだ。冷たい。水を含んだ服は少し重たいが、足をとられるほどではない。
膝の下くらいまで浸かっただろうか。どうせ濡れるならもう少し行きたい、と水の抵抗を感じながら足を踏み出せば、後ろから腕を引かれた。
「ダメですって、ダメ!」
凛太郎が濡れるのも気にせず走ってきて、俺の腕を掴んだ。風が吹く。帽子が飛んで、砂浜を転がって行った。思わず笑ってしまう。普段と逆だ、と思ったのだ。俺が凛太郎を止めてばかりで、凛太郎はすぐにどこかに飛び出して行ってしまう。興味の赴くまま、好奇心に任せて。
俺も、このまま海に入ったら凛太郎はどういう顔をするだろうかと思ったのだ。
俺が黙って浅瀬に立っているのを、凛太郎は強く腕を引いて砂浜まで引き上げた。水から出てみると、濡れた服は重たくて不愉快だ。
「一本木さん、あのね……本当に、お願いしますから」
「うん、悪かった。ふざけすぎた」
凛太郎が俺の腕から手を離さない。もう波打ち際に行くことは出来なくて、二人で砂浜に座り込んで、しばらく打ち寄せる波だけを見ていた。
日が沈みかけ、冷たい風が海から吹いてくるようになった。夜は近く、身体はすっかり冷えている。温泉に行くにはちょうどいい頃合いだが、凛太郎が俺の腕を掴んだまま離さない。
「凛太郎、もう海には入らないから。そろそろ戻ろう」
「……本当にびっくりした。旅行の練習って言ったのに、酷いですよ一本木さん!」
「何となく、気が向いたから」
凛太郎が驚く顔が見たかったから、というのは何となく違う気がして、黙っておいた。着物の砂を払って立ち上がったのに続いて、俺も砂を払って靴を履く。のろのろと歩き出した凛太郎の横に並んで、ゆっくり歩いた。
「もお……温泉に行くつもりで来たらああいうことするから、お兄さんびっくり……」
「ごめん」
「まだ本番の旅行でどこ行くかも決めてないんですよ? それに一緒に奇書で遊んでくれる人がいなくなるのは寂しいし、居てもらわないと困るんですよボク……」
ただ海に入りたくなっただけなのだが、凛太郎はどうも嫌な想像をしてしまったらしい。まあ確かに、お話なんかではよくあるものなのかもしれないが、俺には無縁のことだ。
「凛太郎は行きたいところあるのか」
「そうですねえ……雪を見ながらっていうのもオツですよね。あ、一本木さんってお酒飲めるんでしたっけ?」
「あんまり強くない」
話しているうちに気分が良くなってきたらしく、ようやく凛太郎が顔を上げた。風に飛ばされた帽子は見つからなくて、いつもは見えない凛太郎の頭のてっぺんがよく見える。三つ編みに砂が絡んでいるのが見えて、海に入ってきたときについたのか、砂のついた手で触ったのか、どちらだろうと気になった。
ホテルには誰もいないのに、温かな明かりが灯っている。俺たちのほかに客はいないのに全室の明かりが点いていて不自然なようにも思えるが、一応これは奇書の異世界であるから、明かりは一元管理のものなのかもしれない。
「うん、まあなんていうか、ボクも楽しみになってきました」
凛太郎が俺の方を見て、にんまりと笑う。乗り気になってくれたならいい。不用意に驚かせたことは申し訳なかったが、機嫌を直してくれたようで俺もほっとした。
「ま、とりあえず今日はここにお世話になりましょうね!」
温泉、温泉、と鼻歌交じりにホテルへ飛び込んでいく。とりあえず練習と言いながら、ほとんど旅行と同じである。実際に行くときもこんな風なんだろうと思うと、俺も釣られて笑ってしまった。

