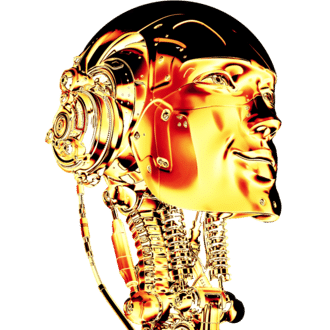思い出「蜃気楼のヒーロー」
【転校生】
10歳の時。
俺は、三郷団地から東京の荒川区に転校してきた。
転校してきたばかりの時は、誰にも話しかけられず1人ぼっちだった。
でも1週間位たつと、ほとんどのクラスの子達と会話する事が出来た。
そして、気が合いそうな子もちらほら解ってくる。
当時のクラスの子達は、仲が良い子同士がグループを作っていた。
俺はその中でも、気が弱いグループに入った。
悪ガキグループもあったけど、俺は気が弱かったので入らなかった。
この気が弱いグループは、いつも誰かの家に集まって遊んでいた。
そこで遊ぶのは、テレビゲーム。
俺は、テレビゲームが大好きだったので、凄く楽しくてしょうがなかった。
ゲームソフトも新しいのを買う時は、みんな別々の物を買った。
そうする事により、みんなの家を回れば色々な種類のゲームが出来た。
俺の家は、ゲームをする時間が1日1時間しかできなかった。
でも、友達の家に行けばゲーム時間が決められてなく何時間でもできた。
だから俺は、大体他人の家に押しかけてゲームをしていた。

【自慢満々】
ある時ゲームばかりじゃなく、どこかに遊びに行きたいと言う事になった。
そしてどこが良いか相談したら「アメージングスクエア」が良いという。
ここは、人が実際に入って探索する立体迷路だった。
俺は、ゲームでの3Dダンジョン迷路が得意だったので即OKした。
俺が得意だったゲームは「ファンタシースター」というゲーム。
このゲームは、ダンジョン部分が3Dの迷路になっていた。
俺は、このダンジョンの地図を暗記のみで進む事が出来、超得意だった。
この時、きっとリアルでも俺の得意な迷路で自慢できると意気揚々だった。
行く場所は、隣町の北千住。
人数は、5人で行く。
当時ここは、まだ全然開発されてない街で、広大な空き地があった。
そこに仮設的に作られた迷路が「アメージングスクエア」だった。
俺は、母親に出かける事を伝え、5000円のお小遣いを貰う事が出来た。
そして当日、みんなで集まって電車で北千住に向かった。
北千住駅を降りたら、目の前の広大な土地に、デカデカと迷路がある。
我々は、楽しさで興奮して早速迷路に潜入していった。

【感ナビゲーション】
俺は、とりあえず適当に歩いて大体の地図を暗記した。
みんなも、適当に歩いて、個人個人でグルグル回っている。
この調子なら、俺が1番最初に出られるなと確信していた。
俺は、頭の中で作った「感ナビゲーションシステム」で出口に向かった。
しばらく歩いていると、感ナビに載っていない場所が現れる。
それは、2階部分だった。
この時、俺はこの迷路が3階建てだと言う事を初めて知った。
確かに高い位置にコースがあったのは見えた。
でもそこは、ただの展望台だと思っていた。
俺は、この階層を制覇しないと外には出られない事を悟った。
仕方ないので、感ナビに無いこのコースに潜入していく。
そうしたら、この立体迷路が超複雑で、何度も同じ場所を回ってしまう。
途中、友達と会ったけどそれっきり誰にも会わなかった。
きっと、うまく出口方面に進んだのだろう。
俺は、何度も上に行ったり下に行ったりして、永遠に出られないでいた。
この迷路には、途中リタイヤできるようにコースの所々に出口がある。
でも、下らないプライドが許さずここからは、意地でも出たくなかった。
こんな調子で迷路を回っていたら、入り口に戻ってきてしまった。

【ビリケツ・ヒーロー】
俺は、入り口から外側を見たら、何故か全員ゴールしていた。
得意だと自信満々だったこの俺様が、皆ゴールしているのにまだ入り口?!
この時俺は、あまりにも恥ずかしくて速攻迷路の中に走って消えていった。
まだ入り口にいる事がバレたら、絶対ヘッポコ野郎のレッテルが張られる。
そして、もう頭がパニックになりながら焦って入り口を探し始めた。
30分くらい迷路で迷っていたら、迷路の1番高い部分に友達4人がいる。
そして友達がそこから「さっきスタート地点にいただろー!」と叫んだ。
俺は、恥ずかしくて頭の中で「ヽ( ;´Д`)ノ ヤメテー言わないで!」と発狂した。
4人の友達は、俺だけ迷路からなかなか出てこないから心配してたようだ。
そしてゴール地点から再度迷路に侵入して、コースを教えに来てくれた。
友達は、1番高い所から下を見下ろし、俺にコースを教えてくれた。
俺は、その指示されたコースをたどってゴールに向かった。
そして高台で友達と合流してゴールまで案内され、やっと出る事が出来た。
ゴールにたどり着くまでかかった時間は、4時間位かかっていた。
みんなは、1時間半から2時間位でゴールしていたみたいだ。
俺はこの時、精神的にも肉体的にもクタクタになっていた。
そして友達に「お前ダッセーな(笑)」と言われてしまう。
もう、ショックで気を失いそうだった。
最後に我々は、名物の手作りアイスを食べて帰った。
アイスを食べている時、まだ気が動転していて、味なんて覚えてない。

いいなと思ったら応援しよう!