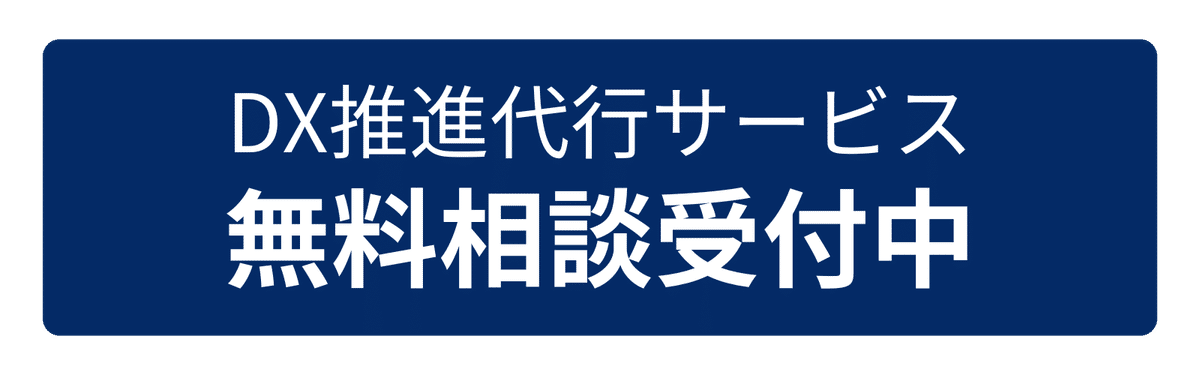DX時代の「業務フロー」完全ガイド~1000枚の経験から導いた成功の法則~
この記事をご覧になっているということは、業務フロー作成について関心がある、または「そもそも業務フローってどう作ればいいの?」と悩んでいる方が多いのではないでしょうか。
私自身、これまで10年以上で1,000枚以上の業務フローを作ってきました。DX推進や業務改善、新規事業の立ち上げなどに携わり、たくさんの成功例と同時に、失敗例も目の当たりにしてきました。
その中で痛感したのは、業務フローは単なる「手順書」ではないということ。適当に作った業務フローでは、いざプロジェクトが動き出したときに想定外の問題が発生し、最悪の場合、事業の撤退にまで追い込まれることもあります。一方、しっかりと設計された業務フローは、現場に安心感をもたらし、プロジェクトをスムーズに進める土台となります。
この記事では、私が実際の現場で培った経験をもとに、実践で使える業務フロー作成のコツをお伝えします。専門用語は最小限にしつつ、「業務フローってこういうことか!」と腑に落ちるような内容を目指しました。この記事を読み終えた後には、「これなら自分でもできそう」と思ってもらえるはずです。
業務フローって、なぜ必要?
業務フローは、ただ「作るべきもの」ではありません。ちゃんと理由があって作るものです。
ここでは、業務フローの役割を4つに分けて説明します。
1. 業務の抜け漏れを防ぐ
「これ、誰がやるんだっけ?」「あのデータ、どこに入力するんだっけ?」という状況、身に覚えがありませんか?業務フローは、そういった抜け漏れを防ぐための地図のようなものです。たとえば、新規顧客を獲得したときの契約締結プロセスを明確にしておけば、契約書が未送付のまま放置される、なんてミスは起きません。
2. システムやデータの要件整理
業務フローがあることで、「この作業にこの機能が必要」「ここでこのデータが必要」といったことが明確になります。逆に業務フローがないと、システム開発の段階で「そんな機能、最初から必要だって言いました?」という食い違いが発生します。業務フローは、要件を整理し、全員の認識を合わせるための道具でもあるんです。
3. 未来の関係者への引き継ぎ
プロジェクトが進む中で担当者が変わることは珍しくありません。業務フローがしっかりしていれば、新しい担当者でも「この通りにやれば大丈夫」と業務をスムーズに引き継げます。逆に業務フローがなければ、慣れるまでに無駄な時間がかかり、ミスも増えがちです。
4. 業務改善の基盤
業務フローは、現状を見える化する役割も果たします。一度描いてみると、「このプロセス、いらないかも」といったムダが発見されることも多いです。新しい仕組みを作る前に、まず業務フローを作る。これが業務改善の第一歩です。
業務フロー作成におすすめのツール
業務フローを作成するためには、適切なツールが必要です。ツール選びを間違えると、作業効率が落ちるだけでなく、後々の修正が面倒になることも。ここでは、おすすめのツールを3つご紹介します。
1. FigJam
直感的に操作でき、チームで共同編集もできるツールです。修正が簡単で、長期的に運用しやすいのが特徴。クラウド上で作業できるため、DX推進の現場では特に重宝します。
2. スライドツール(GoogleスライドやPowerPoint)
「うちの会社ではFigJamは使ってない」という場合でも、スライドツールなら代用できます。見た目もきれいに仕上がるので、関係者への説明資料としても使いやすいです。
3. ExcelはNG
意外とExcelで業務フローを作っている人もいますが、これはおすすめできません。操作性が悪く、修正や管理が大変です。業務フローは「見やすさ」と「使いやすさ」が命なので、Excelは避けましょう。
実際に、作成して途中に業務をを追加したことある方は分かるかと思いますが、心が折れますよね。
業務フローはExcelという常識を作った人を呪いましょう。笑
業務フローの定義を決める
ツールを決めたら、次に業務フローの「定義」を明確にします。このステップでは、業務フローのスコープ(範囲)と粒度(詳細さ)を定めることが重要です。
スコープ(業務範囲)
業務フローでどこからどこまでの業務を対象にするかを決めます。たとえば、顧客問い合わせ対応のフローを作成する場合、「問い合わせ受付」から「解決報告」までをスコープとする、といった形です。
粒度(詳細さ)
粒度とは、業務をどの程度まで細かく分解するかの基準です。以下を目安に考えるとよいでしょう
作業目的が変わる(例:問い合わせ内容の確認と回答作成が別の目的で行われる場合)
作業者が変わる(例:営業担当からサポート担当に引き継がれる場合)
作業タイミングが変わる(例:即時対応と後日対応が異なる場合)
作業環境が変わる(例:オンライン対応とオフィス対応の違い)
ポイント: 粒度が細かすぎると「作業マニュアル」になり、抽象度が高すぎるとフローとしての価値が薄れます。適切な粒度を保つことが、実用的な業務フローを作るカギです。

表記ルール
BPMNは参考程度に。複雑にしないことがカギ
「業務フロー作成にはBPMNを使うべき」という話を聞いたことがある方もいるかもしれません。確かにBPMN(Business Process Model and Notation)は、業務フローを標準化するための便利な記法です。でも、現場でフル活用しようとすると、かえって分かりにくくなることも。
私のおすすめは、BPMNを参考にしつつ、使う記号は8個程度に絞ることです。以下に例を挙げてみます。
※全然BPMN無視してますが、これが最適解だと思っています。

この程度に収めれば、シンプルで分かりやすい業務フローになります。
業務フロー作成のプロセス
業務フロー作成を成功させるには、ただ手順を追うだけでは不十分です。正しい考え方と進め方を押さえることで、実用的かつ効果的なフローが完成します。ここでは、業務フロー作成を進める上での6つの具体的なプロセスを解説します。
※作成イメージ

1. 関係者の巻き込みとヒアリング
業務フロー作成の第一歩は、プロジェクトに関わる関係者を集め、現場の意見をしっかり聞くことです。現場を知らない状態でフローを作ると、後から「実態と違う」という問題が必ず出てきます。
ヒアリングのコツ
最初から全員を巻き込む必要はありません。業務をよく知るキーパーソンに絞って話を聞きます。
「誰が、何を、いつ、どこで、どうやって、なぜ行うのか」という5W1Hを明確にしながら進めます。
問題点や課題も合わせて聞き出すと、業務改善のヒントになります。
ポイント: ヒアリング時に得た情報をすべてフローに盛り込む必要はありません。あくまで核となる業務の流れに集中することが重要です。
2. 現状フローの見える化
現状の業務をまずフローに落とし込みます。この段階では、ありのままを描くことが大事です。理想の状態を考えるのは後回しにしましょう。
方法
図解ツール(FigJamやスライド)を使い、現在の業務フローを図式化します。
無理にきれいにまとめる必要はありません。雑にでも、全体の流れが把握できる形にすることが目的です。
手作業やシステム操作など、どのような方法で処理されているかを明示します。
注意点: 現状フローを描くとき、「こうしたい」という意見が混ざることがありますが、今はそれを除外してください。後で改善するステップがあります。
3. ボトルネックや課題の特定
現状フローを見える化したら、次はボトルネックや課題を洗い出します。ここが業務改善や新規フロー設計の基盤になります。
課題を探す視点
同じ作業が複数箇所で重複していないか?
手動で行っている作業を自動化できないか?
ボトルネックとなる作業が原因で、後工程が滞っていないか?
具体例:
たとえば、営業プロセスで「契約書の承認」が毎回2日以上かかる場合、それが全体の業務を遅らせている可能性があります。この部分に注目して改善案を考えることが、効率化への第一歩です。
4. 理想のフローを描く
現状の課題をもとに、理想的な業務フローを設計します。この段階では、「どうしたら業務が最も効率的になるか」を徹底的に考えます。
理想のフローを描くコツ
未来の関係者を想像する: 将来的に関わる人が迷わないよう、わかりやすい構造を意識します。
シンプルにまとめる: 複雑にしすぎると現場で運用できません。
自動化やツールの活用を前提に考える: 現状の手作業を見直し、システム化できる部分を積極的に組み込みます。
ポイント: 理想のフローを描く際には、現場の「現状のやり方」にとらわれすぎないことが重要です。現状維持バイアスを外し、最適な形を考えましょう。
5. ステークホルダーとの確認・フィードバック
理想のフローを設計したら、それを関係者に確認してもらいます。ここで重要なのは、意見を聞く際に事前に「こういう形が理想的」と方向性を示しておくことです。
確認時のポイント
現場の視点から、「実際に運用可能か」を評価してもらいます。
意見が分かれる場合は、最終的に「事業にとっての最適解」を優先します。
誰がどのタスクを担当するか、責任の所在を明確にすることで、曖昧さを防ぎます。
注意点: この段階で全員の納得を取る必要はありません。「最低限合意を得られる」形を目指しましょう。
6. 試行運用と改善サイクルの開始
業務フローは完成がゴールではありません。実際に運用を始めることで、見えてくる課題があります。それを随時修正することで、より完成度の高い業務フローに近づきます。
試行運用時のコツ
まずは限定的な範囲でテスト運用を行います(パイロット運用)。
現場の意見やフィードバックを定期的に収集し、フローを調整します。
想定外のイレギュラーが発生した場合、その都度対応策を考え、フローに反映します。
実例:
新しいフローで問い合わせ対応プロセスを改善した場合、問い合わせ件数が急増するケースがあります。これに対応できるキャパシティが必要かを試行運用で確認し、必要なら担当者を増やすなどの対応を取ります。
補足:業務フロー作成で陥りやすい落とし穴
最後に、業務フロー作成でありがちなミスについても触れておきます。
理想を詰め込みすぎる: 「これもやりたい」「あれもやりたい」とフローが複雑化し、現場で使えなくなる。
現状のフローを無視する: 現場を無視した理想形は、運用フェーズで破綻します。現状とのギャップを埋めることが重要です。
関係者の意見を聞きすぎる: 意見を集めすぎると、フローが妥協の産物になりがちです。事業全体にとっての最適解を優先しましょう。
最後に
業務フローは、ただの「図」ではなく、事業の未来を支える基盤です。完璧を目指す必要はありませんが、「実際に使えるもの」を意識して作ることが大切です。
この記事を読んで、「業務フローってちょっと面白いかも」と思ってもらえたなら幸いです。何事も経験です。ぜひ、今日から一歩踏み出してみてください!
ちょっと宣伝
株式会社スナネコでは、"現場定着型DX"という現場が使いこなせる使い続けられるDX推進を支援しております。
DXに失敗した経験がある。これからDXを始めていきたいけど、何をすればいいかわからない方がいれば、お気軽に無料相談してくださいませ。