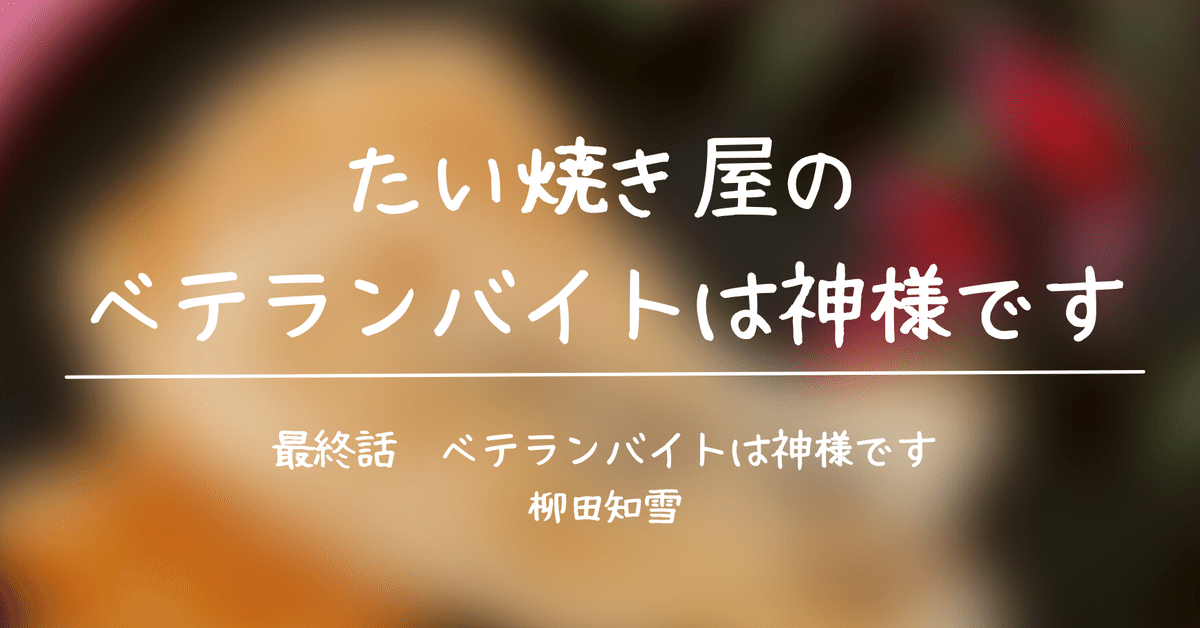
柳田知雪『たい焼き屋のベテランバイト』最終話 ベテランバイトは神様です 前編
<前回までのあらすじ>
入院が伸びた祖父の代わりに、たい焼き屋『こちょう』の代理店長を務める結貴。
こちょうが並ぶたちばな商店街では、夏祭りが開かれることに。真昼くんの大学の友人がそこで出し物をするという。それは、こちょうでバイトする龍神、和泉さんの伝説を元にした舞台だった。そんな舞台で、和泉さんの友人である宇迦さんが何やら企てていて……?
今までのお話はこちらから!
第一話 大丈夫だって言われたい 前編・後編
第二話 我が家が一番? 前編・後編
第三話 曲げない流儀
第四話 そこに楽しいはあるか
第五話 憧れのカタチ 前編・後編
第六話 甘い思い出 前編・後編
第七話 祭り前夜の焦燥 1・2・3
最終話 ベテランバイトは神様です 前編
商店街は提灯と夕日に照らされて赤く染まっていた。
普段、居酒屋をやってる店は店先に机を出して焼きそばを、その向かいの花屋では持ち手に花のコサージュをつけて風船を売っている。
いつもとは違う商店街の風景。まさに非日常という光景に、老若男女問わず浮かれていた。祭りと人混みの熱気に当てられてか、冷たいものを求めてこちょうで売り出しているソフトクリームも、冷やしフルーツたい焼きも売上は好調だ。
「冷やしフルーツたい焼き、ソフトクリームトッピングで二つお願いします!」
「はいよ!」
ソフトクリームを巻くのは苦手、と言っていた和泉さんだったが、今日は注文が多すぎて、いつしか芸術品のような渦巻きを作るようになっていた。天辺でツンと立ち上がったクリームの角と、そんな雪山のようなソフトクリームに寄り添うたい焼きに、お客さんたちはにこにこと頬を緩める。
新メニューを作るまでには至らなかったけれど、冷やしフルーツたい焼きをいつもの倍ストックしておいてよかった。この調子なら早めに売り切れてしまうこともなく、祭りが終わる頃には完売も夢ではなさそうだ。
在庫を確認していると、ソフトクリームが出来上がるのを待っているお客さんが受付口の隣に佇む鳥居を指差した。
「あの、この鳥居ってなんですか?」
今日の祭りに合わせて、夏仕様に周りを飾った鳥居。可愛い、と声を上げながらスマホを構える彼女に応えようとした瞬間、和泉さんが注文のソフトクリームを突き出してフン、と胸を張る。
「俺の社だ! 分祀だが、お参りするといいことあるかもなぁ!」
「えーお兄さん面白い! じゃあ、おつりの十円入れちゃお」
「おう! 毎度あり!」
祭りの空気に財布の紐も緩んでいるのだろうか。今日はいつも以上に賽銭箱にお金を入れてくれる人が多い気がする。おかげで和泉さんもどこかご機嫌だった。
時計を確認すれば、真昼くんたちの演劇の時間も迫ってきていた。劇の間は店を閉めて和泉さんと見に行こうかと話していたのだが、この盛況ぶりに若干後ろ髪を引かれないでもない。
しかし、演劇を中心となって動かしている宇迦さんのことも気になった。
「結貴さんっ!」
突然、店の前へと駆けてきたのは息を切らした真昼くんだった。
「どうしたの?」
「卯野ちゃんが倒れた!」
「えっ!?」
卯野さんは和泉さんの龍神伝説をモチーフとした舞台で、和泉さんの恋人となるみすずさん役を務めることになっていた。
舞台を回すのは地域伝承研究部の部員と、真昼くんの助っ人を入れても五人という少数精鋭だ。ひとりでも欠けたら成立しなくなることは容易に想像できる。
普段は何とかなる、と笑っている真昼くんがこれだけ慌てているのも当然だった。
「代役……を立てるのも難しいよね。今から台本を直すなんて無理だし……」
「それもだけど、卯野ちゃんが舞台に出るって言って引かないんだよ!」
「え……」
「熱もあるのに……でも、牛尾も誰もみんな止めなくてさ。何とかなる! って変に熱くなってて……」
宇迦さんの顔が脳裏を過る。今、彼らを動かしているのは牛尾くんに取り憑いた宇迦さんの力と言っても過言ではない。練習中から何かしらの術を使い、伝承研究部のみんなの心を惑わせているようだった。
卯野さんの強行も、もし宇迦さんに操られているとしたら? そんな疑念に、すっと心臓が冷えていった。
今日まで、牛尾くんたちに多少の負担があると知りながらも、それ以上に宇迦さんの和泉さんへの想いの強さを否定できなかった。否定できるほどの正義感も私にはなかったし、何より、和泉さんが消えないで済むのなら、と私自身もどこかで願っていた。
願いながら、その責任を全部宇迦さんに押しつけようとしていた自分はどれだけ都合が良いのだろう。自分だけ手を汚さずに、その結果だけを欲するなんて。
「和泉さん」
「あ? 何だよ、今から次のくりぃむ巻いて……」
「お店、しばらくお願いしてもいいですか?」
「はぁ!? このくそ忙しい時にどこ行く気だよ!?」
和泉さんが紙のカップを握り潰しそうになりながら私を振り返る。
宇迦さんのことは、和泉さんには話していない。多分、宇迦さんが自分から話していないということは、和泉さんにわざわざ伝えたい話でもないだろうから。そして、私の牛尾くんたちへの罪悪感が何となく口を重くさせていた。
伝承に沿ったあの劇によれば、和泉さんは好き勝手に暴れて人を困らせてはいたけれど、それは別に生贄が欲しいからでも、恐れられたいからでもない。暴れたいから暴れただけ。まるで足を動かすことを覚えた子供が走りたくなるように、動機はシンプルなのだ。
私や宇迦さんの願いなんて関係ない。ただ生きたいから、和泉さんはたい焼き屋で働いている。生きて、いつか未知のお菓子を好きなだけ食べに行けるように。
それならば、私も好き勝手にやろう。
「ごめんなさい! 理由を説明してる暇はないので、今はただ、行かせてください!」
深々と頭を下げると、和泉さんは頭を掻きながら言葉を探すように唸り声を上げる。
「ったく……二人分働くんだ。給料倍にしてくれんだろーな? 店長代理」
「も、もちろんです! ありがとうございます!」
エプロンを脱ぎ去り、裏口から店を出ていく。窓越しに店を切り盛りする和泉さんを見遣って、外で待っていた真昼くんへと視線を移した。
「卯野さんたちのところに行こう!」
「ごめん、結貴さん……」
「真昼くんが謝ることじゃないよ」
どちらかと言えば、謝るのは私の方かもしれないのだから。
控室用のテントへと駆け込んでいくと、本当に舞台に出るつもりなのか赤い顔をした卯野さんが衣装へと袖を通していた。
「ダメだよ、そんな体で動いちゃ!」
立ち上がろうとする彼女をパイプ椅子へと引き戻す。私が少し触れただけで簡単に尻もちをつくほど、彼女の身体に力はなかった。少し触れただけで、身体が異常を訴えるように熱を放っているのが分かる。
「でも、私が出ないと舞台にならないんです……体調を崩したのも私のせいなんだから、自分で責任を取らないと周りに迷惑が……」
「舞台中に倒れたら、それこそ大変でしょ? 舞台どころか、もっとたくさんの人に迷惑かけちゃうし……何より、卯野さんが心配だよ」
「結貴さん……でも、私……」
真昼くんと一緒に彼女を説得していると、ふっと背筋に冷たい視線を感じる。そろそろと振り返ると、表情という表情を削ぎ落した牛尾くんが立っていた。
「見逃して、って言ったよね?」
暖炉の火のような温かさを感じていた緋色の瞳は、今はただ目の前のものを焼き尽くす業火のように冷酷だった。そんな牛尾くんの姿の宇迦さんと、改めて真正面から向き合う。
「邪魔をするつもりはありません。私は、手伝いに来たので」
「手伝い?」
この方法しか解決策は思いつかなかった。一瞬、躊躇うように唇が震える。でも、きゅっと引き結んで、改めて喉に力を込めた。
「みすずさんの代役、私がやります」
「え?」
その場にいる誰もが驚きの声を上げた。自分でも無茶を言っていると思う。思うけれど、言い出したからには引っ込まない。
「まだ本番まで時間もあるし、練習だって見てたから、みすずさんの台詞も動きも覚えられます。だから、卯野さんを休ませてあげてください」
「結貴さん……」
真昼くんの心配そうな声が耳に届く。正直、演劇なんて小学生の学芸会以来だ。
でも、宇迦さんにだけ汚れ役を背負わせない。卯野さんたちを、これ以上苦しめない。
そのために、私はここに来たのだ。
「……分かった。確かに、君以上の代役はいないだろうからね」
宇迦さんのその言葉に引っ掛かりを覚えるも、背を向けていた卯野さんが私の服の裾を力のない手で掴んだ。
「私は、本当に大丈夫なので……!」
「卯野さん……」
彼女が練習を頑張ってきたのは事実だ。私はそれを、ここ数日間目の当たりにしてきたのだから。
「ごめんね、無理させて……頑張ってくれて、ありがとう」
手を解いたのは宇迦さんだった。卯野さんの手を取り、そして熱で汗の浮かぶ彼女の白い額へと手を差し伸べる。彼の手の平からふわりと光が零れたかと思うと、すうっと卯野さんの瞼が閉じていった。
「今、何を……」
「眠っただけだよ。台本を変えてから、人一倍練習してたから……心身ともに疲労が溜まってたんだろうね」
宇迦さんの呟きに、真昼くんは重々しく頷いた。
「卯野ちゃんは人一倍、責任感強いから……多分、羽鳥も猪川ちゃんもそんな卯野に引っ張られてたと思うよ」
そんな彼女の代役なんて引き受けられるのだろうか、と弱気な自分が顔を出す。しかし、今更撤回するわけにもいかなかった。
「真昼くん、ギリギリまで演出のこととか教えてくれないかな」
「もちろん! 羽鳥も呼んで練習しよ!」
真昼くんと羽鳥くんに音のタイミングや舞台袖での動きなどを教えてもらいながら台本を確認する。幸いなことに卯野さんと背丈もそれほど変わらなかったため、衣装はすんなり着ることができた。
いよいよ時間が目前に迫ってきて、控室用のテントの裏で周りに響かない程度に台詞を声に出す。そうして少しでも確認していなければ落ち着かなかった。
時計を見る度に緊張は高まり、舞台へ上がった瞬間、もし台詞が飛んでしまったら……なんて最悪の想像をして胃が痛む。卯野さんも、こんなプレッシャーと戦っていたのだろうか。
「うぅ……でも、上司に詰られる日々を思えばこれくらい……」
「大丈夫ですか?」
蹲る私へとかけられた声に、ふと顔を上げる。そしてパチリと目が合った瞬間、互いに目を丸くした。
「さ、佐久間くん……!?」
目の前に立っていたのは、ヤムヤミーの同期である佐久間くんだった。夏らしいラフな格好の彼が、舞台衣装に身を包んだ私を頭から爪先まで眺めていく。
「今川さん!? っていうか、その格好は……」
「あ、いや、えっと、今から祭りの野外ステージでやる劇に出ることになって……佐久間くんこそ、どうしてこの商店街に?」
「友達がこの商店街で店やってて、ずっと忙しくて行けなかったんだけど、祭りの時くらい顔を出そうかな、って」
「そうなんだ……」
まさか、こんなタイミングで佐久間くんと会うとは思わなかった。完全に不意を突かれて戸惑ってしまい、世間話のひとつも浮かばない。
沈黙を破ったのは、やはりコミュ力抜群の佐久間くんの方だった。
「なんだか、前会った時よりすごく元気そう」
「あ、うん……そう、だね。前よりは元気になったかも」
「じゃあ、復帰ももうすぐだ」
復帰という言葉に、胸にわずかに苦いものが広がる。
休職が明ければ、またヤムヤミーの社員に戻る。確かに、少し前までの私もそう思っていた。それ以外の選択肢など、まるで残されていないかのように。
「ごめん」
さすがに唐突だっただろうか。私の謝罪に佐久間くんはキョトンと首を傾げる。でも、もう決めたことだから、彼を見据える瞳はぶれなかった。
「まだ正式には出してないけど、私、ヤムヤミー辞める」
「えっ!?」
「実は……他にやりたいことできちゃったから」
昨夜、和泉さんの本当の願いを知った。まだ見ぬお菓子を食べまくって、いつかこちょうに戻ってきたら、その時は私が作った冷やしフルーツたい焼きに負けない面白いたい焼きを作ってやると。
それが果たされるのはいつになるか分からない。ならば、いつまでも私がこちょうを残してやろう、と決めたのだ。何より、こちょうもこちょうに来るお客さんとも、離れるなんてできそうにない。
私の決断に面食らっていた佐久間くんは、くしゃりと笑う。
「なんかいいな、そういうの……でも、やっぱ同期が減るのは寂しいなぁ。今川の作る資料って見やすくてさ、俺すっごい助かってたのに」
そんな風に思ってくれていたとは初耳だった。しかし、控室のテントから真昼くんの声に呼ばれる。
「ごめん、行かなきゃ!」
「おう、頑張ってな」
佐久間くんの何の衒いもない声に送り出され、テントの中へと戻っていく。まさか、こんなに気持ちよく送り出してもらえると思えず、足元はふわふわしている。
佐久間くんに決意を打ち明けられたことで、心は軽くなったのかもしれない。盤石な道とは言えないけれど、自分で見つけた新しい道にその一歩を踏み出せたからだろうか。恐怖よりも、楽しみや期待に胸は満ちていた。
テントの中で待っていた牛尾くんの顔を見て背筋が伸びる。彼を中心にできた円陣の輪の中に加わると、互いに顔を見合った。
「今日が最初で最後の本番……大丈夫、練習通りやればできるよ!」
牛尾くん、もとい宇迦さんの掛け声にそれぞれが頷き返す。テントの外では演劇の始まりを告げるアナウンスが流れ、鼓動は忙しなく高鳴った。
「さぁ、開演だ」
続きは12月6日(月)に公開予定です。
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?

