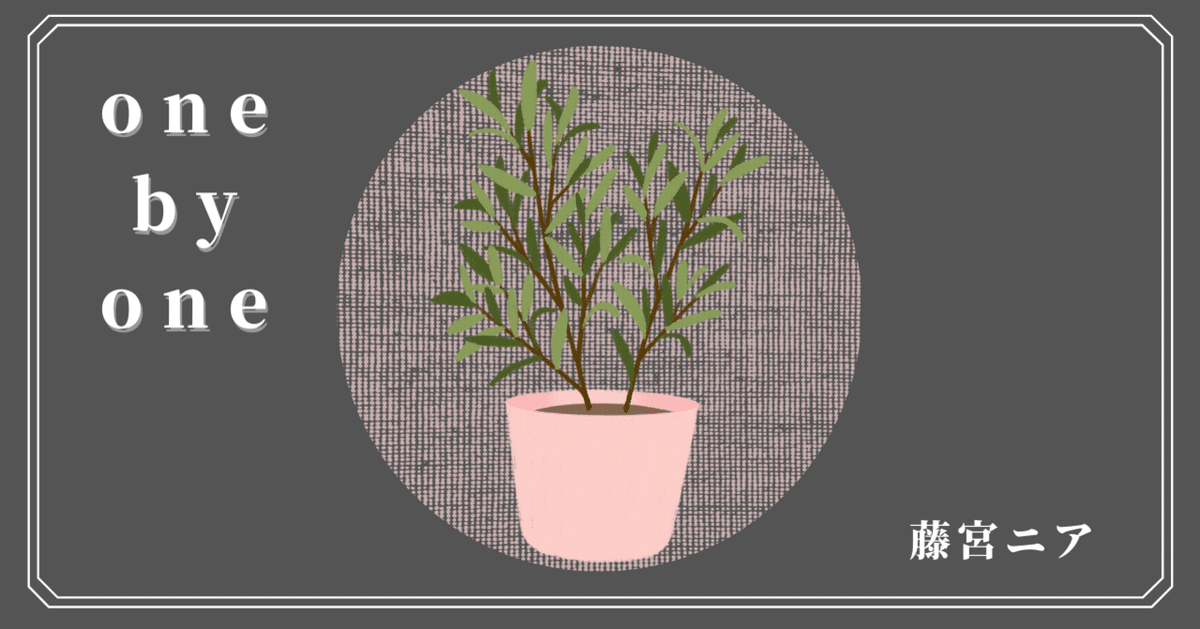
【小説】藤宮ニア『one by one』
今月はゲスト作家として藤宮ニアさんが登場です。
--天井と、支給品のベッド。それから煙草に、Podのご飯。キムの生活で大切なものはそれくらいだった。
ある世界の、暮らしのものがたり。
※こちらは全文無料でお読みいただけます。
機械に仕事が奪われると、言われていた時代があるらしい。この前Podで聞いた話を思い出しながら、キムはぼんやりと天井を仰いでいた。建設業者がクロスを適当に張ったのか、元からこういう仕様なのか、それとも経年劣化的なものなのか、くすんだ壁紙の一部がぼこりと波打つように形を変えている。キムはこの不恰好な天井のことが好きだった。あの中には何か生き物が潜んでいるかもしれないとか、水がたっぷり溜まっていてある日急に落下してくるかもしれないとか、そういうことを無意味に考えながら、昨日と今日の変化を探そうとする。変わっているのかいないのかはいつもよくわからないけれど、なんとなく、この行為は日常の一部になっていた。
キムにとっては、目が覚めた時間こそが朝になった。外の光の具合は彼の暮らしにはあまり重要な事柄ではなく、けれどだからこそ、目覚めた時の世界の様子は毎日ほんの僅かに彼を楽しませた。今日は部屋の窓を覆う黒いネットの端から、微かに光が差し込んでいる。伸びた光が、キムがぼんやりと眺める天井にも淡い線を引いていた。外にはきっと太陽が出ているのだろう。どこか遠くで何かが割れる音がして、人間が怒鳴り合うような音も聞こえる。賑やかな朝だ。
自分の意思とは無関係のところで、キムの口がぐわと開いて欠伸が溢れる。音が遠くなり、耳の奥が暖かくなって、もう一度眠ってしまえばいいと誘われているような気がした。半端に潤んだ瞳でもう一度天井を見る。さっきまであんなに眺めていたはずの歪みを、キムは一瞬見失ってしまう。
*
天井と、支給品のベッド。それから煙草に、Podのご飯。キムの生活で大切なものはそれくらいだった。ベッドが何でできているのかを知らなくても、寝心地がイマイチでも、キムはベッドというものを気に入っている。毎日毎日、ベッドの上で眠りに入る瞬間と、目が覚めて天井と目が合う瞬間を合わせて1と数えることで、キムは生きている実感を得た。キムにとっては、その「1」が生まれる瞬間というのは、とても大切なものだった。
今日の分の1を数えて、起き上がる。最近寝起きにも腰が痛むことが増えたかもしれない。なんとなく弱めのストレッチのようなことをしながら共同水場に向かえば、既に何人かが待っている様子で立ち話をしていた。
「なんだ、今日はもう少し待たないと出ないって?」
「あーあ、昨日のうちに汲んどきゃ良かったな」
「うちの分まだ余ってるけど、ちょっと使う?」
善意の申し出に群がる姿を眺めながら、ちょっとってどれくらいまでのことを言うんだろうと考える。あの群れの中に入る勇気は無いなと視線を落とした先で、キムは自分の足の爪が伸びていることに気がついた。
「監視屋、今日の仕事は終わったか?」
知っている声に顔を向ければ、予想通りの大男がそこにいる。恐らく彼こそ仕事帰りなのだろう、汚れた制服には所々血の染みができていた。
「そっちは忙しそうだね、お巡りさん」
キムの言葉に、大男は胸を張る。お巡りさんことナカムラは、元々はこの辺のエリアでよく問題を起こす厄介者だった。艶を微塵も残さないように脱色された髪を振り乱して暴れていたのを、キムも昔に何度か見たことがある。それがいつの間にか人々の安全を守るヒーローになるのだから、結局人間の善悪なんてあってないようなものなのだろう。ナカムラの逞しい肉体を包む制服は、この辺のエリアを巡回して揉め事を諌める役割の人間が身に着けるそれだった。
「最近また増えてきてるからよ、ボディ狙いの犯罪。お前もしっかり仕事してくれや」
相槌と返事の間のような曖昧な音がキムの口から漏れる。ナカムラは仕事熱心な男になったようだ。持て余したエネルギーをぶつけられるなら、仕事でも暴力でも何でも構わなかったのだろうなとキムは思う。自分のようにエネルギーが少ない人間からすればよくわからない動力ではあるけれど、生き生きと仕事に励むことができるのは良いことだろうと、そんな感覚でキムはナカムラを観察していた。こんな風にナカムラと当たり前に会話をするようになるなんて、仕事というやつは奇妙なものだ。
「どうせ今からすぐ仕事って訳じゃねぇんだろ? 水も出ねぇしよ、Pod行って腹ごしらえでもするかと思ってんだけど」
そう、とキムが返しかけたところで、反応の薄さに気づいたナカムラが「一緒に行くか?」と付け足す。誘われていたのかと理解したキムが、少しの逡巡の後、「行こうかな」と答えた。伸ばしっぱなしの前髪の間からちらりと視線を向ければ、一本歯の欠けた口でナカムラがにかりと笑っているのが見える。やっぱり、自分は奇妙な関係性を生きていると、キムは思った。
帽子とマスクを被り、ナカムラと連れ立って建物の外に出る。外には今日も、あっちもこっちも同じ規格で作られた建物たちと、古い瓦礫が広がっていた。やはり太陽は昇っている時間帯だったようで、キムは一瞬目が眩むのを感じて眉根を寄せる。この太陽は人体にとってあまり良くない光を発しているらしいといつか聞いたけれど、それが何でどういうことが起こってしまうのかということまでは、キムもナカムラも、おそらくこの辺のエリアの人間のほとんどが理解はしていなかった。
エリアのあちこちに残る中途半端な建て替え工事の痕跡は、ここが見捨てられた証だと人々は言う。過去にあった巨大災害の後、完全な更地にする経費を削減するためにこのエリアは放置されていた。僅かに生き残った人間たちの動向をみて、誰もここに残らなければそのまま手をつけずにいようとしていたのではないかという推察も聞いたことがある。時間をかけて少しずつ、その時々に生きていた人間たちが「ここにも暮らす者がいる」と主張をすることで、ようやくこの建物たちが整備されるようになったらしい。
「ナカムラさん、さっきは助かったよ」
唐突に聞こえた溌剌とした声に顔を上げるけれど、キムから相手の顔は見えなかった。前を歩くナカムラの背中にほとんど隠れているその人が動くたび、キム達と同じように身につけているのであろう帽子の端が少しだけ見え隠れする。
「機械のメンテナンスは大丈夫そうか? 壊される前にあいつらぶん殴れなくて悪かったな」
「いいんだよいいんだよ、あれくらいなら自分でも直せるから。それよりさ」
意味ありげに言葉を区切ると、「これ、お礼に」とヒソヒソ告げる声。相手が何かをナカムラに手渡したらしいということは、声の主が見えないままでもわかった。
「お。悪いな。貰っとくよ」
隠そうという気もなさそうに起源良くナカムラが手を振る。去っていく相手の後ろ姿で初めて、それが女の人かもしれないとキムは気づいた。再び歩き始めるナカムラの後をゆっくりついて歩くキムに、ナカムラが不意に振り返って声をかける。
「お前も吸うだろ?」
そう言って差し出す手の中にあるのは、煙草の箱だった。吸ったことはあるけれど、普段はあまり買わないラベル。キムは「あぁ」と頷いて、自分のポケットの中にある潰れた小箱のことを思い出す。あと何本くらい残っていただろうと考えながら歩く途中、底の薄い履き物越しに、少し痛いくらいの瓦礫のでこぼこがキムの足裏に伝わった。
*
Podはキムの家から少し離れたところにある小さな店だ。飯も出せば飲み物も出すし安酒も出す。どこかから集めてきた古い映画や本もあり、あちら側の世界のニュースなんかも一応、この辺では一番情報として手に入りやすいスポットだった。
瓦礫の中に無理やり作ったような階段を降りて、扉を開く。中に入ると同時に、ナカムラが「アダム」と店内に向かって声をかけた。
「飯か?」
濁声がすぐに返ってくるのを聞いて、ナカムラは嬉しそうに肩を揺らした。「監視屋も一緒だ」とナカムラが返す後ろで、キムは店の奥のモニターを仰ぐ。画面の右下でリアルタイムに数字がくるくると動き続けているのを見て、あちら側の世界のことを少しだけ想像した。
二人がカウンター席に腰掛けると同時に、アダムが瓦礫のブロックから作ったらしい灰皿を差し出す。店内には二人以外誰もいない様子で静かだった。
「誰もいない」
キムが言うと、アダムが「さっきまでは満席だったんだ」と本当か嘘かわからないことを言う。何を食べたいかと聞くこともせずに、アダムは何やら冷蔵庫から取り出して調理を始めていた。
「で、そっちは最近どうなんだよ」
一仕事終えた達成感に満ちているナカムラが、高揚感を漂わせたまま煙草に火をつける。大きな体はカウンターに収まりきっていない感じがすると思いながら、キムはまだ自分が顔を洗えていないことを唐突に思い出した。
「顔、洗ってもいいかな」
カウンターの奥に声を投げ込むキムに、アダムが目配せで「使え」と示す。椅子を降りて水場を覗き、控えめにタンクの口を開いて水を注いだ。コップに入れた水を服の裾に染み込ませて、キムはそのままゴシゴシと顔を拭く。
「布くらい使えよ」
「いや、こっちの方が服も洗える気がしていい」
キムの答えにナカムラが笑う。残った水で口の中を濯いでカウンターの席に戻ると、何事もなかったかのようにキムは口を開いた。
「仕事はまぁ普通だけど、確かに少し、現地業務が増えてる気はするかな」
「だろうな。最近あっち側から溢れるやつが出てきてるらしい」
「溢れる?」
ナカムラが吐き出す煙に招かれるように、キムも潰れた煙草箱を取り出す。ナカムラが「こっち吸えば?」と差し出す煙草に、一瞬迷って、有り難く甘えさせてもらうことにした。
「よくわかんねーけど、あっちでもカクサが出てきてるんだと。落ちこぼれとか、金が無いとか」
いつもとは違う、けれど吸ったことのある煙草だった。煙を吐き出しながら、キムはふぅんと相槌を打つ。
「そうなった時に居づらくなったり居られなくなったりして、こっちに帰ってきて窃盗したり、ボディ狙って復讐する奴も出てきてるんだと」
「……やっぱり、奪うのは機械じゃなくて人間なんだなぁ」
キムの言葉に、ナカムラが「なんだよ」と首を傾げる。灰を落として、キムは煙草を咥え直した。
「昔、人間の仕事を機械が奪うって話があったんだって。この前ここで聞いて、目が覚めた時になんとなく思い出してた」
「奪われるも何も、人間が機械に吸い込まれちまったじゃねーか」
ナカムラのその表現に、キムは少しだけ笑ってしまう。
大災害を経て、物理的分断と資源の枯渇、人口減少が同時に発生した結果、点在する少数で社会を構築して暮らしていくことが必要になった人間は、“機械に吸い込まれて”暮らすようになった。正確にいえば、物理的制約から解放されるべく、当時流行していたデジタルの世界をより人間と近づけて、現実社会のベースに採用したという方が正しい。多くの人々は今、あちら側の世界をベースに生きている。
「機械は人間を食ったりしねぇよ」
顔も上げず、ぶっきらぼうにアダムが言う。ナカムラは何も言えず、煙草が燃えていく指先に視線を落とした。
「まぁ、俺はそのおかげで仕事ができてるから、有難いなって感じだな」
キムの声に、ナカムラが「俺だってそうだけどよ」とすかさず続ける。灰をとんとんと落としてから、「けど、あっち側の奴の世話までするのはちょっとなぁ」と複雑そうな声でぼやく。
人間は自分の肉体をボディと呼び、あちら側で生きる主体とは別のものとして管理するようになった。あちら側に接続中のボディはひどく無防備で、それを狙う犯罪は後を絶たない。金持ちはしっかりしたセキュリティの中で接続できても、そうではない人間たちも多いのが事実だ。自分達の仕事は昔で言う保険屋のような仕事だと、今の仕事を始める時に上司から説明を受けたなとキムは思い出す。
「ナカムラは好きだもんな、こっちに残った人間のこと」
ふぅと煙を吐き出して言いながら、灰皿の縁に煙草を置く。キムの席からは、アダムが皿の上に何やら盛り付けているらしいのが見えていた。
「こっちが好きっつーか、都合良すぎるんじゃねぇのって」
「そうかな」
「そうだろ。あっち側で色んなモン使って楽しくやっといて、そっちで居場所がなくなったらノコノコこっちに戻ってくるのかよ」
お前はそもそも人間に興味がなさすぎるんだとナカムラが息巻く寸前で、アダムの腕が伸びてくる。皿には野菜と肉を炒めたものと、口の中の水分を奪いがちな、Podでよく見るパンが乗っている。
「アダムぅ、このパンもうちょっとどうにかなんねぇの?」
「ガキが。嫌なら食うんじゃねぇ。今は昔のレシピじゃ手に入らねぇもんが死ぬほどあるんだぞ」
アダムの濁声には迫力がある。ナカムラの気持ちもわからないではなかったが、キムは大人しく黙って皿を受け取った。パンは飲み込みづらくても、アダムの作る飯は美味い。決して豊かとは言えないであろうこちら側の、さらに小さなこのエリアにPodがあり続けてくれるということの有難さを、キムは時折ふと噛み締める。
*
食事を終えて酒を飲み始めるナカムラを置いてキムがPodを出たのは、まだ外も明るいうちだった。それでも行き道よりは靄がかったような外の世界は、時間の経過を少しばかり感じさせる。これから眠りにつくまでの間、キムはいつもの通りに仕事をこなして、いつも通りの1日を終えるのだ。
モニターの並ぶ仕事部屋の真ん中、いつものように椅子に腰掛ける。適当に画面を切り替えても、今のところどこにも異常はなさそうだった。何か異常が起こってアラートが表示されるまで、キムには何もすることがない。仮にアラートが表示されたところで、キムに出来るのは事実確認のための現地業務と通報のみで、直接誰かを助けることも、何かをサポートすることも許されてはいなかった。価格に応じたサービス提供を行うのは何事も同じだろうけれど、目の前で異常が起こっている時にも手出しを許されないこの仕事にはある種の向き不向きがあるとキムは思う。きっとナカムラのような人間は、この監視屋には向いていないだろう。
画面越しに、色々な人間があちら側の世界と接続している様子をただ見守る。音声が遮断されているからか、モニターの色味のせいか、画面の中で動いているボディを見ても、まるで偽物のようだなとキムには思えた。
背もたれに体重を預けると錆びた音がする。暇なのは良いことだと、欠伸混じりに天井を仰ぐ。
「あ」
見つけたのは、天井に波打つ小さな膨らみ。自室と似たようなその歪さは、前にこの部屋に入った時には見かけなかったものだった。
「キムさん、います?」
控えめなノックに答えると、同僚のリアが顔を出す。
「これ、ノノさんからです。部屋にでも飾っとけって」
「何これ?」
「人工花ですって。まだ何も咲いてないですけど」
小さな鉢植えは、リアのいう通りまだ花の予兆さえ見えない草の塊だった。なんで、という疑問をキムが口にする前に、受け取ろうとしないキムを無視してリアが近くの机に鉢植えを置く。
「植物は人間にパワーを分けてくれるそうですよ。すぐに枯れちゃう場合は、その分いっぱいパワーをくれた証拠なんですって」
ノノさんが言ってましたと告げるリアに、キムはふぅんと相槌を返す。
「人工花でも、パワーくれるの」
キムの言葉に、鉢植えを眺めていたリアが視線を上げる。色素の薄い瞳をゆっくり瞬かせれば、切り揃えられた毛先を揺らして、ふふと笑った。
「キムさんって時々、残酷なこと言いますよね」
「え?」
「自分だけで大丈夫な人は、他人の大事なものがわからなかったりするのかも」
何を言ってるんだとリアを見るキムの黒い瞳に、真っ直ぐに目を見るリアが歪んで映る。瞬きの合間、一瞬笑顔を消したリアが背後のモニターを見ていたことにキムは気がついた。
「一つくらい、お守りみたいなもの持っていたっていいじゃないですか。私たち、こんな何もない世界で暮らしていかなくちゃいけないんだもん」
キムが何かを言う前に、リアがにこりとキムを見る。
「じゃ。ノノさんに会ったら、ちゃんとお礼言っておいてくださいね」
あ、とかうん、とか。結局まともな言葉を一つも返せないまま、キムはリアの背中を見送った。残された鉢植えを見て、リアが見つめたモニターを見て、頭の中で、リアの言葉を繰り返す。
「……お守りみたいなもの」
呟いて、天井を仰ぐ。自室のものとは違うけれど、確かにそこに、歪みはあった。
アラートが鳴る。キムが急いでモニターを確認すると、モニターに映る男性が苦しそうに胸の辺りを抑えてうずくまっていた。
「監視員K-21です。ボディトラブル発生、タイプC-3、緊急度A。ボディメンテナンス班は向かってください」
通報の後、該当する顧客のデータを探して転送をする。登録時の写真より、モニターの中の男性はひどく痩せていた。長くあちら側にいられるように薬でボディを保つ人は多いと聞くけれど、庶民には所詮価格に見合う程度のものしか回ってこないということなのだろう。
モニターの中で男性が痙攣し始める。キムは手元で時間を計測しながら、他のモニターの様子にも目を配る。隣の部屋から、慌ただしくドアが開く音がした。恐らく現場に向かう同僚だろう、急ぐ足音が響く。Podでのナカムラの話と、リアの視線。それらを思い出しながら、キムはモニターの中をただただ眺める。
「……これもお守りなのかもな」
呟きが吸い込まれて数秒、モニターから視線を剥がして、キムが立ち上がる。机の隅に置かれていた鉢植えを抱えて、そっと、光を放つモニターの横に置き直した。
END
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
