
システムアーキテクト 業務のデジタル化【論文の書き方】(令和4年春問2)
2023/3/15 誤記の対応および表現を微修正しました
2023/7/19 メンバーシップ開設に伴う修正
本記事ではシステムアーキテクトの午後II(論文)対策として、令和4年問2で出題された過去問を分析します。
実際に論文を書く上での考え方を整理し論文骨子を設計するところまでやっていきます。
※本記事は、メインである論文の書き方については無料で読めます。論文本文のみ有料部分なので、読みたい方は記事の購入またはメンバーシップの加入をご検討ください。
問題(令和4年問1)

過去問は試験センターから引用しています。
表題:『業務のデジタル化について』

設問文は以下の通り。
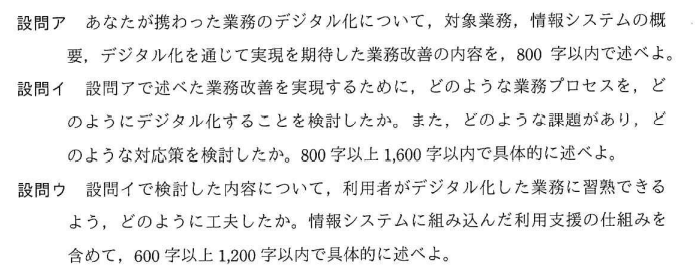
何が問われているかを把握する
本問で問われているのは「業務のデジタル化」という一見広い概念ですが、問題文を通して読むと、「紙媒体」という言葉こそが真のキーワードであることが分かります。
問題文にある例示でも、「稟議書」という紙媒体が出てきています。
最後の段落でも、紙媒体などで運用していた業務をデジタル化したことにより、利用者が新しい業務に習熟できない…という課題が書かれています。
よって紙媒体をデジタル化するというシナリオで論文を展開するとよいでしょう。
設問アでは対象業務、情報システムの概要、業務改善の内容が、設問イではデジタル化の検討が、設問ウでは利用支援の仕組みが問われています。
設問イとウではそれぞれの観点で課題の定義とその解決策を工夫したことも書く必要があります。
まとめると、問われていることは次の通りです。
設問ア
対象業務
情報システムの概要
期待した業務改善の内容
設問イ 業務プロセスのデジタル化
デジタル化の方法
課題
対応策
設問ウ 利用支援の仕組み
出題要旨と採点講評からの分析

試験センターから公表されている出題要旨と採点講評を確認して出題の意図と論述のNG例を把握します。
出題要旨

採点講評

出題要旨の2文目に、「効果の高い業務を見極めて」という一文があります。なぜその業務をデジタル化したのかというところを論述する必要があります。設問アの後半か、設問イの前半で述べておくとよいでしょう。
3文目には「デジタル化における課題の想定と対応策が必要」とあり、設問イで問われていることが重要視されていることが分かります。
採点講評には「現行の業務をデジタル化で解決するといった趣旨に沿えていない」というNG例が紹介されています。
現行の業務をデジタル化する際に何らかのアナログ(紙媒体)に触れられていないなどがNGになると考えられます。
論文を設計する

問われていることの概略を把握したら自身の経験や用意してきた論文パーツに当てはめてどのように論述を展開するかを設計します。
設問アの設計
設問アは設問イで主に述べることになる業務のデジタル化について、対象の業務と情報システムの他、デジタル化したことによる業務改善の内容を聞かれています。
ポイントは既存の業務においてどのような「紙媒体」があるかをイメージすることだと思います。
新規にシステムを作る場合にしろ、既存のシステムを改修する場合にしろ、既存の業務にある「紙媒体」がデジタル化されたことによりどのように業務改善につながったかのアウトラインを書く必要があります。
1-1. 対象業務
問題文の例示では「りん議業務」にあたるところです。
登場する紙媒体は「稟議書」です。
業務を説明するにあたり、どのような紙媒体が登場するかを書きます。
私の場合は多店舗展開しているホームセンタにおける在庫管理業務とし、
・発送票に基づく発送業務
・紙の在庫管理台帳に基づく台帳の更新業務
を挙げました。
1-2. 情報システムの概要
1-1.に対応させたシステム名とするのがよいでしょう。
問題文の例示では「りん議業務」に対して「ワークフローシステム」と言っているところですね。
販売管理業務であれば販売管理システム、
課金請求業務であれば課金請求システム
のように対応させるのが分かりやすいと思います。
私の場合は「統合在庫管理システム」としました。
"統合"と頭につけることで多店舗をまたいで一括で在庫管理ができるというニュアンスを含めました。
1-3. 期待した業務改善の内容
問題文の1文目に「紙媒体の管理コストの削減及び業務の効率化」、2文目に「情報が検索しやすくなったり、モノの動きがリアルタイムに把握できたり」という例が挙げられています。
設問イでは業務プロセスのデジタル化の方法を書きますが、なぜその業務プロセスを選んだのかという根拠が1-3.に対応します。
私の場合は業務改善の内容として
紙媒体による管理コストの削減
判読できない文字による非効率・形骸化の打破
在庫問合せの手間の削減
をあげました。
1.と3.は問題文の例示に寄せています。2. については手書きならではの非効率を書きました。
次の設問イにおいてなぜその業務プロセスを選んだかというと、ここ(1-3.)に書いた効果が高いから、という理由付けになっています。
設問イの設計
設問イは業務のデジタル化について、どのような業務プロセスをどのようにデジタル化したことについて問われています。
また生じた課題と対応策についても問われています。問題文の例示も参考にしながら、出題の意図を掴んでいきましょう。
この時、後述する設問ウでは利用支援の工夫を書くことになるので、課題のネタが被らないようにする必要があります。
具体的には、使いづらさ・分かりづらさといった「使用性に関する課題」は避けた方がよいでしょう。
2-1. 業務のデジタル化の方法
どの業務プロセスをデジタル化したかについて明確にする必要があります。問題文の例示においては「りん議業務」ということになりますが、出題要旨にある通り、「なぜその業務プロセスをデジタル化の対象に選んだかと言えば、効果が高いから」と書くとよいでしょう。
効果が高いことの根拠として、1-3.の期待する改善内容に触れるのがよいと思います。
また、2-2.で課題、2-3.で対応策を書く場合は、2-1.である程度どのようにデジタル化するのかを説明しておくと展開が繋がりやすくなります。
私の場合は在庫管理業務における「発送業務」と「毎日の在庫管理台帳更新業務」を挙げました。
発送業務では、
発送票をデジタル化し手書きの発送票は廃止。
専用端末にて対象商品と数量を入力し印刷した発送票を貼りつけて発送。
入力したデータは在庫マスタと連携して情報を更新。
在庫管理台帳の更新業務では、
紙媒体の台帳は廃止。
発送票の控えを確認する業務の代わりに専用端末より発送の履歴を確認する業務に変更
というようにデジタル化された業務を説明しました。
2-2. デジタル化における課題
問題文においては次の3点が例示として出されているところです。
リモートワークでは従来の印鑑での押印ができない
決裁ルートに長期の不在者がいた場合、決済が滞る
情報漏えいなどのセキュリティリスクに対処が必要
このうち2点目はデジタル化における課題というよりも現状の業務プロセスでも発生する課題ですが、「代理決裁者」を「システム的に」設けることで「システム的に解決できる」ので良いと解釈しました。
私の場合は
誤入力が在庫マスタに即反映されてしまうと影響が大きい
情報セキュリティの脅威に対応する必要がある
専用端末の故障時に在庫管理業務が滞ってしまう
としました。
このうち1.は解決策を「承認機能を設ける」とするので、例示の1.に寄せた内容になっています。
2.は例示の3.と同じですね。
3.については、何かをシステム化する時に必ず発生する避けては通れないものです。汎用性の高い課題なので本問に限らず意識しておくとよいでしょう。
2-3. 検討した対応策
問題文の例示では次の3点が対応しています。
承認欄にログインユーザの情報・タイムスタンプを記録
代理決裁者を設ける
アクセス権限強化やログの監視をする
私の場合は
入力を即反映させるのではなく、店舗の責任者による承認機能を設ける
ウイルス対策ソフトウェアなどの導入により情報漏えいや改ざんのリスクを減らす
故障時は発送票を手書きで記入できるようにする
としました。
特に3.はアナログ業務を一部認めることになりますが、実際の現場でも発生しうるデジタル業務移行の課題の対応策としてよく登場する内容です。
設問ウの設計
設問ウはイで生じた課題と対応策の関係に近いですが、利用者の支援の仕組みを書くので「使用性に関する課題」を書き、それを解決するというシナリオで書くのが良いでしょう。
「使用性に関する課題」ネタを持っていれば、比較的定型的に展開・論述できる設問であったように思います。
3-1. 使用性に関する課題
問題文においては、例示は無いので経験などから考える必要があります。
私の場合は
高齢者が多いため画面上の細かい文字を目で追えない
情報システムに習熟していない利用者が多く入力方法が分からない
としました。
3-2. 利用支援の仕組み
問題文においては、次のような例示があります。
業務の頭文字で電子文書をアイコン化する
情報システムへのガイド機能を組み込む
私の場合は
可能な限り表示する文字を大きくした
次に入力するべき箇所を活性化させて目立たせた
としました。
論文骨子

以上を踏まえ、論文骨子は次のようになりました。
1.対象業務、情報システムと期待する業務改善
1-1.対象業務
ホームセンタS社の在庫管理業務。
発送業務:発送票に基づく店舗間の商品の発送・受取
在庫管理台帳の更新業務:毎日、発送票の控えと商品の受取をもとに在庫管理台帳を更新
1-2.情報システムの概要
店舗をまたいで一括で在庫管理ができる統合在庫管理システム。
1-3.期待した業務改善の内容
紙媒体の管理コストの削減。
判読できない文字による非効率・形骸化の打破。
在庫問い合わせの手間の削減。
2.業務のデジタル化
2-1.在庫管理業務のデジタル化の方法
発送業務と在庫管理台帳の更新業務のプロセスを見直し。
デジタル化するにおいて特に効果の高い業務プロセスであるため。
発送業務:発送票をデジタル化し手書きの発送票は廃止。
専用端末にて対象商品と数量を入力し印刷した発送票を貼りつけて発送。
入力したデータは在庫マスタと連携して情報を更新。
在庫管理台帳の更新業務:紙媒体の台帳は廃止。
発送票の控えを確認する業務の代わりに専用端末より発送の履歴を確認する業務に変更
2-2.デジタル化における課題
①誤入力が在庫マスタに即反映されてしまうと影響が大きい
②情報セキュリティの脅威に対応する必要がある
③専用端末の故障時に在庫管理業務が滞ってしまう
2-3.検討した対応策
①入力を即反映させるのではなく、店舗の責任者による承認機能を設ける
②ウイルス対策ソフトウェアなどの導入により情報漏えいや改ざんのリスクを減らす
③故障時は発送票を手書きで記入できるようにする
3.情報システムに組み込んだ利用支援の仕組み
3-1.使用性に関する課題
利用者が混乱することを想定し、使用性に関する課題について仮説を立てた。
習熟に時間がかかれば、業務改善の効果が低減するため。
①高齢者が多いため画面上の細かい文字を目で追えない
②情報システムに習熟していない利用者が多く入力方法が分からない
3-2.利用支援の仕組み
在庫管理システムのパッケージをカスタマイズして工夫。
①可能な限り表示する文字を大きくした
②次に入力するべき箇所を活性化させて目立たせた
まとめ
いかがでしたでしょうか?
本記事ではシステムアーキテクトの午後II(論文)対策として、令和4年問2で出題された論文の書き方を紹介しました。
汎用的な構成ではあったものの、「紙媒体をデジタル化した」という経験がものをいう出題であったように思います。
また、他の区分・過去問の【論文の書き方】の記事については以下リンクを参照ください。
論文の書き方 カテゴリーの記事一覧 - スタディルーム by rolerole
今後も、【論文の書き方】記事を充実して参ります。
ではそれまで。
論文全文
ここまででも十分考え方はお伝え出来たかと思いますが、論文全文を参考にされたい方は有料とはなりますがここから先の部分をご購読お願いします。
※なお、メンバーシップ(システムアーキテクト合格支援コース 月額800円)にご加入いただければ本記事以外のSA対策有料記事も読み放題となり、さらに専用フォームからのご質問もし放題となります。ぜひご検討ください。
■設問ア
1.対象業務、情報システムと期待する業務改善
1-1.対象業務
ホームセンターS社の在庫管理業務が論述の対象であ
る。S社は10店舗を地域展開しており、各店舗は小売
機能を持つと同時に倉庫機能を持つ。
品揃えは各店舗で異なっており、必要な場合は店舗間
で商品の発送・受取を行う。発送時は複写式の発送票に
発送する商品・数量を記入し梱包した箱に貼り付け発送
する。
各店舗の倉庫では一日一回在庫管理台帳を更新してお
り、発送・受取があった日は発送票または控えを目視確
認した上で台帳に反映させている。
ここから先は
Amazonギフトカード5,000円分が当たる
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
