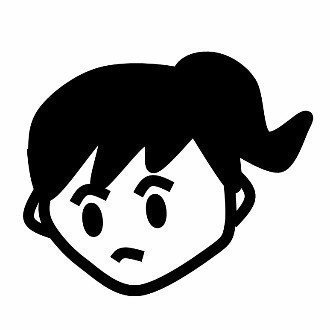脳内にたまった記憶を解放するためにつけた日記(1/9~1/11)
2025.1.9
犬も歩けば棒にあたったような一日だった。
年賀状がきていたので、今年はださないぞと思っていた私も、年賀状くらいしか連絡がないとはいえどの人も大事な人だしな、と返信の年賀状を書いた。天気が良かったので、いつも車移動ばかりだけど、近所でいちばん近い郵便局を検索して歩きで出かけたのだった。
郵便局がみつからない。こういうとき私はよく妙な気を起こす。Googleマップを開かず自力でたどりつきたいという欲望に駆られる。そして道を行きつ戻りつしたあげく、その地区では見つけられなかった。もうすぎてしまったのかと思ったけれど、同じ道を戻るのも嫌。でそのまま進んで次の街のいつも車でいく郵便局へ向かうことにした。天気もいいことだし。
無事、郵送し終えて、今度は歩いて帰るのも嫌になり、職場に置きっぱなしの自転車を思い出して乗って帰ることに。そこまではよかった。家に帰りついてもまだ半日ある、布団も干せる。
自転車にまたがると私は人が変わったようになる。自動車教習所でも「ハンドルを握ると人が変わったように気が大きくなるので、気をつけましょう」と性格判定された。
いやしかし、ふだん自転車に乗らない人が自転車に乗ると、その万能感に気持ちが湧き立つのは万人共通なのではないだろうか。
私はいちもくさんに、家とは逆の、街の方角へむけてペダルを漕ぎ出した。どう考えたって、この先にはおもしろいものがたくさん転がっている気がする。
昨日は八日堂縁日の護符を受けて、一年の祈願をしたばかり。財布の中はすっからかん。しかしなんといっても、上田の街には魅力的なお店がたくさんある。行ってみたくてマップにピン留めしてある店舗は無数だ。道をゆけば、ピンをさすどころかマップも把握していない小さな店だって見つかる。
ちょうど時刻は昼時。大好きないつものカフェでガレットでも食べようか、と細い道に入って、下り坂を自転車はころころ進んでいくが、さっと目に入った「ギャラリー」の看板に両手がブレーキを握る。
今年は陶芸を始める予定だ。来週には窯の見学もいれてある。ここに寄らない手はない。
建物は新築っぽいシックな風合いのきれいなおうち、その一角でギャラリーをやっているらしい。扉を開けてすぐ、入り口に座るふたりの女性と目があった。やっていますか、と聞くと、笑顔で中に通してくれた。
ギャラリーには小ぶりなお猪口や小皿。壁にかけてあるのは陶製の動物の顔をかたどったもの。床に近い低い棚には、ツボのような大きな作品も何点かあった。
どの作品も風合いの差こそあれ、凛としてオーセンティックな空気を醸し出している。ギャラリーの主の女性も、陶工育成機関の出身者だ。もう一人居合わせた女性は、陶工ではなく、上田紬の職人だった。
上田の街は、上田城を中心に、ふるくから大きな街として発展していた。その年月は上田の土壌に多くの文化的要素を植えつけ、今でも文化度は東信地区でも随一だと、小諸や佐久で暮らしてきた私は感じている。けれど上田に育ちいまも上田で暮らす人にしてみると、文化の素地はあるものの、古く良質な土蔵を開発のためにかんたんに壊してしまったり、補助金をつかってアートの企画をしても長続きしなかったりと、少し思うところも煮詰まってきているようであった。話をきく限り。
アート。
私には遠い存在だと思っていたその言葉は、今の本屋に勤めはじめてがらりと印象がかわった。店内には、手作りの陶器や布のクラフト、シールや絵画、文章の作品などが溢れている。ただ客として寄っていたときには「これなにかな」で、確認もせず思考が止まっていたその冊子、じつは同人誌だったりする。
そしてそれらの作品を手がけるのは、本当に一般の、仕事をしながらクラフト品を作る、ふつうの人々なのだ。小説家、エッセイスト、画家、彫刻家、陶芸家、写真家、イラストレーターなんかにならなくたって、それらの活動をすることは許されている。
アートの素地があるから、その要素を使って街を元気にしたい。そう、ギャラリーの主人は言った。
そんなことができたら、おもしろいだろうなあ。
山本鼎(やまもとかなえ)は、1882年に生まれた版画家で、こどもたちに自由な絵を描かせる「自由画運動」を推進したことでも知られる。それまで、アートは一部の格式高い正統派アーティストの手によってのみ作られていた。
この思想をもとに、アートを一般に広める活動をしている、ということだった。
自由にやって、楽しく生きられたらいいのにね。
どうしてアートを追求すると、自由は引きしぼられていってしまうのだろう? なんとなく蒸しパンをつくるときに似ている。よかれと思って、おからを入れたのだ。かさ増しになるし、大豆の栄養たっぷりだし、値段も安いおから。
それなのに、パンがぜんぜんふくらまなかった。つるつる、てろてろした食感の、まるで「カップ入りういろう」のようなものになった。
おからを味噌汁などの汁気の中にいれると、きゅーっと水を吸う。卯の花をつくるときに、油を加えてもどんどん吸い込んで、からからになる。
つまり、アートを楽しく隆盛させようとしたら、あまり注力しないことが大事なんじゃなかろうか(アートとおからを一緒にするのもあれなのだが)。いい栄養や、環境や、補助金や、賞や、先生を、どんどん加えて加えて、蒸しパンはふわっと膨らみたいのに必要な水分をどんどん吸い取られていって、最後はむちむちの外郎になる。
元気に育ってほしければ「蝶よ花よ」と温室につめこんではいけない。
けれどただニコニコ見守っているのでも、それじゃただの荒野のままだ。適度に水をやって、日当たりを見てやって……育てることは、繊細な行動だなあ。
うちの多肉植物は、水だけやっているが文句も言わず、時期になれば新芽をだして勝手に増えている。ちょっと見ないでいるとひび割れたりしているが、自分で膜をつくってなんとか元気にやっている。買ったままの鉢だから、土の栄養が切れたら成長もしなくなるのだろう。
事業が尻すぼみにならないようにするには、自然に栄養が回ってくる路地に植えるのがよい、ということかもしれない。路地に植えて、世話は適度に。
なんて、まあ私がいうことじゃないか。私はただ手を動かして陶芸がしてみたいだけ。論じたいということは、私にも思うところがあるのだ。前職であったような、地域おこしをするには、続けるには、お役所というやつは、というところに心残りがあるのかもしれない。少しは。
お店にいとまを告げて、お気に入りのカフェに寄ってガレットを頼む。
調理を担当している女性が料理を運んできてくれて、初めて言葉を交わした。前にも作ってもらったガレット、自分でやってみたけれどあんまり似せられなかったと伝えたら、「あとで教えてあげる」と最初からタメ口で、快活な笑顔で、すっとまっすぐなストレートのポニーテールで、金色の髪留めをしていて、他のお客さんにもサバサバした対応で、要するに心を鷲掴みにされた。
ええなあ。こんな人になりたいんだよな、私。
2025.1.10
今日の朝は、生きている感じがした。
ちゃんとした排便があった。下痢もしてないし、朝ちゃんと出た。
ここから読み始めた人は、なんだこの文面はと訝しがるかもしれない。私は本当に自分の腸の不調にうんざりしてきた。それが今日、改善のきざしを見せたのだ。
何時にトイレに行こうが、出せるなら関係ない、という場合もあるだろうが、私の場合は時間帯がとてもものをいう。午後の明るい時間はだめだ。
便意は、排泄物が大腸から直腸へ移行して起こる。直腸にものが入ると、神経を通って脳へその情報が伝えられ、脳は蠕動運動を腸におこさせて、排泄がおこる。
解剖してみたわけではないので真偽のほどは不明だが、直腸に便があるとき「残便感」というのが起きている気がする。私の場合はこれが起こることはめったになく、便秘といえば、多分、直腸へ下りてこられないという状況を指す。それが午後の明るい時間には、直腸へ下りてもなお蠕動運動がおこらない。そのせいで腹圧ですべて処理せねばならず、一進一退の攻防になる。
これはやはり、自律神経のリズムが影響するのだと思う。自律神経のうち交感神経は日中に優位になり、夕方にむかうにつれだんだん下がり、夜には副交感神経が優位になる。午後の明るい時間は、交感神経が高い位置にあるため、それを緩めるのが難しいのだろう。
じっと止まってみたこと、ありますか?
現代人はとかく、スマホを見たり動画をみたり、もちろん仕事をしたり人としゃべったり、人の輪からはずれて人のことや自分のことやらをあれこれ考えたりして、体も止まって思考も止める瞬間が本当にない。一瞬たりとも無駄にしない生き方を、私はしてきた。「スキマ時間」とかいって勤勉にスキルを磨いたりして。
けれど、じっと止まってみるとわかる。体内は、動いているのだ。私がじっと座って、何も考えないよう頭を空に空に、と念じて、体をしんとさせているあいだも。身体のなかで、内臓がうごく、音をたてる。それはそうだ、そこでは無数の新陳代謝が行われている。心臓が拍動し、肺は酸素を体内へとりいれ二酸化炭素を肺側へ吸い出して放出し、消化管のなかを食べたものが通り、細胞のひとつひとつは原子を入れ替えて脱皮みたいに生まれ変わって、それでこの体を80年も90年も支え続ける。
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?