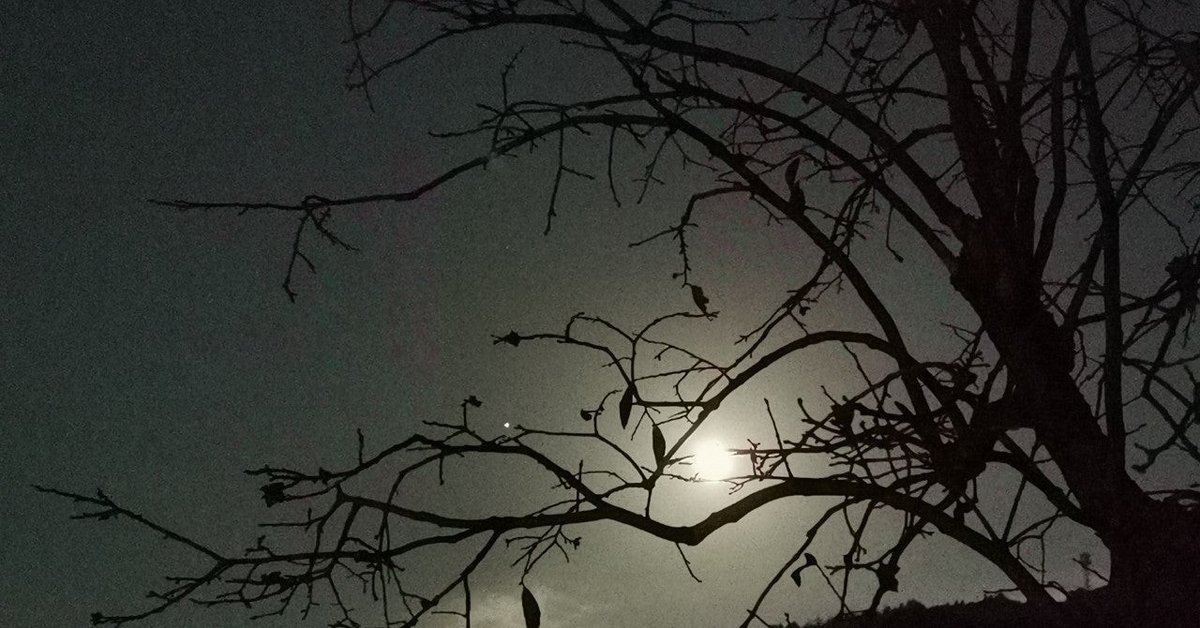
ドイツ人にとって、ブルックナーとは 「北国の春」みたいなものかもしれない。
少し前に、九十歳になったベルナルト・ハイティンクの引退コンサートが放送された。

昨年のザルツブルグ音楽祭の最終日、ウィーン・フィルを相手に彼が指揮をしたのはブルックナーの交響曲第七番だった。終始ゆったりしたテンポで、きめ細かく、ほとんど祈るように音楽を進めていく。彼女は「ブルックナーの七番ってこんなにきれいな曲だったかなと驚いた」と言っていた。そうさせたのはまさしくハイティックの力量だし、最後の演奏会という特別な何かがおそらく力を貸したのだろう。
思えばカラヤンもチェリビダッケも朝比奈隆も、人生の終盤にブルックナーの名演をこの世に残した。集大成にふさわしい音楽ということなのだろう。
ドイツ人にとって、ブルックナーは特別な存在だと聞いたことがある。
ワーグナーのようにナチスに悪用された過去を持たない彼の音楽は、純粋にドイツ民族の良心を気高くくすぶる何かを秘めているのだ。キリスト教精神に基づいた敬虔さとどこか懐かしいドイツの黒い森への郷愁。
日本人の僕にはいまひとつピンとこないこの感覚。なにか似ているものがあるかもしれない。
と思って気がついた。そうだ、千昌夫! あの「北国の春」みたいな感覚じゃないだろうか。
昔、紅白でいやというほど聞かされた「北国の春」。決して自分から聞こうとは思わないが、あの曲が日本人の郷愁をそそる効果があることは理解できる。僕だってそのうち、かぐや姫の「神田川」を聞きながらしめじめと涙を流す日が来るかもしれない。同じことだ。
人の心を震わせる音楽は、時代や土地に応じて実にさまざまな顔をしているものなのだろう。

数年前、当時在籍していた合唱団で、ブルックナーのあまり知られていないモテットを歌ったことがある。
「ロークス・イステ」(ここは神により作られた)は混声四部による三分ほどの短い曲。ハ長調のいたってシンプルな曲なのだが、途中、いわゆる「ブルックナー転調」という部分があって一気に盛り上がる。アカペラで歌っているとシンプルなだけにハーモニーを作るのが難しく、でもうまくいったときは無上の喜びを感じることができる。
指導してくれた先生はとても情熱的な人で(男性です)、大のブルックナー好き。高校時代、クレンペラーが指揮する第七番から第九番までの交響曲を夜通し聞いて、「俺はこの先、どうやって生きていけばいいんだろう」と悩んだとか。ちょっと暑苦しい話だ。
それにしても、この曲を現地の教会、あるいはブルックナーが長くオルガン奏者を務めた聖フローリアン修道院で歌うことができたら、どんなに素晴らしいだろうと夢見てしまう。
そういう経験をしない限り、ブルックナーに対するドイツ人の思いを理解することはできないのかもしれない。

話は逸れるが、このブルックナーマニアの先生、アンコールに日本の歌を持って来るのが好きで、いままでに「愛燦々」、「見上げてごらん夜の星を」、「時代」を歌ってきた。
で、このアンコールがだいたいいちばん受けるのだ。「テ・デウム」やシューベルトのミサ曲をメインで歌っても、最後は絶対お客さんにそう言われる。
母国語の曲は、なんといっても偉大なのである。
