
アオタケプロジェクト 採択者紹介① 濵田翔真さん
アオタケプロジェクトは、青森、秋田、福島地方の若手人材を対象として起業家を発掘・育成しています。採択を終え、現在アイディアを磨き上げている採択者の姿をご紹介します
今回ご紹介するのは…
濵田翔真さん
会津大学4年コンピュータ理工学部、京都府出身
思い出の中の温かい情景をARで再現したい
>>>まずは濵田さんが進めている事業内容、プロジェクト内容について詳しくお聞きしたいです。現在、ユーザーの過去の写真やビデオを使い、その思い出を追体験できるようにARを使ったアプリを作成しているとお聞きしました。そこについて詳しく教えていただきたいです。
濵田:僕が実現したいと思っているのは、映画でよく見る、例えばおばあちゃんと孫が手をつないで歩いているような後ろ姿のシーンのような、温かい情景をイメージしたものです。
今あるアプリケーションだと、単純に画像や動画をそのまま表示するというものはすでに多く存在しています。しかし、僕はそれをもっと実体験に近い形で表現したいと考えています。
例えば、最近注目されているAI技術を活用して、1枚の写真から3Dモデルを生成したり、動画から立体的な動きを再現するなどの技術を取り入れています。これにより、ARを通じて体験ができるものを作りたいと考え、今まさにその開発に取り組んでいるところです。
>>>面白いですね!具体的にアプリとして実現する場合、写真を撮った際に立体的に表示されるイメージなのでしょうか?
濵田:そうですね。写真フォルダから選んだ画像をアップロードすると、AIが3Dモデルを生成してくれます。現時点では完璧ではないですが、3Dゲームのキャラクターのように、自由に回して見ることができるようなモデルを作ることができます。今はまだ顔の部分が少し不完全で、その点を改善している段階です。
最終的には、街中の特定のスポットで昔の写真、例えばおばあちゃんやおじいちゃんの写真、友人の写真などを使って、AR上で人が動いているように見せられる体験を作りたいと考えています。それが実現できれば、とても面白いものになると思っています。
アオタケプロジェクトに挑戦した理由とARへの思い
>>>なるほど。思い出を追体験させたいという気持ちはどこから来てるのでしょうか。このテーマに決めたきっかけは何ですか?
濵田:まず、なぜこのアオタケプロジェクトにチャレンジしたかというと、昨年、先輩のプロジェクトに業務委託として参加させてもらった経験が大きいです。実際にその場で面白いプロダクトを作っているのを見て、漠然と「自分もやってみたいな」と思うようになりました。そのとき、何か勝負するならARに取り組んでみたいという考えがあったんです。
会津大学にはA-PxL(アイヅピクセル)というXRサークルがあり、1年生の頃から所属していました。3年生の時には副代表を務めていて、その時の代表は、今一緒に開発しているメンバーの一人です。
ただ、僕自身、XRの開発はあまりやっていませんでした。どちらかというと、サーバーやアプリ開発がメインだったんです。でも、やっぱりXRのプロダクトを実際に自分で作ってみたいという気持ちが強くあり、プロダクトとして形にしたいと思いました。
もう一つの理由として、僕は現実、つまり「人生」がとても好きで、その現実から派生したものを技術を使って作れたら面白いと思っています。特にARという技術には強い興味があって、ぜひ挑戦してみたいと考えていました。
テーマにしている思い出の部分に関しては、色々考えた結果、地元である京都の南にある城陽市の風景が思い浮かびました。最近では高速道路が通り、便利になってきていますが、昔の田舎の原風景がどんどん失われていく寂しさを感じています。
高校時代、田んぼの中を自転車で通っていた道に高速道路ができ、昔の景色とは全く違う風景になってしまいました。この変化を後世に伝えても、実感してもらえないだろうなという寂しさがあり、それをどうにかして表現できないかと考えました。
地元は自分にとって特別な場所でありながら、今は会津で暮らしているため、地元と切り離されたような孤独感があります。そんな感情を、何かアプリケーションを通じて解消できればと考えています。例えば、亡くなったペットをARで再現して、寂しさを紛らわせたり、ハッピーな気持ちになれればと思い、このテーマで進めてみようと考えました。
>>>ありがとうございます。とっても素敵です。
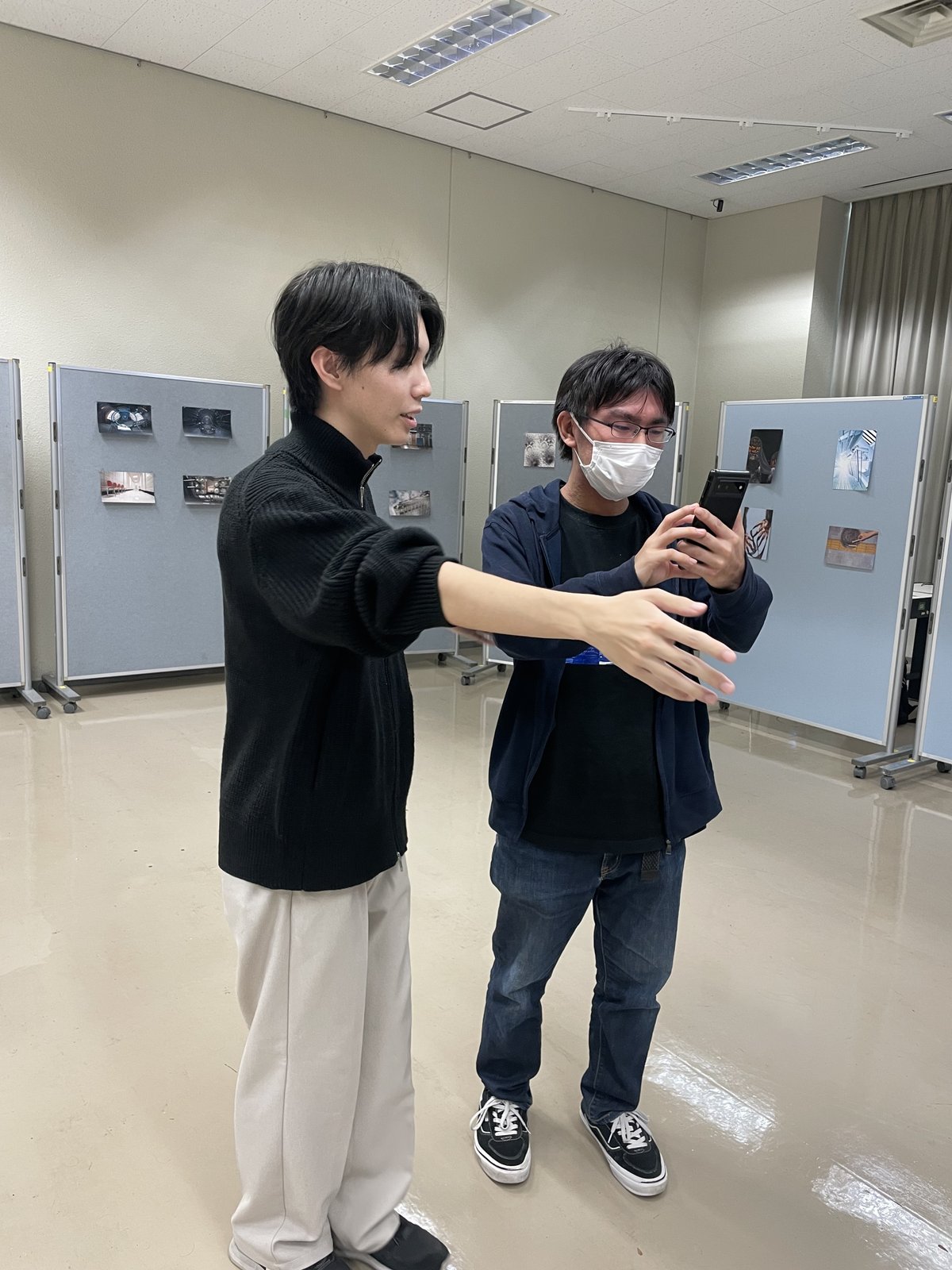
リーダーとしての挑戦と成長
>>>アオタケプロジェクトに参加して今までを振り返っていかがですか。
濵田:そうですね、正直なところ、やっぱり難しいなと感じています。ただ、これはマイナスな意味ではなくて、今まで友人たちと一緒に開発したり、プログラムを書いたりといった経験はありましたが、予算をうまく使ったり、メンターとスケジュールをきっちり決めて進めたりするのは新鮮な体験です。インタビューを行い、プロジェクト全体をリードする立場として調整することが求められる点は難しいと感じています。
また、研究や日常のことも並行してバランスよく進めなければならないので、それも本当に難しいですね。メンターさんをはじめ、たくさんのことを勉強させていただいていて、本当に貴重な機会をいただいてありがたいというのが今の正直な気持ちです。
>>>確かに、今まで経験してこなかったリーダーの役割を担うのは大変そうですね。
濵田:そうですね、友達としてだけではなく、リーダーとしてしっかり責任を持って進める必要があります。特に開発に関して、友人たちに多く頼ってしまっている部分もあり、申し訳なく感じることもあります。自分がもう少しうまくできたらいいなと思いながら、学ぶことがたくさんありますし、反省する部分も多いですね。
成果が見えにくい中でも前進するために
>>>そのような困難な場面はどう乗り越えられたのですか?
濵田:今はまだ発展途上の段階だと思います。ただ、毎日少しずつ前に進んでいくことが大事だなと感じています。アオタケプロジェクトに限らず、どんなことでも「もうやめたいな」と思う瞬間はあると思いますが、そういう時こそ、少しでも進めてみる、友人とコミュニケーションを取って少しでも進捗を出すことが大切です。
僕は8月から9月にかけて1ヶ月間インターンをしていて、フルタイムだったのでアオタケプロジェクトの方に時間を割けなかったんです。でも、その間も隙間時間を使って友人や先輩に声をかけ、インタビューに伺うことで、時間をうまく計画的に使うことができたと思います。なんとか乗り越えられたのかなと感じています。
技術の壁を越えて「思い出」を形にするプロジェクトの難しさ
>>>今プロジェクトを進めていて感じる現状の課題や不安は何でしょうか?
濵田:やはりAIを使ってモデルを作るという部分が難しいです。今回は、手作業で1つ1つ作るのではなく、写真をアップロードしたら自動的にモデルが生成されるフローを作りたいと考えています。そのため、モデルを作成できる人に1つ1つモデルを作ってもらうというのは不可能なので、AIに任せて効率的にモデルを作れるようにすることが今回のメインテーマです。
AIの発展は目覚ましいですが、写真から顔を認識させるのはかなり難しい部分です。論文を調べてみると、ある大学がその機能を実現しているらしいのですが、まだ一般に提供されているプログラムはないようです。それが使えれば一瞬で解決するのですが、現状では妥協が必要かもしれません。しかし、今回のプロジェクトは「思い出」や「視覚情報」を重視しているので、雑な作りではユーザー体験に影響が出てしまいます。特に顔が潰れてしまうと、ユーザーにどう映るかが課題です。
また、インタビューやアンケートも難しいと感じます。調査方法やバイアスの問題、時間の調整など、いくつかの壁があります。リファラルで人を集めるにしても、参加者が少ないことが多く、なかなか進めにくい状況です。
それでも、僕たちがこのプロジェクトに参加した理由は、まず「これを作りたい」という強い気持ちがあったからです。社会的意義も大切ですが、まずは自分たちが作りたいものを形にしてみようというスタンスで進めています。

アオタケプロジェクトのゴールと未来展望
>>>アオタケプロジェクトのゴール、もしくはこのプロジェクト自体をどうしていきたいとか、今後の展望をお聞きしたいです。
濵田:アオタケプロジェクトとしては、まずはリリースまで進められれば、一旦は成功かなと思っています。その中で、自分たちが社会に向けて発信したいこと、アウトプットしたい内容を形にできることが、最も大切な成果だと考えています。これがアオタケプロジェクトとしてのゴールだと思います。
今後の展望としては、学生であるうちは、自分たちが本当に作りたいものをしっかりと形にして、自分の世界観や価値観を、良い意味で人に伝えられるようなものづくりを続けていきたいです。アオタケプロジェクトをうまく活用しながら、自分たちのアイデアをアウトプットしていくことが、これからの目標です。
>>>ありがとうございます。世界観を伝えるというのはとても素敵ですね。
濵田:自分の中の世界観は、日々変わっていくものだと感じています。原体験や昔の経験、好き嫌いの判断基準などが影響していると思います。最近特に感じるのは、好きなものはすぐに「これが好き」と言える一方で、嫌いなものを見つけるのは意外と難しいということです。「なんとなく嫌い」という感覚はあるものの、それを明確にするのは時間がかかりますよね。
そのため、自分の好き嫌いだけでなく、絶対に実現したいこだわりを研ぎ澄ませることが重要だと考えています。これはアオタケプロジェクトのサブテーマでもあり、自分自身のテーマでもあります。この過程を通じて、自分の考えを整理し、より豊かな人生を送れるようになれば良いなと感じています。
インタビュアーによるまとめ
濵田翔真さんは、会津大学に在籍し、現在AR技術を活用して過去の写真やビデオを通じて思い出を追体験できるアプリの開発に取り組んでいます。自身の技術的興味とともに、地元京都の風景が変わっていく寂しさから、「思い出」をテーマにしたプロジェクトを進めています。
濵田さんは、リーダーとしてこのプロジェクトに参加している経験やヒアリングを通じて、技術面以外での学びを得られたと話していました。新しい成長を感じられているんだなと思います。
濵田さんのプロジェクトのゴールは、まずリリースまで進めることですが、それ以上に、社会に向けて発信したい内容や世界観を形にすることを大切にしていると感じました。今後も自分の価値観を伝えられるものづくりを続け、自らのこだわりを研ぎ澄ませていき、より豊かな人生を歩んでいくことを目指してほしいと思います。
スパークル株式会社について
地域に本社を構えるベンチャーキャピタル・プロフェッショナルファームとして、新しい世界の経済循環をつくりだすことを目指しています。
所在地 :宮城県仙台市
代表取締役 :福留秀基
X :https://twitter.com/Spurcle_tohoku
Facebook :https://www.facebook.com/Spurcle.tohoku
話を聞いた人
佐々木栞
宮城大学事業構想学群2年 宮城県仙台市出身
