
非認知能力特集その4 感情にうまく対処する能力「感情調節」
感情調節とは
人は家庭や職場、画工などさまざまな状況で、楽しい、嬉しい、腹が立つ、悲しい、寂しいといった感情をいだきます。そして状況に応じて、感情を表情や言葉で表したり、あるいはそれらを表さないように我慢したりします。
以下がこの言葉の定義です。(1998年・Gross)
人がいつ、どのような状況で、どのような感情を経験したり表出したりするかに影響する一連の過程を捉える概念。
日常生活において、人はさまざまな方法を用いて感情の調節を行っている。感情を望ましい状態に保つことを目的として、また他の目的のために、手段として感情の調節が行われることもある。例えば、友達の悩みを引き出すために、あえて笑顔を消し、声のトーンを下げ、ポジティブ感情を低くすることなど。
感情調節の多くの場合は、自分の感情を調整することを目的として行われる。これを、内的感情調節と呼ぶ。

内的感情調節
例えば、イライラしたときに自分の気持ちを落ち着かせようとすること。
一方で、相手の感情調節を目的として行われるものを外的感情調節と呼ぶ。
外的感情調節
例えば、困っている子どもを泣き止ませて落ち着かせるために助けの手を差し伸べること。
そして、感情の調節は意図的に行われることもあれば自動的に行われていることもある。
顕在的感情調節
意図的に行われる感情の調節のこと。
潜在的感情調節
自動的に、意識せずとも感情を調節するようになること。
例えば、ある生徒がクラスで仲間外れにされることに腹が立っても、当初は意図的に怒った表情を隠すようにしていた。しかし繰り返し仲間外れの状態が続くうちに、自動的に表情を消すようになっていく、といったこと。
一般的には、日常生活でのネガティブ感情を低くするために感情調節を行っているが、喜びや興味、安心などポジティブな感情を高めたりするために行うこともある。

感情調節のプロセス理論(1998年・Gross)
人の感情が沸き起こる際には、4つのプロセスを経ている。
1:状況 ➡ 2:注意 ➡ 3:評価 ➡ 4:反応
これを土台として、感情を調節する際には以下の5つの調節が行われているという理論。
①状況選択
ある感情を喚起させる状況を選んだり、避けたりするプロセス。
例:学習する科目や場所などの状況を選択すること
②状況修正
状況を直接変えるプロセス。
例:テスト中の不安を解消するために、難しい問題は後回しにし、易しい問題から解くようにする。授業を受ける際に、自分にとって都合の良い(うるさくない、不安になりにくいなどの)座席を選ぶ。
③注意配置
注意を向けたり、逸らしたりするプロセス。
例:週末に喫茶店で勉強する時に、周囲の会話に気をとられないようにするためイヤフォンをして音楽を聴いて気持ちを落ち着かせる。
④認知的変化
状況の評価や捉え方を変えるプロセス。
例:大切な試験に臨む際に、自分が充分に準備してきたことを思い出し、合格できると期待することで不安を抑える。また、結果が不合格だったとしても、今回が最後のチャンスではない、と捉えなおすことで悲しみを抑えようとする。リフレーミングも。心の健康に低~中程度の効果があるという研究結果あり。
⑤反応調整
表情やしぐさなどの反応を変えるプロセス。
例:授業中に退屈しているとき、あくびを堪えること。友人の悩みを聞くときに笑顔を消す。
※日常生活において、人はこれらのプロセスを明確に区別せずに用いている。また、これらの感情調節の結果、として、状況は刻一刻と変化していく。

感情調節をうまく行えると起きること
1 前向きに捉えなおし、抑圧を避けられる。
ポジティブな捉えなおしの力(再評価と呼ぶ)が、心の健康を維持することに役立つ。また、本心を明かさない抑制の傾向が強いと、心の不健康と強い関連があることも判明。抑制は児童期や思春期を含む成人期以前に比べて、成人期以降で効果が強い。
➡ 抑制という状況は何とか避けた方が心の健康につながる。
言いたいことも言えないということはポイズンであるということ。
ただし、あまり直接的な表現を好まない日本のような文化圏では、状況によって効果的な抑制を用いることで人間関係が円滑になることもある。
例:自分の好みではないプレゼントを受け取った時の反応として、自分の気持ちを抑えて笑顔で受け取れる子ほど、「友達として選ばれやすい」という結果。
2 学力にも影響
幼児期の読み書きや小学生での算数の成績、中学生では国語と数学の成績がよいことが2007年の研究で示された。(Graziano et al.2007)
これは、幼児期において言語と感情の理解が発達した後、児童期において感情を調節する能力が発達し、先生や友だちとの関係が良く保たれることで、結果として学習への動機づけとスキルが向上し、よい学業成績へとつながっていると考えられている。
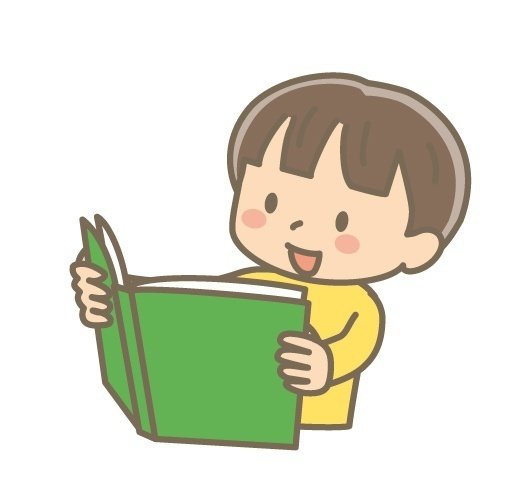
具体的な介入手段
学習プログラムとして、社会性と情動の学習(Social and Emotional Learning :SEL)が提案され、実践されてきた。このSELは、感情調節を含むスキル、心の健康、学業成績に効果があることが報告されている。
以下に具体的手法を紹介。興味のある方は調べてみるとよいかもしれません。
(1)RULER(Recognize, Understand, Label, Express, Regulate emotions)
【感情を認識し、理解し、名づけ、表出し、調整する】の頭文字をとった、SELのひとつである指導方法。下記リンクは英語記事ですが、わかりやすくまとめられています。
(2)PATHS(Promoteing Alternative Thinking Strategies)
(3)やさしさの教育(Kindness Curriculum)
(4)Incredible Years プログラム
(5)強い子プログラム(Strong Kids)
具体的に今日からでもできそうなことをまとめると…
①子どもが助けを得やすい環境を整えること
②子どもが安心して感情を表出し、感情について話し、感情を調節する練習ができる場をつくること
③子どもの感情をとらえ、その感情に名前をつけ、感情を言葉で表したり、指導したり助けたりすることで、子どもが怒りやイライラといったネガティブ感情を調節する機会を提供する。
例えば、大人が子どもに対して「イライラしてるね」(➡名づける)「一緒に息を吸って、吐いてみようか」(➡助ける)など。

感情の円環理論&ムードメーター
https://note.com/fair/n/n8a0f600b2491
https://studyhacker.net/kayo-iketeru-interview02
子どもと関わるすべての大人に心の余裕を!
今、公教育に関わっている身として、先生も、生徒も、保護者の方もそれぞれが忙しく、余裕のない状況にあることをヒシヒシと感じます。そして、大人のそういった余裕のない状況は、焦りや苛立ち、不快感を生成します。やがてそれらが、どう隠そうと努力したとしても言葉や態度に表れ、子どもにぶつけられます。
子どもはそういった反応にものすごく敏感です。笑顔の裏をみています。
教育を語る際にしばしば目にする「寄り添う」という言葉。これは簡単な言葉ではありません。相手の心の状態を察知しようと努力し、適切な範囲で介入を行い、子ども自身が自分への理解を深め、ポジティブに物事を捉えられるようになり、今ある環境に感謝し、自己実現に向けて自ら歩み出すことに向けて支え、励ますことだと思います。
大人がイラついていては、そのような環境設定ができません。今あるルールや環境が本当に子どもの学びのために役立っているか。不要なルールを優先するあまり、子どもの学ぶ機会を奪っていないか、今一度検証する必要があるかもしれません。
私たちは、常にこの意識をもって学びの環境設定に努めていこうと決意を新たにしているところです。
どうぞ今後とも、よろしくお願いいたします。
今回は第4回として【非認知能力特集その4 感情にうまく対処する能力「感情調節」】についての学びをまとめてみました。
Supportiaでの学びは、こうした非認知能力に関する最新の知見をもとに、教育の責任者と環境設計責任者とが議論を重ねながら学びの環境を整えています。体験イベントも年内は月に2回程度実施していますので、ご参加をお待ちしています。下記フォームからご参加いただくことができます。
https://docs.google.com/forms/d/1_qHGcyQbvZ0dWVjZn7xSClh9egprun34p5J8mTHOCPk/edit
また、HPもマインクラフト教室を中心にリニューアルしましたのでぜひ参考となれば幸いです。
