
「万能」になるか「コミュニケーター」になるか −これがプロダクトマネージャーの生きる道−
プロダクトマネジメントについて、色々な本を読み、色々な人の話を聞いて考えたことをまとめてみる。
1. プロダクトマネジメント/プロダクトマネージャーとは何か
まずは、ソフトウェア・プロダクトの定義から考えていく。僕は、ソフトウェア・プロダクトの定義を、コアバリュー(≒プロダクトが社会に提供したい本質的な価値)を、テクノロジーの力を用いてエンハンスすることで、顧客にコアバリューを”利便性が付加された状態”で届ける手段として考える。これは『プロダクトマネジメントのすべて』の著者である及川卓也氏が先日講演で使っていたモデルを自分なりにカスタマイズしたものである。
この定義から、プロダクトマネジメントを以下の2つの課題解決を行うための方法論であると捉えてみる。
①プロダクトのコアバリューを適切に定義する
②プロダクトのコアバリューを伝えるためのテクノロジー的な利便性を大きくする
①②は、ソフトウェア・プロダクトの定義を前後半に分割し、それぞれに対して述語部をつけただけの簡便な定義だが、それなりに納得感のある形にまとめられたと思っている。①の遂行にはイシューへの感度を高めるアントレプレナー的な素質が、②の遂行にはエンジニアリング、ユーザー体験、マーケティング等、顧客がプロダクトに触れる際のインターフェースの全てに対する統合的な知見が、それぞれ要求されると考える。
プロダクトマネジメントそのものの困難さは、上記の通り広範な領域に対する満遍ない素質と知見を求められるところにある。少しでも理解の欠けている領域があれば、それがプロダクトチームの活動における致命的な欠陥になりうるのである。
以下では、プロダクトマネージャーが組織設計上極めて難易度の高い役割を与えられていること、そしてその役割を果たすために非常に高い能力が要求されることを、「万能」と「コミュニケーター」という切り口でまとめてみる。
2. 「フラットで自律的なチーム」の組織論的考察
時折耳にする、「プロダクトマネージャーは、メンバーのやっていることがわからなくても、ある程度理解していれば良い」とか、「少なくとも興味関心を持っていて、会話ができる程度であれば良い」といったアドバイスは、プロダクトマネジメントを組織論の観点で考えると適切だとは言えない。むしろ、組織設計上、プロダクトマネージャーは「万能」であることを義務付けられていると理解した方が適切だというのが僕の考えである。
プロダクト・マネジメントチームの鉄則はフラットで自律的であることだが(理由は色々な人が説明してくれているので省略する)、まず個人間の情報やスキルの非対称性が大きい集団は、フラットで自律的なチーミングに適していない。これは端的に、組織や人は、情報の非対称性を常に自己の利得を最大化するために利用するためだ。
ここから先は「組織の経済学」という経済学の一領域の理屈を用いて、少し理論的な話をするので、理屈に関心のない方は読み飛ばしていただいて構わない。関心がある方は菊澤研宗先生の「不条理」シリーズを一読されることをお勧めする。
例えば、僕がいま外部ベンダーにとあるシステムの入れ替えを外注しているとしよう。僕は一切システムやエンジニアリングのことを理解していない。この時、ベンダーは僕の要求が気に入らなくて跳ね除けたいと考えているとする。ベンダーは、どのように行動するのが最適だろうか。それは、「技術的に困難である」とか「実装に時間がかかる」とかいって、煙に巻いてしまうことである。情報の非対称性を梃子に自己利得を大きくしようと試みるのは、個組織にとって極めて合理的な行動である。特にこの場合、ベンダーは外部の組織だから、僕には彼らを制御することも管理することも難しい。
このような「情報の非対称性を梃子に自己利得を大きくしよう」とする問題、簡単に言えば「サボり」に対処するために私ができる有効な手立ては、自分の組織のヒエラルキーに組み込んでしまうことである。ヒエラルキーは、組織や個人が情報の非対称性に基づく「サボり」や「自己利得の最大化」といった行動をとることを抑制するために導入される仕組みだ。サボらないようにきちんと管理監督しよう、プロセスをきちんと実施しているか見張ろう、成果物にはきちんと品質管理の検査を入れようといった形で、上部組織が下部組織の行動を束縛し、「標準化」された行動をとるよう管理監督するのである。前段の例であれば、ベンダーの「サボり」を抑制するために、ベンダーを買収してシステム開発業務自体を内製化してしまうというのが典型的な解決策である。ベンダーを自分の組織組織ヒエラルキーの下部に置くことで適切な管理監督を行い、「サボり」を働くことを難しくするのだ。
ただし、このヒエラルキーによる管理監督は、突きつめると必ず管理コストがメリットを上回る。情報の非対称性は絶対に消えないため、「ズル」を抑制するための管理監督プロセスが延々と増殖するからである。その結果、何の価値を生んでいるのか不明な謎の「管理業務」が本来の仕事を圧迫するようになり、組織はどんどん鈍重になっていく。システム開発で重たいやたらと重たいゲート管理プロセスを引いてしまい、その管理業務の方が時間がかかるというのはあらゆる現場で起こっている悲劇である。
ここから、価値を生まない中間プロセスを縛るのではなく、下部組織にある程度の自律性を認めるかわりに「結果責任」を丸ごと負わせる形に組織をデザインした方が効率が良いという結論が導かれる。前段の例を引き続き使えば、システム開発に関連する部署を丸ごと「事業部」という単位で括り、結果責任(売上)を負わせる代わりにプロセスには自律的な権限を与えるのである。このような設計を行うメリットは、組織や個人がプロセスではなく結果に責任を負うことで、情報の非対称性に基づく「サボり」や「自己利得の最大化」を行うインセンティブが働きにくくなるという点である。結果が悪ければ損をするので、結果を改善するのが最適行動となるからだ。
このような「組織の経済学」の理論枠組みは、プロダクト・マネジメントにおいて自律的でフラットなチームを良しとする主張の組織論的なバックボーンになっている。もっと詳細な理屈は以下の書籍に詳しいので、関心がある方はぜひ手に取っていただきたい。
3. プロダクトマネージャーは「万能」であることを義務付けられている
自律的でフラットに組織されたプロダクトチームは、「組織の経済学」の観点では理想の組織形態だと言えそうである。しかし、ここには見落とされがちな問題がある。
確かに、事業部制やそこから更にラディカルに派生するフラットなプロダクトチームは、自律性と結果責任を与えることで、情報の非対称性を利用して「サボろう」とするモチベーションを持ちづらい構造になっている。しかし、だからといって完全に情報の非対称性の問題は完全に解決しているわけではない。例えば、自分が納得していないのに「イケてない施策」を、プロダクトマネージャーが進めようとしている時、一番簡単にそれを邪魔する方法は、自分とプロダクトマネージャーとの間の情報の非対称性を利用することである。プロダクトマネージャーがエンジニアリングのことを理解していないのであれば、「実装が難しい」とか「技術的なコストに成果が見合わない」などと言ってのらりくらりとやりごして、提案自体を煙に巻いてしまえば良い。デザイナーでも、スクラムマスターでも、マーケターでも、アナリストでも、自分の職能を梃子にして同じことができる。
お分かりだろうか。プロダクトマネージャーは、プロダクトの要件を決めるという大きな責任と権利を有する代わりに、あらゆるメンバーが「情報の非対称性」を通じて利得を最大化しようとするという問題を引き受けなければならないのである。この問題に対処するには、プロダクトマネージャーが、全ての職能に対してチームメンバーと同じ程度にプロフェッショナルである必要がある。そうすることで、情報の非対称性を極小化することでメンバーの自己利得を最大化しようとする行動を抑制することができるからである。組織の経済学の理屈は、このように「万能」なプロダクトマネージャーを要求するのだ。
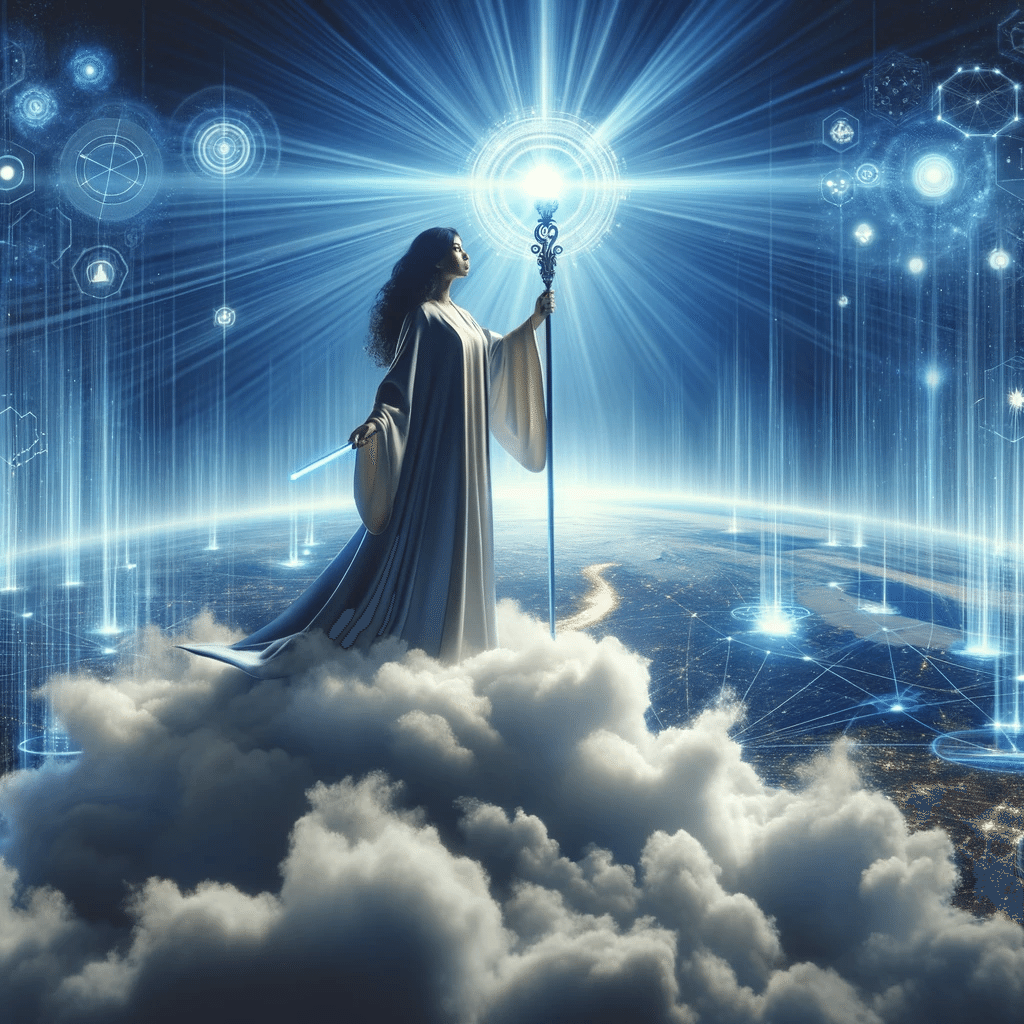
4. プロダクトマネージャーは「コミュニケーター」であることを義務付けられている
しかし、こんな魔法みたいに「万能」な人にお目にかかることは滅多にできないし、ましてや自分がなれるわけがないと誰もが思うだろう。だからこそ、プロダクトマネージャーは何よりも優れた「コミュニケーター」でなければならない、というのが僕の見立てである(なお、この見立ても及川卓也さんの考えにインスピレーションを受けている)
まず前提として、全ての職能に対する基本的な解像度をもち、その職能がどのようにプロダクト作りに貢献するのか、その職能におけるメンバーのスペシャリティが何でどの程度優れているのかを理解していること。これは、最低限プロダクトマネージャーが満たす必要がある素養である。その上で、良きコミュニケーターとしてビジョンを伝えることで、個々人の内発的な動機(自分のうちから湧き上がる興味関心)を引き起こす力、つまり変革型リーダーシップを持つことが極めて重要だと僕は考えている。変革型リーダーシップとは以下の4つの特徴を持つリーダーシップのことである。
(1)インスピレーションを与える動機づけ(Inspirational Motivation)
(2)理想化された影響(Idealized Influence)
(3)知的な刺激(Intellectual Stimulation)
(4)個人への配慮(Individualized Consideration)
このうち重要なのは(1)インスピレーションを与える動機づけの部分で、要するにプロダクトマネージャーが話すプロダクトのビジョンやそれがもたらす価値が、チームメンバーにとって心からコミットしたいものだと思わせる力を意味している。また(2)理想化された影響とは、(1)のビジョンや価値をまさに自分自身が体現しており、それがメンバーのロールモデルになっている状態を表す。要するに、プロダクトマネージャーが、プロダクトそのもののコアバリューがもたらす価値を体現し、それを伝え、モチベートする存在であれば、その人は変革的リーダーシップを持っていると言えるだろう。変革型リーダーシップを持つ人は、だから常にメンバーにプロダクトの価値やビジョンを「コミュニケーション」する人でなければならない。
プロダクトマネージャーが変革型リーダーシップを持っていれば、その人自身は必ずしも「万能」である必要はない。「万能」を必要とするのはコマンドアンドコントロール型の組織、つまり「サボり」を抑制するためにメンバーのスキルやパフォーマンスを厳しく管理監督するリーダーシップ(これを変革型リーダーシップと比較して取引型リーダーシップという)を必要とする組織である。変革型リーダーシップによるチーミングは、管理監督による外的報酬の適切化ではなく、コミュニケーションによる内発的動機の最大化を目指す。ここに従来型の組織とプロダクトチームの大きな違いがある。
無論、プロダクトマネージャーは「万能」であることに越したことはないし、全てのメンバーの職能に対して一定以上の理解を持っておくことは極めて重要である。現に、変革型リーダーシップを構成する(3)知的な刺激や(4)個人への配慮といった要素は、個人が常に学習し成長し続ける様子や、メンバーの状態への細やかな配慮を見せる態度を表す。学習を通じて適切に個々人を観察し、評価する力を示すこともリーダーシップの重要な要素の一つである。
しかし、「賞罰」をモチベーションとするプロダクトチームは、「ビジョン」をモチベーションとするプロダクトチームに勝つことはできない。前者におけるメンバーの関心は情報の非対称性を利用した自己利得という外的報酬の最大化になるのに対し、後者はプロダクトの価値やプロダクトマネージャーのリーダーシップへの同一化といった内発的動機によって動くからである。内発的動機に基づく行動の方が持続性があり、長期的な生産性の向上に寄与することは、すでに経営学や心理学が長い時間をかけて立証してきた。
変革型リーダーシップと内発的動機づけに支えられたチームであれば、メンバーの関心は自己利得の最大化ではなく、内発的な動機の充足になる。情報の非対称性は消えないが、それを利用した外的報酬の最大化にメンバーのモチベーションが無いのであれば、わざわざ細々とした管理監督を行う必要はないのである。
長くなってしまったが、要するにこういうことだ。プロダクトマネージャーは「万能」になるか「コミュニケーター」になるかの2つの選択肢がある。どっちを選ぶと聞かれたら、前者になるより後者になる方が容易なのではないか、というのが僕の今の所の考えである。

