
【文例付き】寒中はがきは、いつ、どういう場面で出しますか?
寒中見舞いのはがきは、寒さが厳しい時期に友人や知人を気遣う挨拶状です。年内であれば喪中はがきの代わりに、年賀を過ぎたときは年賀状の代わりとして、季節の挨拶状のなかでも多様な使い方ができるのが寒中はがきです。
この記事では、2031年に創業100年を迎える東京新富町の紙製品メーカー・山櫻が、多様化する寒中見舞いはがきの基本的なルールと、すぐ使える文例をわかりやすくお伝えします。
暑中はがきについては、こちらの記事をご覧ください。
喪中はがきについては、こちらの記事をご覧ください。


寒中見舞いはがきとは?
寒中見舞いの役割
寒中はがきは「一年のなかで最も寒い時期に友人・知人の健康を気遣う」挨拶状というのが本来の役割です。郵便事情が近代化した明治以降に広まったとされ、なかでも、寒さが厳しい地域で活発になったという説があります。
暦では、寒の入りから小寒、大寒を経て寒明けまでの期間を「寒中」と呼びます。
寒の入りは1月5日頃で、松の内を過ぎた頃に始まるため、喪中で年賀葉書のやり取りを行わなかった相手への年賀代わりの挨拶としても使われるようになりました。
寒中見舞いハガキの役割
現代では、寒中見舞いは次のような使い方ができます。
●自分が喪中であることを相手に知らせる
喪中のために年賀状を控えたことを伝えて、年始の祝いの言葉を避けて挨拶をします。自分の近況と喪中である旨を記し、お詫びの言葉を添えます。
●いただいた年賀状へ返信する
年賀状を受け取ったものの、喪中などの理由で返信できなかった場合に、寒中見舞いとして返礼します。
●喪中の相手へ送る
相手が喪中の場合、年賀状の代わりに寒中見舞いを送ることで、相手の気持ちに配慮した挨拶ができます。
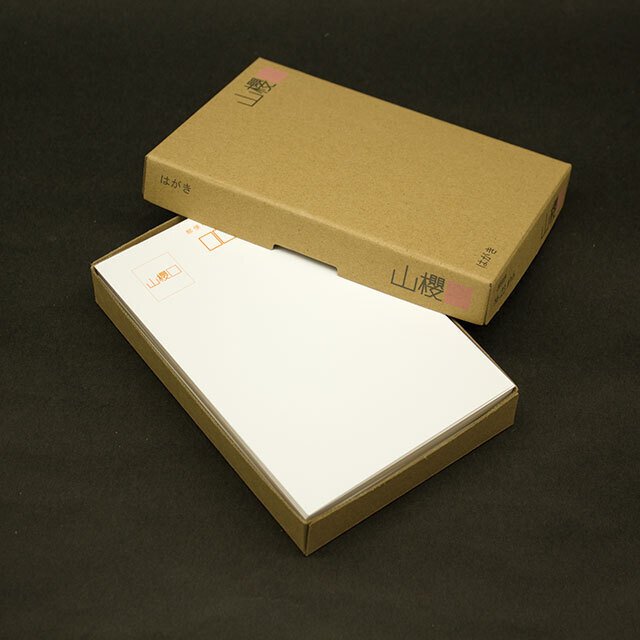
【いまさら聞けない】寒中はがきの素朴な疑問
ここからは、寒中はがきを出すときの疑問を解決します。
寒中はがきはいつ出せばいいですか?
寒中見舞いを送る時期は、松の内が明けてから立春までの期間に送るのが一般的です。
地域によってもその時期は少しずつ異なり、たとえば関東地方では1月7日以降、関西地方では1月15日以降に寒中見舞いを送る場合が多いようです。
寒中見舞いと余寒見舞いの違いはなんですか?
寒の入りから小寒、大寒を経て寒明けまでの期間が「寒中見舞い」であるのに対して、寒明けを過ぎて立春を経てもまだ寒い場合には、「余寒見舞い」を送ります。
夏の時期に「暑中見舞い」と「残暑見舞い」を使い分けるように、冬の時期も、暦に合わせて「寒中見舞い」「余寒見舞い」の時期が異なるのですね。
寒中見舞い:
1月7日から立春(2月4日頃)までに送る、寒さが厳しい時期の挨拶状。
余寒見舞い:
立春(2月4日頃)を過ぎてから2月末までに送る、暦では春になっても、以前として寒さが残る時期の挨拶状。
寒中はがきのNGは?
●相手が喪中の場合は、おめでたい表現は避ける
寒中はがきでは「賀詞(がし)」はNGです。「賀詞(がし)」とは、「寿」「迎春」「謹賀新年」などの祝いの言葉のこと。まるで喪中を祝っているかのように受け取られかねないため、使うのはNGです。句読点も極力使用しません。
●文頭や文末の慣用表現はいらない
寒中見舞いには「拝啓」や「敬具」などの頭語や結語は不要です。
●年賀はがきを使ってはいけない
寒中はがきに、年賀はがきを使い回すことはできません。通常の無地のはがきや私製はがきを使うのがマナーとされています。
文具メーカーや紙製品メーカーのはがきを使うのは問題ありません。


【スグ使える】寒中はがき文例
ここからは寒中はがきの文例について紹介します。
寒中見舞いの基本構成
季節の挨拶: 「寒中お見舞い申し上げます」
時候の挨拶 :「厳寒の折、皆様におかれましてはご健勝のこととお喜び申し上げます」
年賀状の返礼やお詫びの言葉: 「先日はご丁寧な年賀状をいただき、誠にありがとうございます」
自分の近況報告 :「私どももおかげ様で大過なく過ごしております」
結びの挨拶 :「寒さ厳しき折、どうかお身体を大切にお過ごしください」
日付(差出し月): 「令和七年一月」
そのまま使える文例
◉一般的な寒中見舞いの文例
寒中お見舞い申し上げます。
厳寒の折、皆様にはご健勝のこととお喜び申し上げます。
私どももおかげ様で大過なく過ごしております。寒さ厳しき折、どうかお身体を大切にお過ごしください。
令和○○年大寒
◉年賀状の返礼としての寒中見舞いの文例
寒中お見舞い申し上げます。先日はご丁寧な年賀状を頂き、誠にありがとうございます。
私どももおかげ様で大過なく過ごしております。今年も変わらぬお付き合いのほど、よろしくお願い申し上げます。
令和○○年大寒
◉喪中の相手への寒中見舞いの文例
寒中お見舞い申し上げます。ご服喪中と存じ、年頭のご挨拶は控えさせていただきましたが、いかがお過ごしでしょうか。
ご家族の皆様はお力を落としのことと存じますが、お心を強くお持ちになってお過ごしください。
令和○○年大寒
◉自分が喪中の場合の寒中見舞いの文例
寒中お見舞い申し上げます。ご丁寧なお年始状をいただきありがとうございました。昨年11月に父が永眠し、年頭のご挨拶を控えさせていただきました。
ご連絡が行き届かず、誠に失礼いたしました。今年も変わらぬお付き合いのほど、どうぞよろしくお願いします。
令和○○年大寒
「【文例付き】寒中はがきは、いつ、どういう場面で出しますか?」まとめ
◉寒中見舞いはがきの役割
-自分が喪中であることを知らせるため
-いただいた年賀状への返信として
-喪中の相手への挨拶として
◉寒中はがきを送る時期
松の内が明けてから立春まで(関東では1月7日以降、関西では1月15日以降)
◉寒中はがきのNG
-相手が喪中の場合は「寿」「迎春」などの賀詞は避ける
-頭語や結語(「拝啓」「敬具」)は不要
-年賀状ではなく、文具メーカーや紙製品メーカーの私製はがきで送る
SOREALでは、寒中見舞いとしても使える喪中・弔事はがきを豊富に取り揃えております。詳しくはこちら。
