
『逆転こそがカードゲーム』か?
どうも。くーぼー(@soranaki00)です。
時が経つのは早いもので、2024年もいつの間にか終わりに差し掛かっています。
ところで皆さん、今年のデュエル・マスターズの標語を覚えていますか?
そう、『逆転こそが、カードゲームだ。』ですよね。
デュエル・マスターズの持つ、ハラハラドキドキのシールドを巡る攻防を表したこの標語。そしてデュエル・マスターズの『シールド』メカニズム、その面白さの根幹にあるギミックこそが『S・トリガー』です。
当初は『従来のライフ制のようにキャラクター自身が攻撃を受けても傷つかないように、しかし漫画的に映える演出として』漫画D・M原作者松本しげのぶ氏から提案されたこの『プレイヤーの身を守る』ギミックは、開発を担当するウィザーズのフィードバックを受けて『シールド』『S・トリガー』という形となって生み出されたものでした。(※1)
そして、『シールド』『S・トリガー』ギミックは、そのダイナミックな"逆転"をもたらすデザインの秀逸さから、今や当初の意図から大きく離れた所でも、類似したギミックを搭載した後発カードゲーム(デュエマライク・フォロワーTCG)の登場という形でTCG界に影響を及ぼし続けています。
とはいえ、デュエル・マスターズの『シールド』ギミックはそれらの類似ギミックの元祖であるが故に、初期段階ならではの欠陥が存在しないとは言えない事もまた然りです。
そこで、一つの疑問が生じます。
では、『シールド』ギミックに影響を受け、自らのルールに導入した後発TCG達は、『シールド』のどこに魅力や問題点を見出し、各々どうやってそれを継承、あるいは解決しようと試みたのでしょうか。
今回の記事ではそのトピックについて、いくつかのTCGを例を取って一緒に考えてみましょう。
1.デュエル・マスターズ『シールド』
まずは「王道」のデュエル・マスターズから、改めて『シールド』とはどういうギミックかをおさらいしましょう。

先述の通り、『シールド』はプレイヤーの身を守る為のギミックであり、ゲーム開始時に設けられた5枚のシールドがクリーチャーの攻撃などによって全て破壊され、直接攻撃を受けるとそのプレイヤーの敗北となります。つまり、シールドは『勝敗条件に関わる重要なライフカウント』なのです。
デュエル・マスターズの兄とも呼べる、ウィザーズ社製・最古のTCGである『マジック:ザ・ギャザリング』では、この『勝敗条件に関わる重要なカウント』の役割は"ライフポイント"が担っています。
デュエマと並んで国内TCGの雄と言える『遊戯王OCG』や、DCG界の先駆者である『ハースストーン』も同じようにライフポイント制を採用しています。これらは『MtGライク・フォロワー』のTCGと呼んでもいいかもしれません。
『シールド』と『ライフポイント』を比較する上で重要なのは、『ゲーム外の数字カウンター』で管理される『ライフポイント』とは違い、『シールド』はゲーム内、それも自身のデッキ内のカードから展開されるギミックであるという事です。
つまり、ライフカウンターそのものをゲーム内・デッキ内に組み込む発想が『シールド』なのです。
デュエル・マスターズのゲーム性においては、『シールド』ギミックの導入によって、"ライフのやり取り"部分がゲームにそのままシームレスで関与する、という側面をライフ制度に与えている事を意味しています。
破壊されたシールドは手札に加わり、相手のリソースに変わってしまいます。これは単なる数値の変化しか起こさないライフポイント制と大きく異なる部分であり、戦闘面に異質なスリルとエキサイティングさを生み出します。
初期手札が5枚であり、しかも毎ターン手札のカードをマナとして手放さければプレイ権が増えていかない、他TCGと比較しても『手札事情が極めて窮屈な』デュエマにおいて、シールドから見込まれる手札リソース5枚は非常に貴重で、だからこそ安易な攻撃は抑制されるのです。
また、破壊されたシールドが『S・トリガー』なら、リソースどころか無料でプレイする権利まで与えてしまいます。
これらのギミックによって、プレイヤーたちは攻撃し得なタイミングでライフを詰める味気ない戦闘ではなく、常に『逆転』の種を相手に与えながら攻撃しなければならないというリスクの享受、逆の視点では『シールド』からの逆転の希望を見出す事になります。
この受け手有利な『シールド』のギミック性が成り立っている背景には、初期シールド5枚、かつ全てのクリーチャーが最低でも1枚はシールドを破壊できる(6回攻撃できれば勝つ)、という極端なまでの攻め手有利属性が一方で備わっている事が挙げられるでしょう。
この2つの属性のぶつかり合いによって、デュエル・マスターズはスピーディでありながらダイナミック、強固な牢壁も迅速な速攻も存在できるゲームレンジの幅広いカードゲームとなりました。
……と、ここまでは『シールド』の影響と良い部分について説明してきました。
が、実際の所、『スピーディでダイナミックなデュエマ』が実現した理由は主に後々のカードデザインで力を尽くした結果であって、初期のデュエマは低速志向のゲーム、しかもその要因にシールドが絡んでいた事は明らかでした。
第一に、攻撃する側のパワーがまだ未成熟な場合、デュエル・マスターズの『シールド』の「破壊されたら手札に加わる」という性質は受け手側にこそ過剰に働きます。
特に、手札に余裕のないデュエマというゲームにおいて、速攻戦略は自らのリソースを投げ捨てながら攻撃に全振りする戦略であり、自らは『シールド』という5枚ものリソースを手にする事ができないばかりか、相手にはそのリソースを与えなければならない時点で、よほど強力な攻撃ギミックが存在していない限りは受け手側の5枚の『シールド』を貫通する前に息切れを起こし敗北します。逆転など起こらずに。
第二に、そこまでして攻撃したとしても、カウンターとなる『S・トリガー』の強力さに全てが塗り潰されてしまう事が挙げられます。
そもそも、デュエル・マスターズのゲーム性において、他TCGのように相手ターン中にカウンターとして使用出来るカードはごく限られています。
「能動的に使用できる」という条件なら尚更です。
これには、コンバットトリックによってゲームが複雑化する事を避けたいという意図があるのでしょうが、詰まる所、他のカードには許されない"特権"が『S・トリガー』には許されているという事なのです。
そんなあまつさえゲーム性に異を唱えるカウンターギミックが、『シールド』という非公開領域のランダム性が絡むとはいえ無料でプレイできてしまう、という点において『S・トリガー』の支配力は他のキーワード能力の比になりません。
現に、どんなに劣勢な状況でも、シールドから《ヘブンズ・ゲート》が現れてしまえばそれまでのゲームを全て無に返してしまう事は『守りの王道』を見ても十分に理解できる事でしょう。
ここまでの内容を要約すると、『シールド』というギミックは『デッキ内のカードをライフに見立てるという手法』で独立していたライフ制度をゲームに関与させる方策であり、それはゲームの成熟が進むにつれてスピーディさとダイナミックさ、激しく熱いゲーム展開を実現する素晴らしいギミックであるものの、ことインフレの進んでいないゲームの展開初期段階で言えば『手札リソースに変わる事』や『S・トリガーの支配力』というゲームを停滞化させる問題を引き起こす、といった指摘が可能だ、という事になります。
さて、ここで挙げた『シールド』の問題を、他のTCGはどのような解答で応えたのでしょうか。
2.WIXOSS『ライフクロス』
『WIXOSS』は2014年からタカラトミーによって展開されているTCGであり、販売元を同じくするデュエル・マスターズにとっては妹分のようなカードゲームです。
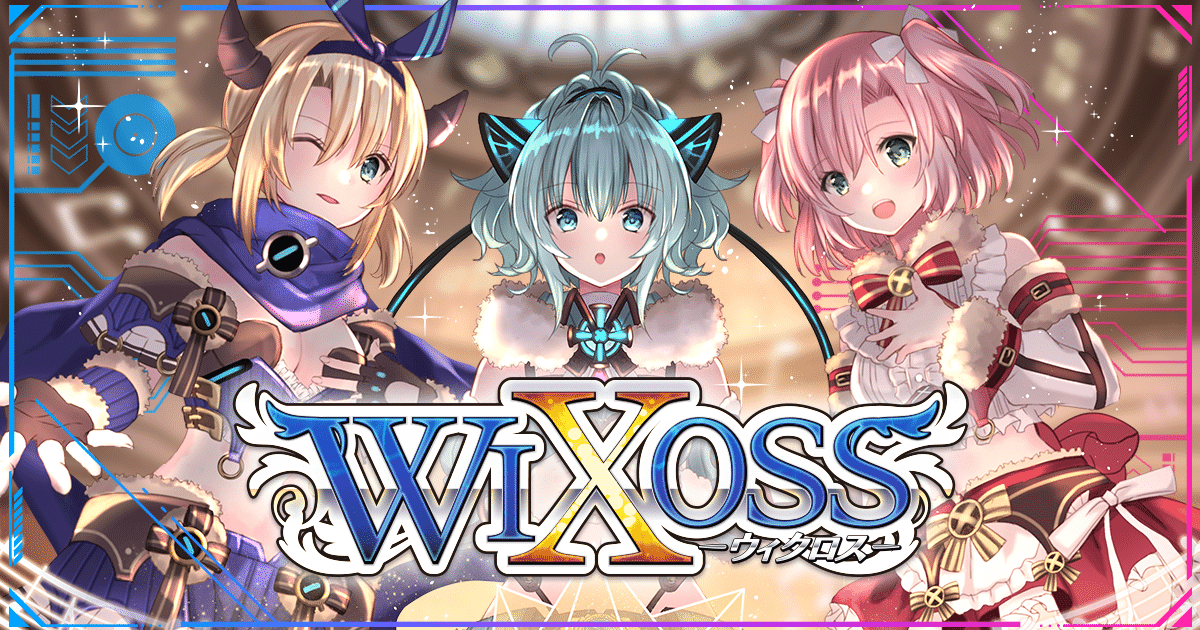
細かいゲーム性は割愛しますが、WIXOSSにもまたデュエマにおける『シールド』のようなギミックがあり、それが『ライフクロス』です。
枚数こそ7枚と違いがありますが、プレイヤー自身を守る為の盾である事、『ライフクロス』が全て失われた状況で攻撃を受けると敗北となる事など、概要はやはり『シールド』と酷似していると言っていいでしょう。
しかし、『シールド』と『ライフクロス』には大きな違いがあります。
それは、『ライフクロス』が破壊された場合はエナゾーン、デュエマで言う所のマナゾーンに移動するという事です。
これには様々な示唆が冨みます。
まず、WIXOSSはターン開始時に2枚ドローするゲームである事。これによりリソースの厳しさは開始時ドローである程度緩和し、代わりにライフ部分で急激に手札リソースが増えないように調整する事で、デュエル・マスターズで問題だった"手札が窮屈なのに他の手札リソース部分が5枚の『シールド』に依存している"という部分を解決しています。
また、『特定の行動時にエナ(マナ)を使い切りで消費する』というプレイパターンが存在し、増加したマナは有限の使い切りリソースとして利用する事で、ゲーム内でのエナ、ひいてはライフクロスを破壊する事の影響度を意図的に調整しています。
また、WIXOSSにも『S・トリガー』のようなカウンターギミック『ライフバースト』がありますが、実はルールによってデッキ内に採用できる上限枚数が定められています。
こうした構築制限に関しては次の項により詳細な解説を譲る事としましょう。
3.ビルディバイド『ライフ』
アニプレックスから販売され、先日『ビルディバイドブライト』との統合も発表されたTCG『ビルディバイド』。

このゲームのゲーム性もまたデュエル・マスターズに近しい部分が多分に存在していますが、代わりにライフ部分で大きな違いとして挙げられるのは『初期ライフが10枚』である事と『破壊されたライフは手札ではなく墓地に送られる』事でしょう。
これだけ見ると"ライフカードがリソースに変化しない"という意味でライフポイント制の亜種のように捉えられるかもしれませんが、『S・トリガー』系のギミック『ショットトリガー』と、その逆に自らがダメージを追加で食らう『バーストトリガー』の存在がそこに意味を持たせています。
利己行為どころか利敵行為であるこの『バーストトリガー』は、『シールド』系ギミックのアイデンティティに大きな問いかけをしているとも見る事ができます。
ビルディバイドのルールでは『ショットトリガー』は12枚まで、『バーストトリガー』は12枚確定で採用する事が義務付けられています。
つまり、誰もが平等にこの自傷ギミックを受け入れる必要があるのです。
『シールド』や『S・トリガー』が、非公開領域から捲るカードによるハラハラドキドキの逆転を企図したギミックであるならば、これもまた自分も相手も非公開領域によって勝敗を左右されてしまうという、挙動としては真逆でありながらある意味で共通した『逆転』のテーゼが存在しているのがこのギミックの発想の面白いところです。
それだけでなく、ライフ10枚というともすれば冗長になりかねないゲーム性を加速させる意味でもこのギミックは大きな意味を持っているのです。
4.蟲神器『縄張り』
『蟲神器』は百均ショップとして有名なダイソーが独自開発したTCGであり、その安さとパッケージキャラクターの話題性からSNSでも話題になりました。

そんな蟲神器、ルールとしては比較的デュエマに近く、何なら『シールド』に当たる『縄張り』ゾーンの挙動も"破壊されたら手札に加わる"というようにデュエマと同じ挙動になります。
ですが、蟲神器の特異性は『縄張り』部分のルールではなく、『縄張り』が破壊される条件にあります。
蟲神器では、デュエマのように相手の場に生物がいる場合も無視して『シールド』を攻撃する事が出来ず、生物が存在している場合は場にいる生物に必ず攻撃しなければなりません。
その代わり、場の生物が破壊された場合も『縄張り』から1枚手札に加える、つまり生物の破壊=縄張りの破壊、という図式が成り立っているのです。
これによって何が起こるか?
それは生物同士の睨み合いの抑制です。
デュエル・マスターズのコントロール戦法の一つとして、相手が攻撃してきた所にひたすら殴り返して場を制圧する、クリーチャー除去コン というものがありました。
こうなった場合、攻撃側は下手に隙を見せられず、盤面に打点を貯め続ける動きを取り、お互いに盤面が膠着する事が多々ありました。
こうしたゲームの停滞に対して、蟲神器のルールは互いに互いの生物同士を破壊し合う事がゲームの進行に繋がり、それを推奨するように作られています。
『シールド』そのものよりも、周辺のルールによってこうしたゲームの停滞化を防いでいる、という点において、『縄張り』システムの工夫の面白さを感じ取る事ができるでしょう。
まとめ:『逆転』の本質
ここまでで見てきた通り、『シールド』ギミックという根幹はそのままに、他TCGが様々な工夫を持ってそれらを翻案しようと試みている事が分かっていただけたでしょうか。
WIXOSSは『ライフが数少ない手札リソースになってしまう』事を、ビルディバイドは『トリガーによる逆転は受ける側にだけ恩恵をもたらしてしまう事』を、蟲神器は『シールドがもたらすゲームの膠着』をそれぞれルールによって解消しようとしています。
しかし、『シールド』制のゲームの本質として、より深い部分にあるのは、「手札・山札」以外の部分にあえて設けられた『不確定要素による逆転』が相手ターン中に起こり得る事の無軌道さ、面白さ、そしてドラマチックさです。
事実、構築制限によるバランス調整などありつつも、ここまでに挙げたカードゲームは全て『トリガー』系のギミックをその中枢に置いています。
『シールド』という非公開領域から『トリガー』がめくれる事自体は運ですが、その『トリガー』は自分のデッキに入っていなければ絶対に発動しないものです。
人事を尽くしたからこそ、天命は得られる。
その運と実力のバランスこそが、『逆転』を擁する『シールド』ライクなカードゲームが人々を惹き付けてやまない理由なのでしょう。
※1
https://corocoro-news.jp/news/87632/より
【お知らせ】
現在、ゴイケン(@duemagoiken)さんと合同で『記事の読み比べ』企画を行っています(詳細はコチラ⬇)


各々が『シールド・トリガー』という同じテーマをどう調理したのか、ゴイケンさんの記事と読み比べてお楽しみください。
両方読んで頂いた方はぜひアンケート投票にもご協力お願いします!
記事が面白かったのは
— くーぼー (@soranaki00) December 31, 2024
