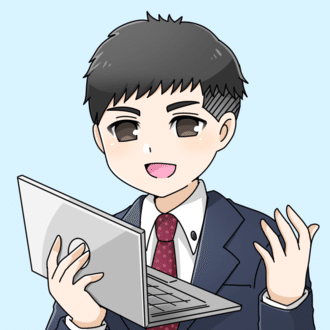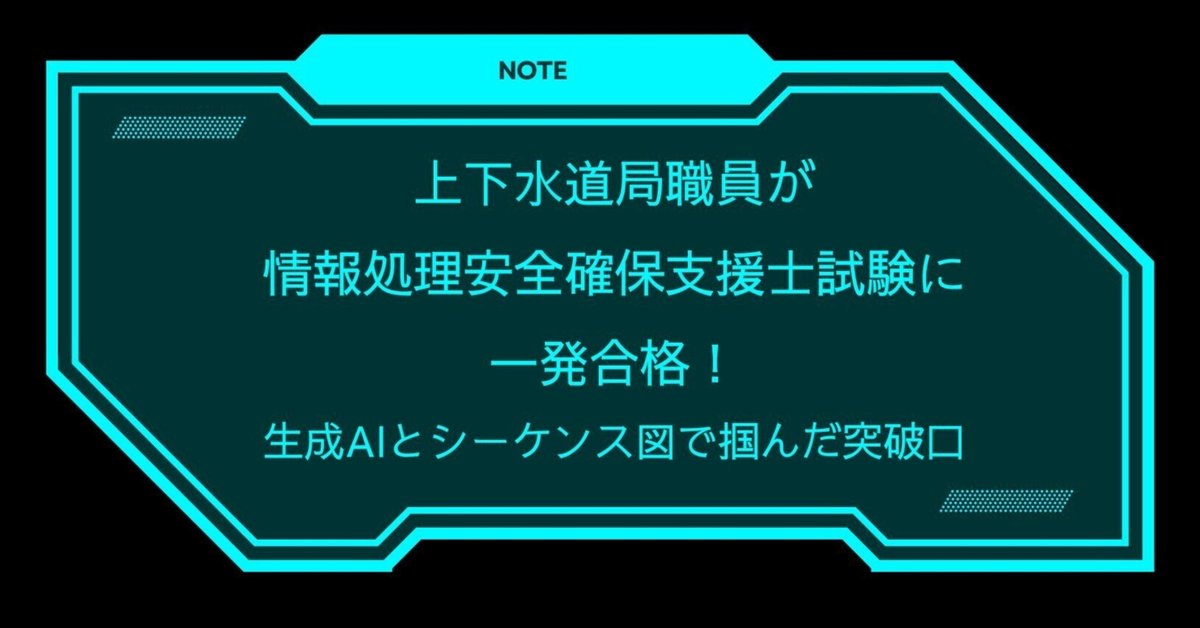
上下水道局職員が情報処理安全確保支援士試験に一発合格!~生成AIとシーケンス図で掴んだ突破口~
2024年10月13日に実施された情報処理安全確保支援士試験の合格発表が、12月26日にあり、無事合格することができました!
今回の試験は、記述問題の字数制限が全問撤廃されるなど、大きな変更があったため、受験前は不安でいっぱいでした。合格率も直近最低の15%程度とかなり厳しい戦いでした。
情報処理安全確保支援士試験 合格率推移 (直近10回分)

それでも、4歳と2歳の子供を育児中という、限られた時間の中、工夫した学習方法で乗り越えられたので、これから受験される方の参考になればと思い、私の合格体験記を共有させていただきます。
なぜ情報処理安全確保支援士を目指したのか?
私は、市役所のIT採用の職員で、今は上下水道局で経理担当職員として働いています。日々の業務の中で、セキュリティに関する提案を受ける機会も多いのですが、以前、ある業者から「FWさえ入れておけば大丈夫」「NTP設定は不要」といった、明らかに誤った認識に基づく提案を受けたことがありました。また、市職員(情報部門を含む)の中にもセキュリティに関する誤解が多い方が一部いらっしゃると感じていました。
そこで、市民の安全を守るため、そして職員のセキュリティ意識向上のため、体系的なセキュリティ知識を身につけ、正しい情報を発信できるようになりたいと強く思うようになり、情報処理安全確保支援士の資格取得を目指すことを決意しました。
情報処理安全確保支援士試験の試験内容
試験時間・出題形式・出題数(解答数)

R5秋から午後1と午後2が統合されています。
私の勉強方法:生成AIとシーケンス図を活用
育児と仕事の両立で、まとまった勉強時間を確保するのが難しかったため、限られた時間の中で効率的に学習することを意識しました。具体的には、以下の方法で勉強を進めました。
1. テキストを活用した基礎固め
全体像を掴むために「情報処理安全確保支援士試験 ALL IN ONE オールインワン パーフェクトマスター」をメインテキストとして使用しました。
この本は、情報セキュリティの基礎知識から応用知識まで網羅的に解説されており、試験範囲全体を効率よく学習することができます。
さらに、生成AI(Google AI Studio)を活用し、テキストの内容をより深く理解するように努めました。具体的には、生成AIにテキストの内容を要約してもらったり、質問を投げかけて疑問点を解消したりすることで、効率的に学習を進めることができました。(生成AIの出力が、テキストと合っているかは要確認です!)
苦手な分野は、「ゼロからスタート! 教育系YouTuberまさるの情報処理安全確保支援士1冊目の教科書」で重点的に学習しました。
この本は、図解やイラストを豊富に用いており、初学者でも理解しやすい内容となっています。
応用知識と午後問題対策には、「情報処理安全確保支援士「専門知識+午後問題」の重点対策」を活用しました。
この本は、過去問を分析し、出題傾向に合わせた解説や練習問題が充実しており、実践的な力を養うのに最適です。
2. 過去問道場での徹底的な演習
午前Ⅱ試験対策として、過去問道場を利用し、過去12回分の問題を繰り返し解きました。
過去問を解くことで、出題傾向や自分の弱点 を把握し、効率的に対策を立てることができました。目標は、9割以上の正解率を達成すること。そのため、ただ問題を解くだけでなく、間違えた問題は必ず解説を読み、なぜ間違えたのかを理解するように努めました。また、何度も繰り返し解くことで、知識の定着と解答スピードの向上を図りました。
過去問は暗記で通用するのは午前Ⅱ(マークシート)までです。午後試験の論述問題は、理解していないと解答できません。そのため、過去問を解く際は、解答を暗記するのではなく、なぜその解答になるのかを理解することに重点を置きました。
ちなみに私は午前Ⅰを受験したことがないので、そちらを受験される方は別途応用情報技術者範囲のマークシートが必要と思われます。私は、午前Ⅱの過去問道場で92%の正答率で当日を迎えましたが、76点でした。25問中10問までは間違いが許されます。当日、所見の問題を確実に合わせるのはリスクがあるため、過去問から出題される問題の正答率を限りなく上げておく必要はあると思います。
3.午後問題の注意事項
情報処理安全確保支援士試験の午後問題は、令和5年秋期試験から大きく変わりました。
以前は午後Ⅰと午後Ⅱに分かれており、解答時間はそれぞれ1問あたり45分と120分でしたが、統合されてからは1問あたり75分となっています。
この変更により、過去問対策にも注意が必要です。
75分用の過去問は数が限られているため、時間配分の感覚を掴むのが難しいという現状があります。
45分用の過去問に慣れてしまうと、本番で時間不足と分量への対応ができない可能性もあります。
そこで、過去問を活用する際は、以下の点に注意しましょう。
45分用の過去問で短時間で解答をまとめる練習をする。
120分用の過去問にも挑戦し、必要な情報を取捨選択し、論述する力を養う。
75分を意識した時間配分を練習する。
時間配分と解答の質のバランスを意識することが、合格への鍵となります。
4. Notionでのアウトプット
学習した内容をNotionにまとめ、mermaid記法でシーケンス図を描くことで、理解を深め、記憶に定着させるように努めました。情報セキュリティの分野では、複雑なシステムやプロセスを理解することが重要です。シーケンス図を描くことで、それらを視覚的に整理し、より深く理解することができました。

特に、認証システムや暗号化技術など、複雑な処理の流れを理解するのに、シーケンス図は非常に役立ちました。Notionは、mermaid記法に対応しており、簡単にシーケンス図を作成できるため、アウトプットツールとして最適でした。
シーケンス図を書き始めたのは、こちらの記事がきっかけです。
5. 生成AIを活用した疑問点の解消
学習を進める中で、どうしても理解できない部分や疑問に思う点は、生成AI(Google AI Studio(Gemini 1.5 Pro))に質問して解消しました。生成AIは、専門的な質問に対しても分かりやすく答えてくれるため、非常に助かりました。(ただし、出力の検証は絶対に必要です)
6. 昼休み時間の有効活用
育児をしていると、まとまった勉強時間を確保するのが難しいですが、昼休みなどの隙間時間を有効活用することで、学習時間を確保することができました。毎日30分の昼休み時間は必ず勉強時間に充てていました。30分あれば、午前Ⅱは1、2回分はできますし、過去問は45分問題なら解くことができます。
7. 受験宣言によるプレッシャーの活用
周囲に受験することを宣言することで、自分にプレッシャーをかけ、モチベーションを維持するようにしました。
試験当日の心構え
試験当日は、以下の点に注意しました。
時間までに受験票(写真要)と筆記用具を持って会場にたどり着く(前提・重要)
昼ご飯の場所を考える(今回は都会なので食べに行けた)
時間配分を意識する
分からない問題は後回しにする
一度書いた回答は、根拠がしっかりしない限りは変更しない
特に、一度書いた回答を変更しないことは重要です。個人的な意見ですが、最初の直感は意外と正しいことが多いので、自信を持って解答することが大切です。
前提として、会場にたどり着くことが一番大事ですので、そこをおろそかにしてはいけません。
試験を終えて
今回の試験は、記述問題の字数制限が全問撤廃されるなど、大きな変更がありました。しかし、個々の分野の知識を丁寧におさえていったこと、そして生成AIやシーケンス図を活用した効果的な学習方法によって、無事合格することができました。
情報処理安全確保支援士試験は決して簡単な試験ではありません。しかし、正しい方法で努力を続ければ、必ず合格できると信じています。
この記事が、これから情報処理安全確保支援士試験を目指す方の参考になれば幸いです。
いいなと思ったら応援しよう!