
スヌーヌーの不思議な旅vol.1 イントロダクション
スヌーヌーの不思議な旅 vol.1 イントロダクション
こんにちは。スヌーヌー主宰の笠木泉です。
このnoteは勉強会「スヌーヌーの不思議な旅」の記録です。
まず「スヌーヌーの不思議な旅」の説明をさせていただきますと、これは私が2024年に自主的に始めた勉強会の名前です。
1、勉強会を始めるまでの経緯
これは私自身の感覚なのですが、俳優としても劇作家としても演出家としても、一人の人間としても「圧倒的に足りない」と感じることが多々あります。もちろん時間と脳の限界はあれど、それにしたって私は「世の知」を知らな過ぎる。勉強不足ゆえに、思考を深めることもままならない。知れば知るほど世界への解像度は深まっていくはずなのに、日々に追われ見て見ぬふりをしている。それが現実だと開き直るのはあまりに哀しいし寂しいなとずっと思っていました。心が寂しいのです。
だから「もっと勉強したい」。
では、勉強しよう。さあ、勉強しよう。勉強のいいところ、それは一人でできるところです。だから「もっと勉強しよう」と訴える自分を鼓舞してさまざまな書籍を読んだり作品を鑑賞したり思考を深めたりすればそれでいいわけです。自分の中で意見交換すればよい。しかしその自己反復にもずっと物足りなさを感じていて。それはなんなのか考えてみたのですが、「ああ自分ひとりでは発酵しないんだな」と気がついたんですね。自分の低い体温だけでは発酵しない。もちろん孤独な学びも大切で尊い、楽しいのは言わずもがなですが、一人で学び深めるには正直限界があるし、なんだか自分の思考がひどくつまらないなあと思う日もあります。他者の意見が聞きたい。他者の言葉が聞きたい。それぞれの意見を出しあい、互いの知を贈り合う。これぞ有機的な学びなのではないか。
だから「そんな場所が欲しい」。
だから「欲しいなら作ってみようかな」。
まあ、そんなことをずっと考えていたのですがいざやろうとなると勇気が必要で、尻込んでいました。しかしある時、某作家が50年続けた勉強会のエピソードを知り、「なんだかやっぱりやってみようかな」と急にやる気になったのです。体が弱り衰えを感じながらも勉強会を続けた人のことを思い、私はその時「知」とはそういうものなのではないかと想像したのかもしれません。
よーしやってみようかなあーとここまで考えが及んだのが2023年の年末です。そこで具体的にどのような会にすべきか、自分なりに規則のようなものを考えてみました。
年齢性別職業あらゆる区別に関係なく声をかける
演劇公演、成果、発表を伴わない
無料である
→ どんな人でもOK。俳優であろうと演劇を生業にしていようとなかろうと会社員であろうと主婦であろうと学生であろうと知人だろうとなかろうと、私の提案する勉強を面白がってくれさえすればOK。
→ 創作の場で発生する緊張感、職業上の上下関係は一切合切取っ払ってただただみんなが純粋に勉強するために繋がる「場所」にしたい。
→ そしてあくまで私がやりたくで始めることなので基本は自分のお金で運営する。
上記がまず自分の中で決めた条件です。
そしてまず手始めにSNSで告知をしてみることにしました。

「スヌーヌーの不思議な旅」という名前は、いろいろ候補もありつつ、なんだかツアーみたいになればいいなと漠然と思っていたのが由来でしょうか。みんなおしゃべりしながらバスに揺られて飛行機に乗って知らない土地を目指すようなイメージ。「勉強会っていうことが伝わらなくないか?」という自己ツッコミも少なからずあったのですが、まあ、思いつきでぱっと決めました。気に入っています。
というわけで、発表前にまずはさすがに仲間に相談しようと思い、スヌーヌーの前回の公演で制作を手伝ってくださった加藤じゅんこさんとスヌーヌーの全公演に参加してくれている劇団はえぎわの踊り子ありさんに話を持ちかけてみました。「こんなことしてみたいんだけど…」と伝えると「それは面白いですね!」「やりましょう!」と言ってくれて心から安堵。何かをスタートするのはやはり勇気がいることです。二人に背中を押してもらい、年明けに告知に踏み切りました。
私の中では「みんなでとんでもなく長い本とかとんでもなく長い映画とか見たいしたいなあ」「読んだことのない戯曲を輪読したいなあ」といったぼんやりとしたビジョンがありました。そんな状況をイメージしてみると、みんなで作品に対して意見を言い合ったりするには参加者は10人ぐらいが理想だなと思い定員を10人に設定。しかしいざ募集をしてみると応募〆切5日前の時点ですでに40人以上の応募が!これは大変だ!と焦って早期に応募を打ちきることに決め、選考に入りました(人数多数の場合は書類選考をさせてもらう旨は告知してありました。また締切後にご応募いただいた方には希望者多数の旨をご説明しお断りをさせていただきました)。
しかし皆さんに書いていただいた作文「なぜわたしはスヌーヌーの不思議な旅に応募したか」を全て読ませていただき、これはもう全員に参加してもらおう、そうするのがベストだと気持ちが変化していきました。皆さんの作文ひとつひとつが豊穣で、そしてある意味切実だと感じたからです。全員にお会いしたい。そう強く思いました。
「私も勉強したい」「もっとたくさんの言葉を知りたい」「評価に関係なく自分の意見を言ってみたい」「普段は演劇の稽古に追われて勉強できていないことが後ろめたい」「ただ知らない人と作品のことでおしゃべりしたい」「不思議な旅に出たい」「いつもと違うところでじっくり考えてみたい」「刺激を受けたい」「旅に出たい」「人の意見が聞きたい」「掛け値なしにみんなと学ぶ場所が欲しい」「スヌーヌーは見たことないけど告知文がよかった」「演劇のことはあまり知らない」「面白い人に会いたい」「この先どのように演劇とつながっていくべきか考えている」「公演を伴わない中でじっくり学びたい」「この世界を生きていくこと自体に不安がある」/それぞれの言葉で「とにかく私も勉強してみたいんです」と語ってくれている。「場所」を欲している。ただ、勉強したい。そう思っている。
「よしこうなったらみんな一緒に旅に出ようぜ!」(私の心の声)
ということで、参加条件が合わなかった数人をのぞき全ての方に参加していただくことにしました。そこから全員とメールでコンタクトをとり、2月末に「スヌーヌーの不思議な旅 vol.1 イントロダクション」の開催にこぎつけるに至ったのです。
2、勉強会初日「スヌーヌーの不思議な旅 vol.1 イントロダクション」開催
2024年2月、「スヌーヌーの不思議な旅 vol.1 イントロダクション」を開催しました。以下はそのレポートです。

2月24日土曜日、晴れ。
横浜市の某地区センターにて集合。
この日は参加者28名、欠席者12名です。
スタッフの加藤さんと参加者の磯崎珠奈さんと早めに合流してレジュメの準備など。参加者40名は次回から「昼の旅」(20人)「夜の旅」(20人)に分かれて勉強会をすることになっていますが、今日はイントロダクション。昼夜メンバーが合同で「ハラスメントに関しての勉強会」、そして全員で自己紹介をすることになっています。
皆さん続々と会場に。顔を見ることができて嬉しい。はじめてお会いする人も多いので、皆さん全員に名札をつけていただきました。
・ハラスメントに対する考え方の話をした
まず私の自己紹介をした後、皆さんに「ハラスメントに対する考え方」のレジュメをお配りしました。厚生労働省で定義している「パワハラ」「セクハラ」「ジェンダーハラスメント」の定義や事例を引用し、皆さんに目を通していただきました。そしてそれを踏まえた上で私自身の考えを少しお話ししました。
この会は「旅の仲間の集まり」であり、ここに上下関係はありません。芸歴(?)、年齢、性別、国籍問わず、です。主宰の私ももちろん皆さんと同じ「仲間」であること。ただ、皆が一緒に純粋に楽しく学んでいくために、この場所を誰にとっても実りある場所にするために、リーダーである私は誰よりもこの場所の公平性を思案し学び実践していくことが必要だと思っています。「共に考えることは共に創作する時間」、スヌーヌーの不思議な旅をそう定義し、常にアップデートをしていく所存です。
例えば「勉強会で起こりうるハラスメント」として、「ある人の意見に対して馬鹿にするようなことを言う」「性差でマウントをとる」「芸歴でマウントをとる」「知識の有無で人を判断する」などなどさまざまなパターンが想定できます。まずここで私が皆さんにお伝えしなければならないことは、私も含めみんな絶対的に平等だと言うこと。そしてこの場は互いを尊重し合うという、例えば「優しさ」と呼ばれるものを大切にする場であること。ハラスメントを生まない場所を作る。主宰である私がまず勉強を重ね、よりよい勉強会にする。その意思を強く持ちます。
…というような話などをしました。
誰にとってもいい場所であるように。そんな場所を目指したい。
皆さんがどういう気持ちで聞いてくださったのか、どんなことを思ったのか、今後いろいろ聞いてみたいと思っています。→ その後メールにて「ハラスメントについて」の話への感想を多数いただきました。またいずれこのレポートで皆さんのご意見を紹介しようと思います。
ここで休憩。続いて自己紹介の時間です。換気、そしておやつに飴やチョコなど。
・自己紹介「紹介したい本を一冊持ってきてください」
ここからは皆さんの自己紹介タイムです。今回は事前に「今興味のあることについて話してください」「本を一冊紹介してください」というお題を出させていただきました。
ここからは本当にワクワクする時間でした。皆さん丁寧にご自分の話や職業、今思っていることなど話してくださる中で、それぞれの日々や生き方や、考え方が垣間見れて面白い。心揺さぶられる。生を感じる。「ZOZOタウンのことばかり考えています」「韓国ドラマにはまっています」「お墓に興味があります」「猫三匹と暮らしています。動物が好きです」「散歩したいです」…一人一人がどのようなことに関心を持ち、今ここにいるのか。なぜ勉強したいのか。なぜこの本が好きなのか。どんな状況で読んだのか。「実は選べなくて2冊持ってきたんですけど…」という方も数名。好きな本を一冊に絞るなんてなかなか難しいものですよね。その気持ち、わかります。でもみんな最終的には一冊を選んでくれて、丁寧にその本の魅力を紹介してくださいました。いやー笑ったり共感したり感心したり泣きそうになったり(そうだそうだ、私はすぐに泣きますので今後もどうぞ気にしないでくださいと参加者の皆さんに伝えておこう)、全ての参加者の自己紹介を堪能。こんな面白い時間あるだろうかってぐらい、私は楽しかったです。すでにものすごく勉強になりました。
ここで皆さんに紹介していただいた本のリストを挙げます。
芥川龍之介「杜子春」(新潮文庫 青空文庫)
宮崎駿「風の帰る場所」(文春ジブリ文庫)
遠藤周作「ただいま浪人」(講談社文庫 絶版)
島田潤一郎 「あしたからは出版社」(ちくま文庫)
二重作拓也「可能性にアクセスするパフォーマンス医学」(星海社新書)
北村薫「リセット」(新潮文庫)
前川知大「散歩する侵略者」(劇団イキウメ)
太田省吾「飛翔と懸垂」(而立書房 絶版)
梨木香歩「歌わないキビタキ」(毎日新聞出版)
ヴァージニア・ウルフ「オーランドー」(ちくま文庫)
きたやまおさむ「帰れないヨッパライたちへ」(NHK出版文庫)
保坂和志「書きあぐねている人のための小説入門」(中公文庫)
河合隼雄「こころの処方箋」(新潮文庫)
侯孝賢「侯孝賢の映画講義」(みすず書房)
ハン・ガン「すべての、白いものたちの」(河出文庫)
宮地尚子「傷を愛せるか」(ちくま文庫)
高橋祥子「ビジネスと人生の「見え方」が一変する 生命科学的思考」(NewsPicksパブリッシング)
佐久間宣之「ずるい仕事術」(ダイヤモンド社)
古賀及子「ちょっと踊ったりすぐにかけだす」(素粒社)
工藤直子 絵・長新太「ともだちは海のにおい」(理論社)
スーザン・ソンタグ「他者の苦痛へのまなざし」(みすず書房)
栗原康「サボる哲学」(NHK出版新書)
ジャン・ジュネ「花のノートルダム」(光文社文庫)
「世界憲法集」(岩波文庫)
大白小蟹「海辺のストーブ」(トーチコミックス)
坂元裕二「怪物」(KADOKAWA)
ますむらひろし「銀河鉄道の夜」(風呂猫等)
石牟礼道子「苦海浄土」(講談社文庫)
よしもとばなな 「ミトンとふびん」(幻冬社文庫)
柳宗理 エッセイ(平凡社ライブラリー)
山極寿一 小川洋子「ゴリラの森、言葉の海」(新潮社)
重松清「きみのともだち」(新潮社文庫)
ルシア・ベルリン「掃除婦のための手引き書 ――ルシア・ベルリン作品集」(講談社文庫)
(後日欠席者の方からも「紹介したい本がある」とメールをいただいておりますので、また次回以降このレポート上でご紹介します)
もうこのリストを見るだけで知の共有が始まったと。「勉強会はじめてよかったよ…」って心から感じています。
最後には時間が足りなくなり駆け足の紹介となってしまった方もいたので、時間配分は次回以降気をつけようと思います。あともう一つ、私はミスをしてしまいました。「写真を撮るのを忘れた」のです。レポートは写真をたくさん掲載して読みやすくしようと考えていたのに、当日はすっかりテンパっちゃって忘れていました。終わってから気がついた。次回からそこはしっかりやります。また、参加者全員への連絡方法も要検討。私の連絡ミス、気をつけます。
この勉強会は毎回レポートを作成し、アーカイブしていくつもりです。また参加者にはプライバシー保護の観点から「レポートでの名前の掲載の可否」等のアンケートを実施しました。今後はそのアンケートの回答に則り記事を作成していきます。
次回からは「昼の旅」「夜の旅」に分かれて、それぞれ違う勉強をスタートさせる予定。月に1度の開催予定ですが、3月は私がミクニヤナイハラプロジェクト「船を待つ」に出演するためにいきなりお休み!まあ、フレキシブルに自由にやっていきましょう。次は4月の開催です。
こうして旅は始まりました。
引き続きどうぞよろしくお願いします。
(文・笠木泉)
---------------------------
毎回参加者の方に感想やレポートを書いていただこうと思っています。
今回は赤羽健太郎さんとキムライヅミさんに執筆をお願いしました!
キムライヅミさん
「スヌーヌーの不思議な旅」イントロダクションに参加してきました。
どんな時でも最初はやっぱり緊張しますね。これから勉強会をご一緒する方々との"初めまして"に期待と不安が交互に押し寄せる感覚。でもその感覚が不思議と嫌じゃないと感じたのは、きっと参加した皆さんも私と同じ気持ちでいてくれたからだと思います。
ハラスメントについて時間をかけて参加者全員で共有した後、勉強会に参加された経緯や興味のあることなどを皆さんお一人ずつ丁寧にお話されていきました。皆さん参加された経緯は違っても、どことなく静かな雰囲気なのに熱く力強い思いを内に秘めているような、そんな印象を受け、こんなにも感情が揺れ動かされていく自己紹介は初めての経験でした。
今回のイントロダクションでは、一人一冊本を紹介することになっていました。小説、ビジネス本、台本、一人として同じものを紹介されることはなく、勉強会に参加する人の数だけ、興味深い本がこれほど集まったことに心がくすぐられるような好奇心が生まれ、それと同時に私の知らない素晴らしい本がまだたくさんあるのだと気付かされました。
次回からは「昼の旅」と「夜の旅」に参加者が分かれることになり、今回限りの出逢いの方もいるかもしれません。ですが、イントロダクションで皆さんと出逢えたことで「スヌーヌーの不思議な旅」への素敵な序章となったことは間違いありません。これから皆さんと不思議かつ楽しい、そんな時間を過ごせますように。一年間どうぞよろしくお願いします。
赤羽健太郎さん
「勉強、もう始まってますねー」参加者の自己紹介を聞きながら、笠木さんがつぶやきました。それは、旅の始まりを告げる合図のように僕には響きました。
今回は「イントロダクション」。事前の案内メールには、「ハラスメントに関しての勉強会」と「自己紹介」を行うことが記されていました。「みんなに紹介したい本を各自一冊ずつ持ってくる」というお題はあったものの、今回はあくまで、これから旅を始めるために必要なものを揃える、いわば「手続き」の回。ハラスメントの勉強会も、大事なこととはいえ、もっとマニュアル的なものを想像していました。しかし笠木さんは、自らの言葉で綴った長文のプリントを用意し、参加者に問いかけるような形をとりました。「ハラスメントについて、いま世の中ではこうなっています。私はこう思います。皆さんはどう思いますか?」というような。
問いかけられたら自らの頭で考えざるを得ません。気がつけば「ハラスメントとはなにか? どうしていけばよいのか?」とぐるぐる思考を巡らせている自分。同じ「勉強」でも、誰かが決めたルールや知識をただおぼえるだけの「勉強」とは少し違う意味の「勉強」が、もう始まっていることに気付きました。
そのことは、続けて行われた参加者の自己紹介で、より明確になりました。
「本を読むのが苦手」とおっしゃった参加者が、何人かいらっしゃいました。でも、その方たちが紹介した本の中に、僕が知っている本は一冊もありませんでした。つまり、その方たちは「僕が知らないことを知っている方たち」でした。役者なのに演劇が好きじゃないかもしれない、という方もいました。読んだ本の内容をノートにつけ続けている方がいました。小学生の頃、世界のウソに気付いた方がいました。お墓めぐりが好き、という方がいました。
その場にいた数十名の参加者の中で、似たような話をした方は一人もいませんでした。どの方も、僕の知識と想像を超えた世界を持っていました。それを知りたい。教えてほしい! と痛烈に思いながら皆さんの話を聞いていた時、隣に座っていた笠木さんがつぶやいたのでした。
「勉強、もう始まってますね」
テーマを決めないで、果たして「勉強会」ができるのだろうか? 実はそんな気持ちも少しだけありました。でも、人が集まり、ただ話をするところに「勉強」は自然発生するのだと、今更ながらに知りました。そんな貴重な瞬間を、これから何度体験することになるのだろうと思うと、今から楽しみです。一年間、よろしくお願いします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
キムラさん、赤羽さん、ありがとうございました!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
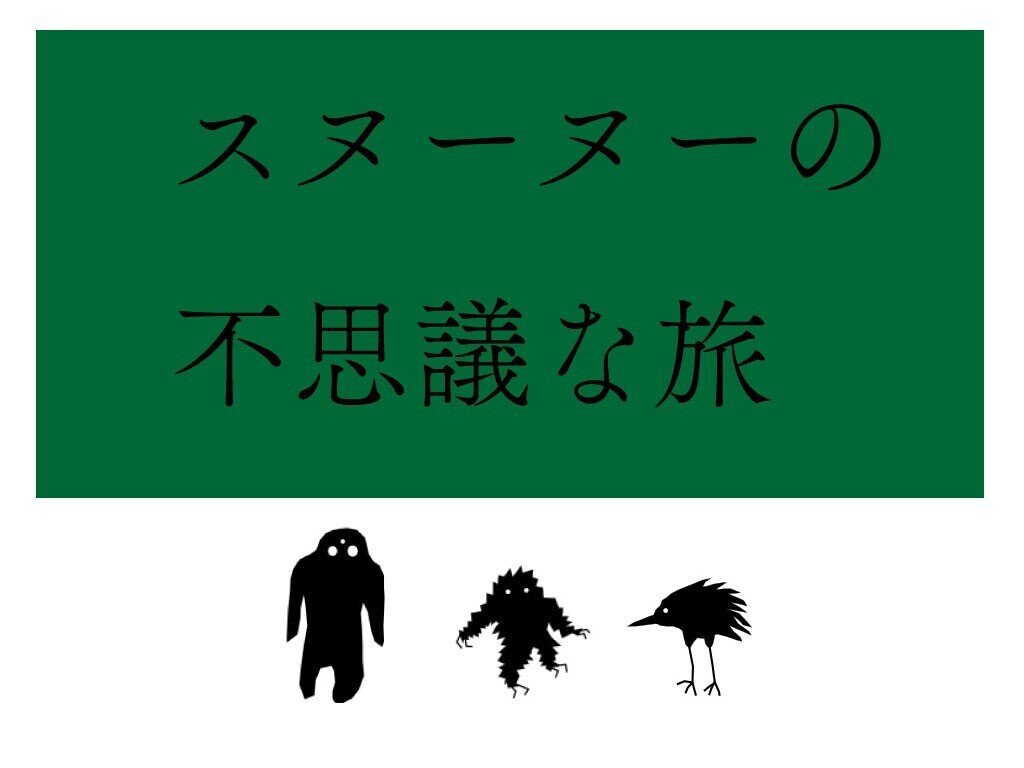
ーーーこのレポートに関するご質問や感想等ございましたらsnuunuuoffice@gmail.comまでご連絡ください。
