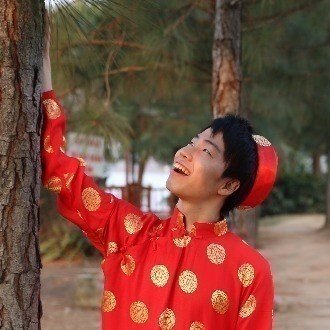#DesignScramble に行ってきました(mixi_under29, mixiゲームUI, IRIAM)
朝7時に家を出て京都駅に向かい、新幹線で東京へ。
#DesignScramble というイベントに参加してきました。
【目次】
0. 参加したセッションとメモ公開
1. mixi流ものづくりセッションで学んだこと
2. mixiゲームのUIデザインセッションで学んだこと
3. Basecamp×IRIAMセッションを聴きながら考えたこと
4. 最後に
0. 参加したセッションとメモ公開
参加したセッションは3つです。
①【Under 29】若手デザイナーが考えるミクシィ流ものづくり
②UIデザインは変化し続ける ~モンスターストライク、ファイトリーグの挑戦~
③経営者と共創して作ったIRIAMのデザインとプロダクトマネジメント
※メモを公開しますが時系列で拾えたものの記述にすぎず、全体的に雑なことはご了承くださいw
1つ目のセッションのメモはこちら
2つ目のセッションのメモはこちら
3つ目のセッションは席がいっぱいでメモが取りにくかった&ほぼほぼ話されていた内容は登壇されていた坪田さんのnoteと塚本さんのnoteで公開されているのでそちらを。
1. mixi流ものづくりセッションで学んだこと
上でも貼ったメモはこちら
特にminimoデザイナーのasami kotaniさんのお話が学びになりました。
未だ新卒ではない身分ですが、「新卒同期で周りがすごいことやってて焦る」とか「これって本当に自分成長してるんだろうか」とか「やり方わからずとりあえずやってみる→困る」はあるあるだろうなと強く強く感じました。
これまで、個人のものチームのものとで、いくつかのプロダクトのデザインに携わってきました。
それらは基本的に立ち上げフェーズで、なんども読み返したこちらのnoteを思い出しながら聞いていました。
kotaniさんはデザインシステムという解決策を見つけ進めていらっしゃいましたが、それもまさに上記noteの「スタートアップのデザイン=スピード神話は正しいのか」という本質的な問いに帰着するなと感じます。
持続的にサービスを提供し、かつ成長させ続けていくために、コーディングにしろ、デザインにしろ、属人化はよくないとされていますし僕もそうだろうと思います。
本日「デザインシステム」という言葉を初めて知ったのですが、なるほどたしかにある方が良いだろうなと考えました。
ただプロダクトの進歩の上で変化していくものもあるはずで、どの程度の粒度で、どのタイミングでそれに着手するのかということが気になりましたし、
おそらくそれには段階があるはずで(早いタイミングで簡易的なガイドを示す、ある程度PMFが見えたところでより綿密なガイドラインにする、など)、各社の事例を知りたいなと思いました。
とりあえずセッションで紹介されていた、以下の3つのデザインシステムを読み込んでみようと思います。
軽く目を通しましたが、HIGやMaterial Designかのごとく思想から細かく記載されていて、興奮を覚えました。
また、12月末には「デザインシステム実践ガイド」なる本が発売されるらしく、ぜひ買って読んでみようと思います(Kindle版が出たら🙏)
2. mixiゲームのUIデザインセッションで学んだこと
上でも貼ったメモはこちら
モンスト(初期のほう遊んでいました!さなぱっちょさんとかも大好きでした!ただ2回目のUIアップデートあたりから知らないですごめんなさい!)と、
ファイトリーグ(初期の初期にYouTubeグループの東海オンエアがサブチャンで紹介していて1ヶ月ほど遊びました!それからは遊んでないですごめんなさい!)から、各1名ずつチーフデザイナーさんがいらっしゃって、「ゲームUIの変遷」についてをたくさん紹介していただきました。
具体的事例の紹介が豊富で、引き出しも増えて非常に学びになるセッションでした。
このセッションの大切なことは、このQAに集約できると思います。
Q:どうしてUIデザインは変化し続けるの?
A1:ユーザーにモンストをずっと楽しんでもらいたいから。純粋に中の人が遊んでいるので、自由に意見が交換したり提案しやすい。スピード持って変化し続けられる状況ができている。(モンストの方)
A2:狙っていくKPIもずっと変わっていくので、UIも変わっていかないとそれを狙えない。(ファイトリーグの方)
楽しんでもらい続けるために、デザインは変わっていく。
楽しんでもらうためにコンテンツや仕様が増えていくと少しずつ複雑になる&重要なものも変わって。そのため使いやすく刷新すべくUIも変化する。
事業としてやっている以上、フェーズによってKPIも変わっていく。ゆえにそれに合わせてデザインも変わっていく。
「なぜデザインをアップデートしていくのか」の問いに対しての一つの考え方・言語化の方法を学びました。
3. Basecamp×IRIAMセッションを聴きながら考えたこと
DUOの塚本さんはエンジニアリングもデザインも何もわからない状態で、「こんなビジョンを持ったプロダクトを実現させたい!!!」との思いだけで突き進み、共犯者を集め、実現させたとのことでした。
なぜそんなことができたのか?という問いに対し塚本さんがおっしゃっていたのは
『共感する力が突出してある。人の話を聞いて、まるで憑依するかのように自分ゴトになることができる』(要約)
ということでした。とにかく人に共感して理解することが天才的に上手で、ゆえにどんどん仲良くなる&どんどん巻き込めると。
さらに、
『意思決定が早い&明瞭でブレない』という仕事のスタイルや、
『坪田さんをはじめメンバーを心から信頼して任せきる』スタンスなど、
素晴らしいチームだし関係者各位は働きがいがあるだろうなと感じました。
自分はPMやリーダー的ポジションをするのがどちらかというと得意ではありません。いつかの機会では塚本さんの考え方を自分に憑依させてリーダーをやってみたいと考えました。笑
そしてもう一つ。
IRIAMプロジェクトで塚本さんは
「あなたの知っているこの分野に強い人を教えて下さい!」
という言葉を言いまくって最初のメンバーを集め、
最強エンジニアと最強デザイナーが入ったところで
「なんとかメンバーを集めてもらえませんか?!宜しくお願いします!!」
というオーダーをし、最強のふたりがさらに最高のメンバーを集めたとのことでした。
いつか自分も『このプロジェクトならこいつだな』
で想像される人間になり、このようなフルハウスチームに参画し、アドレナリンだくだくなプロジェクトをやってみたいと思いましたw
ASEANとEdTechとDesignが僕のキーワードのつもりです。
当面はこの方向にベットしていきます。
4. 最後に
来週はDesignshipというこれまた大きなデザイナー向けイベントがあります。
学習の基本は「良質なインプットと良質なアウトプットを高速で繰り返す」ものだと思っています。
良質なインプットの機会がまた1週間後にあるため、それまでに良質なアウトプットをしておいてインプットで溢れないようにしたいです。笑
いいなと思ったら応援しよう!