
原子炉・加速器で癌を治す 第1回 絶望的な患者
取材・執筆:下山進
原子炉や加速器で癌を治す。
信じられないような治療法が、一昨年、世界に先駆けて日本で薬事承認された。
その対象は、手術、抗がん剤、放射線治療、全てを試しても効かなかった難治癌の患者。
1920年代から始まった物理学の革命の時代に唱えられた理論は、米国での失敗をへて今、日本で花開こうとしている。新時代の免疫療法、遺伝子療法との競走、後発の治療法ゆえの治験の困難──。物理と医学と化学、その交差する点から生まれたこの治療法の開発ドラマを『アルツハイマー征服』(KADOKAWA)を書いた下山進が描く。
その67歳の女性の患者は、万策がつきていた。耳の下が腫れたように膨れ上がり、巨大なコブ状になって、そのコブの中心部からは、粘液がぬぐってもぬぐってもわき出てきた。ガーゼでおさえているが一日に何枚も替えなくてはならない。この粘液をとろうと夫が、毎日懸命にぬぐっていたが、すぐにムチンといわれる粘性の物質を癌細胞が分泌する。
1998年7月16日に大阪大学歯学部附属病院を初診の際の診断は、耳下腺癌だった。すぐに標準治療の第一選択である外科手術を行った。
耳下腺癌の場合、浅葉と深葉その間に顔面神経が通っている。癌細胞は神経まで浸潤している可能性も高い。が、顔面神経を傷つけると、顔がゆがんでしまう。だから、浅葉の腫瘍を手術でとり、顔面神経は残した。あとは、放射線治療でたたくというやりかたを選択した。
担当医は口腔外科の、網野かよ子。
8月25日から9月28日まで放射線をあてた。しかし、放射線障害のひとつである口内炎がひどく、患者は「もう先生これ我慢できません」と、継続照射を拒否した。
すると翌年の3月1日に再発がわかった。
手術も駄目、放射線も駄目ということになり、最後の手段と思って網野は、抗がん剤の投与を決めた。すぐに抗がん剤治療が始まり、2カ月かかって14回全身投与した。
しかし、腫瘍の縮小効果は見られなかった。次の手段として1999年に承認されたばかりのTS-1という抗がん剤を試してみた。これが2001年8月のことだ。
内服型のこの抗がん剤を、一日2回、28日間服用したが、まったく効果が見られなかった。
腫瘍は耳下腺部から下顎骨や顎下部に拡がっていた。中央の部分は潰瘍となり、そこから粘りけの強い粘液が出ていた。潰瘍部分からは出血するようになっていた。
正面から見ると、耳は大きなこぶのうえに、浮かぶようについている。
「先生、痛いし、重いし、何とかしてください」
網野は途方にくれていた。もううつ手がない。2001年10月になると、毎週外来に訪れるたびに、腫瘍が大きくなっているのがわかった。
手術もだめ。放射線もだめ。抗がん剤もだめ。
癌の標準治療といわれる三つの方法を試しても全てだめなのだ。
網野は、同僚だった加藤逸郎に助けを求める。
「加藤先生、○○さんを助けてください。先生、京大で新しい治療法の研究しはってるでしょ」
声をかけられた加藤逸郎は、たしかに大阪府熊取にある京都大学原子炉実験所で、これまでとはまったく違う癌の治療法の共同研究に参加していた。
中性子捕捉療法(Boron Neutron Capture Therapy )略称BNCTと呼ばれるその治療法は、癌細胞を核分裂によるエネルギーで選択的に殺すという奇想天外なものだった。

原子炉を使う「がん治療法」
その60代の女性が、阪大の附属病院を最初に訪れた1998年、地球の反対側にあるアルゼンチンの首都ブエノスアイレス。
ブエノスアイレスにはティグレというパラナ川の三角州に位置する自然豊かなエリアが、市内から電車でほんの30分ほどの距離に広がっている。三角州の中を小さな川があちこちを流れ、人々はボートで移動する。
アルゼンチンの国立原子力委員会の放射線生物学研究課の課長アマンダ・シュウィント、通称マンディは、物理学者の夫と一緒にアメリカからの客をこのティグレでもてなしていた。
米国からの客は、オハイオ大学のラルフ・バース。米国におけるBNCTの権威だった。アマンダは、97年に上司の命で、BNCTの研究を始めていた。
大学で博士号をとってから癌の放射線治療の耐性についての研究をしていたのだが、この奇妙な治療法の研究を始めて夢中になった。
もともとは、1936年に、ドイツからアメリカにわたったゴードン・ロシャーという物理医学者が提唱したアイデアだった。放射線を利用した医学は、1920年ごろからさかんに研究されるようになったが、その中心となったThe American Journal of Roentgenology and Radium Therapy というジャーナルに掲載された論文「中性子の生物学的効果と治療の可能性」に端を発して発展したものだ。

そのアイデアはこうだ。
原子に中性子をあてると核分裂がおこる原子がある。たとえばウラン235に中性子をあてると、イットリウム95 とヨウ素139 に分解されさらに中性子が出る。そのとき質量がわずかに失われるのだが、この質量差が莫大な熱エネルギーとして放射される。それを利用したのが、原子爆弾であり、原子炉だ。核分裂は中性子の放出をともなってなされるから、連鎖的に核分裂が行われ、広島の街ひとつを壊滅させるほどのエネルギーになる。
しかし、ボロン(ホウ素)という原子に中性子をあてると、リチウム原子核とヘリウム原子核に分解されるが、中性子は出ないのである。そしてこのときの分解で出るエネルギーは細胞一個を殺すだけの微弱なエネルギーだ。
つまり、癌細胞だけにボロン(ホウ素)を付着させる方法がわかれば、中性子を照射して、健康細胞を傷つけることなく、癌細胞だけを殺すことができる。
これは従来の放射線療法とはまったく違う。放射線療法はX線、ガンマ線、α線を使ったものなどがあるが、放射線の力で癌細胞を殺すというものだ。たとえばX線の破壊力は強いが、しかし癌細胞のまわりの健康細胞も被害をうける。中性子線は、放射線の中でも、もっとも弱い力しかない。それだけでは癌細胞を殺すことはできないが、健康細胞に対する被害も少ない。放射線療法は、癌を画像によってとらえ、ガンマ線など、放射線をあてる区域をコントロールできる放射線によって癌を焼き切るという方向で進歩してきた。
しかし、画像でとらえきれない癌細胞については、対処のしようがない。
ところが、BNCTではそれができるのだ。BPAというホウ素剤を使うと、健康細胞に比べて癌細胞が2.5倍~10倍のホウ素をとりこむ。そこを狙って中性子を照射するのだ。
しかし、中性子をどうやって癌細胞にあてるのだろうか?
原子炉を使うのである。
外科手術でも薬でもない何か
大阪大学歯学部附属病院の口腔外科にいた加藤逸郎は、癌の患者を何人も診てきたが、母親を2000年10月に血管肉腫でなくしてから、自分の仕事に疑問を持つようになっていた。子宮癌を10年前に患った母親は、その後リンパ浮腫が出て、足と腕が腫れて、悪性の腫瘍になった。腫瘍の専門医であるにもかかわらず、なすすべもなく、母親を見送ったなかで、加藤は自分の診療に疑問を持つようになったのだった。
治る人は治るが、治せない人はただ見送るだけ。同じことを繰り返していいのか、という気持ちがつのってきたのだった。治せないと現在の医療で考えられる人も、治す方法というのは、実は芽として生まれてきているのではないか。
私たちより文明の進んだ宇宙人が地球にきたとして、どんな方法で癌を治そうとするのか。この先何百年あとも外科手術をして腫瘍をとるなんてことをやっていないのではないか。
それでは薬なのか? しかし、薬は必ず耐性菌、癌の場合でいえば、耐性固体が生まれてきて、それを回避する。だから根本治療にはならない。 とすれば、物理的な力を借りるしかないのではないのか。そんなことをぼんやりと考えていたときにある論文を読んでいてBNCTのことを知った。それは、フォト・ダイナミック・セラピーというある波長の光をあてることで細胞を殺す酵素をだして癌細胞をたたくという方法に関する論文だった。そこに、BNCTのことが書いてあったのだ。
そうしたときに、医局の掲示板を日曜日の夕方なにげなく眺めていたら、京都大学原子炉実験所からの張り紙にはっと目がとまった。BNCTに関する共同研究の募集だった。張り紙をよく読むと、公募の期限がすでに1週間ほどすぎていた。
しかし、だめもとで、医局から電話をしてみた。日曜日なので守衛が出たが研究室につないでくれた。するとそこにでた研究者がこう言ったのだった。
「あっ共同研究ですね。そんな期限なんて関係ないから一緒にやりましょう」。
京大原子炉実験所には稼働中の原子炉がある。その原子炉をつかって、さまざまな研究が行われていた。しかも、肝は、学際を重んじたということだ。原子力工学のみならず、物理学、放射線医療、化学、様々な専門家がその実験所には専属でいた。そして外からの研究者の共同研究も積極的にうけいれていたのである。
頭頸部癌でできないか?
米国は、BNCTの臨床研究をもっとも早く始めた国だった。アメリカ合衆国原子力委員会の傘下のブルックヘブン国立研究所(ニューヨーク州ロングアイランドにある)に原子炉がおかれた1950年代には、脳腫瘍の患者を対象に、BNCTを行っている。脳腫瘍をターゲットにしたのは、転移のおこりにくい癌だからだ。グレード3、グレード4と呼ばれる神経膠腫は、当時から治療法がなかった。それをBNCTで治そうというのだ。
しかし、63例の試験的医療照射は、散々な失敗に終わった。脳に壊死がおこり、一カ月と持たず患者は死んでいった。
その理由は、当時は、癌細胞に選択的にくっつくホウ素剤を開発できていなかったことだった。脳細胞は特に放射能に対する感受性が強い。だから中性子による放射線といえども壊死という副作用が起こったのだった。
また、このとき、原子炉からとりだせる中性子は、2.5センチの深さまでしか届かなかった。したがって脳腫瘍への照射は、開頭手術をして行っていたのである。
そして、もうひとつのターゲットは悪性黒色腫(メラノーマ)という皮膚にできる癌だった。皮膚にできる癌であれば、2.5センチという深さの問題もクリアできると考えたからだったが、こちらもうまくいっていなかった。
アルゼンチンの国立原子力委員会で90年代後半に研究を始めたマンディは、まず米国の状況を視察し、ついでその権威であるラルフ・バース博士をブエノスアイレスに招いたのだった。
ブエノスアイレスは大都会だが、電車で30分行ったティグレという巨大な三角州地帯は、水と緑に囲まれている。木陰の草むらに、マンディは夫と並んで腰を下ろした。
そのとき、突然、その考えはやってきたのだった。
脳腫瘍やメラノーマではない、頭頸部癌こそが、BNCTに向いているのではないか?
耳下腺からくる頭頸部癌は厳しい癌になるケースが多い。再発すれば、もう標準治療では対処できない。しかし、この癌は、比較的表面にある。原子炉の中性子の取り出し口に患部を固定するのもやりやすいのではないか?

マンディは他の研究で頬袋に癌が生じるハムスターを使った研究をしていたことがあった。この頬袋の癌を動物実験として使えないだろうか?
物理学者の夫に、「BNCTを頭頸部癌にやってはどうかしら?」とたずねた。
夫は少し考えるとにっこり笑いながら、「それいいんじゃない」と答えた。
米国からの客ラルフ・バース博士は、数メートル離れた場所で他の研究者と話をしていた。そこにマンディは駆け寄って、今閃いたアイデアを説明した。頭頸部癌のBNCTはできないだろうか? 頬袋に癌ができるハムスターをその動物実験に使えないだろうか? ラルフは注意深くマンディの話を聞いたあと、やはりこう言ったのだった。
「うまくいくかもしれない」
こうしてマンディは、頭頸部癌をターゲットにした研究を始めることになった。使うのは、ハムスターだ。ハムスターは頬袋がある。この頬袋に癌を生じさせ、それにBNCTをやってみるのだ。これが頭頸部癌に対するBNCTの動物実験になる。
原子炉は、ブエノスアイレスから飛行機で2時間半、パタゴニア地方のバリローチェという街にあった。
人知らずして慍(うら)みず
90年代、京大原子炉実験所で、BNCTの実用化にむけてとりくんでいた小野公二は、研究がなかなか進展しないことに、いらだちを覚えていた。
日本のBNCT研究は、アメリカのブルックヘブン研究所で、1960年代まで脳腫瘍の照射にかかわった東京大学の畠中坦(ひろし)が帰国し、王禅寺にあった日本で最初の原子炉、日立教育訓練用原子炉で脳腫瘍の患者に照射を行ったのが嚆矢とされる。1963年のことだった。しかし、畠中のやりかたは、手術して脳腫瘍そのものを切除した後に、照射をするという手法であり、しかも、それを論文にして誰にでもわかるようにするということをしなかったため、研究は広く共有されていなかった。いわば畠中の名人芸的なものだったのだ。
それに対して1970年代から、皮膚癌の一種、悪性黒色腫(メラノーマ)をターゲットにしたのが、神戸大学の三島豊のグループだった。三島らは、このメラノーマに対するホウ素剤の開発の過程で、後に使われることになるBPAという化合物を発見するのだが、この話は、第二回目以降にしよう。
日本では、武蔵工業大学にもうけられた原子炉と京大原子炉実験所の原子炉を使って脳腫瘍やメラノーマに対する動物実験や、人への臨床研究が行われていたが、あまりうまくいっていなかった。
もっとも大きな理由は、中性子が2.5センチの深さまでしか届かないことだった。小野は放射線医療が専門で、京都大学医学部から京大原子炉実験所に1991年に移籍した。実験所の教授としてBNCTにとりくみだしていた。この京大の実験炉での照射例は1990年代には世界でもっとも多かったが、原子炉を医療用に使えるのは年間5日だけ。脳腫瘍の患者であれば、開頭手術をしなければならない。脳腫瘍外科医や麻酔医が原子炉にやってきて、麻酔をかけ開頭したうえで、中性子をあてる。大仕事だった。一日に4人の患者にBNCTをやることもあった。
しかし脳腫瘍の場合、副作用である健康細胞の壊死の問題をなかなか解決できないでいた。
そうした中で、原子炉からとりだす中性子をエネルギー量の多い熱外中性子にかえる仕様変更を京大の原子炉では急いでいた。1996年には改修できたが、文科省の認可によって実際に使えるようになったのは、2001年。これによって、中性子が届く範囲は2.5センチから6センチへと広がったのである。このことで、脳腫瘍の照射の場合も、開頭手術をしなくてすむ。
小野は研究が停滞する90年代、幼いころ父に聞かされた論語の一節をくりかえし唱えていたという。
人不知而不慍
不亦君子乎
人知らずしてうらみず、また君子ならずや。人に認められようが認められまいが、そんなことを気にしてはいけない。君子というものは、そういうことにこだわらない人のことである。
BNCTがまったく人に知られなくとも、そんなことは気にしてはいけない。いつか芽がでる。
大正デモクラシーの薫風をあびて育った父が教えてくれた論語のこの一節の前には、こんな一節がある。
有朋自遠方来
不亦楽乎友
遠方より来る。また楽しからずや。
医局の張り紙をみて電話をしてきた大阪大学の加藤逸郎は、まさに遠方よりきた「友」だった。加藤が持ち込んできた深刻な頭頸部癌の女性患者のケースが、研究の地平を開くことになるのである。
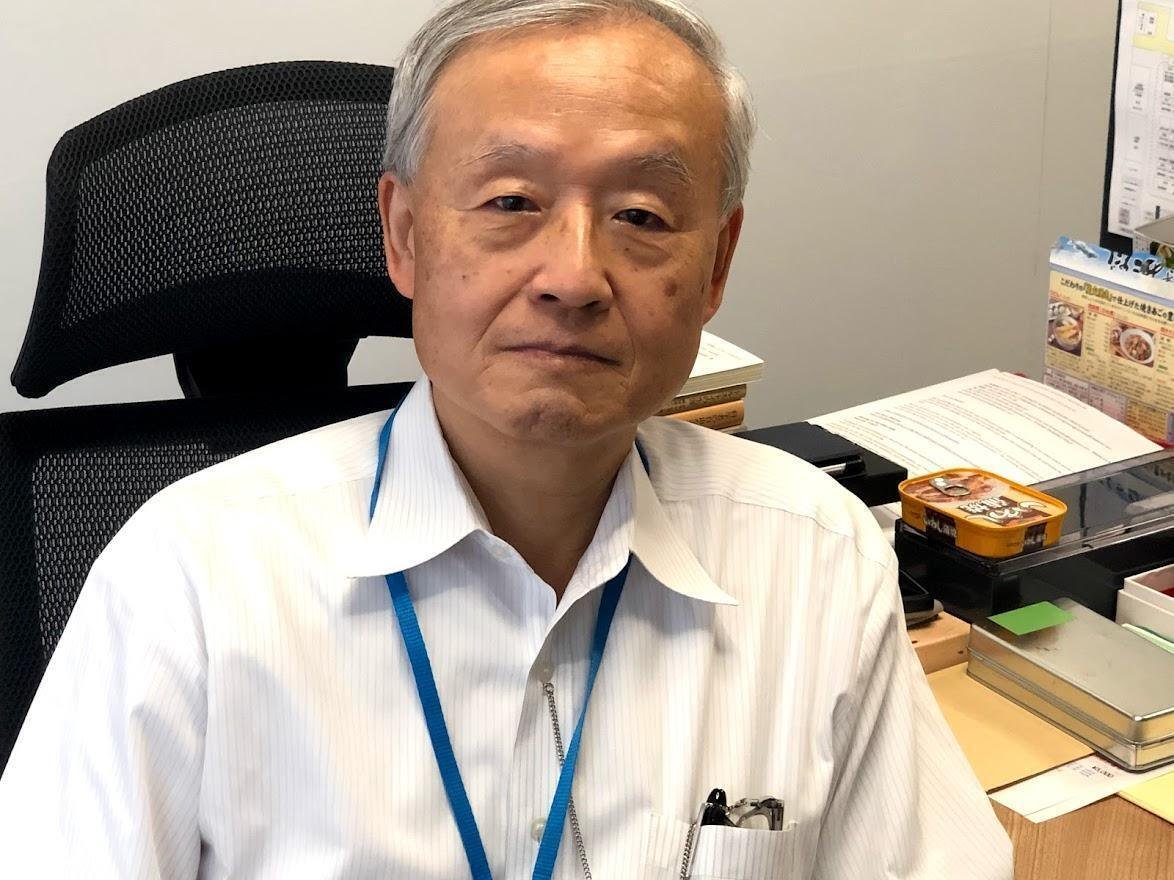
倫理委員会を通過する
しかし、小野も、阪大病院まで行ってその患者を加藤と一緒に実際に診察すると、その病状の深刻さに怖じ気づく。腫瘍には、ガーゼを何枚も重ねているが、浸出液がどんどん出てきてすぐに変えなくてはならない。いつも鎮痛剤を飲んでいるという。顔の左にある巨大な腫瘍がどんどん巨大化する為、頭の左側がどんどん重くなること、肩こりが酷く、寝ていられない、と患者は焦っていた。
医療で薬事承認されていない治療法を臨床研究として試す場合には、倫理委員会を通す必要があった。
小野は京大原子炉実験所で照射をするとすれば、主治医にならなければならないから、倫理委員会のメンバーになることはできない。首を傾げながら加藤にこう言った。
「BNCT原子炉医療委員会(倫理委員会)のメンバーで、もう一人の臨床医である井上俊彦先生を、加藤先生がもし説得できたら治療できるかも……」
井上は大阪大学医学部放射線治療医科の教授だった。加藤が井上の研究室を訪ねると、井上は、同じ頭頸部癌に対して行われた他の療法の説明をしたあと、「BNCTは、唾液腺治療の良い適応になるかもしれない。これいけるんとちゃう?」
このようにして、世界で初めて人の頭頸部癌に対してのBNCTが行われることになったのである。
その照射の日は、2001年12月18日と決められた。
78パーセントのケースで15日以内に癌が消滅
マンディは、23匹の頬袋に腫瘍を生じさせたハムスターを、博士課程にいた助手のエリカ・クレイマンと一緒にバリローチェ原子力センターにつれていくつもりでいた。照射の24時間前に、ボロン剤であるBPAをハムスターに注射する。そしてバリローチェにあるRA-6号炉の照射口から中性子線を照射するのだ。
ところが、バリローチェに行こうとしたその直前に、夫が心臓発作で緊急手術をすることになってしまった。やむなく、エリカを一人バリローチェに派遣することにした。
マンディは日本では、同じ頭頸部癌へBNCTの照射を、人間でやろうとしていたことはそのときは知らない。頭頸部癌への適用にむけた初めての動物実験という興奮のなか、エリカと原子炉のスタッフは5匹ずつのハムスターを中性子がでる原子炉の円形の照射口にはりつけて、中性子を慎重にあてていった。

照射後24時間。
ハムスターの頬袋を引き出して中を見た。
すると、目でみるかぎり23匹のうち7匹は完全に腫瘍が消えていた。
15日後に調べてみると、18匹のハムスターから完全に腫瘍が消失し(78パーセント)、3匹のハムスターは、腫瘍が縮小していた。腫瘍が引き続き増大していたのは1匹だけだった。
エリカはすぐに、この様子を電話でマンディに伝えた。
「先生、腫瘍が消失しています! 」
マンディも電話口で叫び声をあげてしまった。
しかも重要なのは、正常細胞にほとんどダメージがなかった点だった。
たとえば同じ頬袋に腫瘍をもったハムスターに20グレイのX線を照射した例がある。この研究では、当初腫瘍は縮小するものの、14日を過ぎると、再び腫瘍が成長した。しかも、X線照射をうけたハムスターは、すべて照射をうけた頬袋に、壊死や炎症の放射線障害がおこっていた。その放射線障害がBNCTの場合はなかったのである。
マンディらは、この結果を、インパクトファクターも高い「Cancer Reserch」に論文投稿する。
その結語は力強くこう結ばれていた。
<口腔部の癌へのBNCTの適用が有効であることの、初めての証拠をこの実験は示したと言える>
その論文が「Cancer Reserch」に掲載されたのが、2001年12月15日。
日本の大阪府熊取にある京大原子力実験所の原子炉で、頭頸部癌に苦しむ60代の女性にBNCTを行う三日前のことだった。
つづく
証言者・主要参考文献
加藤逸郎、小野公二、Amanda E . Schwint
"Boron Neutron Capture for the Treatment of Oral Cancer in Hamster Cheek Pouch Model" Erica L. Kreimann, Maria E. Itoiz, Juan Longhino, Herman Blaumann, Osvaldo Calzetta, and Amanda E. Schwint, CANCER RESEARCH, December 15, 2001
Effectiveness of BNCT for recurrent head and neck malignancies, Itsuro Katoa, Koji Onob, Yoshinori Sakuraic, Masatoshi Ohmaed,Akira Maruhashic, Yoshio Imahorie, Mitsunori Kirihataf, Mitsuhiro Nakazawaa, Yoshiaki Yura, Radiation and Isotopes (2004)
「BNCTの臨床;頭頸部 頭頸部癌におけるBNCTの適応と可能性について」 加藤逸郎 RADIOSOTOPES 2015年
冒頭のサムネイル Photo / アフロ
