
ジミ・ヘンドリクスが生きている世界線 前編
いきなり引用になってしまうが、私の手元にある本の中の『ジミ・ヘンドリックス』の項にはこのような記述がある。
“ジミがもし生きていたら50歳代の前半である。ミック・ジャガー、キース・リチャーズが共に43年生まれで一歳違い、この世代のロッカーの多くが復活して活躍しまくっているこのご時勢のこと、ジミほどの才能ならば、いったいどんなことをやらかしてくれてたことか、想像するだけで楽しい時間つぶしになる。”
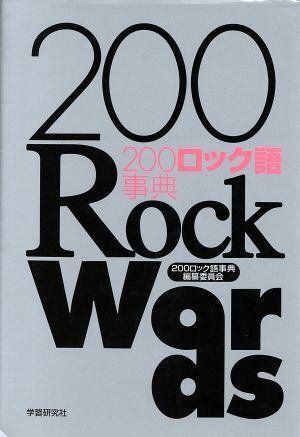
1995年発行のこの本で、ジミのこの項を担当したのは島原裕司氏とのことだが、30年ちかい年月が過ぎた2024年現在ではM・ジャガー、K・リチャーズ両名とも80歳になっているし、島原氏がこの項で;
“現代の既存のビッグな存在になぞらえるなら、たぶんプリンスではないかと思われる。”
と名を挙げたプリンスも、残念ながら2016年に57年の生涯を閉じている。
しかし、1970年に27歳の若さで天に召されたジミ・ヘンドリクス(Jimi Hendrix、以下JH)が現在も‐少なくともクリエイティヴィティを失わず、またその才を十全に発揮するに十分な肉体を保っていたとしていたら、として、私達にどのような音楽を聴かせてくれ、どのようなパフォーマンスで圧倒していたか、という想像は確かに楽しく、興味深いことである。
かつてであればタラレバの烙印とともに一笑に付されたであろうこのような妄想だが、幸いなことに最近では世界線という非常に便利な概念が市民権を得ているようなので今回はそれに甘えて、私なりにJHが現在も生きていたらのifストーリーを書き綴ってみたい。
☆
1947年にシアトルにて生を受けたジミー・アレン・ヘンドリクス(後にジェイムズ・マーシャル・ヘンドリックスに改名)がギタリスト、ジミ・ヘンドリクスとしてのキャリアをスタートさせたのは1963年とされている。
メジャーデビューが1966年、ロンドンのホテルで薬物の過剰摂取とみられる謎の死を遂げたのが前述のように1970年である。
JHの生前の姿を記憶している者達は実に多い。
1966年の12月末、ニューカッスル在住の15歳の少年はその長身を使って18歳と偽り、地元のナイトクラブに出演したJHを観ることが出来た。
彼にとって初めて見るブラック(黒人)でもあったJHの姿は少年の記憶に強く焼き付き、彼がスティング(Sting)と名乗るようになってからも折に触れてJHの楽曲を採り上げている。
JHと同世代または歳下のミュージシャン、とりわけギタリストにとってJHがロンドンで見せたパフォーマンスは強烈を通り越して理解不能ですらあったらしい。このことは後に多くのアーティスト‐すぐに名前が出てくるだけでも;
エリック・クラプトン
スティーヴ・ハウ
アンディ・サマーズ
ピート・タウンゼント
が証言していることでも判る。
だが、その中でも、ただ単に圧倒されただけでなくJHが示した可能性に気づき、悪戦苦闘しながらもギターの表現領域を広げようとしたギタリストがいる。いうまでもなく故ジェフ・ベックである。
ベックはロンドン滞在時のJHとツルんであちこちのクラブに出没していたことが知られているが、ただ単にお遊びを楽しんでいただけではないようで、ある時JHから面と向かって
ブルーズを弾いているときのオマエは猿より退屈だ
と言われたという。
続けて、エレクトリックで冒険するんだよ、オマエならできるはずだ、と言ったそうだ。
もちろん、ただの思い付きやその場のノリから出た言葉かもしれないが、少なくともベック本人はJHのこの痛烈なひと言で何かに覚醒したのであろうことは、その後のベックが残した楽曲や演奏を聴けば何の不思議もない。
JHはベックの中に、ブルーズの模倣に終始するには惜しい才が秘められていることを見抜いていたのだろう。
☆
しかし、生前のJHの真価‐革新性と強烈な個性と真正面から向き合い、正当に評価できた数少ないアーティストのひとりとして、私はマイルズ・デイヴィスの名を挙げる。
マイルズとJHの邂逅が実現したのは1968年、JHのマネージャーからコンタクトがあったそうだ。
“ジミは、オレが「カインド・オブ・ブルー」やいろんなところでやったことを気にいっていて、自分の音楽にジャズの要素を加えたがってるってことだった。(中略)それに彼は、オレのトランペットのサウンドにギターのボイシングが聴き取れるとも言った。(中略)
音楽の話を始めたら、楽譜が読めないってこともわかった。(中略)知り合いにも尊敬する人間にも、一緒に演奏した連中にも、黒人にも白人にも、楽譜が読めないミュージシャンはたくさんいる。だから、そのためにジミにがっかりするなんてことはなかった。(中略)
彼は音楽を聴くための天性の耳を持っていた。だから、いろんな異なったやり方を示してやったり、オレやトレーン(※)のレコードをかけて、何をやっているかを説明してやった。そのうち彼は、オレが教えてやったことを自分のレコードで生かしはじめた。すばらしかったな。彼はオレに影響を与え、オレも彼に影響を与えた。それこそすばらしい音楽が作られる関係なんだ。“
※トレーン:ジョン・コルトレーン(John Coltrane)の愛称
現在では7thコードに#9thの音を足したテンションコードにジミヘンコードの異名が付けられているが、これもあくまでJHが生前に見せた才能の片鱗にすぎないのかもしれない。
1959年の”KIND OF BLUE”でコードの束縛から逃れ、ソロイストの自由度の高い演奏を実現するモーダル(モード)奏法の可能性を提示したマイルズであれば、JHにコードとの向き合い方や、そこから外れていくことの重要性を教授できたであろうし、JHはマイルズの教えを受けるにふさわしい最優秀の生徒だったはずだ。
マイルズとJHの交流はわずか2年足らず、共同でのアルバム制作に取り掛かる寸前でJHが世を去ってしまったため、両者の公式音源は夢と消えてしまった。
☆
後編ではJHが2024年の現在まで生きていたら、きっと歩むであろう変遷を私なりに書き綴ってみたい。
