
「G検定」に3週間で合格したので勉強法と言う名の愚痴をこぼす話
この記事は会社からリスキリングリスキリングうるさく言われ、「しゃーない、とりあえずAIぽいの受けとくか」というモチベーションで受験した、文系社会人による合格体験記である。
タイトルの通りちょっと愚痴っぽい内容になると思う。基礎がないため結構苦労した。文系諸氏でこの試験を受けてみようと思っている方に少しでも参考になれば幸いである。
1.筆者の基本スペック
合格体験記で、自分とこの人はどれくらいの違いがあるのかよく分からないまま進むのは気持ちが悪いと思うので、先に筆者のスペックを開示する。
数学は嫌いだが数字は好き
高校でⅢCまで学びはしたが、虚数iに納得しておらず数字は好きだが数学は嫌い。大学は文系。
システム系部署には数年
システム系部署に勤務していたことがある。そこで結構大きいシステムの基盤更改に携わった。そこで使われる用語についていくために基本的なプログラムやシステムの構造の勉強はしている。
システム系の資格
上記のために、ITパスポートや情報セキュリティマネジメントは取得済。基本情報処理技術者は未取得。
その他参考事項
筆者は週5日仕事をする社会人だ。なお、システム系部署にいたことがあるといっても携わったのは『ビッグデータを保管する側』だったので、AI関連業務等には一度も触れたことはない。
プログラムもネットを見ながらエクセルのマクロを組む程度である。
2.「G検定」にあるハードル
勉強法の前に、個人的に感じたハードルを記載する。
受験料:一般:13,200円(税込) 学生:5,500円(税込)
ーー高っか。
会社の団体受験や2回目は半額、といったような割引はあるようだが、そもそもこの値段に引く人は多いだろう。
学生は5,500円に見合うリターンがあるかどうかをよく見極め、社会人は会社の資格報奨金制度や団体受験制度がないかをまずは検討した方がいいと思う。
資格による独占業務はない
あくまで民間資格であり、その目的も以下の通り知識の確認である。
ディープラーニングの基礎知識を有し、適切な活用方針を決定して、事業活用する能力や知識を有しているかを検定する。
取得しても弁護士のような独占業務はない。システム系資格にはよくあるが「私はここまでは知ってます」「ここまでできます」のスキルの証明程度だ。
メリットが見えにくい
明確に目標がある場合は良いが、ただ何となくで取得するのはおすすめしない。ディープラーニングの基礎知識を有することで何かに活かせる可能性があるか、という視点で受験の取捨選択をするのがよいと思われる。
たとえば、画像生成系AIやChatGPTについて仕組みを知ってうまく使いたい、という人には入り口としては良い資格ではないかと個人的には考える。
3.試験に対する心構え
高い合格率に潜む罠
2024#2の合格率は68.03%と出ている。合格者の職種は以下の通り。

合格者が所属しているのは、ソフトウェア、情報系、製造業、金融系。そもそもディープラーニングの知識を使っている・利用しなくてはいけないといった職種の人々だ。
本試験は基本的に素地がある人たちが受けているという点は認識をしておいた方がいいと思われる。
つまり文系諸氏にお伝えしたいのは、ディープラーニングについて業務で携わる・実地でよく使っているという方以外は、しっかり勉強しなければ落ちるということだ。
ちょっとテキスト読んで、試験として推奨はされていないがチートシート作っておけばいいんだろう、と思っている人は認識を改めた方がいい。
問題数約200問を120分で解く必要性
普通の検定試験ではありえない時間配分の問題数だ。出題範囲は提示してあるものの、広範でありある程度の知識がないと絶対に全問は解けない。
これに対する愚直な対策が必要となる。
自宅等の環境
自分のPCからの受験となるので、落ち着けるところ・ネット環境が安定している必要がある。
チートシート(カンニングペーパー)は非推奨であるが…
G検定で検索すると、チートシートを使った、ChatGPTに聞いたというポストが散見される。
公式には絶対NOと記載がないかつ自宅受験である点でもあり、非推奨乍らもその作成のために調査することが無意味ではないというスタンスのようだ。
筆者個人の意見としては、最終手段として持っておくと安心には繋がるとは思う。なぜこんなことを書くかというと、5.に書くがこの試験は割と意地悪でダメな部分があるからだ。
一方で問題数が膨大なため、チートシートだけで乗り切るのは不可能に近いと思われる。チートシートの検索プログラムを組むような人はさらで合格するだろう。結局は正攻法で行く方が、不合格になって時間を無駄にするよりは良いとは思われる。
4.筆者の勉強方法
テキストとYoutube動画の合わせ技
① 公式HPにあるテキストのいずれかを読む
ちなみに筆者は以下の【1】と【3】を使用した。地味に高いので中古本等をうまく見つけてもよいと思う。

② テキスト内でよくわからない仕組みや単語はYoutubeで検索して見る
生成AI等が話題になっているからか、無料で分かりやすい動画がたくさんあるので、文章だけでなく動画を見聞きすると理解が進む。
単語を入れるだけで親切な動画がたくさん出てくるのでオススメ。はっきり言って、知識ゼロでテキストだけで理解できる人がいたら天才だと思う。
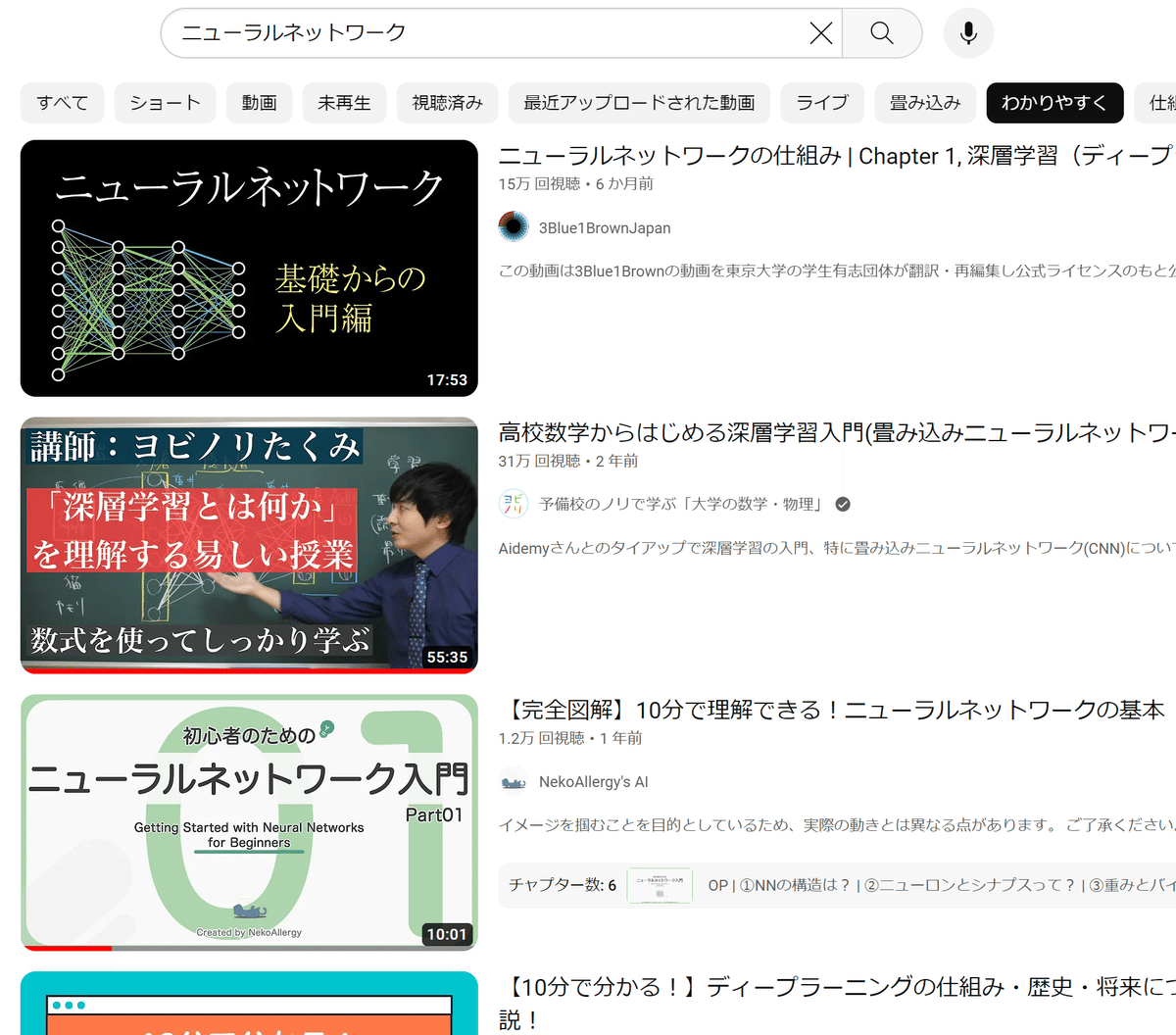
「わかりやすく」で絞るのがおすすめ
スキマ時間に見られるものからがっつり時間を使う
ものまでたくさんの動画がある
問題集を解く
1問1問に時間をかけられないので、問題集を解いて慣れる。無料の問題アプリもあるので、そちらを通勤通学等のスキマ時間に解くのもオススメ。
個人的にはβ版だが、StudyAIの無料問題が手軽にできて感覚がつかめた。
3週間の勉強スタイル
基本的にはスキマ時間と、家に帰ってからの1~2時間程度を勉強時間にあてるスタイル。
最初の1週間でテキスト本は一周し、スキマ時間はYoutube動画視聴。残り2週間は問題演習に時間を使い、そこで出てきた不明なものはYouTube動画検索で確認、そこになければテキスト確認、テキストにもなければさらに検索…で不明点を潰した。
なお、難しくはないが数学の計算問題も少し出題されるので、問題演習時には組み込んだ方が良いと思われる(市販の問題集にはそれらも含まれているのであえて追加する必要はないかと)。
どうしても覚えられない! というものは、最終手段として、チートシートを作ることも考えても良い。
全て検索する時間は試験にはないが、これ見たのに思い出せない、というものからの得点ができる可能性がある。高い試験料を払って落ちるよりかは、できることは全部やっておくべきだと思う。
ChatGPTは条件付けをしっかりしないと検索文面を全部吐き出して時間がかかるので、試験中の使用はやめた方が良いと思う。
5.試験当日
運を天に任せる
個人的に考える、G検定で意地悪でダメな点を記載する(ストレートな悪口)。
まず、本番の問題では筆者の記憶の限りにおいて、テキストに載ってない問題が結構出た。あるいはテキストには説明がなく単語のみ記載があった項目の、説明の選択肢問題だ。
最新論点だから、という話かもしれないが、ならばテキストにきちんと記載して欲しい。
また、同じ項目を違う角度で聞いてくる問題も出る。またこの話かと、おばあちゃんとのおしゃべりを思い出す。
200問近くあれば(直近の試験は191問)仕方ないのかもしれないが、もう少し何とかしてほしさがある。
だから、受験者がチートシートやChatGPTに聞くようになるんだろう。
勉強した箇所が全く出ないということでもないし、基本事項もちゃんと出るようなので、勉強の過程で気になる個所があったら、さらにYoutube等の動画や書籍で確認をする程度で良いと思われる。
また、試験時間を効率的に使うために、わからない問題はいったん飛ばして、どんどん解くのをオススメする。最後にまとめて振り返り、チートシート等に訊ねると良いだろう。
6.筆者の正答率
文句を言いながらもなんとか合格した。合格水準の正答率の開示がないので、筆者の正答率はあくまで参考程度にして欲しい。巷では70%前後とのことだ。
割とギリギリの水準だと思っている。ギリギリでも合格は合格である。

7.おわりに
G検定を受けてみて感じたのは、基本的にはディープラーニングにすでに触れている初心者向けの試験であるという点だ。全くのゼロで、とりあえず受けてみようというのはなかなか難しいと思う。IT関係のリスキリング目的ならITパスポートやセキュリティマネジメントの方が取りやすい印象がある。
一方でこの試験をきっかけにディープラーニング、人工知能についての知識を得ることはできるので、ディープラーニングに“触れてみたい”人の入り口として、どこから勉強したらわからないという人には、まずはこの資格試験を合格することを目標に勉強をするというのはアリだろう。
どちらにせよ、ここまで読んでくださった奇特な方の、勉強の参考になっていれば幸いである。
