
「産学連携」・「COI」。事例を交えて分かりやすく紹介する記事
こんにちは!
SIRU+の川﨑です。
今回は弘前大学を拠点に行っている研究、「健康を基軸とした経済発展モデルと全世代アプローチでつくるwell-being地域社会共創拠点」についてご紹介します!
この記事はこんな人におすすめです。
産学連携について知りたい方
具体的な事例を探している方
ヘルスケア事業におけるCOI事業との関わりについて知りたい方
大学と連携してるってどういうこと?
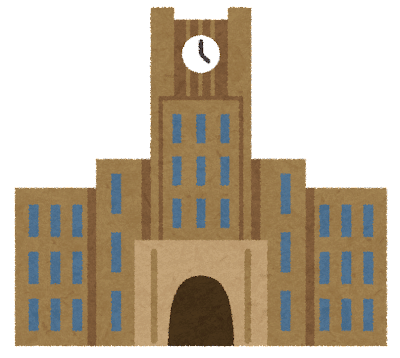
弘前大学を拠点に行っている研究、と言われるとなんだかものすごく厳かな雰囲気を感じます。
しかもこの研究、参画機関を見てみると弘前大学を筆頭に九州大学、京都大学、東京大学など名だたる大学から
東京大学医科学研究所、医薬基盤・健康・栄養研究所などの研究所、
食品メーカーやその他の企業など、多くの機関が関わっています。
その中にも、SIRU+のロゴ、ありますね…!

より
ロゴを見つけるとなんだか嬉しい(笑)
凄そうだなーっていう感想しか思いつかず、ちんぷんかんぷんなので
大学と連携した研究ってどういうこと?を、社長の小原に聞いた話と調べてみた内容を踏まえてまとめてみました
産学連携3.0(産学融合)

企業と大学が連携し、連携テーマの策定や研究開発を効果的に進める場づくり・体制づくりのモデルを産学連携(または産学官連携)といいます。
そして、この産学連携をより一体的に・融合的に行う新たなステージである産学連携3.0(産学融合)の取り組みが生まれ重要性が高まってきています。
下にある、経済産業省が出しているスライドのように産学連携にも時代の変化があるようです。
産学連携1.0:大学や研究機関から企業がライセンスを受けて取り組みを進めて事業化を進める
産学連携2.0:大学や研究機関・企業間を産学連携本部(TLO)が橋渡しすることで取り組みを進める
※TLOとは、Technology Licensing Organization(技術移転機関)の略称です。大学の研究者の研究成果を特許化し、それを企業へ技術移転する法人であり、産と学の「仲介役」PDFファイルの役割を果たす組織です。(経済産業省HPより)
産学連携3.0:大学や研究機関・企業が一体となり取り組みを進める

この弘前大学での研究も「産学連携3.0(産学融合)」の取り組みの一つ。先進事例として全国に展開することでさらに新たなモデルを創出していくことが重要になっています。
産学連携3.0(産学融合)が進むと何がいいのか、というと必要とされる未来ニーズを構想することができます。
技術シーズ起点(この技術があるから、これを使って新しいビジネスを始めようという考え方)ではなく、
未来の社会課題に応え、必要とされるニーズを構想すること(つまり未来からの逆算)はスタートアップが得意とするところなので、相性がバッチリです!

大学側にとっては研究が進むことで研究成果の社会還元が促進される、自治体はその地域の長期的な課題の把握ができる、企業は商品開発のチャンスにもつながる、と三方よしというわけです。
食事の把握ってそんなに難しいの?の話

SIRU+にお声がかかった背景には「ユーザーの栄養素や食生活が把握できる」というアプリの強みがあります。
食事の把握をするツールはもちろんたくさんあります。
簡易型自記式食事歴法質問票(BDHQ):通常の食品(サプリメント等を除く)から習慣的に摂取している栄養素量を比較的簡便に、個人を単位として調べ、個人ごとの栄養素摂取量、食品摂取量、その他、若干の定性的な食行動指標の情報を得るために設計された質問票。
食事記録法:摂取した食物を調査対象者が自分で調査票に記入
する。重量を測定する場合(秤量法)と、目安量を記入する場合がある
(目安量法)。食品成分表を用いて栄養素摂取量を計算する。
陰膳法:摂取した食物の実物と同じものを、同量集める。食物試料を化学分析して、栄養素摂取量を計算する。
24 時 間 食事思い出し法:前日の食事、または調査時点から遡って 24 時間分の食物摂取を、調査員が対象者に問診する。フードモデルや写真を使って、目安量を尋ねる。食品成分表を用いて、栄養素摂取量を計算する
・・・など
質問票は自分で思い出して書くので、簡易ではあるものの正確さに欠ける、食事記録法や陰膳法は正確ではあるものの対象者の負担が大きい、などの特徴があります。

食材一個いっこ重量測るとなるとズボラにはきつい(笑)
しかし!SIRU+は「手軽さ」「正確さ」両方を兼ね備えています…!
SIRU+は食材の重量データも持っていて、ポイントカード連携することで自動で把握することができる、というメリットがあります。
COI事業について

HPより
弘前大学の取り組みが「産学連携3.0(産学融合)」であること、今その取り組みを進めることが重要となっていること、SIRU+が簡単に食生活の把握をできるという特徴から声がかかった、ということは理解できました!
ここから弘前大学の研究の取り組みについて行ってみよう!と思うのですがこの研究、正式名称は「健康を基軸とした経済発展モデルと全世代アプローチでつくるwell-being地域社会共創拠点」。
こんなに長い名前と呼ばれているのか?と不安になりながら調べていると、どうやら弘前COI事業と省略されているようです。
COIってなんだろう。。。。
とまたしても壁にぶち当たったのでこちらも調べてみました。
潜在している将来社会のニーズから導き出されるあるべき社会の姿、暮らしの在り方として3つのビジョンを設定し、このビジョンを基に10年後を見通した革新的な研究開発課題を特定した上で、既存分野・組織の壁を取り払い、企業だけでは実現できない革新的なイノベーションを産学連携で実現するため、平成25年度から「革新的イノベーション創出プログラム(COI STREAM)」を開始しました。
センター・オブ・イノベーション(COI)プログラムとは、10年後の目指すべき社会像を見据えたビジョン主導型のチャレンジング・ハイリスクな研究開発を最長で9年度支援するプログラムです。
つまり長期的に産学連携3.0(産学融合)を行うことで、将来の社会や暮らしの目指す姿を把握し実現していくための取り組みなんですね!
COI拠点は弘前市だけでなく全国で広がっているようで、健康をテーマとした取り組みだけではないようです。
全国的に大規模な形で産学連携の取り組みを進めて、住みやすい社会や暮らしづくりを目指している!と理解しました

センター・オブ・イノベーションプログラムHPより
COI事業の3つのビジョンは、こちらです。
ビジョン1:少子高齢化先進国としての持続性確保
ビジョン2:豊かな生活環境の構築(繁栄し、尊敬される国へ)
ビジョン3:活気ある持続可能な社会の構築

弘前市は、ビジョン1:少子高齢化先進国としての持続性確保 の一つで、
真の社会イノベーションを実現する革新的「健やか力」創造拠点です!
他のCOI事業には、例えばこんな事業があります。
運動の生活カルチャー化により活力ある未来をつくるアクティブ・フォー・オール拠点 〜立命館大学〜
「運動の生活カルチャー化」を合言葉に、運動を通じて多様な人たちと交流できるような社会を作り健康寿命の延伸を目指す
「感動」を創造する芸術と科学技術による共感覚イノベーション拠点 〜東京藝術大学〜
芸術と科学の力によるDX(デジタルトランスフォーメーション)に取り組み、withコロナ、afterコロナに向けた環境変化も視野に入れた「日本の文化立国と国際的な共生社会の実現」を目指す
人がつながる “移動”イノベーション拠点〜名古屋大学〜
高齢者の外出頻度と社会参加率が増加し主観的幸福度が向上する
「高齢者が元気になるモビリティ社会」の実現を目指す
他のCOI事業が気になりましたらセンター・オブ・イノベーションプログラムHPにまとまっていますので是非!
弘前での取り組み

「健康ビッグデータと最新科学がもたらす“健康長寿社会”」
これが弘前COI事業のビジョンです。青森県は日本の中でも高齢化が深刻化している地域の一つで、健康の課題を抱えているからこそ、イノベーションを起こしやすい地域のようです。
弘前COIの研究開発期間:平成 25 年度~令和 3 年度

HPより
SIRU+での取り組み

SIRU+が関わっているプログラムの一つ、
超高齢社会でますます課題となる、肥満や糖尿病、高血圧症といった生活習慣病リスクの低減のために、市民にとって身近な店舗でできる継続的な健康支援プログラム。
目的:「買いもの行動が変容し、知らずしらずのうちに日常の食生活が良好になる」こと
健診機会の少ない人たちにとっても、楽しく健康リスクの低減につながり、健康リテラシーが高まることを目指しています。
実証実験概要:対象者100名にSIRU+アプリを入れてもらい買い物をすることで栄養状態を把握し、連携しているスーパーであるコープあおもりの店頭で「簡単な健康チェック」ができます。
「簡単な健康チェック」とは、簡単な健康調査票に回答していただき、血圧、体組成、内臓脂肪そして日頃の野菜摂取量がわかる皮膚カロテノイド量を短時間で測定し、その場で検査結果を基に食生活に関する健康づくり情報を提供します。
SIRU+は、買ったものから栄養素に変換する技術の提供をしており、
この研究を通じて長期的に健康状態までしっかりと追えるのはSIRU+としても嬉しいことです!

つまりまとめると…
●弘前市:医療・健康・福祉の分野におけるデータの保有、住民への周知、地域の健康課題把握など
●コープあおもり:普段通りのお買い物、店頭で「簡単な健康チェック」
●シルタス:栄養診断・食材やレシピのレコメンド、栄養データなどの保有
●弘前大学:「研究リーダー」がCOI拠点の運営支援等の本部機能、研究開発活動の研究戦略・企画等をサポート、健康ビッグデータの保有
長期的な実施によって今摂っている栄養素が長期的にみて体にどう影響してくるのか見えてくるんですね。
栄養状態の把握から、体の筋肉量や内臓脂肪量・骨密度などの体組成と栄養素摂取量の相関、生活習慣病のリスク予測などさまざまな角度からデータの分析ができます!
最後に
今回の弘前COIでの取り組みは、東京栄養サミットでも発表されています!
東京栄養サミットは、栄養不良の解決に向けた国際的取組を推進するために、日本政府により2021年12月に東京で開催されました。日本の取組を世界に発信しています!
そんな東京栄養サミットでも発表された取り組みの中にシルタスも参加していたと思うと、
今後も「がんばらないヘルスケア」を日本全国に広げていくぞ!という気持ちが増します!
そして、ここまででお話ししてきた弘前COIのプログラムは終了していますが、
弘前大学では、「共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)」が始まっていて
こちらにもシルタス、参加しています!
社長の小原は、弘前大学大学院医学研究科で客員研究員も担当しています!(研究員!!かっこいい!!)
ここまで読んでいただきありがとうございました!
産学連携からCOIの話までしていたらめちゃくちゃ長くなってしまい、全然分からんということでしたらごめんなさい。。。
シルタスのプロジェクトに質問などありましたらどしどし連絡ください!
シルタス株式会社コーポレートサイト
SIRU+アプリのダウンロードはこちら
