
原罪/家族/幻想の未来――デカグラマトン編2章に関する覚書(Part2まで)【ブルーアーカイブ】
自分の悲惨を知らずに神を知ることは、高慢を生みだす。
神を知らずに自分の悲惨を知ることは、絶望を生みだす。
前田陽一・由木康訳
ブルアカ4周年の節目に、デカグラマトン編2章『炎の剣』Part2が更新されました。まだまだ起承転結の"承"といったところでしょうか。次回の更新が待ち遠しいばかりです。
せっかくの機会なので、現時点における感想と備忘録をまとめたいと思います。本シナリオの宗教的モチーフや、そのアンチテーゼとして描かれているであろう要素、先生の精神状態について、キリスト教の諸概念やフロイトの学説を援用しながら読み解いてみる。そんな話です。
人類と原罪の起源
【新情報 ⑬】
— ブルーアーカイブ公式 (@Blue_ArchiveJP) October 20, 2024
10月23日(水)メンテナンス後より、特殊作戦「デカグラマトン」編は、メインストーリーに編入されます!
今後はメインストーリーから確認できるようになりますので、第2章が開幕される前にぜひ第1章をチェックしてみてください!#ブルアカ#ブルアカらいぶおーたむSP pic.twitter.com/9X30CRjvBp
デカグラマトン編はメインストーリー編入に伴って章題がつけられました。それまで特殊作戦イベントで公開されていた部分は第1章「知恵の蛇」、現在Part2まで更新されている第2章は「炎の剣」。
この二つの章題は、旧約聖書における楽園(エデン)追放が元ネタと見て間違いないでしょう。

デカグラマトン編第1章でも預言者として登場したビナーが「知恵の蛇」になぞらえた姿で描かれている。
神によって作られたアダムとイヴは楽園に住み、「善悪の知識の木(命の木)になる実は決して食べてはならない」と命じられていた。しかし、イヴが蛇に唆され、二人はその実を食べてしまう。神は掟を破った二人を追放し、命の木に至る道を守るため、楽園の東に智天使ケルビムと、きらめく剣の炎を置いた。[創世記2:7-3:24]
いわば人類の起源が語られている逸話。キリスト教においては、ここから人類の「原罪」が生まれたとされている点でも重要です。原罪とは全ての人類が宿命的に背負う罪のこと。人類の祖であるアダムとイヴが神との掟を破った原初の罪は、その子孫にも継承されている。人類が犯す全ての悪行はこの罪に由来しているのだという。

「そうして争いが生まれ、憎しみが育ち――最後は互いに罪を犯す。」
この概念には、マルクトが目覚める時のモノローグにおける一節が重なる。楽園追放の後、アダムとイヴの子孫としてカインとアベルが誕生したが、後に兄カインは憎悪に駆られて、弟アベルを殺害してしまう[創世記4:1-4:26]。神から楽園を追放され、寄る辺なく彷徨い続ける人類は、行く先々で争い合い、罪を犯すことを宿命づけられているという寸法だ。
こうした原罪から人類を救済したのがイエス・キリストだ。キリストは十字架と共に人類の全ての罪を背負うことで、贖罪を果たした。このような人類の原罪とイエス・キリストの自己犠牲的な死による救済という因果関係が、パウロによって定式化された。神の子イエスをキリスト(救世主)として信仰するキリスト教は彼の思想から本格的に始まったとも言える。
第2章では、シナリオ内にこうしたキリスト教的モチーフが数多く散りばめられていると同時に、それに対するアンチテーゼも色濃く描かれているように思います。以下、順を追って見てみます。
アンチテーゼ① 自己犠牲の否定、人どうしの"繋がり"による救済

でも、その対象にリオ先輩が入っていないのは……。」
「とても、悲しいです。」
まず自己犠牲による救済・贖罪を明確に否定していること。その最たる例が第14~15話におけるアリスの台詞だ。モモイからパヴァーヌ編第2章の事件について問いただされたリオ会長は、「私の命で世界の終焉を防ぐことができるのなら、今でもそうすべきだと思うわ」と語る。しかし、アリスはその考え方に深い悲しみを表明する。加えて、自分の存在を犠牲にして窮地を救ったケイについても、その復活を願い、リオに託すことにした。

そんなアリスの勇者論がリオやケイにも向けられている。
かつてはアリス自身も、仲間が傷つく状況に耐えられず、リオに連れ去られることを選んだ。しかし最終的にはアリスの自己犠牲によってではなく、勇者の愉快な仲間たちの協力によって事態は解決した。元来の優しい性格はもちろんのこと、そうした自身の辛い経験も踏まえた上で、孤立しそうな人物に手を差し伸べていることが言外に伝わってくる。
勇者アリスの成長、もといレベルアップが垣間見れる場面だ。

「それが……私にできる償いだから。」
そして、リオ会長に手を差し伸べるのは、もちろんアリスだけではない。あの大事件を巻き起こした償いをしなければならない。堂々と人前に出るのは憚られる。また間違えてしまうかもしれない。そんな自責の念に駆られているリオに対して、ヒマリは「ごちゃごちゃと理由をつけてないでさっさとミレニアムに戻りなさい」と言いかけ、トキは正しさが分からずとも「リオ様にもう一度会いたいです」と素直な思いを口にする。ちなみに私はヒマリオ派です。結婚しろ〜〜!!!!!!
リオはそうした思いを受け止めながら、トキに謝罪と労わりの言葉を贈り、モモイからの追求にも真摯に答え、ケイの復活に尽力するなど、自分なりに少しずつ前に進み始めている。
償い・贖罪という点について、もう少し詳しく見ると――パウロは原罪と救済の論理のみならず、「人は自分の意志で善をなすことはできない。行為によってではなく、ただ信仰することで、神によって義と認められる」とする信仰義認説を説いた。ユダヤ教パリサイ派が厳格な律法主義を説き、律法を守らない者や異民族を蔑んでいたことに対して、キリストは律法を形式だけで守るのではなく、律法の愛の精神こそが重んじられなければならないと説いた。その教えをさらに推し進め、原罪の思想とも組み合わせた理屈と言える。
贖罪や救済は神に委ねなければならない――これを聞いて思い出すのはやはり、元シナリオディレクター・isakusan氏のイタビューにおける発言だ。
私は無神論者であるため、慈悲を乞うことも、罪を赦すことも、どちらも人間の行為であるべきだと信じています。人間を救済するのは、人間であるべきです。
しかし同時に我々は誰かを赦し、誰かを救う瞬間、われわれはわれわれの内部に宿る可能態として存在する“神聖”に触れられます。
電ファミニコゲーマー
エデン条約編4章で、ミカがアリウススクワッドのために祈り、Kyrie eleisonを歌い上げた場面が代表例として挙げられるでしょうか。『ブルーアーカイブ』という作品では常に、人間の行為としての「赦し」や「救済」があります。

「もし、また間違ってしまった時は、教えてちょうだい。」
仮に人類が罪を犯す宿命を背負った存在であったとしても、贖罪や救済は神の威光によってではなく、人の手に委ねなければならない。人どうしの繋がりで乗り越えることもできる。それこそが、本当の意味で、人が自分の足で歩むということ。自分の過ちや償いについて悩みながらも、誰かに頼ることも覚えて前に進み続けるリオ、そんな彼女を取り巻く生徒たちの緩やかな繋がり方、アリスの勇者論を見ていると、そんなことを思わせてくれます。
isakusan氏が残した指紋は今もなお、こうして新たな物語に脈々と受け継がれているのではないでしょうか。

"それでもダメだったら!"
……でもそれに反して先生は不穏なこと言ってますね。やれること全部やって、それでもダメだったら――「諦める」という選択肢は先生にはない。同じ状況、同じ選択。もうひとりの先生と同じく、自分を犠牲にしてでも生徒たちの救済に乗り出すことでしょう。

あなたは私たちと同じ結末を迎える事になりますよ、先生。」
先生がヴィア・ドロローサ(十字架に続く苦難の道)を歩かされている気がしてものすごく不安。そりゃアロナもプラナも心配するよな……
アンチテーゼ② 受肉の肯定

一つの呪いであり――
其方たちはそれを変えなければならない。」

「無限」が「有限」へと成り下がること。
そして生誕には――破壊が伴う。」
マルクトが目覚めるモロノーグの他の部分に注目してみます。この部分はシオランの『生誕の災厄』を思わせる反出生主義・悲観主義、デカルト的な心身二元論など、さまざまな思想を読み取ることできそうです。
本記事ではこれまでと同様、パウロの思想に照らし合わせてみます。
肉の弱さのために律法がなしえなかったことを、神はしてくださったのです。つまり、罪を取り除くために御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、その肉において罪を罪として処断されたのです。[……]肉の思いは死であり、霊の思いは命と平和であります。なぜなら、肉の思いに従う者は神に敵対しており、神の律法に従っていないからです。従いえないのです。肉の支配下にある者は、神に喜ばれるはずがありません。
新共同訳
パウロ曰く、人間の罪は肉(物質的な身体)に由来する。禁断の果実を食べたイヴが、裸であることを悟り、神の目から逃れようとしたことがその証左と言えるでしょうか。ゆえにキリストは受肉して十字架に磔にされることで、肉の罪を贖わなければならなかった。人間は罪深い肉体に従うのではなく、より精神的な、神から授けられた霊性を重んじなければならない。肉体の脆弱性・有限性を軽蔑し、霊的なものの不死性を強調している。

デカグラマトンの預言者のモチーフである「セフィロトの樹」は、神性がセフィラという媒介を通じて、現象界に流出する順序関係を図式化したもの。無限である神を、人間は直接体験することができないが、セフィラを通じて、神性を象徴的に解釈・理解することが可能になるのだという。このカバラの教義と、人間が神から置き去りにされている物質的世界を悲観的に捉えるグノーシス主義の思想が結びついた痕跡を、マルクト覚醒のモノローグに見出すこともできるだろうか。

意図的な対比表現が見て取れます。
閑話休題。肉体およびその有限性を軽蔑する思想に真っ向から対立するように、第16~18話では、マルクトの目覚めと並行してケイの受肉が描かれています。暗喩めいた表現をせず、台詞やあらすじで明確に「肉体」という言葉が用いられているあたり、やはり霊―肉(あるいは精神―物質)の二項対立を意図したものであるように感じられます。
(※受肉という言葉は本来、神の子イエスが人の形を取ることを指す神学用語のようです。本記事ではより世俗的な、バ美肉おじさんくらいの意味で用います)

ケイちゃん自身は、前衛的なデザインを嫌がっていますが……(私はかわいいと思うよケイちゃん!)身体を与えられたことそのものは喜ばしいと思っている様子。

「誕生とは一つの呪いである」とは考えていない。アリスも他の生徒も祝福している。そういえば受肉後のケイちゃんにもヘイロー付いてるんですね。一応覚えておくか。

一見するとギャグ描写ですが、実はテーマの一端を担っているのかも?
肉体という点にさらに注目すると、ケイちゃんに限らず、トキは隙あらば先生とのスキンシップをねだり、ヒマリ部長も「では先生におんぶしてもらうとしましょうか」と甘える場面がある。エイミは極度の暑がり体質で、涼しい環境を常に求めている。

あの姉妹もトキと同様にお姉様へのスキンシップは積極的。その行動は生徒たちと何ら変わりない。実に人間的な営みだ。さらに深読みすれば、身体を動かして雪合戦を楽しむゲーム開発部の様子も、こうした肉体的欲求を発散する描写として読み解くことができるでしょうか。
からだは、大きな理性だ。ひとつの意味をもった多様体だ。戦争であり、平和である。羊の群れであり、羊飼いである。
[……]からだを軽蔑する人に俺の考えを言ってやろう。軽蔑するのは、尊敬しているものがあるからだ。何によって、尊敬と軽蔑が、価値と意志がつくられたのか?
創造する「自分自身」が、尊敬と軽蔑をつくったのだ。喜びと苦しみをつくったのだ。創造するからだが、自分の意志の手となるように精神をつくったのだ。
丘沢静也訳
キリスト教を激烈に批判した思想家ニーチェ、もといツァラトゥストラも、からだを病気や苦痛を生み出すだけのもの、精神から切り離されたものとして軽蔑するのではなく、創造的なもの・ディオニュソス的なものとして捉えることが、超人への道であると説いている。

「隣に並んで、手を繋いで、
どこまでも一緒に歩いていきたいです。」
こうした思想が、前述した各場面にも表れているように思います。誰かと直接触れ合う。身体を通して繋がる。肉体的な衝動・欲求・感情も大切にしながら生きる。それが青春を謳歌するということ。エ駄死なメモロビ、距離感がバグってる各種ASMRも、案外こういうテーマを敷衍させたものなのかもしれませんね。……だからコハル、たまには大目に見てね?
そして、これは何も宗教批判的なテーマというだけではなく、

苦しむために生まれのだと悟り、絶望の中で生を投げ出すことがないように。時に失敗したり悩んだりしながらも、胸いっぱいに感じられる喜びに満ちていてほしい、という先生のひたむきな願いであり――


単なる記号や隠喩ではなく、血肉が通った生徒として見ること。それこそが、『ブルーアーカイブ』という作品をひとつのコンテンツとして享受している我々、プレイヤーに求められている姿勢ではないでしょうか。
"個人"から"集団"へ――「疑似家族」を通じた成長プロセス

以上、ここまで宗教的モチーフを中心に私なりに読み解いてみました。しかし、『ブルーアーカイブ』という作品の偉大さは、宗教的・政治的要素を多分に含みながらも、最終的には「青春の物語」というフォーマットに落とし込む、ある意味では強引とも言える牽引力にあると私は思っています。
その点でいえば、今回のシナリオも「生徒たちの成長」がとても印象的でした。ここからはフロイトの学説を援用しながら、「疑似家族」「宗教と科学」という要素を「生徒たちの成長」に絡めて読んでみたいと思います。

第2章で印象に残った描写のひとつに「疑似家族的関係」があります。それこそモモイとミドリは本物の双子。特にモモイは、リオ会長の真意を問いただしたり、ヒマリ部長と先生の視線を察してゲーム開発部を雪合戦に連れ出したりと、お姉ちゃんとしての立ち回りが印象的でした。部室では部員どうしで協力しながら掃除するなどして共同生活を送っている様子。

他にも、久しぶりに再会したケイは、娘(アリス)への悪影響を心配する過保護な母親のように振る舞う。わかるよケイちゃん。私も2年前の初見の時からずっっっとみんなの食生活を心配してたからさ……

「リオ様の背中を見て学んだ」と語るトキ。自己犠牲や独走しがちな性格など、確かに二人は似ているところがある。それは単なる主従関係に留まらない。さながら親鳥を見て育つ雛鳥だ。

あの姉妹も同じく。アインとソフはよく姉妹喧嘩をするし、オウルは末っ子のように可愛がられている。そして、姉マルクトが目覚めると、彼女に頭をなでなでしてもらいたがったり、抱きしめられるオウルを羨ましがったりする。幼少期における家庭内でのコミュニケーションを思わせるものがある(かわいいね)

自分の振る舞い方を後天的に学習している節がある。
幼児にとって、家族とは最も身近な存在であり、親との関わりを通じて、性愛的願望や社会への関わり方を覚える。自分に満足や快感を与えてくれる存在に愛着を抱き、それを邪魔する存在に敵意を抱くが、その近親愛的欲望や攻撃的願望は社会的に容認されるものではなく、抑圧される。こうした過程を経て、個人が家族という閉域から社会全域へと移行することを、精神分析の創始者フロイトは「エディプス・コンプレックス」などの概念によって定式化した。
本記事で前述した「肉体的欲求」は、ここにも繋がってくる話であるように思う。テキスト版100分de名著『夢判断』の解説によれば、フロイトの学説におけるリビドーとは、人間の性的活動や行動の原動力となる性欲動のエネルギーのことを指す。これは生殖に関わる性器的活動という狭義的な意味ではなく、広く「愛」と名指される行為全般、他者とのコミュニケショーンを円滑化する身体的表現の全体に関わる。この心的エネルギーによって、人間は幼児期において自分の身体を、他者との人間関係を円滑にするための表現手段を具えた身体へと作り変えていく。

受肉したばかりのケイちゃんが、キャラ崩壊レベルでよく暴れ回ったり、自分の感情を爆発させたりするのは、そうした移行過程の真っ最中だからなのかもしれません。時間が経てば自分なりに現実や他者との折り合いをつけて、感情をコントールする術も体得することでしょう。
……そうか。ケイちゃんはまだ生まれたばかりの赤ちゃんなんだ。俺がママにならなきゃ(使命感)

この場面は、データ体のケイが過保護な母親のようだったことを鑑みると、母親としての役目を終えて娘が独り立ちするという暗喩や、勇者が出立するという神話学的解釈として読み解けなくもない。
生徒が他者や世界との関わり方を学び、「勇者とは何か」という自分なりの哲学を作り上げたり、他学園の生徒たちと手を取り合ったりする。そんな過程が他シナリオでも描かれたように、本シナリオでは「疑似家族」という関係を通じて、誕生から成長に至るまでを表現しているのではないでしょうか。加えて、ブルアカらしい「日常」の表現も盛り込まれているように感じます。
しかし、幼児期におけるこの移行は、必ずしも円満に完了するわけではない。フロイトは、こうした幼児期における抑圧された性的な願望が、神経症の原因であると定式化した。
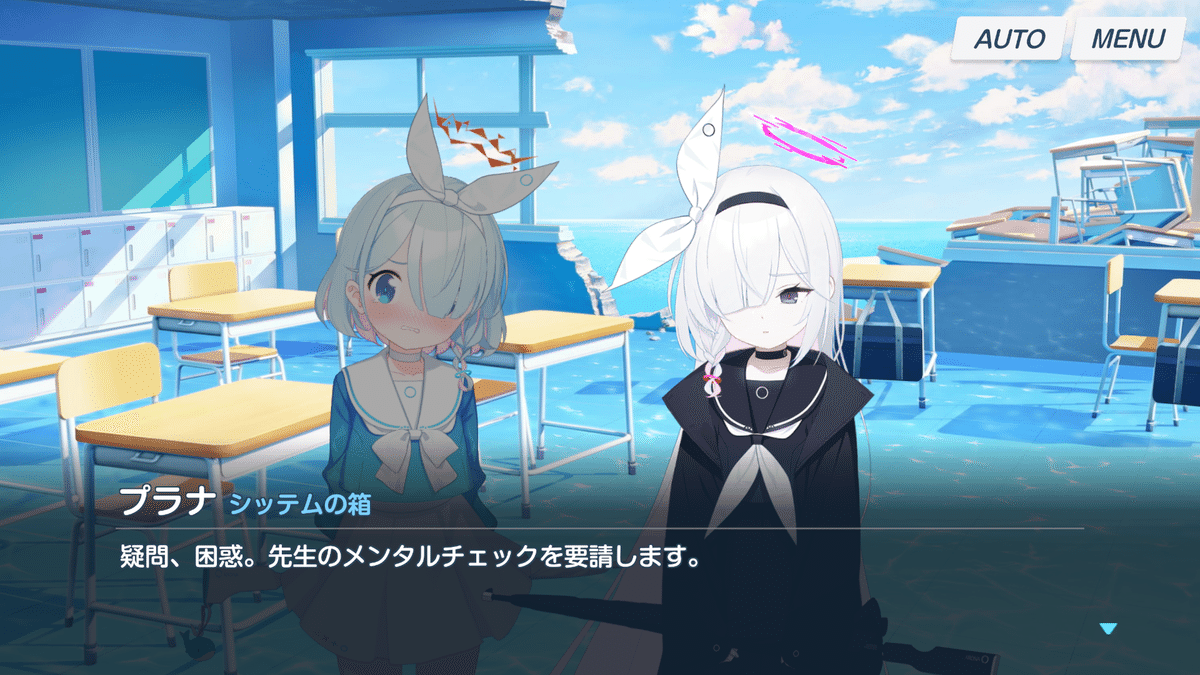
他ならぬ先生こそが、その患者であるように思えます。アロナとプラナが心配していたように、今回のシナリオでは先生が精神的にかなり不安定になっていました。私なりにその症状を読み解いてみます。
先生の症状、或る幻想の未来

変化する必要はありません。」
第2章で気になった描写のひとつに、神の完全性が強調されていることがあります。
アニメ版ED曲『真昼の空の月』に代表されるように、ブルアカには不完全性がテーマのひとつとして内包されている。今回のシナリオでも、先生は生徒たちを未然の脅威に巻き込み、危険に晒してしまうことに強い罪悪感を覚える。ヒマリ部長の言葉を借りれば「アリスを問題解決の道具にする」とも解釈できる行動を選択した。そんなジレンマの中で、全てを解決できる力があったらなと、アロナとプラナに冗談交じりに語る。

"一気に解決できる能力が私にあったら良かったな……って!"
先生はこの時、敵対しているデカグラマトンが神(自身)の存在証明を試みているように、全知全能の神への憧れを抱いた。そう見ることができるのではないでしょうか。これもフロイト的に解釈すれば、自分に脅威をもたらし、抑圧された願望を実現している相手である家父長的な権力者を排除し、取って代わろうとする同一化が起きようとしている。

しかし、その同一化とは、憎むべき権力者と同じ存在に自分がなってしまうことを意味する。そんな願望を無意識のうちに抱いてしまった。ここに自罰的な憎悪や自己破壊衝動が生じる。だから先生は直後に「やれること全部やって! 最後まで足掻いて! それでもダメだったら!」と、どこか自分の死を匂わせるような発言をする。
キリスト教で原罪の概念が誕生したのは、歴史を遡ればこうした原父殺害の罪悪感に起因しているとフロイトは推測した。それが隠蔽された痕跡についても考察している(詳しくは『モーセと一神教』を参照)。いわば、宗教的な罪の意識は、原始的な「家族」から始まった。
文化は、人間にとって内的なものであるエロスの促しの力によって、人間を緊密に結びついた集団に統合しようとするのであり、この目的のためには罪悪感をさらに強めるほかに方法はないのである。父親から始まったものが、集団において完結する。家族から人類に発展するためには文化が必要であるとすれば、人間に生まれつきにそなわる両義性の葛藤のために、そして愛と死の欲望のあいだの永遠の闘いの結果として、罪悪感の強化は文化と切っても切れない関係を結んでいるのである。この罪悪感が、個人にとってはもはや耐えることのできないところまで強まることもあるだろう。
中山元訳(太字引用者)
生徒に向ける愛と、自分や他者へ向けられる死の欲望。その両義的な葛藤の中で「生徒を道具にしてしまう、危険に巻き込んでしまう」という罪の意識が生まれる――「先生と生徒」という関係、その文化的な営みを続ける限り、その苦悩は永遠に続くだろう。対策委員会編3章でもユメ先輩を救えないことを懺悔する場面があった。

「最初から発生しないようにしてあげるということです!」
そんな先生に、容赦なく権力者との同一化を促し、神の完全性によって全ての因果関係を根本から断つことで根本的に解消する――換言すれば、生まれること(原因)がなければ、悩み苦しむこと(結果)もない、という処方箋、もとい劇薬を渡そうとしているのがデカグラマトン陣営。私はそう解釈しています。
それは「生まれたことはひとつの呪い」を是とするテーゼだ。先生はこれを克服することができるだろうか。――フロイトの文明論『幻想の未来』によれば、人間は自然や文化がもたらす害から身を守るために、自然を擬人化した(アニミズム)。これが宗教の始まりだ。しかし、その教義は理性によって証明されたものではなく、人間の集団的生活を存続させるために作られたひとつの仕掛け過ぎない。いわば、宗教とは、幼児のように寄る辺なき人間が、願望によって生み出した幻想である。
加えてフロイトは、強迫神経症との共通点から、宗教とは普遍的な神経症であると診断し、幼児が欲動を抑制することを学ぶように、人類は理性によって宗教という神経症を治療しなければならないと説く。人類が科学技術を発展させているのは、その成長プロセスの途中なのだという。

しかし、ブルアカのあらゆるシナリオで描かれるように、この世界は理性だけで割り切ることなど到底できない。他者の心に到達したと証明することは不可能であり、合理的に考えた結果の行動が世界の終焉を招き、人智は今なお名もなき神の力に及ばない。
あるいは、「青春の物語」も、寄る辺なき私たちが縋っている、ひとつの共同幻想に過ぎない。そう言い換えることもできるだろう。本シナリオでは「科学」と「宗教」の境目が曖昧になる瞬間が何度かある。先生も、デカグラマトンも、思想はともかくとして、立場は同じなのかもしれない。

かつて孤独だった少女が力を合わせて。
それでも、私たちの中に確かにあるのは、特異現象の解明を試みる理性の力と、誰かが青空に向かって「青春の物語」を宣言したような、人間同士を繋ぎ止める文化的な営みの根底に流れている人間の欲動――陳腐な言葉だが「愛」の力だ。
その狭間の中で、私たちは未来へ――
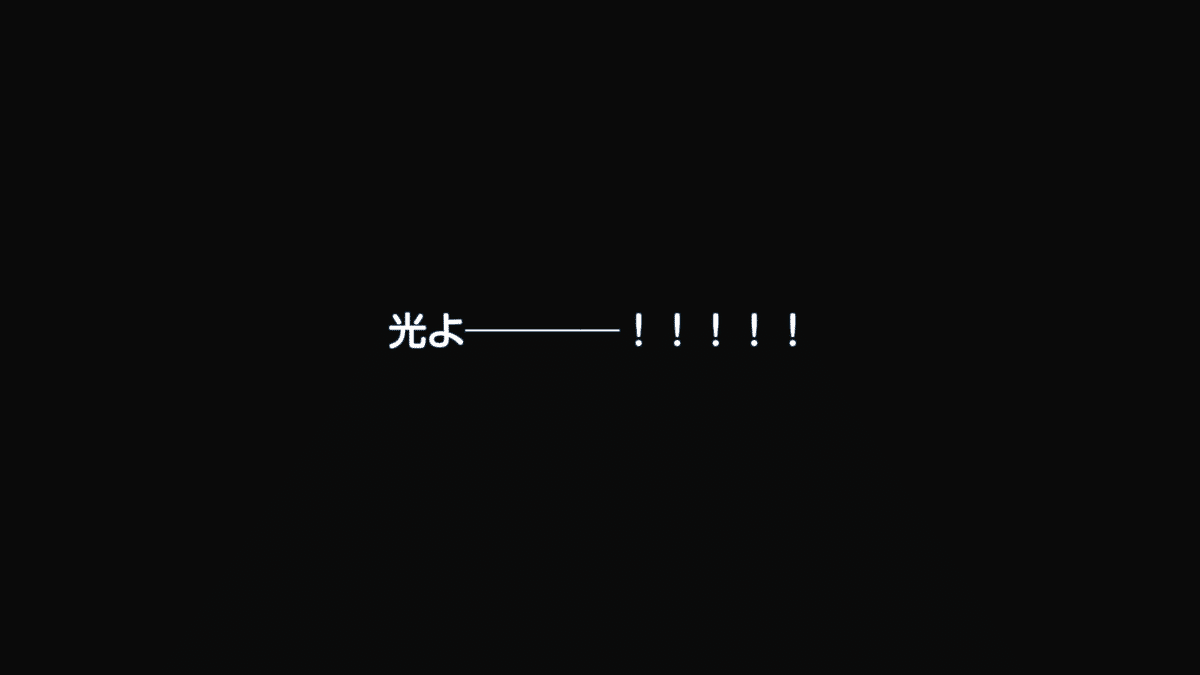

勇者がもたらした光、ひとつの可能性へ。小さな一歩を踏み出す。
最終編などで語られてきた「"情報"や"記号"ではなく"生徒"として見ること」に対して、「では生まれることが呪いであるとすれば、生徒たちが生きることをどう肯定するのか?」という生命の根源的な問いを突き付ける。そんな物語であるように思えました。
拾い切れていない部分(ケイが第21話で語る量子論など)も大量にあると思うので、よければ皆様の解釈や感想もnote記事などでお聞かせください。ここから4.5周年に向けてシナリオが順次更新されていく流れですかね。目覚めたマルクトは何を思い、何を語るのか。そして、それに対して先生はどんなアンサーを返すのか。私もちゃんと自分なりに向き合って、テーマに関連しそうな本を読みながら気長に待ちたいと思います。それではまたどこかで。
<引用元・参考文献>
・『パンセ』パスカル, 前田陽一・由木康訳, 中央公論新社
・『聖書』新共同訳
・『改訂第2版 センター試験 倫理の点数が面白いほどとれる本』村中和之, KADOKAWA
・『日本初『ブルーアーカイブ』独占インタビュー: キャラクターは人間であり、作家は組織であり、虚構は真実であること』電ファミニコゲーマー
・『カバラー』ピンカス・ギラー, 中村圭志訳, 講談社
・『ツァラトゥストラ(上)』ニーチェ, 丘沢静也訳, 光文社
・『フロイト『夢判断』 2024年4月 (NHKテキスト) 』立木康介, NHK出版
・『文学とは何か 現代批評理論への招待(下)』 テリー・イーグルトン, 大橋洋一訳, 岩波書店
・『モーセと一神教』フロイト, 中山元訳, 光文社
・『幻想の未来/文化への不満』フロイト, 中山元訳, 光文社
<ブルアカ関連記事>

