
"シスター"と"悪い子"の狭間で――『Serenade Promenade』の伊落マリーについて【ブルーアーカイブ】
罪を犯してはならないと言うときほど、自分の神に不誠実であることはない。
中山元訳
ブルアカの新イベント『Serenade Promenade』を読んだ。巷では、本シナリオにおける伊落マリーについて、賛否両論や「解釈違い」の声が巻き起こっているようだ。
その原因のひとつに、冒頭の場面における「伊落マリーがカタカタヘルメット団に銃を突きつけてバイクを奪う」という行動がある。この描写について、「本来は温厚な性格であるはずのマリーが、"清楚なシスターが銃を突きつける・バイクで爆走する"というギャップやギャグ演出のために、意図的に性格を捻じ曲げられてしまった」というような声をいくつか見かけた。
しかし、あくまで個人の感想ですが、私は本シナリオで伊落マリーという生徒がないがしろにされたとは思っておらず、むしろ平和や心の安寧を願う祈り手である彼女が必然的に直面する倫理的問題や葛藤を深化させていたように感じました。以下、キリスト教における平和主義・非暴力主義の問題や祈りの考え方などを基に、私の感想をまとめてみます。
(※メインシナリオ、伊落マリー絆・愛用品ストーリーのネタバレも含みます。未読の方はご注意ください)
バイク奪取――平和主義者の現実
まず冒頭のバイク奪取の描写について。この行動には重要な前提がある。「トリニティ総合学園の内戦勃発を防ぐために、現場に急行しなければならない」という使命をマリーが自身に課していたことだ。
トリニティにおける内戦勃発はどれほどの危機をもたらすのか。エデン条約編2章1話のミカによれば、そもそもトリティ総合学園は、多数の分派による紛争を調停する「第一回公会議」によって誕生した学園だ。その後も、公会議後に異端視されたアリウス派は弾圧され、今もなお、パテル派・フィリウス派・サンクトゥス派を中心に派閥争いが続いている。

トリニティの歴史に内戦あり。サクラコ様とミネ団長の対立の噂に尾ひれがついて急速に広まったのは、こうした現在進行形の歴史的事実も背景にあったことだろう。些細な争いがきっかけで、あの紛争の歴史が繰り返されかねない。万が一の可能性がある。トリニティの生徒にとっては決して楽観視することができない、切実な問題だ。

迷いや葛藤を抱いていることが窺える。
マリーの固有武器の説明には「実際に撃つところを見たという声はほとんど聞かない」とあるのだから、彼女が安易に銃を抜くはずがない、という意見がある。しかし逆に言えば「マリーが銃を抜かなければならない、悪事に手を染めなければならないほどの差し迫った状況であった」と解釈できる。サクラコ様と連絡が取れないため真偽を確かめることができず、一分一秒を争う事態。他に思いつく手段も無かったのだろう(結局、サクラコ様とミネ団長の対立は誤解だったわけだけど)
何にせよ、普段のシスターとしての彼女であれば絶対にしないだろう。バイク奪取はあくまでも「より多くの人を救うためにやむを得ず」という利他的な動機からの行動である。

もう少しマリーの心情を見てみると、「私のせいです」と彼女は述べている。そして「……どうか、私の罪をお赦しください」と、自分の行動が罪であることを自覚しながら実行に移っている。自分のせいでこうなってしまったのだから、自罰の意味も含めて、罪や労苦を自ら背負わなければならないと考えていたのだとしたら、それは敬虔な信徒であればこその誠実な思いから生じたものだろう。
とはいえ、功利主義的な大義名分があるからといって、あるいはカタカタヘルメット団が善良な生徒を人質に取るような悪党だった(第3話)からといって、銃をつきつけて脅すようなことをシスターがしてもよいのか? それでは自分自身が悪党になるのと変わらないのではないか? そうした指摘はもちろんあって然るべきだ。
しかし――
キリスト教会も所詮は人間の集まりなので、世界には、口では綺麗事を言いながら、実際には攻撃的で暴力的な態度をとる人もいる。あるいは、たまたま平穏で恵まれた生活環境に生きているからこそ、感傷にひたりながら優雅に平和主義を主張できるという人もいるだろう。また、正当防衛として条件付きで武力行使を認めると最初から明言している人たちもいれば、正当防衛のみならず、先制攻撃を支持する人たちもいる。さらには、大勢の命が脅かされている壮絶な状況下で、暴力を「悪」とわかっていながらも、あえてその罪を犯すしかないと苦悩した人もいる。
同じ信仰のもとに生き、同じように愛と平和を祈っているように見えても、現実的な振る舞いとして選び取られる選択はさまざまである。それぞれが、自分のやり方こそ正しいと思い込み、あるいは、正しくはないがその状況ではそう振る舞うしかないと考える。互いに批判したり批判されたりしながら、困難な現実のなかでどうにかやっていこうとするのが、キリスト教徒たちの現実であり、人間の現実なのである。
(太字引用者)
たとえば愛する者たちに危機が迫っているのに、それでも悪事を避けたり、平和主義・非暴力主義を貫いたりすることは正しい行動だろうか。その場合、敬虔なシスターとして健全に振る舞うよりも、社会的な悪を成す方が正しいのではないか――現実にはそうした倫理の崖っぷちのような状況が多々あり、そして、それに対する選択や思想も実に多様である。
歴史では正戦論の議論が繰り返されている。新約聖書では「右の頬を打たれたら左の頬をも向けよ」と非暴力主義を説いているが、聖書中心主義のルターは同じく新約聖書の『ローマの信徒への手紙』13章の記述を元に、暴動を起こす農民は狂犬も同然であり、打ち殺さなければならないという見解を示している。いかなる時も非暴力主義を貫徹すべきとする立場がある一方で、そうして悪を放置するのは無責任であるとする立場もある。絶対的な正解はない。愛と平和を説く同じ宗教を信奉する者の間でも思想に相違がある。

固有武器装備時の台詞は「あまり、武器は使いたくないのですが……平和のためでしたら」。あまり武器は使いたくない。しかし同時に、武力行使が時として必要になるという現実も、彼女は承知しているのだろう。
愛と平和を説く敬虔な信徒であればこそ、清廉潔白な理想をただただ唱えるだけではなく、そうではない凄惨な現実を直視し、「いかなる状況でも社会的悪を成さないことは正しいのか」といった倫理的な命題に積極的に応答しなければならない。
そして今回マリーが行動で示したのは――愛する者を守るためであれば、いざという時に自分の手を汚すことを厭わない。たとえそれが、平和を祈りながらも悪事に手を染める、欺瞞的な行為であったとしても。理想と現実に板挟みになり、ジレンマを抱えながらも自分なりに最善を尽くそうとする、その切実な強い覚悟が、一連の描写には詰まっているように思う。

マリーも今後同じことが起きないように努力するだろう。
「心」に向き合う祈り手
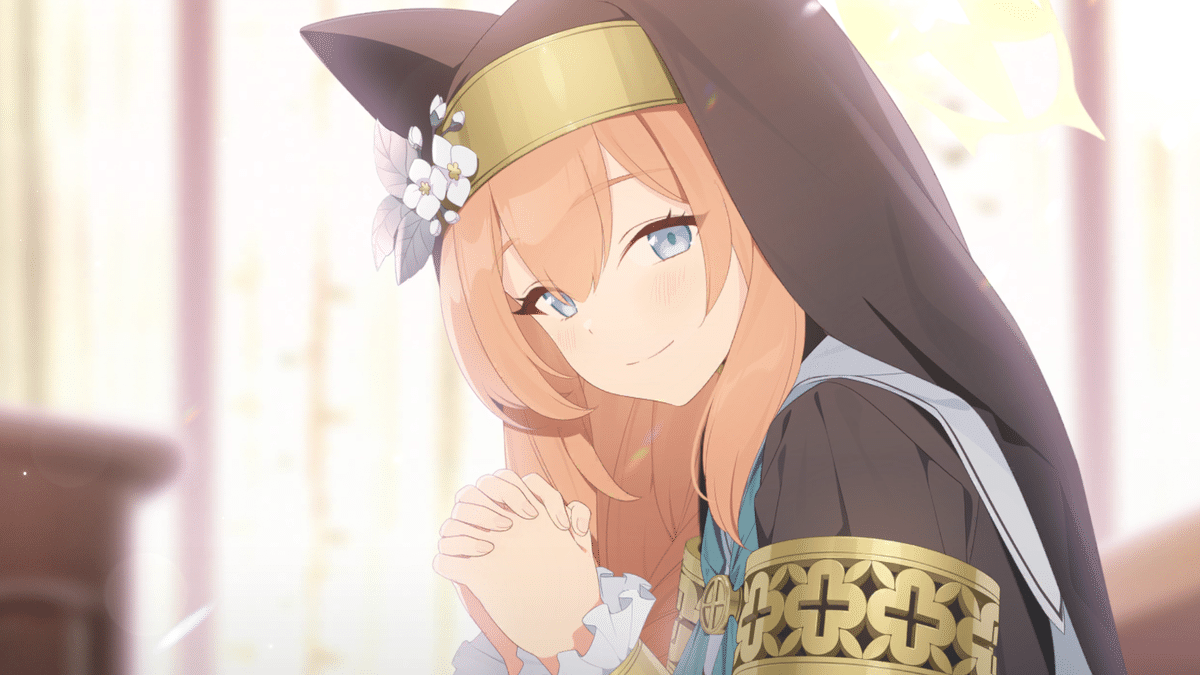
話は少し変わるが、マリーといえば聖堂で祈りを捧げるメモロビが印象的だ。現代人の感覚では、祈りとは単純に「心」を込めた行為であればいいように思える。
しかし、『神を哲学した中世』(八木雄二著)によれば、中世ヨーロッパにおけるキリスト教信仰は、「心の姿」というよりも、「一定の秩序を守った祈りの行動」であった。たとえ自分の心の中では神に向けた真剣な祈りであろうとも、教会が定めた秩序に従い、司祭のもとで行わなければ、神に通じないとされた。それどころか、教会の秩序に反する祈りは信仰そのものに反する、神に反抗するものであるとする見方もあった。
歴史が示している通り、こうした思想は外面だけを取り繕う形式主義に陥りやすい。新約聖書の『ローマの信徒への手紙』において、パウロは表面的・形式的に律法を守ろうとする律法主義を厳しく批判し、人は行いではなく信仰によって義とされると説いた。また中世後期においても、贖宥状の販売や聖職の売買が行われた教会の腐敗に対して、ルターも「信仰のみ」(信仰義認説)を説き、宗教改革の端緒を開いた。

ウタハ先輩曰く、アイドルにとって大事なのは「心」。皆それぞれ、気持ちを言葉に乗せて、感情を伝える。
今回のアイドルユニット結成は、救護騎士団やシスターフッドが抱えるマイナスイメージを払拭するためであった。しかし、煌びやかな衣装で外面を取り繕って歌って踊るだけでは、観客の心を動かすことは叶わないだろう。「嘘はとびきりの愛なんだよ」とは言うが、愛がなければ薄っぺらい嘘にしかならないとも言える。

"正直に答えてくれると嬉しいな。"
自分の本当の「心」に向き合うこと――Antique Seraphim参入の提案を断り、二人のステージ成功を祈るという選択もあっただろう。しかし、「本当は自分もアイドルをやってみたい」という気持ちに向き合わず祈ることは、それこそ形ばかりの祈りではないだろうか。

絆ストーリーにおいても、マリーはシスターとして誰かに奉仕する存在であることを理想に掲げながらも、同時に、シスターにはふさわしくない気持ちを自分が抱いているという悩みを打ち明ける。最近実装された愛用品ストーリー「本当の気持ち」においても、質素倹約を心がけなければならないのに「可愛いから」という理由でコサージュを買ったこと、それをごまかすために先生に嘘をついてしまったことを懺悔する。

絆ストーリー1話
シスターにふさわしくない部分から目を逸らさない。またその贖罪を外部装置に担保せず、自分自身の「心」に真正面から向き合い、罪の感覚を抱きながらも、立派なシスターであろうと誠実に努力する。先生の言葉を借りれば、そんな心意気を抱ている彼女は立派なシスターだ。
形だけに囚われず、自分の心に向き合って祈ること、心を込めて歌って踊ること。形だけのアイドルでは指導者は務まらない。Antique Seraphimにとっては、誰よりもアイドルに憧れていた「心」の持ち主であるマリーの参入こそが、パズルの最後のピースだったのだろう。

(エデン条約編2章2話)
そして、これまで絆ストーリーや今回のイベントで描かれてきた「自分の心に向き合う」という彼女の行動が、エピローグで結実する。
仮面――"悪い子"を自覚しながら

仮面を被っていても、先生はすぐに気づいてくださるのですね。」
ステージ後、マリーは仮面を被って先生のもとに訪れる。そして仮面を外して、隠していた思いや悩みを打ち明ける。素直に読み解けば、この描写はシスターという社会的な仮面を剥いだまっさらなマリーであることの暗喩だろう。偶像ではないマリーとも言い換えられる。
マリーは今回の謝肉祭を通して「先生と一緒に過ごしていると、自分でさえ知らなかった部分が見えてくる」と気づいたと語る。実際、この後のマリーは、普段の温厚さからは想像できない行動を見せる。

写真をいきなり破いて捨てるわ、サクラコ様に圧をかけるわ、

先生にはこっそり写真を渡して、二人だけの秘密を作るわ。

……まあマリーの尊厳のために言っておきたいのは、この写真、何かと"煽情的"なんですよね。サクラコ様は純粋に「素敵な写真」「可愛らしい」と思ったようですが、マリーにとってはかなり恥ずかしかった様子(ミネ団長も「サクラコ様も悪気があるわけでは……」と何となく事情を察したっぽい)

写真を破り捨てた件についてはその少し前に、先生の前ではズルいことをしてしまったり、甘えたがったりと、"悪い子"になっている自分を自覚している。もちろん一概に"悪い"とは言えず、年相応の可愛らしい言動ばかりだ。
これまで、ブルアカでは「私とは何か」という実存的な問いかけが何度も出てきた。エピローグにおけるマリーの言動もその延長線上にあるように思う。前述したように、マリーは謝肉祭での活動を通じて、自分でさえ知らなかった部分を見つけた。いわば"自分という存在の再発見"があった。

(絆ストーリー4話)
それに対する先生のアプローチは、常に「そういう自分がいてもいいんだよ」という旨の言葉だった。そんな先生の言葉があったからこそ、マリーはシスターにふさわしくない自分の部分も殊更に露悪的に捉えず、受容しながら、前に進み続けることができたのだろう。

「明日から、またシスターに戻ります。」
"シスター"としてのマリー、"悪い子"としてのマリー。どちらが本当のマリーなのか? ――きっと、どちらも本当のマリーだ。私も先生としては、やはりどっちの自分がいてもいいんだよって伝えてあげたいし、「生徒がなりたい自分になること」を応援したい。
総じて、「バイクを奪取する」「写真を破り捨てる」といった結果や形だけにこだわれば、確かに今までとは全く異なる"悪い子"としてのマリーがいる。しかし、彼女がその行動に至った過程を丁寧に追っていくと、倫理的な問題、理想と現実、私心の中で葛藤を抱きながらも、務めを果たそうとする"立派なシスター"としてのマリーがいる。"シスター"と"悪い子"の狭間で揺れ動く波のような存在としての"伊落マリー"。それはこれまでの絆ストーリーでも見られた彼女の素行に重なるように思う。
更に、神の御前では隠された被造物は一つもなく、すべてのものが神の目には裸であり、さらけ出されているのです。この神に対して、わたしたちは自分のことを申し述べねばなりません。
新共同訳
そうして包み隠さずに自分に向き合いながら「心」を込めて祈ることこそが、祈り手であるマリーの信仰のあり方であり、生き様なのだろう。神の御前に裸身で祈り、自分のことを申し述べる。そこには何となく、宗教改革の精神や、人間性を再発見するルネサンスの精神すらも見出すこともできる。

この方も仮面が剥がれた姿を見れたと言えるか。
以上、感想でした。解釈は人それぞれ。何かしら参考になれば幸いです。
蛇足になるので端折りますが、シナリオ全体の感想としては、短いながらも軽いサクッとした食感で楽しめました。後日談も充実しており、かわ、こわーい放課後スイーツ部を拝めたり、久しぶりにティーパーティーのやり取りも見れたりと満足。なんか初期のイベントっぽいドタバタした雰囲気で微笑ましかっ――

……ごめん、奥空アヤネさんが眼鏡かけてないのやっぱつれぇわ。でも可愛いからOKです❗❗ それではまたどこかで。
<ブルアカ関連記事>
参考文献・引用元:
『善悪の彼岸』ニーチェ, 中山元訳, 光文社
『キリスト教と戦争』石川明人, 中央公論新社
『神を哲学した中世―ヨーロッパ精神の源流―』八木雄二, 新潮社
『聖書』日本聖書協会

