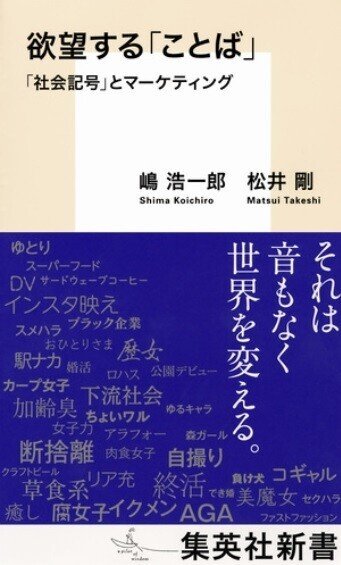『ことばとマーケティング 「癒し」ブームの消費社会史』
【マーケティング定番書籍】その21
『ことばとマーケティング 「癒し」ブームの消費社会史』
著著:松井 剛
出版社:碩学舎
第1刷:2013年3月25日
1. 本書を読んだ背景
一橋大学教授の松井剛さんと博報堂ケトル嶋さんの共著(『欲望する「ことば」』)の記事は、2020年9月に書きましたね。
今回ご紹介するのは松井剛さん渾身の学術書籍で、値段も4,000円弱、読みごたえ十分です。
松井先生の代表作と思ったので躊躇なく購入し読んだ本書でしたが、テーマの「癒し」についてはあまり興味がなかった、といいますか、少々ナメていました。
「あ、癒し? 2000年代のコンピCDだとEMIの『feel』、sonyの『image』、BMGの『flow』あたりでしょ?」みたいな。でも、二度も読むと「癒し」をテーマに選ばれたこと、よく納得できました。
2. どんな人に向いているのか?
本書はもちろん、実務書ではなく研究を目的とした学術書です。ですので、ノウハウ的なものを求める方は見向きもしない、というかそもそも“縁”がありませんよね。書店でもWeb空間でも。
では、本書を読んでどんなことがわかるのでしょうか?
それを私は、“ブームの構造”と呼ぶことにしましょう。経済、社会、時代、生活者、企業、マスコミ。このうち、企業、マスコミの2社にフォーカスを当ててます。
そして、分析の対象、それは“空気”です(笑 どうです? 興味持たれましたか? 「はじめにニーズありき」というお考えのリサーチャーの皆さんには無用ですね(笑 もちろん、私のような文化マーケティングの人間にとっては、バイブルの一冊となります。
「文化とは深層」、ですので、深層を押さえておく必要がありますんで・・・。
3. 本書のポイントと感想
3-1. 導入部で改めて私が感じたのは、松井先生のマーケティング観です。私を含め、ほとんどのマーケター、マーケティング・リサーチ関係者がいかに“マーケティング進歩史観”に毒されているか、思い知らされました。「毒されている」というのはきつい言い方ですけど、マーケティングリサーチの実務を通して、割と実感させられることが多いですね。ここでは本題ではないので、これ以上、ここでは書きませんが・・・。
3-2. ボリューム満点の力作なんですが、結論はわかりやすくシンプルにまとめられています。「癒し」ブームとは、消費者ニーズが唯一の起点としてあったわけではなく、企業による集合的なマーケティング努力やメディアによる言説を通じて強化された、消費者ニーズを創り上げるメカニズムというわけです。
3-3. 最終的なまとめとしては、「創造的適応」ということになるんですが、「創造的適応」とは、ぶっちゃけ「消費者ニーズを創りだす」(石井淳蔵先生)ということになるんですね。そのメカニズムを研究されたのが本書なわけです。「言説」「行動」「意味」の3項関係という理論的枠組みで。
以上です。
「やる気のなさそうなサインだなぁ・・・」と思てたんですが(@下北沢「本屋B&B」)、よくよく見るとお書きになるのに慣れてないだけで、練りに練られたサインですね(笑

松井剛こと「まつたけ」。椎茸が嫌いな私でも松茸は大好物です!
椎名先生じゃなくって良かったなと(笑
◆デスクリサーチ資料はこちらです(↓)
◆ホームページはこちらです(↓)