
『Deep Dive』して、プロダクトを磨き上げる
こんにちは。リンクアンドモチベーションでUXデザイナーをしている辻井です。会社として、3ヶ月サイクルでチームの目標や方針を定める文化があり、今日は今期のテーマについて書いていきます。
直面していた壁
先期は、過去最多のメジャーリリースを行い、開発チームとしての出力を大きく高めることにチャレンジしました。決して大規模なチームではないのですが、職種間の連携を深めることで、アウトプットの目標はしっかりと達成することができました。
一方で、各リリースに対して定めていた「アウトカム目標」の結果は、決して芳しいと言えるものではありませんでした。機能ごとに「解決する課題」や「実現したい状態」を定めているのですが、課題が解決されていなかったり、そもそもユーザーに利用されていなかったり、という状況だったのです。
「機能追加・改修を積極的に行うことで、プロダクトをどんどん進化させよう」という狙いがありましたが、結果としては成果はアウトプットまでに留まり、アウトカムに届いていなかった。この課題を解決するべく、今期のテーマを定めました。
ユーザーの深層に"潜る"
掲げたテーマは「Deep Dive」。ユーザーへの理解を深め、思考・感情・行動への解像度を高め、ユーザーが本当に困っている課題を解決しよう、という決意を込めました。プロダクトをつくる上で何よりも大切なこの原点に立ち返って、付加価値の高い開発をしよう、という方針です。
この方針に沿って、チームとして変えることを3つ定めました。
①「妄想ドリブン」→「事実ドリブン」
これまでの自分たちの取り組みを振り返った時に、
「"きっと"ユーザーはこう感じている」
「この課題に一番困っている"はずだ"」
というように、インサイトに自分たちの思い込みが混ざり込んでいたことに気付きました。ユーザーのことを何よりも大切に考えているつもりでしたが、いつの間にか「自分たちにとって都合の良いユーザー」の虚像をつくり上げていたのです。
そこで、今期はとことん「事実」に基づいて、ユーザーへのインサイトを深めることにしました。定量的な利用データと、定性的なインタビューデータを組み合わせながら、ユーザー像のリアリティを高めていっています。
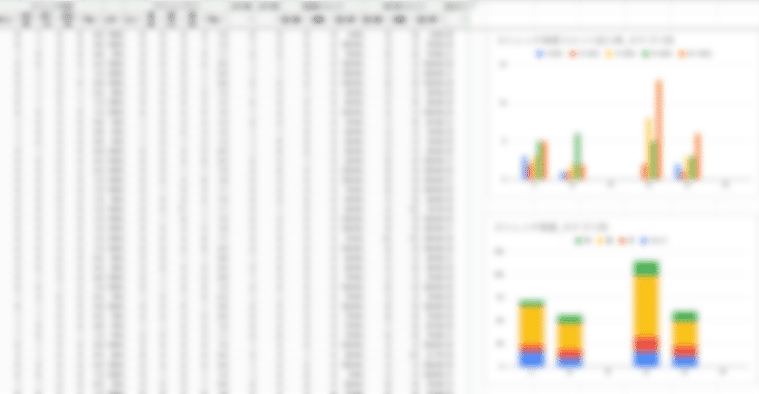
②仮説構築の主体を「個人」から「チーム」へ
これまでは、リサーチャーがインタビューに基づいて課題仮説を立てたり、エンジニアがデータを見ながらユーザーの行動を類推したりと、個人で仮説を組み立てる構図になっていました。結果として、各自がアクセスできる限られた情報をもとに、一個人の主観・バイアスの影響を大きく受けた状態で仮説が構築されていました。
今期からは、仮説が具体化されて形になっていく前から、チームでディスカッションする時間を多く設けるようにしました。2~3時間のロングMTGを押さえて、事実の棚卸しから一緒に進める形式で、『もくもく仮説タイム』と名付けています。

一見すると非効率的にも見えますが、多角的な視点から検討を進めるメリットは大きく、仮説の量と質をともに向上させられている感覚があります。職種横断での議論が活発になることで、開発チーム内の風通しもさらに良くなりました。
③仮説を「リリースして検証」ではなく、「開発前に検証」
これまでも、開発前の段階で仮説の整理を行い、優先順位を付けながら開発を進めてきました。しかし、先述した「アウトプットできても、アウトカムまで届かない」要因は、この開発前の検証の粗さにあると考えました。
「ユーザーが実際にどう動くかは、リリースしてみなければ分からない。スピーディーにリリースして、価値を検証しよう」という原理原則に、囚われすぎていたのかもしれません。リリースしなければ分からないこともありますが、リリース前、もっと言えば開発に着手する前の段階でも、仮説の精度は向上させられるはず。
そこで、「事前の検証が甘く、結果として70点のリリースをする」くらいであれば、「事前の検証に多少時間がかかったとしても、120点の成果を生み出すリリースをしよう」とアプローチを変え、開発前の仮説検証に大きくリソースを投資しています。もちろん、120点が約束されたリリースなど存在しないので、一定の不確実性を残して開発に入ることにはなりますが、ベースとしての考え方・進め方の転換を試みています。
さいごに
まだ、新しいフォームにチャレンジして1ヶ月程度なので、このチャレンジがどう結実するかはまだ分かりません。ただ、プロセスやマインドを変えたことで、「ユーザーとの距離感」や「仮説の精度」が変わってきた手応えを感じています。
大きな価値を生み出せるように、試行錯誤を積み重ねていきます。
