
【直木賞受賞作】今村翔吾『塞王の楯(さいおうのたて)』冒頭70ページ無料公開!!
今村翔吾『塞王の楯』
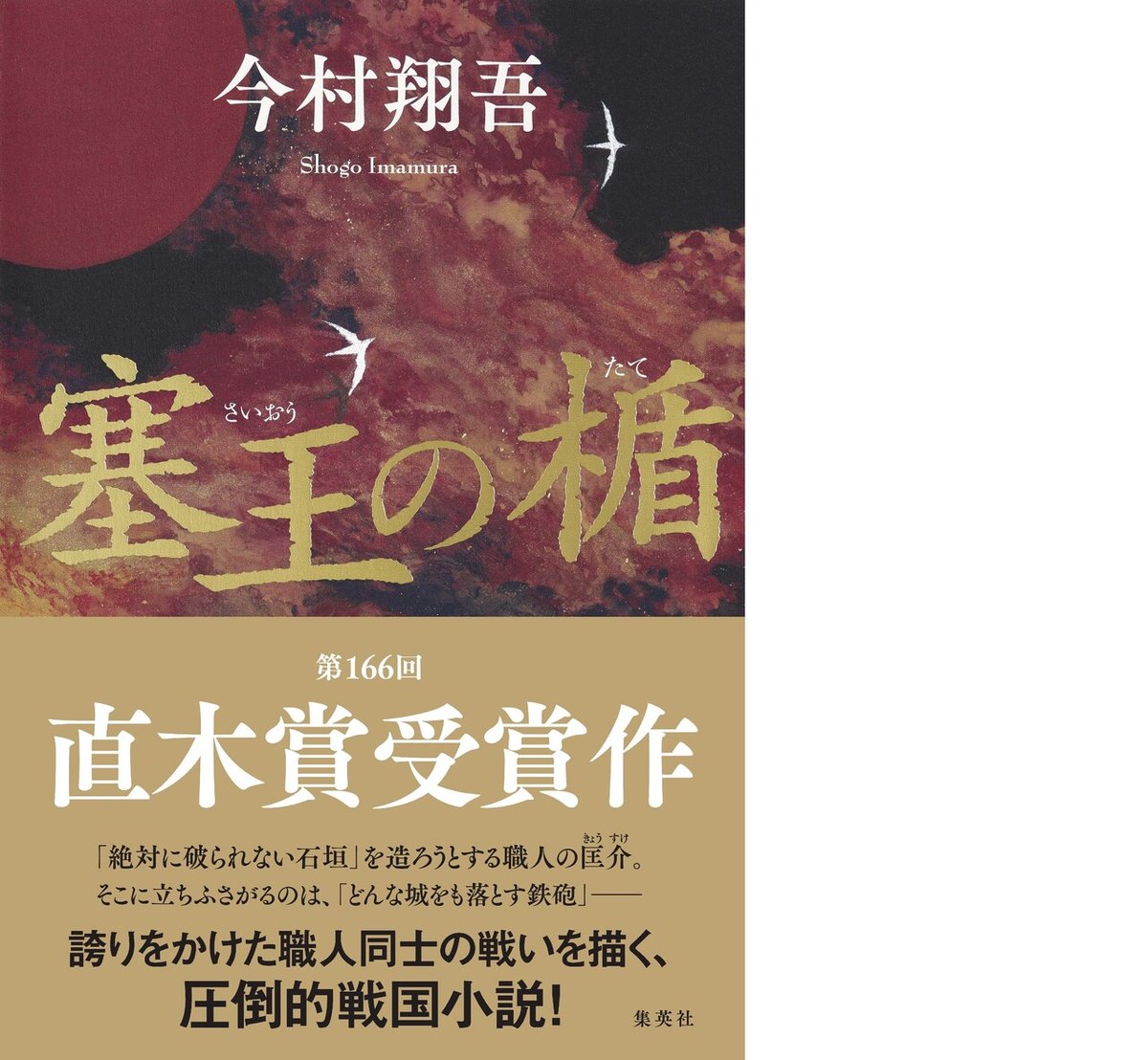
序
男の嘆き、女の悲鳴が町中を覆っている。まるで町そのものが慟哭しているようであった。
皆が我先にと入り乱れて逃げ惑う。親とはぐれて泣きわめく幼子に見向きもしないなどまだましというもの。老婆を突き飛ばしてその背を踏み越える者、娘を蹴り飛ばして道を開こうとする者。このような時、人は人であることをやめるらしい。
「諦めては駄目!」
母は骨が砕けんばかりに強く握って手を引く。こうでもしていないと、とっくに恐慌する人々の群れに吞み込まれて離れ離れになっていたに違いない。一乗谷にはこれほどの人が暮らしていたのかと驚く。もう秋だというのに人が擦れた熱で、躰は激しく火照り、息も出来ぬほどに苦しい。
「どこに――」
言いかけた時、追い越した男の肘が頰に当たり、声が途切れた。
「お城に」
母はそれに気付かずに、館の背後に聳える山城を見上げた。
一乗谷城と呼ばれるこの城が、陥落したことはこれまでない。こう聞けばさしも名城と思いがちだが実際はどうだか判らない。この城が戦で使われたことは、ただの一度もないだけなのだ。
越前での朝倉家の威勢は強く、一揆程度なら一乗谷に迫るまでに鎮圧されてきた。この地は朝倉家によって、百年の安寧が保たれてきたのである。
そんな一乗谷が騒然となったのは今日の夕刻のこと。朝倉家の当主、義景は二万の大軍を率いて盟友である浅井家の救援に向かっていた。それが這う這うの体で戻って来たのだ。兵はどの者も酷く窶れ、目の下に墨を塗ったような隈を浮かべ、眼窩は窪んで奥に怯えの色が窺えた。躰に矢が刺さったままの者、兜を失って髪を振り乱した者。まるで白昼に幽鬼が現れたかと見間違うほどである。
そして放たれた一言によって、一乗谷は戦慄した。
――間もなく織田軍が踏み込んで来る。
浅井家への救援が失敗し、朝倉軍は逆に追撃を受けた。越前の最南端である疋田城で踏み止まろうとしたが、そちらも猛攻を受けて陥落したとの報が入る。義景は行き先を変えて本拠一乗谷への撤退を決めた。
その間も織田軍の追撃はさらに苛烈を極め、重臣忠臣の多くが刀根坂で討ち取られ、ここまで戻った兵の数は五百にも満たないというのだ。
百年の平和というものは、人を弛ませるには十分だった。現実とは思えないのか、初め一乗谷の民はどこか夢の話を聞くような顔をしていた。しかし遠くから鬨の声や銃声が耳に届く段となり、民もようやく夢から覚めたように慌ただしく動き始めた。家財を纏める者、着の身着のまま逃げ出す者、まだその段になっても、
――お城があるから心配ない。
と、余裕を見せていた者も少なからずいたのも確かである。
織田軍が踏み込んで来たのはそれから僅か一刻(約二時間)後のこと。兵のみならず民も容赦なく襲われた。動くものあれば犬さえも撫で斬りにせん勢いに、町は蜂の巣を突いたような騒ぎになった。民は羅刹の如く振る舞う織田軍に追われ、北へ北へと逃げ出した。
初めは父母と二つ年下の妹の花代の家族四人で逃げていたが、芋を洗うような混雑の中、途中で父と花代とはぐれた。押し合いへし合いする肉の壁の狭間から、顔を涙に濡らしながら救いを求めて手を伸ばす花代を見たのが、最後の姿となっている。
「花代は……」
「心配ないから」
振り返ろうとしたが、母は一層強く手を引き人の隙間に、身を捻じ込むように進む。
一乗谷とはその名の通り渓谷の盆地に造られた町。町の外へ出ようと思えば南北二つのどちらかの道を使わねばならない。南の道からは織田軍が肉薄し、さらにそれよりも早く焰が追いかけて来る。皆が北への道に殺到して、牛の歩みほどに滞っている。
「お城を目指せ! 朝倉様が踏み止まって下さる!」
別れ際、人込みの中、姿も見えない父の叫び声が聞こえた。全体から見れば己たちの位置は中ほどだろうか。このままでは逃げるより早く、炎に巻かれてしまうかもしれない。せめて先を進む母と己だけでも行かせようと考えたのだろう。
母はそれに従って城を目指しているのだ。こちらは北への道に比べれば、まだ人の数は少ない。
「館までもうすぐです」
朝倉家代々の当主が住まい、一乗谷の民が「館」と呼ぶ建物が近づいている。当然、中に入ったことはないが、入ることを許された町の長老の話によると、主殿や会所のほかに庭園や花壇まである大層華美な造りであるらしい。己のような子どもだけでなく、大人たちもまるで御伽噺の竜宮城のようなところを想像して、いつか入る栄誉にあずかりたいと胸を膨らませていた。
その館は四尺(約百二十センチメートル)ほどの高さの土塁で取り囲まれており、その隅に櫓や門が備えられている。さらにその外側には幅五間(約九メートル)の堀が巡らされているものの、戦国大名の防備としては心許ない。これは家臣の謀叛に備える程度のもので、万が一敵国の侵攻を許した場合は、館の背後にある山城に籠って戦うのだと幼い頃から聞かされていた。
館の西側の正門に近づいたが、門は貝が蓋をしたように閉ざされている。加えてこれほど混雑しているのに、門の前に僅かな空間が出来ている。
館を守る武士が数人刀を抜いて、殺到する人々を近づかせぬように威嚇しているのだ。
「御屋形様はどこに!?」
「織田軍を追い払って下さい!」
「退がれ、退がれ!」
民から悲痛な声が上がるが、汗に顔を光らせた武士たちが、刀や槍を向けて追い払おうとする。すぐ後ろに織田軍が迫っているのだ。一刻も早く館に逃げ込み、さらにその後ろの一乗谷城に籠りたい。そうすれば当主義景が守ってくれる。名家朝倉を救わんと各地の大名が救援を送ってくれる。一乗谷の民は耳に腁胝が出来るほど聞かされており、この逼迫した状況でもそれを信じて疑わない。
「早く! 織田軍が─」
「お城に入れて下さい!」
再び縋るような声があちこちから起こる。押し問答をしている間は無いと、民の一人が無断で館に踏み込もうとした。若い武士がその襟を摑んで引き倒し、胸元に刀を翳した。
「退けと申しておろう! さもないと……」
倒された民は恐怖に顔を引き攣らせている。その時である。年嵩の武士が刀を素早く腰に納め、諸手を突き出して止めに入った。
「やめよ!」
「しかし……」
「この場は儂に任せよ。皆の者、気を確かに聞いてくれ!」
年嵩の武士は人々に向けて高らかに呼びかける。何が始まるのかと皆が固唾を吞んで見守る。一時静かになったせいで、銃声、怒号、悲鳴の入り混じった音が耳朶に届いた。
「御屋形様はすでに落ちられた」
年嵩の武士が発した一言に皆が呆気に取られる。衆の中の一人が声を震わせながら尋ねる。
「今……何と?」
「織田軍の追撃が思う以上に早く、ここ一乗谷ではもはや守り切れぬと考え、先刻さらに奥へと退去された。皆の者も銘々落ち延びよ。すまない……」
捲し立てるように一気に言うと、他の武士に向けて合図を出す。武士たちは一斉に頷き、その場を離れ始める。
「俺たちはどうなる!?」
「守ってくれるんじゃなかったのか?」
「今まで年貢を納めていたのに、何てことだ!」
怨嗟の声が渦巻くが、武士たちは見向きもせずに引き揚げていく。ただ先ほどの年嵩の武士だけが心苦しそうな顔でその場を離れようとしている。
「ふ、ふざけるな!」
民の一人が怒りを爆発させて武士に殴りかかった。武士は堪らぬと刀を抜いて斬り下げる。けたたましい悲鳴が上がる。
「仕方なかったのだ……こんなことをしている場合ではない。早く─」
言い訳をする武士が絶句した。他の民が体当たりして武士の腰の脇差を抜き、そのまま腹に捻じ込んだのである。武士は顎を震わせてその場に頽れた。
これで人々の中に残っていた最後の箍が外れた。背後の織田軍など忘れたかのように、目の色を変えた民は叫びつつ武士に向かって行く。武士も槍や刀で応戦するが、圧倒的な数に押しつぶされ、散々に踏みつけられる。
この地獄絵図のような光景に躰が震えた。昨日まではきっと戦を嫌う温厚な民であったはず。それなのに武士を袋叩きにし、人の好さそうなあの年嵩の武士も倒され、血反吐を吐くまで殴打されていた。
次に民たちは塀を乗り越え館に踏み込む。誰かが閂を抜いたのか、門が内側から開かれ、我先にとどっと館に踏み込んだ。館に逃げたところで、織田軍の猛攻を避けられるはずもないことは子どもの己でも解る。せめて金品を奪って逃げようというのか。
いや何も考えていないのかもしれない。まるで集団が一個の荒れ狂う獣になったかのように館へ迫る。後ろからも人の圧が強まり、指一本動かすにも苦労するほどであった。銃声はさらに近づき、後ろでは悲鳴が連続する。織田軍が追いついて来たのだ。
「山へ……館を回って、山へ逃げなさい」
胸を圧迫されて顔を歪める母は、手を摑んでいるのもやっとという有様であった。館からは山城までの道が整えられているが、そこを通れるのはいつになるか判らない。山肌を駆け上がって行けというのだ。
「でもおっ母は!」
「子どもなら足元を潜って抜けられる。早く……後で行くから!」
このような母の形相は見たことが無い。剣幕に気圧されて頷くと、膝を折って身を揉むようにして屈んだ。人々の脚が無数に並んで揺れている。その光景はまるで闇を抱えた森の如くに見える。己を突き動かすのは死への恐怖か、生への執着か。懸命に息を吸い込んで生々しい木々を搔き分けていく。
ようやく森を抜けた時、大きく胸を膨らませた。これほど息が出来ることがありがたく感じたことはない。躰は頭から水を被ったほどの汗で濡れている。
「おっ母……」
今しがたまで己がいた、一つの塊となって揺れる集団を見た。しかし母の姿を見つけることは出来ない。黒光りする甲冑に身を固めた一団が向かって来る。馬上で指揮を執る将が何かを喚くと、ずらりと鉄砲隊が展開した。
「あっ――」
指揮棒が振り下ろされる刹那、踏みつぶされた蛙のように地に伏せた。轟音と絶叫が頭上を乱れ飛んでいく。頭を押さえてがたがたと震えたのも束の間、毬の如く跳ねて走り出した。このままここにいれば必ず死ぬ。躰が己の命を守ろうと足搔いている。
迷いは無かった。間断なく聞こえる銃声、断末魔の声を聞かぬように努め、ただ頂を目指した。
今度は真の森。道なき道を駆け上がっていく。途中、腐った葉で足が滑り、斜面に顔を強かに打った。頰に切り傷が出来たがそれも気に留めず、すぐに脚を前へと動かした。
斜面には土を掘削して作られた畝、こんもりと積み上げられた土塁が幾つもある。迫る敵を食い止める城の備えである。だが戦があれば、当然いるはずの兵の姿は無い。もしいたならば助けを請うことが出来る反面、誤って殺されたかもしれない。
普段はこれほど冷静に考えることはないだろうが、重大な危機が己の心を無理やり大人に近づけようとしていると感じた。
頂を目指すのだから、ただ駆け上がって行けばよいと思っていた。だが事はそう単純ではないらしい。兵を配するために斜面は平たく削られ、そこからうねるように路が延びている。そこを走ると登っているつもりだったのに、知らぬ間に下っている。敵を欺くための迷路のようになっているのだ。道なき道を進もうかと思ったが、それを阻むかのように木々が乱立し、時には崖に差し掛かった。これを搔き分けて、よじ登っていくのは難しい。
途方に暮れかけたが、ふと斜面に露わになった岩肌に目が留まった。
――こっちだ。
目を凝らした。別に声が聞こえた訳ではない。ただ何となくではあるが、岩がそのように言っているように思えたのである。日常が瞬く間に崩壊したことで、己の心もどこかおかしくなったのか。そのようなことを考えたのも束の間、やけになって、岩の語ったほうへと走り出した。
城下に火が放たれたのであろう。ここまで薄っすらと明るい。途中、何度も目を動かした。剝き出しになった岩、転がっている石、全てが語り掛けてくるような気がする。迷った時に目を瞑って声が聞こえぬかと試してみたが、上手くいかない。刮目すれば再び話しかけてくる。己は何かを見て声を聞きとっている。色か、形か、紋様か、それは己にも解らない。考えても全く解らないし、考える余裕も無い。声のするまま、無我夢中で脚を動かした。
どれほど歩いただろう。四半刻(約三十分)は過ぎていたかもしれない。森の向こうに山を削ったような平地が見えてきた。そこには複数の武士が慌ただしく動いている。
――助かった……。
森から飛び出すと、近くにいた武士たちはぎょっとして槍を構えた。
「……子ども?」
「助けて下さい! 下でおっ母が……皆が!」
必死に訴えたが、武士たちは曖昧な表情になる。
「もう無理だ。敵の侵攻が速すぎる。城からはもう撤退が始まっている」
一人が苦々しく零した。ようやく気付いたが、武士の背後にある兵糧庫らしきものが開け放たれている。そこには大量の米俵が積み上げられており、革袋を手に持った武士が激しく出入りしている。逃げる間に自身が食う分を確保しようとしているのだ。
「そんな……」
昨年の秋の、たわわに実る黄金色の稲穂が、風に揺れる光景が目の前を過った。領民は実入りの半ば以上の年貢を大名に納めている。だからこそ武士は田を耕すことなく生きていける。朝倉の殿様はそれのみならず華美な着物、調度品を揃え、京から公家を招いて連歌に興じたりしている。その金は全て領民の暮らしから捻出されたものだ。
それでも領民がせっせと働いて年貢を納めるのは、いざという時に武士が民を守ってくれると信じていたから。そのいざという時は今をおいてない。今、守ってくれないならば、父母は、一乗谷の民は、朝倉の領民は、何のために諾々と従ってきたというのか。
「我らも山の裏側より逃げる。小僧も……」
武士が言いかけた時、沸々と腹の底に湧いていた怒りが口から飛び出した。
「ふざけるな……ふざけるな!」
「小僧! 誰に向かって――」
無礼を咎められてこの場で斬られても仕方ない態度に、武士たちは気色ばんだ。しかし怯まない。己はどうなったとしても、父母を、妹を守りたい。その一心が突き動かす。
「それでも武士か! ここまで悲鳴が聞こえている。それでも助けないのか!」
悲痛な叫びに武士たちも困惑する。中の一人が苦悶の表情を浮かべて零した。
「救えるものならば救いたい……俺の妻と子もあそこだ」
武士の視線の先は阿鼻叫喚が渦巻く一乗谷の城下である。町の外れが茫と明るくなっている。織田軍が火を放ったのである。歯を食い縛り武士は続けた。
「一乗谷は丸裸だ……織田軍の苛烈な侵攻に逃げる時すらも稼げぬ」
一乗谷の町は、京の都を模して造られている。真の京がそうであるように、極めて攻めやすく、守りにくい地形になっていると聞いたことがある。
「塞王を招聘して、守りを固めようという矢先に……」
「さいおう……」
聞き慣れぬ言葉。唇が自然と反芻を命じたように動いた。
「お主の家族もきっと逃げ果せたはずだ」
手を引いて逃げようとした武士の手を払った。武士たちはばつが悪そうに顔を見合わせたが、
「小僧、すまないな……」
と、蚊の鳴くような小声で呟くと、もはや猶予は残されていないと見たかその場を離れていく。
「誰か!」
目に入った次の武士に助けを求める。まだ諦めなかった。諦められるはずがない。しかし今度の武士はけんもほろろに話も聞かず走り去っていく。
次、次、次と助けを請うがどの者も手を差し伸べてくれない。酷いものになると、邪魔だと足蹴にして去って行く武士もいた。両手一杯に女物の着物を抱えており、子どもの己にも火事場泥棒を働いていると判った。
やがて周囲を見渡しても人影も無くなってくる。初めからこの城には誰もいなかったと思えるほど、辺りが静寂に包まれる。耳に届くのは城下からの禍々しい音だけ。
恐る恐る崖へと歩を進め、一人で眼下の町を見つめた。先ほど放たれた火が瞬く間に広がっていく。下から吹き上げて来る生温かい風が頰を掠める。
武士たちは家族も逃げ果せたはずと言った。己もそう信じたいが、眼前に広がる死の渦巻く光景、山にまでうねるように届く慟哭の声を聞けば、子どもの己でも慰めだと解る。
戻れば死ぬることになる。そうなったとしても家族の近くにいたい。そのように思って、来た道を引き返そうとした時、背後から怒鳴り声が飛んで来た。
「何をしている! 早く逃げろ!」
ゆっくりと振り返った。そこに立っていたのは一人の男。歳は三十半ばといったところであろうか。総髪を無造作に束ね、口と顎に紙縒りのような髭を蓄えており、川で捕ったことのある泥鰌を彷彿とさせる相貌であった。甲冑はおろか胴丸すら着けていない平装であることから、武士ではないらしい。
逃げるようにと叫んでいた男だが、視線が宙でかち合った時に息を吞んだ顔になる。どうやら己は死人のような顔をしているらしい。
「おっ父……おっ母が……花代が……」
「城下から逃げてきたのか」
男は近くに寄ってくると、そっと手の甲で頰を拭ってくれた。それで滂沱たる涙が頰を濡らしていることに気が付いたほどに、心が搔き乱されて己の躰の勝手が判らなくなっている。
「逃げるぞ」
男は先ほどの武士のように手を取った。
「戻る」
ぐっと手を引いたが、男は力を込めて離さない。その鈍い痛みで手を引いてくれた母を思い出し、また胸が詰まった。
「駄目だ。もう助からない」
男はとっくに解っていたことを口に出した。下手な慰めよりも、そちらのほうが余程心に響き、必死に耐えてきた嗚咽が漏れた。
「一緒に……」
必死に絞り出すが、男は手の力をさらに強めて首を横に振った。
「お前が死ねば、家族を知る者はこの世にいなくなる。それでよいのか。それこそ真に死ぬということではないか。家族の誰がお前に共に死んで欲しいと望んでいる」
男は膝を折って顔を覗き込む。何も言い返せず、奥歯を擦れるほど嚙みしめることしか出来ない。歯の隙間からなおも漏れる嗚咽に触れるように、男は残る手を頰に当てて続けた。
「人は元来、自ら死ぬようには出来ていない。生きろ。己の命を守るのだ」
男の懸命な想いが胸に染み、こくりと頷いた。
「山を向こう側に下りる。曲輪沿いに北西に進み、竪堀にぶつかったところで西の土塁を越える。そこで万が一追いつかれたとしても、伏兵穴があるからそこに身を隠してやり過ごせる」
安堵させようとしているのか、男は手を引きながら逃げる道順を語る。平装の男が何故ここまで城の造りに詳しいのか。もしかして子攫いではないか。恐怖がさっと心に広がり、数歩後ずさりした。男はこちらの心の動きを察したかのように、自らの名を名乗った。
「飛田源斎と謂う。この城に……この町に楯を造るはずだった者だ」
「楯……」
「ああ、こうならぬための……命を守る楯だ」
「そんなこと……」
「出来る」
源斎は凜然と言って茂みを分けた時、足を止めて振り返った。
昨日まで己が家族と暮らしていた町、幾つもの笑みが行き交っていた町、百年続いた一乗谷の町が、轟々と渦巻く紅蓮の炎に包まれている。
もう嗚咽は湧いて来ない。源斎の言う「楯」があれば、変わらぬ今日が訪れていたのか。そのようなことを茫と考えた。
「行こう」
源斎は手をゆっくりと離した。
「うん」
小さく頷き、茂みに足を踏み入れる源斎に続く。もう振り返ることは無い。父が、母が助けてくれたこの命を守り切るつもりになっている。救ってやることが出来なかった妹に、懸命に生きて償うと誓っている。
源斎は迷いなく山を下っていく。町の火灯りが薄くなってきたところで、初めて足を止めて周囲を見渡した。
「少し待て」
「何を……」
「山の形を思い出している」
「こっち……じゃないかな……」
生い茂った木々の隙間の獣道を指差し、ぽつんと零した。
「山に来たことがあるのか?」
源斎は怪訝そうな顔を向けるので、頭を横に振る。
「ううん」
「では何故判る」
頭がおかしいと思われるのではないか。そのような考えも一瞬過ったが、何故かこの男は馬鹿にしないという確信があった。
「岩や石が……こっちだと言っているような……」
「何……」
源斎は勢いよく首を振り、近くで剝き出しになった岩を凝視して尋ねた。
「岩の何を見た。色か、形か、目か」
「目?」
「紋様とでも言えばよいか。ともかく何を見てそう思った」
「判らない……ただ、見ていれば声が聞こえるような気がする」
「そうか」
源斎は片眉を上げて苦笑した。源斎は再び岩に目を移し、その後に改めて周囲を確かめる。そして二度、三度頷くと、己の示したほうへと歩を進めた。
さらに暫く行ったところで、源斎は草を払いながら口を開いた。
「山の岩というものは、ある場所の高さによって、目が違うものだ」
聞いたことの無い話である。そのようなものかと思って黙って聞いていた。
「恐らくお前はそれを見たのだろう」
「どうかな」
岩の目が高低によって変わることも知らなかった。ただ己に訴えかけてきている声を聞いたに過ぎず、それが正しいかも判らない。このような切羽詰まった状況でなければ、その得体の知れない声に従ったとも思えなかった。
「名は」
斜面を駆け下る源斎が、振り返りもせず短く問うた。
「匡介」
「きょうすけ……どのような字だ」
気を紛らわせようとしてくれているのか、源斎は背で話し続けた。
「きょうはコの字の反対に王。すけは介添えの……」
「難しい言葉を知っている。俺より余程学がある」
源斎の声が高くなる。父は越前でも有数の象嵌職人であった。品物を納めるやり取りで文も使うことから、読み書きが出来ねばならないと、教え始めてくれていた。
「良い名だ」
目の前に突き出た枝をぱちんと折って源斎は呟いた。己のために道を開いてくれている。
「え……?」
匡介が声を上げると、源斎は半ば振り返った。
「王を守っている」
意味が解らなかった。源斎は片笑むと、再び前を向いて進み始めた。この男に付いていくほか道はないと思い定めている。匡介はそのようなことを頭に浮かべつつ、源斎の背を追いながら鬱蒼と広がる森の斜面を駆け下っていった。
第一章 石工の都
吸い込まれそうなほど高い蒼天に、端が滲んだような白雲が西から東へ流れてゆく。
叡山東側の山肌を削って出来た岩壁に臨む匡介からすれば、山が雲を吐き出しているかのように見えた。心地よい風が吹き抜け、周りを取り囲む木々を揺らす。眼前にひらりと舞い落ちた木の葉は、最後の命を燃やそうとしているかのように赤い。季節は秋から冬へと移ろいつつある。
岩肌に向かって十数人の職人が張り付き、突き立てた鑿に鉄の鎚を振っている。これは己たちの間では「石頭」と呼ばれる道具である。
丹田を揺らすような鈍い音、耳朶を弾くような甲高い音。岩の質、大きさ、打ち所によって音は変わり、一つとて同じものは無い。
手頃な岩に腰を掛け、どこに流れつくとも知れぬ雲を眺めていると、岩肌の前に立つ男が振り返って呼びかけてきた。この男の名を段蔵と謂う。
「若、ご覧になっていますか?」
「ああ」
匡介は視線を落としてぞんざいに答えた。
「頼みますよ。若には飛田屋の……いや穴太衆の将来を背負って立って貰わなくちゃなりません」
段蔵は項を搔きながら苦笑する。
今、段蔵が言ったように、匡介は穴太衆と呼ばれる集団に属している。
穴太衆。その名の通り近江国穴太に代々根を張り、ある特技をもって天下に名を轟かせていた。それこそが、
――石垣造り。
であった。世の中には他にも石垣造りを生業とする者たちがいるにはいるが、いずれも細々とやっているのみ。この技術においては穴太衆が突出しており、他の追随を許さないからである。
穴太衆には二十を超える「組」があり、それぞれが屋号を持って独立して動いている。銘々が諸大名や寺院から石垣造りの依頼を受け、その地に赴いて石垣を造る。軽微な修復など一月足らずで終わるものから、巨城の大石垣など数か年掛かる仕事もあった。
「爺がそんなこと思っているかよ」
「頭と呼びなされと何度……」
鼻を鳴らすと、段蔵は大きな溜息を零した。
匡介が爺、段蔵が頭と呼ぶ男の名を源斎と謂い、飛田屋の屋号で仕事を受けていることから、世間では飛田源斎と呼ばれている。
源斎は穴太衆千年ともいわれる歴史の中でも出色の天才との呼び声が高く、他の組の頭たちからも一目置かれている存在であった。
「爺がそう呼べと言ったのさ」
「そうでしたな」
段蔵はこめかみを指で搔いて苦笑した。
匡介は飛田屋の副頭にして、後継者に指名されている。だが大抵の組の頭が己の血筋の者に跡を継がせるのと異なり、匡介と源斎に血の繫がりは一切無かった。
匡介は越前国一乗谷で、象嵌職人の父の下に生まれた。二十三年前、朝倉家が織田軍の侵攻を受け城下は灰燼と化した。匡介が独りで山城に逃れた折、朝倉家から石垣の仕事を受け、下調べに来ていた源斎と邂逅したのだ。源斎は炎に包まれた一乗谷から、己を連れだして近江穴太の地まで導いた。
源斎は子がいないどころか、妻さえも娶っていなかった。若い頃には人並みの幸せを考えたこともあったらしいが、ある時を境に石積みに生涯を捧げようと決心したらしい。
配下の者たちもこのままでは跡取りが出来ないと、考えを翻して妻を娶るよう源斎に進言していたが、飄々と受け流すのみであったという。そんな中、一乗谷から連れてきたばかりの己を皆に引き合わせた。源斎は己の頭にぽんと手を乗せ、
「こいつを跡取りに据える」
と、鞣革のような頰を綻ばせたものだから、配下の者たちが仰天したのを匡介も幼心に覚えている。
「山方はどうです?」
岩壁での作業が滞りないか、段蔵はちらりと確かめつつ訊いた。
「俺はずっと積方にいたんだぞ。何でいきなり山方に……」
匡介は自身の腰掛ける岩を軽く叩いて零す。
穴太衆の技と聞いて世間は石を積むことだけを連想する。しかし実際はそうではなく、大きく三つの技によって成り立っている。
まず山方。これは石垣の材料となる石を切り出すことを担っている。といっても適当に石を取っている訳ではない。石の大きさは一から十まで大まかに等級分けされており、総頭が欲する数だけそれぞれ用意しなければならないのである。しかも決めた大きさの石を切り出すのは存外難しい。鑿の角度、石頭を振るう強さは勿論、岩には「目」というものがあり、それに沿って打ち込まねば思わぬ形にひびが入ってしまう。その目は熟練の職人でなければ見ることが出来ないのだ。未熟な者がやると、歪な亀裂が入って望んだものと違う形で割れてしまう。まるで石が、下手な者に使われるのを拒絶しているかのようである。
眼前の段蔵は、飛田屋山方の小組頭を務めている。歳は源斎の二つ年下の五十五。匡介がここに来るより前、もう三十年も山方の小組頭を務めており、石を生み出すことに関しては穴太の中でも三本の指に入ると言われていた。
「次は荷方に行かれるのでしたな?」
段蔵は眉を開いてみせた。
二つ目は荷方。切り出した石を石積みの現場まで迅速に運ぶ役目である。運ぶだけならば誰にでも出来る。素人はそう言うが、これは石垣造りの三工程の中でも最も過酷とされる。
泰平の世ならば時を掛けてゆっくりと造ることも出来る。しかし戦火の止まない乱世となると話は違う。堅牢なことは当然、迅速に造り上げねば、敵に隙を見せることになる。いくら早く積もうと思っても、その資材となる石が届かねばどうしようも無い。これを左右するのが荷方である。雨が降ろうが雪が降ろうが、敵が攻めてきて矢弾が降ってこようが、綿密に練られた計画通りに石を運搬する。
場合によっては縦横幅二丈(約六メートル)を超える巨石を運ばねばならぬこともあり、その時は安全にも相当配慮せねばならない。実際に織田信長が安土城を建てようとした時、坂道を上る途中に縄が切れて百数十人が巻き込まれて死ぬという事故が起こっている。それらの惨事が起きないように配慮しつつ、期日までに何としても石を届けるというのが荷方の役目である。
「ああ」
匡介は小さく舌打ちをする。その意味を段蔵はすぐに察して困り顔になる。
「ほんに嫌そうじゃ。若は玲次と喧嘩ばかりしていますからな」
「すぐに突っかかってくるあいつが悪い」
匡介は鼻を鳴らして顔を背けた。
「玲次も色々と思うことがあるのでしょう」
段蔵はしみじみとした口調で言った。
玲次は荷方の小組頭を務める男で、源斎にとって唯一の親類でもある。歳は匡介と全く同じ。飛田屋先代の三男の子であり、現頭である源斎の甥に当たる。故に玲次は己こそ、正統な飛田屋の後継者と思っていたようで、どこの馬の骨とも知れぬ匡介が跡取りに指名されていることが面白くないのだろう。
「爺は玲次を跡取りにすればよかったんだ」
匡介は半ば投げやりに言った。確かに己が玲次の立場でも不快であろうと思うのだ。ふと視線を戻すと、段蔵の顔から笑みが消え、じっとこちらを見つめている。
「積方はそう甘い考えでは務まらぬこと、よくご存じのはずでは?」
「まあ……うん」
妙に素直で子どもっぽい返事になってしまったのには訳がある。
源斎は石積みについては教えてくれるが、他のことに対しては放ったらかし。その代わりに甲斐甲斐しく面倒を見てくれ、時に悪さをすると𠮟ってくれたのもこの段蔵。段蔵はいわば気の好い叔父のような存在であった。その頃の癖なのか、改まった口調で言われるとそうなってしまうのだ。
「確かに才は親から子に伝わりやすい。故に子が跡を取ることが多いのも事実」
段蔵は嚙んで含めるように続ける。
「しかしより才のある者がいれば、肉親であらずとも継がせる。それほど積方は重要なのです」
飛田屋では積方の小組頭が副頭も兼ね、跡継ぎでもある。つまり匡介はその立場にあった。
積方を極めるには、他の二組以上の時を要する。まず石垣の中に詰める「栗石」というものを並べるだけでも、少なくとも十五年は修業しなければならない。
匡介は八つから本格的に修業を始め、すでに齢三十。未だ己だけで一度も石垣を組ませて貰っていない。ようやく一通りの修業を終えて、いよいよと意気込んでいた時に、
「匡介、明日から三月ほどは山方へ行け」
と、源斎に命じられたのである。しかも次の三月は荷方へ行けとも言う。
「折角、大きな仕事が目の前にあるのに……」
また不満が沸々と湧いてきて、匡介は再び舌を弾いた。
百数十年前より、各地で群雄が割拠して戦が頻発するようになり、この国は乱れに乱れていた。戦というものは技を一気に育む。戦の勝敗に直結する築城、その中で穴太衆の石積みの技は重宝されて発展してきた。匡介も自らの石垣を構築したいという思いで、修業に明け暮れていたのだ。
――しかし全てが変わった。
不世出の英傑、豊臣秀吉によって天下は悉く統べられたのである。それによって穴太衆への仕事の依頼は激減した。
それからも御手伝普請と称して大型の城が築城されることはあった。朝鮮出兵の拠点、肥前名護屋城などもそうである。しかし豊臣家の威信を示すための城となれば、半人前の己などではなく、経験も実績も豊かな源斎が受け持たねばならぬ。そのような訳でなかなか自らの石垣を造る機会を得られず、匡介は鬱々としていた。
だが三月前に機会が訪れた。閏七月十三日の夜更けに凄まじい地揺れが起こり、伏見城の天守が倒壊したのである。だが石垣は数か所が軽く崩れただけで無事であった。この石垣も源斎が造ったものである。
秀吉はこの機会に現在ある指月山から、木幡山に伏見城の移築を計画した。このことで石垣も取り壊して、改めて組み直す必要が出て来たのである。次に石垣を組む時はお前がやれと言われていたこともあり、匡介は勇み立っていたのだが、
「これはお前じゃあ無理だ」
と、源斎は前言をいきなり翻した。それだけでなく山方、荷方の仕事ぶりを見て来いと付け加えたのだ。そして今ようやく三月が過ぎ、山方に張り付く期間が終わろうとしている。
「頭には何か思惑があるのでしょう。故にこれまで積方一筋でいた若に、山方、荷方を見させようとしておられる」
「そうだろうな」
段蔵が言うように、何かしらの意図があるとは思っている。だが己の手で一つの石垣を組みたいという欲求のほうが勝り、苛立ちをなかなか抑えられずにいた。今すぐにでも伏見に走り、源斎に直談判しようかと何度も衝動に駆られている。
この三月の間、ずっと苛立ちを覚えていたせいで、段蔵はともかく山方の連中はどこか腫物に触るように己を扱っていることを感じていた。
「焦ることはありません。天下泰平でも城は築かれます。乱世の頃の守る城とは些か変わり、見せる城になりましょうが」
段蔵はそのように言うが、それが気に喰わない。城の、その土台たる石垣の美しさとは何か。それは見た目の華美さでもなく、整然さでもない。誰にも打ち破られぬという堅さこそ美しさではないか。匡介はそのように思うのだ。
段蔵は匡介の胸の内を知ってか知らずか、流れる雲に合わせるように鷹揚に語り続けた。
「これからの時代は荷方が重要になります」
「荷方が?」
確かに積方は習得するのにより時が掛かるが、それでも源斎は三組いずれも重要だと常々言っている。泰平になれば荷方が重要になるという意味が解しかねた。
「ええ。若はどのようなところに城が造られるかお解りか?」
世間が聞けば石積みの副頭に対し、小馬鹿にしたような問いだと思うかもしれない。だが匡介は答えに窮してしまった。これまでは言われた場所に赴いて石垣を積んできたのであって、どこに城を建てるかはこちらの与り知らぬところなのである。またこれまでの二十数年の修業は過酷で、そのようなことを考える暇すら無かった。
「それは……守りの要だろう」
当たり障りのない答えに、段蔵は二度三度頷いた。
「それは間違いござらん。しかし乱世の中ではもう一つ考えねばなりません。それがこれです」
段蔵は振り返り、石頭を振り続ける配下の者を掌で指した。
「なるほど。石場か」
「はい。幾ら城を建てたくとも、近くによい石場が無ければ、遠路遥々石を曳いていかねばならぬことになる」
それには相当の時と費用が必要になってくる。いつ戦が起こって攻め込まれぬとも限らぬ戦国の世では、そのような悠長な真似は許されなかった。
「つまり石場のあるところに、城を建てているといっても過言ではないということか……」
「左様。だがそれが、がらりと変わりつつあります」
天下が統一されて世から戦は無くなり、城を建てたいと思った場所に、遠くの石場から時を掛けて石を曳いていくことが可能になった。また御手伝普請は諸大名に人足や資材を負担させて力を削ぐという一面もある。むしろ金が掛かるのも好都合である。
移築に伴う追加の石が必要だが、そもそも伏見城の傍に適当な石場は無く、こうして近江国から運んでいっている始末である。
「だから荷方の役割が大きくなるということか」
段蔵は頰を緩めてゆっくりと頷いた。
「頭は、変わりゆく世でも若が石積みを続けられるようにと考えているのでしょう。玲次の仕事ぶりを見ておいて損はないかと」
「解った。段蔵、世話になったな」
匡介は軽く会釈して立ち上がった。石を積むことに関しては、源斎に次ぐ腕前になっている。だが、今聞いたような話すら己は知らなかった。他のことを学んでいては極める境地などには辿り着けないということもあるが、そもそも己は石積み以外に興味を示して来なかった。
先ほどのように、この三月の間、段蔵は余計なことは何も言わず、こちらが訊いたことにのみ懇切丁寧に答えてくれた。
そして今日が最後の日。これより大津に向かう。ここには荷方が「流営」と呼ばれるものを布いている。これは武士が戦をする際に布く陣のようなもので、それを起点に石の動きを差配していた。
「はい。お役に立てたでしょうか。最後に自ら切り出してみなさるか?」
これまで匡介は見るだけで、一度も切り出す作業をしたことはなかった。段蔵はそれにも小言を零すことなく見守ってくれていたのだ。これがここに来て最初で最後の進言ということになろう。
「ああ」
受け入れるとは思っていなかったようで、段蔵はおっと小さな驚きを見せる。
「誰か、若に石頭――」
「持っているさ」
腰の辺りを軽く叩いた。
「左様でしたな」
失念していたといったふうに、段蔵は自らの額を叩いた。
匡介は鞣した革で太い帯を巻いている。そこに幾つかの穴が開いており、石頭や鑿を常に差し込んで持ち歩いている。まるで武士の二本差しのような恰好である。もっとも武士が左腰に刀を差すのに対し、匡介は道具を右腰に差している。
このようにしているのは飛田屋だけでなく、穴太衆においても匡介ただ一人であった。幼い頃、己の暮らしが一変するようなことを経験したからか、常に持ち歩かねば安心出来なくなっているのかもしれない。
「若……」
匡介が歩み寄ると、山方の皆が手を止めて視線が集まる。
若い者の目には羨望の色が浮かんでいる。これでも己は飛田屋の跡取り。誰が言い出したかは知らぬが、いつかは源斎を超える逸材などと吹聴されており、年下の者には畏敬の念を抱かれている。
反面、古株の者の目には恐れの色が浮かんでいた。すでに二十年以上共に暮らしてきているが、碌に会話を交わしたことも無い者が殆ど。人と話す何倍もの時を、石との会話に費やしてきた。時に手の内の石に向けて、
――お前はどこへ行きたい。
などと、語り掛けているところを見た者もあり、実力こそ認めてくれてはいるが、
――若はどこかおかしいのではないか。
と、陰口を叩かれていることも知っている。
羨望、恐怖、あるいは入り混じって畏敬。様々な要因はあるかもしれないが、皆は己に微妙な距離を置いていることを感じていた。
匡介としても別にそれをどうこうしようとは思わない。己の目指す極みに上るためには、そのような無駄なことに時を掛ける余裕は無いのだ。
そうしたこともあり、己に気兼ねなく話しかけてくれるのは師である源斎、山方の小組頭で叔父のような存在の段蔵、そして何かにつけて文句ばかり零す荷方の玲次くらいなものであった。
「邪魔をするぞ」
一声掛けただけで、若い山方が目を輝かせて頷いた。
間際で足を止めると、目を細めてじっと岩壁を見つめた。暫し無言の時が流れる。鑿の音はすっかり途切れ、耳朶に触れるのは鳥の囀りと、木々の騒めく音のみである。
――俺を使え。
「ああ」
「何か……?」
山方の若い衆が耳を近づけて訝しんだ。古株はまたかといった気味悪そうな目を向けている。
「いや、何でもない」
匡介は彼らを一瞥すると、手をひらりと宙で舞わした。いつの間にか段蔵は少し後ろに立ち、腕を組んで匡介と岩壁を交互に見ていた。
腰に右手を伸ばして鑿を取ると、放り投げるようにして左手に持ち替える。投げた時には再び右手を下げており、石頭を抜くと同時に旋回させて構えた。
「いくぞ」
段蔵、もしくは他の若い衆に語り掛けたと思っているだろう。あるいは独り言と思われたかもしれない。だが匡介の呼びかけた相手は確かに別にいた。
女の頰に指を添わすように鑿を岩にそっと当て、軽く石頭を振った。細く高い音が周囲に響く。
「若、もう少し強く打たねば――」
若い衆に呼ばれて振り返る。だがその向こうの段蔵は目を見開いて岩壁を凝視していた。
「下がれ」
「え……」
匡介は若い衆を押して二、三歩下がった。壁面から微かな音が立ち、糸のような細い線が浮かんでくる。やがてその線は少しずつ太くなり、弾けるような音がしたかと思うと、壁からごろりと石が転げ落ちて来た。石は視線を集めつつ斜面を転がっていき、やがて動きを止める。驚愕の表情を浮かべて固まる若い衆の中、段蔵は呼吸を整えるようにゆっくりと息を吐いた。
「お見事です。この境地に至るまででも十年は掛かりましょう。それを三月で……」
「これまで二十年以上、石積みをしていたからだ」
謙遜ではない。その期間が根底にあったからこそ出来たのであって、一朝一夕でやれるはずはない。これで若い衆が萎縮して貰っては困ると付け加えた。若い衆は爛々とした憧憬の目で見つめる。古株たちも実力だけは認めてくれているようで、腕を組みながら舌を巻いている。
「それでも流石としか言いようはありませんな。若はしっかり石の目が見えているのですな」
何も石を割るのは山方だけではない。積方も場合によっては石を割って適当な形に変える必要がある。力任せでも出来ぬことはないが、無駄な力を使ってしまい、しかも断面が歪になりやすい。石の目と呼ばれるものを読んで割れば、ささやかな力しか要せず、形も綺麗になるのだ。だがその石の目を読むのに、どれほど優れた者でも十年は掛かると言われている。
「いや、目を見たことはない」
「謙遜を」
他の山方は勿論のこと、段蔵でさえそう取った。今まで己がどのようにして石と触れて来たのか、それは師である源斎の他に語ったことは無い。
「聞こえるから」
匡介はぽつんと呟いたが、同時に一陣の風が吹き抜け、木々の騒ぐ音に搔き消された。先ほどまで岩壁に収まっていた石を今一度見た。何百、何千、あるいは何万年もの時から解き放たれ、新たな旅に向かうことに喜び勇んでいる。匡介にはそのように思え、誰にも気付かれぬほど小さく頷いた。
叡山の石場から大津までは目と鼻の先。翌日の早朝に石場を離れ、匡介が飛田屋の流営に辿り着いたのは、秋の優しい陽が中天を少し過ぎた頃であった。
流営の語源は定かではないが、源斎の祖父が、
「祖父の代にはもうそう呼ばれていた」
と言っていたことから、少なくとも百年以上前からの呼称であることは確からしい。
大陸の前漢時代、周亜夫と謂う将軍が匈奴征討のために細柳という地に陣営を置いた故事から、本邦では幕府のことを「柳営」と呼ぶ。穴太衆の遥か先代がその響きを気に入ったのだろうか、石の差配所を本来の文字から一字変えてそのように呼び始めたのではないか。
源斎と共に細川家の田辺城の石垣を増築した時、隠居で古今の故事に詳しい細川幽斎が語っていたので、妙に納得したのをよく覚えている。
その流営に行くと、飛田屋荷方の若い衆が慌ただしく動いている。昼間とはいえ肌寒くなってきているのに、どの者も諸肌を見せて荷造りに追われていた。
「若!」
若い衆の一人がこちらに気が付いて声を上げた。
「おう。玲次はいるか?」
「小組頭は……」
若い衆が向ける視線の先、指を差しつつ差配する男がいた。己は身丈五尺七寸(約百七十二センチメートル)と大柄であるが、玲次も決して低くはなく五尺六寸はあるので目立つ。吊り眉をいからせて、早く縄を掛けろだの、手と足を同時に動かせだのと吼えている。
「喜三太、手が止まって――」
別の方向を向いていたはずなのに、余程視野が広いのか、こちらの若い衆の手が止まったことを見逃さない。玲次は言いかけたところで、己の存在に気付いて顔を少し顰めた。
「匡介、邪魔するな」
地を踏み鳴らすように大袈裟に歩み、こちらに向かって近づいて来た。飛田屋の中にあって、源斎を除けばこの玲次だけが己を名で呼び捨てる。こちらとしても、無理に副頭や若などと呼ばせようとは思わない。元々同じ釜の飯を食ってきた相弟子である。
「爺からお前の仕事振りを見ろと言われているんだ。文句を言うなら爺に言え」
匡介も負けじと返すと、玲次は渋々といった様子で零す。
「勝手に見て学べ。俺は何も教えねえ」
「爺は解らないことは、玲次に逐一訊けと言ったぞ?」
匡介が片眉を上げると、大袈裟に舌打ちをして玲次は身を翻す。己の後ろについて学べと言いたいのだろう。
「邪魔するなよ」
「俺が来ただけで、仕事に障りがあるのか?」
「口の減らねえ野郎だ」
玲次は項を搔き毟って吐き捨てた。
「よそう。仕事だ」
いつまでも小競り合いをしていても始まらない。匡介は手をひらりと振って話を転じた。流営には山から切り出されてきた大小の石が大量に集まっている。
陸での石の運び方は様々である。まずは地車。台に直径三尺ほどの車輪が付いているもので、牛馬が曳いて運搬する。今は人が抱えられるほどの、比較的小さな石が積み上げられて縄を掛けられている。
次に石持棒。これには様々な形がある。井桁のように組んで中央に大きな石を縛りつけ、複数人で運ぶものもあれば、棒一本の両側に籠を付けて一人で運ぶものもある。後者には拳ほどの大きさの栗石が入れられている。
三つ目は「修羅」と呼ばれる橇。筏のように丸太を組んだものに縄が付いている。この上に石を置いて大人数で曳くのだ。これには一丈四方ほどの石が積まれている。
最後は「ころ」である。丸太を地に並べ、その名の通り石を転がして移動させる。人の身丈を超えるほどの巨石を運ぶ時はこれを用いる。これで長距離を運ぶのは時が掛かり過ぎるため、このような巨石は石船と呼ばれる船で運ばれた。ころは、石船に載せた巨石を降ろす時に主に用いる。
それらが入り交じって作業が進められている中を、縫うように歩きながら匡介は呟いた。
「凄まじい荷だな」
「御頭からの注文だ」
「石垣を組み替えないのか……」
伏見城は移築されるのだ。これまでの石でもう一度組み直せばよい。今回の地揺れでは、幸いにも火事は起こらなかった。木材はそのまま流用されると聞いている。
「積方のお前が聞かされてないのか?」
玲次の言葉に棘を感じた。確かに積方の己が解らねば、荷方の玲次に解るはずが無い。
「縄張りをする前に山方に飛ばされたからな」
「まあ……俺たち荷方が指月山に呼ばれなかったということは、一から積むということだろう」
石垣を移築するならば、指月山から木幡山に石を運ばねばならない。そのためには荷方の力が必要になる。山方にいた時もえらく切り出すなとは感じていたが、それは石垣を大規模に増やすものだと思っていた。
「山から降ろして、山へと運ぶ。これは最も大変だ。覚えておけ」
玲次はこちらを向かずに言った。
「へえ、そうか」
「お前、何年穴太衆にいる。何も知らないのか」
間延びした返事に玲次は嚙みつく。
「仕方ねえ……」
玲次は源斎の言いつけだからと、ぶつくさ言いながらも解説を始めた。玲次は源斎に対して絶大な信頼をおいているのだ。
「そもそも一つとして同じ地はなく、全く同じ石垣は組めない。それは知っているな」
「ああ」
玲次に言われずとも、そのことは積方の己のほうが詳しいだろう。
「いらない石を弾くだろう?」
「だいたい三割ほどは使えなくなる」
地形に合わせて石垣を組むのだから、不要な石も出て来る。時と場合によるが二割から四割は用を成さなくなってしまう。
「石垣を崩す。移す。石を吟味する。足りぬ分を山方は凡その大きさを聞いて切り出す。荷方がそれを運ぶ。組み替える……やるべきことが六つになるな」
「確かに、そうだ」
「だが一から組むならば……」
「三つ」
「そうだ」
山から切り出す。運ぶ。組む。量こそ多くなるが、それでもこちらのほうが迅速に石垣を組めるという。
匡介は現場に到着した石と格闘することだけを二十余年続けてきた。故に山方、荷方がそれぞれ苦労して石を供給していることは知っていたが、その考え方や方法は全くといっていいほど知らない。別に山方や荷方に興味が無かった訳でなく、
――石と向き合うのに、幾ら時があっても多過ぎるということはない。
と、源斎から耳に腁胝が出来るほど聞かされた。現にこの歳になっても、まだ一人で石垣を組むことを許されていない。余事にかまける余裕は無かった。だからこそ今回の山方や荷方へ行けということの訳を汲み取れずにいるのだ。
「急ぐ必要があるということか……何故だ?」
戦国の世ならば、速く造るということも重要なことであった。うかうかしていれば敵が攻めて来るかもしれないからである。だが天下は豊臣家によって保たれており、一揆などを除けば戦は起きていない。穴太衆としてもわざわざ作業を遅くしようとは思わぬが、かといって疾風の如き速さで組む必要はない。
「知るかよ。御頭に訊け」
玲次はぞんざいに答えた。そもそも速く造るというのも、源斎の意思ではなかろう。穴太衆はあくまで技能を売る集団。依頼主がいてこそ成り立っている。
どのような石垣を構築するかは相談に乗るものの、その普請の期日などは依頼主の意向を優先する。要求されたその期日が短くとも能うならば受け、能わぬならば断るだけである。
伏見城は豊臣秀吉が隠居のために建てた城。これの移築となれば当然、依頼主は秀吉となる。つまり秀吉が何らかの訳で急いでいるということになる。
「戦が起こるのか……」
一介の石積みの己には天下の情勢は解らない。だがこの突貫での移築はそうとしか考えられない。
「俺たちは石垣を造ればいい……おい、とっとと縄を掛けろ。日が暮れちまうぞ」
玲次は会話の合間にも、縄掛けに手間取っている若い衆に指示を飛ばした。
「後はどうでもいいってか?」
意識した訳ではないが、声が低くなる。
昨今、穴太衆の中には石垣を造り、銭さえ受け取れれば後はその城がどうなってもいいと考えている者も多くいる。訳は簡単で、二度とその城に携わることが無いからである。穴太衆の中では、
――五百年で一人前。三百年で崩れれば恥。百年などは素人仕事。
と、専ら言われている。穴太衆に身を置くものならば、どれほど下手に組んだとしても百年から二百年は崩れない。つまり軽微な修復はともかく、己が組んだ石垣をもう一度組み直すことは生涯訪れないのだ。
とはいえ、それで手を抜く穴太衆はこれまでいなかった。しかしこれも泰平の弊害か、少しでも多く仕事を取り込もうと、質を捨てても速く造ればいいという不逞の輩が昨今増え始めている。
「そうは言っていない。俺たちの腕が疑われるからな」
玲次はこちらを向いて凜然と答えた。
飛田屋の中にはそのような輩は一切いない。飛田屋を率いる源斎は、
――千年保つ石垣を造れてようやく半人前だ。
と、穴太衆の常識よりも遥かに高い目標を掲げ、どこの組にも負けぬ丁寧な仕事を心がけてきた。乱世では仕事が溢れ、各組が大車輪のように仕事を取り込もうとした時も、源斎だけは慌てず騒がずに至高のものを目指した。故に多くの仕事を取りこぼし、他の組に飛田屋は悠長だと小馬鹿にされたこともある。
だが戦が鎮まり、天下に静謐が訪れてからというもの仕事は全体として激減した。当時に多くの仕事を受けていた組は暇となったが、飛田屋は以前と変わらず、いやそれ以上に仕事が舞い込んできている。諸大名が飛田屋の石垣を高く評価しているからである。
「俺に貸せ。よく見て覚えろ」
先ほどの若い衆が未だ手間取っている。玲次は見かねて自ら巨石に縄を回し始めた。
玲次は弛みなく手足を動かしながら、話を戻した。
「しかし、地揺れや、野分はともかく……戦となれば、破られることはある。俺たちは最善を尽くせばいい」
「それじゃあ駄目だ」
匡介が言うと、玲次は一瞥して舌打ちした。
「馬鹿。千人で守る城に、十万が攻めかけてみろ。いくら石垣が良くとも、城は落ちるさ」
「それでも守れる石垣を造ってみせる」
玲次は縄を捻って輪を作ったり、その間を通したりと流れるように手を動かす。要所では石に足を掛けて締め上げ、それを何度も繰り返して最後に縄を結んだ。
「一朝一夕じゃあ無理だ。また俺がやる時に声を掛けるから見に来い」
玲次はぴしっと石を叩いて、若い衆に向けて言った。
「はい!」
若い衆は頰を紅潮させ頷く。何も怒鳴り散らしているだけではなく、自ら率先して手本も示す。口は悪いのに玲次が配下の者に慕われる一端を見たような気がした。
玲次は片頰を顰めるようにして、こちらに歩を寄せてきた。
「どんな大軍でも撥ね返す石垣を造るってか?」
「ああ、そのつもりだ」
「この話になるといつもそうだ」
玲次は辟易したように、深い溜息を零した。初めて玲次と大喧嘩したのもこの話題だったのだ。以後、似たような話で何度もぶつかってきている。互いに齢三十となった今、摑み合い、罵り合うようなことはないが、未だにその点では折り合いがつかないでいる。
あれは確か十八年前のこと。織田信長配下の将、荒木村重が摂津有岡城に立て籠って反旗を翻した。遡ることさらに三年前、この有岡城の大改修の折、石垣を組んだのが当時三十六歳の源斎であったのだ。
織田家の大軍の前に、有岡城は一年もの長きに亘って耐え抜いたが、やがて陥落した。城主の荒木村重は落城前に逃走し、残された女房衆百二十二人が鉄砲や刀で殺された。一族郎党五百十二人も四軒の農家に押し込められ、生けるままに火を放たれた。中には齢五つの子どもまでいたという。
――どんなに堅牢でも、破られれば意味が無い。
子どもながらに匡介はそのように口にし、それを源斎への侮辱と取った玲次が激昂して喧嘩に発展したのである。
「穴太衆が如何に鉄壁の石垣を拵えようと、愚将が守れば用を成さない」
湖岸から琵琶の湖へと視線を移しながら玲次は言った。
荒木村重は摂津を自らの手で切り取った実績を持ち、決して凡庸な男ではなかった。しかし謀叛の後の彼の行動は、名将とはかけ離れたものであったことは確か。織田家の大軍の前に腰が引け、全てを捨てて逃げ去った。長い籠城は神経を削り、人を変貌させる。その時の荒木も正気ではなかったのだろう。その証左に、荒木は後に自ら「道糞」という号を名乗った。読んで字の如く、道端の糞という意。妻を捨て、子を見殺しにした己を恥じ、自虐的な号を付けたと思われる。
「それでも有岡城は一年もの間耐え抜いた。御頭の楯が良かったからな」
穴太衆では時に石垣のことを「楯」と呼び、玲次もそれに倣っている。
「楯を生かすも殺すも将次第か……名将とはどんな男なのだろうな」
匡介も遠くを見つめた。煌めく湖面の先、対岸に近江富士とも呼ばれる三上山が見える。
「俺には解らないが、殿下が今の世には二人の天下無双がいると仰ったと、世間で専らの噂だぜ」
殿下とは、百姓から天下の主にまで上り詰め、今の安寧を作り出した男、太閤秀吉のことである。玲次は半年ほど前に京を訪れた時、噂話の好きな京雀たちが話しているのを耳にしたらしい。
「一人は本多忠勝か」
「当たりだ」
かつて織田信長の盟友にして、豊臣秀吉とも天下を争った徳川家康。後に和議を結んで傘下に入って、今は豊臣政権の五大老筆頭の席に座っている。その家康の配下の猛将である。四十数度の戦に出て一度も傷を負ったことが無く、秀吉と戦った小牧・長久手でも豊臣軍を散々に悩ませた。以来、秀吉は本多忠勝を買っており、事あるごとに褒めそやしていると、世事に疎い匡介でも知っていた。
「もう一人は?」
尋ねると、玲次は拳を口に当てて咳払いをして答えた。
「東に本多忠勝と謂う天下無双の大将がいるように、西には立花宗茂と謂う天下無双の大将がいる……だとさ」
「立花宗茂……」
名は聞いたことがあるように感じたが、匡介は詳しいことを何も知らなかった。
「筑後十三万石の大名で、鎮西一の武将との呼び声が高いらしい。驚くことに歳は三十だとよ」
「俺たちと同年の生まれじゃないか」
少し吃驚して声が上擦った。齢三十は立派な大人であるが、天下の双璧と語られるには若すぎるといってもよい。何でも島津の九州統一に抗い、齢二十にして抜群の武功を立てたのを皮切りに、この十余年で負けらしい負けは無いらしい。今も唐入りに従軍して、十倍からなる明軍を難なく屠ったと伝わってきているという。
「そのような男に石垣を任せれば、鬼に金棒かもしれないな」
玲次の言う通り、いくら穴太衆が堅固な楯を造ろうとも、愚将が扱えば紙の壁のように脃くなる。反対にそのような名将ならば鋼の如き守りになるのが現実かもしれない。
――だが、それじゃあ駄目だ。
匡介は心中で呟いた。籠城戦が始まれば、城下の民も城に逃げ込む。民が逃散することを恐れ、領主が無理やり城に詰め込むことも多々ある。つまり民は領主の勝手で強制的に戦に参加させられ、落城の時には悲惨な目に遭うことになる。そんな馬鹿げた話があってはならないと匡介は思う。
だが往々にして城に押し込められるということは、少なからず劣勢を強いられているということ。攻め方の実力が勝っていることのほうが多かった。その差を埋めて敵を撥ね返すことこそ、己たち穴太衆の務めではないか。
「お前は気負い過ぎなんだよ……」
横から玲次がぽつりと零した。
「そんなことは――」
「お前を見ていると、賽の河原を思い出す」
玲次は苦々しく言うと、身を翻して配下の若い衆の下へと歩んでいった。玲次も匡介の生い立ちは知っている。これまで何度も激しく罵り合ったが、そのことだけには触れてはこなかった。今も直言ではないが、これまでで最も踏み込んだ一言だったかもしれない。
――賽の河原か……。
匡介はそっと屈みこむ。湖畔には豆粒ほどの砂利から、抱えてようやく持ち上がるほどの石までが散乱している。そのような言葉はないが、ここは河原ではなく湖原ということになるだろう。
拳ほどの石を見繕って重ねて置いた。積方ともなれば石の重心を即座に見抜けねばならない。三つ、四つ、五つと、手早く石を積み上げていく。
「くだらない」
七つまで積み上げた時、崩そうとして手を翳した。だが馬鹿馬鹿しいとは思うものの、崩すことに気が引けた。匡介の脳裏に浮かぶのは妹の姿。笑っている顔を沢山見てきたはずなのに、こんな時に思い出すのは、決まって最後に見た己に向かって手を伸ばす必死の形相であった。
穴太衆は道祖神を信奉している。村の境や、辻、三叉路などに祀られる石造りの神で、村を守ってくれると信じられていた。その形状も様々で石像や石碑などが最も多いが、五輪塔のような複雑なもの、大きな石をそのまま据えただけのものもあった。
大陸では古くから祀られていた「道祖」と、この国古来の境界を守り邪悪を撥ね除ける「みちの神」が合わさって今の形になったらしい。
石を駆使して敵を撥ね除ける穴太衆にとって、石の結界を張る道祖神を信仰するのは自然な流れだったのかもしれない。中でも穴太衆が祀っているのは、「塞の神」という神であった。
結界によって悪から守るという点は他の道祖神と共通しているが、その性格は曖昧で時に字が似ているからか、人が死んだ時に訪れるという三途の川の河原である「賽の河原」を守る神とも同一視されている。
賽の河原では親に先立って死んだ子が、親不孝の報いを受けて石の塔を積まされるという。これが完成すれば親への供養となり、自らも苦役から解放される。
しかし石が積み上がる間際になると、どこからともなく鬼が来て塔を壊してしまう。何度も同じことが繰り返されることで、子どもたちは一向に解き放たれない。
だがそれでも諦めずに積み続けると、神仏が現れて救ってくれる。これこそ地蔵菩薩だと言う者が大半だが、本来、仏教とは関係ないことからもはきとしない。道祖神を祀る穴太衆では、この地蔵菩薩こそが塞の神、あるいは賽の神だと信じられている。
考えれば不思議である。地蔵菩薩にしろ、塞の神にしろ、助ける気があるのに、何故初めから助けてやらないのか。子の多くは早世を望んだわけではない。生きたいと願っていたのに、飢えによって、病によって、あるいは戦によって命を落としたのだ。その無念に鞭を打つように苦役をさせる意味も解らないし、さっさと救ってやればいいではないか。この疑問にも穴太衆の教義は答えを持っていた。
神々というのは人の祈りを力に変えておられる。人々が社に参るのはそのためだという。塞の神も一刻も早く子を助けたいと願っているが、子らを供養したいと祈る者がなければ、姿を現すことが出来ない。故に穴太衆は、
――賽の河原の子を想い、現で石を積む。
そうすれば塞の神が祈りを聞き届けて下さり、苦しむ子たちに救いの手を差し伸べに現れてくれるというのだ。本当かどうかは判らない。石垣造りという戦に纏わるものを商いにしている負い目が、そのような救いの幻想を生み出したのかもしれない。
だが匡介は穴太の地に来て間もなくその話を聞き、そして信じた。妹の最後の表情を夢に見て、毎夜のようにうなされていたから、何か出来ぬかと苦しんでいたためかもしれない。
源斎が仕事で出ている日は、修業は昼過ぎには終わることになる。そんな時は、一人で穴太を流れる四谷川の河原にふらりと出かけるようになった。己が石を積めば、妹の花代を助けられるのではないかと思ったのだ。
それこそ源斎が摂津有岡城の石垣造りを差配していた頃、早朝から未の刻(午後二時頃)までみっちり石に触れた後、やはり匡介は河原へと向かった。
歯を食い縛って大きな石を運んで据える。それに一回り小さな石を。次は拳大のもの。さらに蜜柑ほどの大きさのものと石を重ねていく。下が大きく、上に行くにつれて小さな石を積み上げねば、途中で崩れてしまうのは、何も穴太衆でなくとも判ることである。
「駄目だ……」
三つ、四つまでは上手く積める。だがそれが五つ、六つになると途端に難しくなり、均衡を失って崩れてしまう。幾つ積めば終わりかは知らない。だが少しでも高く積み上げねばならないという衝動に駆られ、匡介はまるで己が賽の河原の囚われ子のように、何度も何度も石を積み上げることを試みた。
傾いた陽が河原の石を薄茜に染める。日が暮れるまでにもう一度、そう思って石を手にした時、背後から石の擦れる音が近づいて来ることに気付いた。
振り返ると、源斎が顎髭をごしごしとしごきながら近づいて来るのだ。
「父……上」
源斎は己を養子に迎えて、飛田屋の跡取りに据えると宣言した。故に衆目がある場では師匠と、無い場では父上と呼ばねばならないと、段蔵から嚙んで含めるように言われた。
だが実父も、父であると同時に己に象嵌の技を教えてくれた師匠でもあった。父としては優しく、師匠としては時に厳しく、共に過ごした日々を大切に胸にしまっている。源斎を父や師匠と呼ぶことは、実父への裏切り、共に生きた時を消し去るような気がして躊躇われていた。
「相変わらず呼びにくそうだ」
源斎は苦笑しながらこめかみを指で搔きつつ言葉を継いだ。
「段蔵の申すことは気にしなくてもいい。爺とでも呼べ」
「それは……」
実父と歳もそう変わらず、源斎はとても爺と呼べるような歳ではない。
「お前は祖父の顔は知らぬと言ったな」
一乗谷から穴太に向かう間、源斎は匡介の身の上について多く問いかけた。それは己という人を、まずは深く知ろうとしているように思えた。故に祖父はすでに亡くなっていることも知っている。祖父は父と異なり、酒浸りで碌に金を家に入れず、父たちは大層苦労したと聞いている。故に匡介は何の感慨も持たぬどころか、会ったことも無いのに淡い憎しみすら抱いていた。
「祖父殿の代わりなら構うまい。恨み言をぶつけられぬ分、俺に当たればよい」
からからと笑いながら、源斎は自らの胸を拳で軽く小突いた。
「何故……ここに?」
源斎は仕事で摂津にいるはずで、帰りはまだ数日後だと聞いていた。
「用済みさ」
源斎は手をふわりと宙に上げ、苦み走った笑みを浮かべた。
「え……」
「荒木様は俺の石垣が気に喰わなんだらしい」
源斎は有岡城に未だ誰も仕込んだことのない石垣を拵えた。戦の中では必ずや役立つものと確信しているが、どうも荒木から見れば見栄えのよくないものだったらしい。
「見栄えなんて……」
「ああ、見栄えなんてな」
匡介が呟くと、源斎は全く同じ言葉でこたえて頰を緩めた。
「いくら綺麗でも、守れなけりゃ意味が無い」
まさしく一乗谷という町が、朝倉という家がそうであった。町は京風に整然と整備され、美しい土塗りの壁、その上には細工の施された瓦が葺かれていた。朝倉家は格式を重んじ、公家風の暮らしを好み、世間に威をふるっていた。しかし実際それらは戦には何の役にも立たず、一夜にして夢のように霧散した。
「石垣の美しさは堅さ。それに尽きる」
傍らに立つ源斎は、顎髭を撫ぜながら全身で風を受けるように仰け反った。
「堅さ……」
「人が何と言おうが、破られないものが最上。人の命を守るものが醜いはずはないだろう」
全くその通りだと思った。一乗谷に住む全ての者が「醜い」というものでも、父母や花代の命を守ってくれたならば、匡介だけはそれを美しいと言い切っただろう。
「だがそれが難しい。人が造ったものは、人の力で必ず崩せる」
源斎は膝を曲げて屈むと、今しがた匡介が積んだ石の塔をじっと見つめた。確かにこれを指で小突けば、ばらばらと音を立ててすぐに崩れる。
「塞王が積んだものでも……?」
「お前、それをどこで?」
匡介が尋ねると、源斎は意外そうに問い返す。
「皆が話しているのを聞いた」
飛田屋の面々、その他の穴太衆から聞いたことである。
穴太衆は紙に一切の記録を残さない。穴太衆は石垣積みだけでなく、依頼主から縄張りの相談にも乗る。城造りに自信の無い依頼主だった時などは、縄張りを穴太衆に全てまかせることさえあった。それほど穴太衆の技術が高く評価されているという証左である。
城の縄張りは重要な機密であるため、穴太衆は紙に一切の記録を残さず、全て頭の中に図面を引いて行う。そしてそれは同じ穴太衆であっても決して外に漏らさない。
積み方の技術も同様である。一子相伝、しかも全て口伝である。こうして穴太衆は技術の漏洩を防ぎ、依頼主の信用を勝ち取ってきた。
だがその弊害として、穴太衆の起源はよく解らなくなっている。ある組では陸奥から流れてきた者が土着したと言い、またある組は蘇我氏に従って飛鳥にいた者が流れたと伝わっている。飛田屋では遥か昔、大陸の一族が九州を経てこの地に至ったと信じられている。だがどの組にも一つだけ共通する伝承がある。
穴太衆の祖は塞の神の加護を受けており、どのような地揺れにも堪え、どのような大軍からも守る石垣を積んだと言われている。故に穴太衆たちはその祖のことを、神に次ぐ者の意として「塞王」と呼んでいる。
そこから転じ、穴太衆の中で当代随一の技を持つ者が塞王の称号を名乗ることになっていた。そして当代の塞王こそ、この飛田源斎なのである。
源斎は苦く笑って口を開いた。
「俺が積んだ石垣も同じ。人の力で崩せる。塞王なんて本当にいたのかは判らないが……いたとしても崩れないなんて話、後の世の誰かが付け加えた噓じゃあないかと思う。だから神じゃなく、王なのさ」
王も所詮は人。幾ら卓越した技術を持っており、極めて優れた石垣を生み出せたとしても、神とは異なり決して破られないということはない。塞王の呼称には、そのような戒めの意が含まれているような気がすると源斎は言った。
「崩れない石垣を造る者が塞王……はて、そんなものか」
源斎は独り言のように零し、ぞんざいな手付きで拳大の石を拾い上げた。源斎は塞王として持ち合わせる事柄を別に考えているような口振りである。
「他に何が……?」
自らの膝を抱え込むように屈んだまま、匡介は上目遣いに尋ねた。
「ふむ。今のお前に話しても無駄だ。この下手くそめ」
源斎は石の塔を目掛けて顎をしゃくった。
「爺……」
源斎の仕草が何とも憎たらしく、思わず口を衝いて出てしまった。
「お、呼べるではないか。小僧、よく出来た」
先ほどまでは神妙に話していたくせに、急に話をはぐらかした。子ども相手に大人の取る態度ではなかろう。揶揄っているのは解るのだが、妙に腹が立ってくる。
「俺は塞王になる。なって爺を引きずり降ろす」
「ふふ……意気はよい。だが下手くそに出来るかな」
「出来る」
「おう、やってみせろ」
源斎は言うや否や、手に持っていた石を石塔の頂点にさっと据えた。匡介はあっと声を上げた。最も上の石は親指ほどの大きさである。拳大の石など載せれば瞬く間に崩れてしまうと思ったのだ。
「え……」
石塔は崩れない。ぴくりとも揺るいでいなかった。ここしか無いという重心を捉えている。それもまるで地の上に石を置くかのように軽々と、目を疑うほどの速さで源斎はやってのけた。
「下手くそ」
源斎はからりと笑うと、立ち上がってその場を後にした。確かに源斎の言う通りだと認めざるを得ない。たかが河原での石積みであるが、それほど源斎の手際は鮮やかであった。
だがいつかこの男を超えてやるという闘志も、同時に心の中に渦巻く。離れていく源斎の背を見つめていると、その感情が昂って思わず叫んだ。
「俺はあんたを必ず超える。塞王になってみせる!」
源斎は何も答えずに片手をひょいと上げて遠ざかっていった。
この日、匡介は初めて源斎を意識し、石積み職人として頂点を極めようと心に誓った。川面が今日を名残惜しむ夕陽に煌めき美しい。賽の河原に神が現れたならば、このような心地ではないか。豆粒のように小さくなっても、なおも大きく見える源斎の背を見つめ、そのようなことを茫と考えていたのを今もよく覚えている。
出発当日の朝、玲次は積み荷の最後の確認を行った。縄が緩んでいないか、石の積み方に無理はないか、荷方の頭が自ら調べていくのである。匡介もその横を歩いて共に見廻った。
玲次は一台の荷車の前で足を止めた。縄に指を掛けると、弓の弦を扱うように思い切り弾いた。
「少し緩んでいるな……」
玲次は一度縄を解くと、改めて結び直そうとする。縄に輪を作って捻り、その中に縄を通す。もやい結びといわれる結び方で、これが最も締まる。最後に荷車に足を掛け、思い切り締め上げた。流れるような手捌きで、これまで何度もこの作業をしてきたのが一見して判った。
「新米が締めたんだろうよ」
玲次は呟きながら両手を払った。
「荷方は数が多いからな。目配りが大変だろうな」
己と言い争っている時の玲次と違い、この場で見ると無性に頼もしく見え、匡介は素直に感心した。
荷の仕分けが終わり、居並ぶ配下を玲次はゆっくりと見渡す。そして横に立っていた匡介が、耳朶を覆いたくなるほどの大音声で叫んだ。
「目指すは伏見。かねてより打ち合わせた通り行くぞ!」
「応!!」
応じる配下の野太い声が固まりとなって、蒼天を衝くが如く立ち上った。段蔵が率いる山方も威勢がよかったが、玲次の荷方はそれ以上である。
まず数が違う。山方は三十人ほどであった。それに対して荷方は百を超える。いや純粋な数という意味ならば、匡介がいる積方も負けぬほど多い。だがその大部分が近郷から季節で集める人足で、純粋な飛田屋となると源斎と己も含めて八人しかいない。源斎が総指揮を執り、匡介がそれを補佐。残り六人が指示を人足に的確に伝えて積ませていく。荷方はこれとも違い、この百人超全てが飛田屋の職人であった。
匡介は積方として、いつもは現場で彼らを迎える立場である。到着する四半刻(約三十分)前、山間などだと一刻(約二時間)も前から、荷方の活気溢れる声が聞こえてくるのだ。だがこの輪に入って聞く声の熱量は、その時に感じるものよりも遥かに大きい。
持ち場に散って行く配下を見ながら、匡介が呆気に取られていると、
「石船が出るぞ」
と、玲次は湖岸に近づいて行く。
石船には二種類ある。一つは船の構造は他とそう変わらないもの。これには小ぶりの石を積載する。余りに積み過ぎれば転覆の恐れがあるので、喫水線をしっかりと確かめる。
もう一つは巨石を運ぶための船。飛田屋では「潜船」と呼ばれている。構造としては大きな筏を並べ、二本の丸太でつなぎ合わせた恰好である。その間に縄で括った石を沈めて運ぶのだ。浮力を利用するため、巨石でも難なく運び出すことが出来た。目的地近くの川まで来たら、修羅と呼ぶ橇で引き、そこからはころでもって陸に上げるのだ。
出航する船団に向けて玲次は叫んだ。
「明日は空が荒れるかも知れねえ。瀬田川は一気に抜けろ! 遅れるなよ!」
船の中から配下が手を上げて了承の意を伝える。
琵琶の湖から瀬田川に出て、天ヶ瀬の渓谷を抜ける。そこから徐々に川幅が広がって、その辺りからは宇治川と呼ばれるようになる。宇治川は今回の目的地である伏見のすぐ傍を流れている。その地点で石を降ろす段取りになっていることだけは聞いていた。船に荷の七割は載せてあるが、他は地車や石持棒に括られたままとなっていることに気づいた。
「船の戻りを待って、残りを積み込むのか?」
匡介が訊くと、玲次は鼻を小さく鳴らした。
「そんな無駄なことをするか。悠長に構えていたら荷方は務まらねえ」
「じゃあ……」
匡介は言葉を詰まらせる。
「走るのさ」
玲次は不敵に片笑み、ことも無げに言い放った。その目の奥に矜持のようなものが見えた気がし、匡介は暫し茫然と眺めていた。
大津から伏見までは約五里(約二十キロメートル)。並の旅人の脚ならば休みなく歩いて約二刻半ほど。実際には小休止も挟むことになるだろうから三刻。距離だけでいえばそうなるが、大津から京に入るまでには、勾配のある逢坂の関を越えねばならず、今少し時を要するだろう。
しかしこれは身軽に歩いての話。今回は大量の石を携えていくのだから訳が違う。石持棒を担ぐ者は旅荷の何倍もの重さを担うのである。牛馬が曳く地車を誘導する者は一見楽そうに思えるが、速く駆りすぎては潰れてしまい、遅ければ一行から遅れる。飼葉を食わせたり、水を飲ませたりと、とにかく気を使う。
「二刻で行く」
玲次はそう宣言した。石を運びつつ、並の旅人よりも速く走破するということ。一度も休憩を挟まないことは当然、平地では駆け足になる。常人なら当然、他の穴太衆でも驚愕する速さである。
「皆の衆、行くぞ!」
荷方百余名の内二十人は船に乗った。残る八十余名が玲次の号令で、喚声を上げて動き始める。
匡介も石持棒を肩に載せ歩を進める。荷方の若い衆たちは、副頭にそのようなことはさせられぬと止めた。しかし匡介は、
「俺の好きにさせてくれ」
と、有無を言わさず加わったのである。
源斎が何のために、己を山方や荷方に行かせたのかは解らない。だがここでやれなければ、
――お前も根性がねえな。
などと、白髪交じりの髭を撫ぜつつ、薄ら笑いを浮かべるのが容易に想像出来、それも癪に障る。
匡介は皆と共に駆けた。駆け足程度の速さであるが、石を担いでいるためすぐに息が弾んだ。揺れと共に棒が肩に食い込んで鈍い痛みも走る。
だが他の荷方は平然として担いでいる。武士が槍や刀を長年握って手に腁胝が出来るように、荷方を務める者の肩は瘤のように盛り上がっている。約二里ごとに載せる肩を交換するので、左右どちらもがそうなっており、皆がいかり肩のようになっていた。
「どうだ。痛いだろう?」
玲次は横を並走しながら言った。玲次は気合いをかけながら鼓舞する。そのため担ぎ手には加わっていない。
「心配ない」
匡介は歯を食い縛って答えた。
「やせ我慢はするなよ。苦しくなったらすぐに交代だ」
玲次の他に三人、玲次と同じように手ぶらで走る者がいた。誰か体調に異変があれば、すぐに交代させる。疲れが顕著な者も同じく一度担ぎ手から外して、休ませつつ向かうのだという。その差配も荷方の頭である玲次が行う。そのために常に皆を見渡していた。
「事故を起こさない。それが荷方にとって、もっとも重要なことだ」
玲次は話している間も、絶え間なく首を振って目配りをしている。
石の運搬で事故が起こることは珍しくはない。穴太衆全体の中で年に一、二度は起こっている。一人が気を失って倒れ、均衡が崩れて石を地に落とす。足の上に落とせば骨折だけで済まず、切断しなければならないこともある。それでも命があるのはまだましというもの。命を落とすような事故も珍しくはない。
「遅れが生じちまう」
命を守るためとでも言うのかと思ったが、玲次の思いのほか乾いた物言いに面食らった。それを察したか、玲次はすぐに言葉を継いだ。
「例えば今の体制だと、一人が離脱するまでは何とか埋め合わせられる。だが二人ならば半刻。三人ならば一刻。四人ならば二刻は遅れる。それ以上ならば半日、一日の遅れは避けられねえ」
玲次は淡々とした調子で続ける。
「荷方は決められた時刻に、決められた分を必ず運ぶ。それが全てだ。いつ敵が攻めて来るか判らない時、石が一日遅れて石垣が造れず、落城したなんて笑い話にもならねえ」
確かにそれは積方でも同じである。堅い石垣を造るのは当然のこと、一刻でも早く完成させることを肝に銘じている。それで敵が攻めて来なければよい。攻めて来る可能性が残る限り、最速で最高のものを積み上げる。
他の組の中には、戦国の真っただ中ならいざ知らず、この泰平の世で敵などいないと鼻で嗤う者もいた。だがいつ何時誰かが謀叛を起こさぬとも限らない。万が一のことがあって、あと一日早く積み上げていればと後悔しても後の祭りである。
「積み上げる一日を稼ぐために、俺たち荷方が全力で運んでいるのを覚えておけ」
「全てを船で運ばないのも……」
「ああ、時が無駄になる」
即座に答えた。全員が乗船したならば、必然的に運べる石はその分だけ少なくなる。出来るだけ多くを積載して川を下らせるほうがよいのだ。
しかし目的地の傍に着けば、船から石を降ろさなければならず、それには多くの人手がいる。故に走って先回りして船を待ち受けるのだ。その際に手ぶらで走らず、三割程度の石を携える。これを先に石積みの現場に送り届け、船着き場まで急いで走って石を迎え入れる。これが今回、もっとも時を無駄にしない方法だと言う。
「これこそが荷方の頭としての重要な務めだ」
このように目的地まで最も早く、効率のよい運搬計画を練る。その際に天候や川の流れにまで気を配る。これさえしっかり考えられれば、荷方の仕事の八割は済んだようなものだと玲次は言う。匡介もただ漫然と運んでいる訳ではないと思っていたが、ここまで緻密に計算されているとは知らなかった。
だが玲次が幾ら気を配っても、天候が荒れて川が渡れず遅れるようなこともあった。そんな時に匡介は苛立って、
――運ぶくらいとっととしやがれ。
と、腹の内で罵っていたこともある。だが初めて荷方に加わって、ただ運ぶだけだなどとは口が裂けても言えないと思った。運ぶということで、荷方も石垣を造ることに大きく寄与している。
「すまないな」
思わず口から零れ出た。玲次は目を丸くして驚いていたが、ちっと舌を鳴らした。
「気持ち悪いことを言うな。俺たちはきちんと運ぶから、とっとと積みゃあいい」
「しかし何で今更……」
このような苦労があるのならば、早く知る機会があればよかったと素直に思う。だが二十数年もの間、同じ組にいながら山方、荷方の苦労は表面上しか解っていなかった。
「栗石十五年……だろ。積方にそんな余裕はねえ」
玲次は通った鼻筋を指で弾いた。
石垣を造る時、栗石という拳大の石を敷き詰め、その上に大きな石を載せる。そこに「飼石」という石を嚙ませ、巨石と交互に積み上げるのが野面積みの基本的なやり方である。
その栗石の表裏、向き、配置によりその敷き詰め方は無限にある。その中で最善を見つけねばならない。この作業を覚えるだけでも、最低で十五年の時を要すると言われた。己は人より早く次の工程に進むことを許されたが、それでも十二年目の春であった。
「それで半人前。一人前になるには三十年は掛かる。お前は早いほうだ」
「どういうことだ」
「聞いていないのか?」
玲次は片眉を上げて続けた。
「今から二十八年前。頭も跡を継ぐ前、山方や荷方に回されたんだとよ。段蔵爺が言っていた」
二十八年前から飛田屋にいた者は段蔵一人となっている。玲次も聞くまではそのようなことがあったことを知らなかったらしい。その話を聞いた時に段蔵からは、腹に据えかねることもあろうが、くれぐれも若を頼むと念を押されたのだという。
「そんなことは一言も……」
「まずかったか」
玲次は首を捻って苦い顔になるが、意を決したように続けた。
「間もなく、修業も終わりが近いということだろう」
いつ終わるかも判らぬ修業に二十三年もの間没頭してきた。ある意味それは賽の河原の石を積むのに似ている。そんな日々に終わりが近い。そう聞いてもなかなか実感が湧いてこない。
もう少し喜んだらどうだとでも言いたげに、玲次はまた舌打ちをくれる。荷方の連中の喚声に包まれながら、匡介は長い坂道の先に浮かぶ白い雲を見つめた。
荷方一行は休むことなく駆け続けた。途中、京の東山を抜けた時などは野次馬が集まり、やんやと囃し立てる。玲次は先頭を駆けながら、野次馬に道を開くようにと叫び続け、よくそれで喉が嗄れないものだと感心した。
野次馬の中には、石に向けて両手を合わせて拝むような媼もいる。村々に注連縄を回した石を置くなど、穴太衆の信仰する道祖神は、民衆の暮らしにも深く根付いているのだ。
人の想いが籠った石は強い。迷信かもしれないが玲次はそれを信じているようで、石持棒を担う一組の脚を止めさせ、
「婆さん、もういいかい?」
と、一転優しく話しかけた。己たち積方の下に届くまでに、このようなことを経ているのだということも、恥ずかしながらようやく知った。
棒が肩に擦れ、皮が捲れて腫れあがる。これを何度も繰り返して硬い皮が張ってようやく荷方としてものになる。匡介は痛みに耐えつつ、必死に脚を回した。
「よし、もうすぐだ! 気合いを入れろ!」
伏見木幡山の麓に辿り着くと、玲次はさらに気勢を上げた。
ここまで石を担いで休みなく駆け通して、最後の最後で山を登るのだ。常人ならば倒れ込む者が続出するだろうが、荷方の体力には目を瞠るものがある。
「俺たちは手ぶらなら、日に二十五里も走れますからね」
隣で棒を担ぐ荷方が口元を綻ばせる。名を権六と謂い、もう四十は超えているはず。汗こそ滝のように流しているが、疲れの色は一切見えない。権六のような初老でもこうなのだ。二十、三十の荷方はけろっとしている。
膝が笑うのを叩いて抑え込み、匡介は最後の力を振り絞って木幡山を登り切った。陽が中天を過ぎた頃である。玲次が初めに見立てたように二刻で走破したことになる。
「おー、来たか。案外早かったな」
石積みの現場にいる積方二人が迎え入れた。
――何を吞気に……。
こちらの苦労に比べ、積方の対応が余りに気楽な調子に思え、怒りが込み上げて来た。
「もう少し、早く送るつもりだったんだが、すまねえな」
玲次は怒るどころか、さらりと詫びの一言で返した。玲次からすれば慣れたことなのか、いや本心から少しでも早く石を送ってやりたいと思っていたのだろう。
匡介もよく見たやり取りではある。ただ常に己は向こう側、積方のほうにいた。見る側が違えばこうも景色が違うのか。
「お、若!」
石を置いた時、積方の一人、己より二つ年上の番五郎がこちらに気付いた。
「玲次、若は荷方を見分に行っているだけだ。何も担がせることは――」
番五郎が血相を変えて玲次に詰め寄ろうとするのを、匡介は声を荒らげて止めた。
「俺が好きで、やってんだ!」
「若……」
今日、ここに荷方が到着することは積方も承知しており、着き次第、水と飯を配って休ませる。積方の中で最も下の者の役目である。
いつもは飯を配っているのを横目に見ながら、匡介は黙然と石積みを続けていた。その己を荷方の者たちはどんな目で見ていたのだろうか。そのようなことを考えると、無性に己に腹が立つ。
「とっとと、飯の用意をしろ」
匡介が苛立ちを隠さずに言うと、番五郎は弾かれるように走り出して指示を出し始めた。
「へえ……」
玲次が腕を組みつつ眉を開いた。匡介は小さく舌打ちをしてその場を離れ、手頃な木にもたれ掛かってどかりと腰を下ろした。息は一向に静まらず胸を上下させる。肩は傷口に塩を摺り込まれたように痛み、脚は棒になったかと思うほど強張っていた。
麦の混じった握り飯が配られ、荷方の連中は旨そうに頰張る。己の下にも運ばれてきたが、匡介は吐き気を堪えるのが精一杯で喉を通りそうになかった。
瞼を持ち上げるのも億劫で薄目で顎を上げた。生い茂る葉の隙間から茜が零れる。風で葉がさざめくと共に影も揺れている。
「ほらよ」
声がして視線を下げると、そこには柄杓を片手に持った玲次の姿があった。ぶっきらぼうに差し出された柄杓には水が満たされている。
「まずは喉を潤せ。そのあと飯を流し込んでおけ」
口端から零れるのも気にせず、匡介は柄杓に嚙みつくように水を流し込んだ。大きな嘆息と共に柄杓を膝の上に落とす。
「きついだろう」
玲次は横に腰を落として言った。
「ああ、思った以上だった」
「この後、川に降りて船の石を陸に引き上げる。そしてまたここに運ぶ。二往復でいける予定だ」
全体の八割の人数で、三割の石を運んできた。石は残り七割。船に乗っていた人員も合流するため、二回で運び終える。人の動きにも一切の無駄が無いように計画されている。しかも先に三割の石が届いたことで、積方は作業に入ることが出来るのだ。
「色々、考えていたんだな……」
握り飯を少し齧り何度も咀嚼した。米の仄かな甘みがいつもより強く感じられた。
「当たり前だ。俺たちは積方の仕事が少しでも捗るよう、支えているつもりだ」
「すまない」
玲次は今一度謝った匡介を一瞥して苦笑する。
「俺もずっと積方にいるつもりだった」
「ああ」
穴太衆の他の組では山方になったら石を切り出すだけ、荷方は石を運ぶだけしか出来ない。だが飛田屋に限っては違う。まずこの道に入った時、三年ほど基本的な石の積み方を覚えさせられるのだ。故に飛田屋の職人は、積方は当然、山方であろうが、荷方であろうが、皆が最低限には石を積むことが出来る。
「いわば石の手習いのようなもんだよな」
玲次は昔のことを思い出しているのだろう。飯を頰張る一等若い荷方を眺めながら言った。
まず三年間、石積みの基礎を学んだ後、全員が実力順に甲乙丙の三つに分けられる。最も優れた甲は積方、次点の乙は山方、それ以外の丙は荷方となるのだ。
では玲次は石積みが下手だったのか。それは違う。下手どころか常に己と一、二を競い合うほど達者であった。
源斎は己を跡取りにするつもりだと宣言したが、やはり必要なのは石積みの技。当初、跡取りと言われていた者を抜き去り、他の者が跡を取った例など、穴太衆には掃いて捨てるほどあった。玲次も諦めずに己の技を磨き続けたのだ。
「だがな……技を磨けば磨くほど、頭がお前を跡取りに指名した訳が、解るようになった。口惜しいがお前は常に俺の一歩前を行っていたからな」
柔らかな風が吹き、耳の前に零れた玲次の髪が揺れる。
匡介は何も言えなかった。玲次がずっと己を意識していることを知っていた。確かにほんの少し、僅か半歩ほどの差だが、己が先を歩いていたのも事実だと認めてもいる。
風に顔を押し込むように天を見上げ、嚙みしめるような口調で言葉を継ぎ足す。
「そんな時、頭が荷方へ移る気はないかと言ってくれた。ああ、本当に俺は才が無いのだと諦めがついたんだよ」
職人たちは最初の三年で振り分けられたところで、一生働くことになるが、それぞれの小組頭だけは違う。玲次も途中までは己と共に積方にいたし、山方の小組頭を務める段蔵も遥か昔に積方であったと聞いている。今から九年前の天正十五年(一五八七年)、二十一歳だった玲次は、源斎の勧めに応じて荷方へと移っていったのである。
「爺はお前を頼りにしている。俺以上にな」
そこで初めて匡介は口を開いた。同年代の者を上手く纏め上げ、下の者から慕われ、年配からも可愛がられる玲次の気質は天性のものだと源斎は言っていた。さらに石積みのいろはを学ぶどころか、積方でも一、二を争う玲次ならば、どの石から順に送れば有効に使えるか判断がつく。飛田屋の長い歴史の中でも、随一の荷方になるだろうと話していたのを覚えている。
「こっちが向いていたんだろうな。初めは腐る心もあったが、二、三年もすればすっかりこっちが性に合っていると思うようになった」
「そうか」
何故か匡介は安堵して息を漏らした。己が源斎に拾われなければ、きっと玲次が飛田屋を継いでいただろう。どこかでその負い目をずっと感じていたのだ。
「飛田屋全員が石積みの基礎を学ぶには意味がある。特に荷方に関してはな。あの地車、素人が積めばあの半分くらいだろう」
玲次は思い出したように視線を下げると、先ほどまで皆で曳いてきて、まだ石を降ろしていない地車を指差す。その高さは地から一丈にもなる。縄を掛けられているとはいえ、素人が見れば車輪が僅かな轍に嵌まっても、崩れるように見えるに違いない。確かに適当に積まれたならばそうなるであろう。
だが匡介から見れば、あれは簡素であるが動く石垣のようなもの。大小の石を嚙み合わせてしっかりと組まれており、少々の揺れでは崩れることはないと解る。
荷方は如何に効率よく石を運ぶかが肝要。そのために最も良い道のりを検討するのは勿論、一回で少しでも多くの石を運ぶことも考えねばならないと玲次は語った。
「皆が石を積めるというのが、飛田屋の強み。荷方にも活きたって訳だな」
「ああ、お蔭で荷方といえども、地侍の屋敷を囲むような、ちょっとした石垣なら朝飯前で積めちまう。他にもう一つ……皆が積めなきゃならねえ訳は解っているな」
「懸……だな」
戦国の世、悠長な仕事ばかりではなかった。時には敵がこちらに向けて進軍している最中、石垣の修復を依頼されることもあった。そんな突貫作業の時、飛田屋では「懸」の号令が発せられる。
積方に加え、山方、荷方、総出で石垣を積むのである。そうすれば人足を集める手間も省けるし、何より全員が石に精通している者たち。同じ人数ならば倍以上も早く石を組み上げられる。この突貫の手際の良さも、飛田屋が各地の大名に重宝された理由の一つである。
その懸が最後に発せられたのは十四年前のこと。当時、十六歳であった己や玲次も初めて呼ばれた。それ以降は一度も発せられておらず、つまり己たちに限って言えば最初で最後になっている。
「もうあの時のようなことはないだろうな」
玲次は目を細めてこちらをじっと見つめた。
「心配ない」
匡介が間をおかずに即答した。
「ならいいがな」
玲次は小さく鼻を鳴らし、己を置いて配下の元へとつかつかと歩んでいった。何を言いたいのか解っている。
――もう私怨に囚われることはないだろうな。
と、言いたいのである。
十四年前のことが昨日のことのように思い出された。匡介はこれまで一度だけ源斎に殴られたことがある。それがその時だったのである。
活気溢れる荷方の声が飛び交う中、匡介はそっと頰に手を触れた。記憶を喚び起こしていると、頰の痛みさえも滲むように蘇ってきたような気がした。
(つづきは本でお楽しみください!)
公式サイトはこちらです。
購入は全国の書店さん、またはこちらからどうぞ!

