
「ユースBで学んだこと」を整理する
こんにちは、シュウです。
ユースBの講習会が終わり、少し時間が経ちました。
すごく充実した時間だったなと思う反面、随分と昔の事のようにも感じている今日この頃です。
ただ、最終日前日にやった捻挫がまだ少し痛みますので、まだ最近のことなんだなと"痛感"しています…笑。
さて、記憶が薄れる前にこの一年で学んだことを少し整理したいと思います。
少しでも参考になれば嬉しいです!
1.「成長する指導者」は、こういう人!
JFAの講習会を受けたことがある人は聞いたことがあると思いますが「オープンマインド」という言葉があります。
オープンマインドとは…
日本サッカー協会(JFA)の理念や取り組みを共有した後、「オープンマインド(開かれた心/多様な考えや意見に耳を傾け、他者を理解し、受け入れようとする意欲)」の姿勢で臨むこと
講習会が始まる際には「オープンマインドな姿勢で講習会に臨みましょう!」とスタートします。
この「オープンマインド」という言葉
私は、とても好きです!
ただ、前期に私はやらかしました。
仲間の指導実践の際、自分は選手役でプレーしていました。指導実践なので当たり前ですが、フリーズがかかりたまたま自分に対してコーチングが入りました。
しかし、自分としては納得のいかない指摘だったので、感情的になってしまいよくない態度をとりました。
その後も指導実践が続き、終わりを迎えて
実践後に振り返り…
そして、しばらく経って私が落ち着いた頃
その時に指導実践をされてた方が
「あの時、どう伝えたら良かったですか?」
と自分のところに来てくれました。
そこでお互いの擦り合わせというか、話ができたので考えを整理することができました。
その時に、気づきました。
この方の姿勢が「オープンマインド」なのだと…
きっと逆の立場だったら「はぁ?何コイツ?」で終わっていたと思います。
でも、彼は違った。
前期から指導力ある人だなと思っていたけれど、後期になって更にレベルアップしていて「そりゃそうだよな、こういう指導者が成長していくんだよな」と思いました。

誰に対しても
「否定から入らず、良さをみつけること」
「公平であり、誠実であること」
「相手の気持ちや考えに寄り添えること」
そもそも、指導者である前に「人として」どうなのか…
こういった当たり前の部分が、ベースにあってこその「オープンマインド」なのだと改めて学ぶ機会となりました。
2.サッカーって「シンプル」だから難しい?!
このユースBでは「サッカーの全体像」の理解がとても重要でした。
正直なところ、私は頭でなんとなくわかっていただけなんだなと受講しながら痛感しました。
攻撃と守備、それぞれにおける目的は、ボールを「奪う・失わない」、ゴールを「決める・守る」です。
サッカーには、「攻撃」・「守備」・「攻撃から守備への切り替え」・「守備から攻撃への切り替え」の4つの局面しかありません。
そして…
3ゾーンの理解
「相手ゴールに近い位置なのか」・「中盤の位置なのか」・「自分のゴール前の位置なのか」
または…
時間やスペースは「あるのか、ないのか」
数は「いるのか、いないのか」
質は「あるのか、ないのか」
などなど…
一見、構成する要素は多くありそうですが、そもそも、サッカーは、お互いにボールを相手ゴールに蹴り込むスポーツです。
攻めるゴールはお互いに1つずつ、そして守るゴールも1つずつです。
これ以上でも、これ以下でもありません。
難しく考えがちですが、とても「シンプル」です。
難しい戦術を語れる人もカッコいいけれど、今回、ユースBを受講して、自分自身、サッカーを難しく考えすぎていたなと思いました。
ボールを前に運んだら相手が奪いにくるし、ゴール前で相手に寄せなきゃシュートを打たれるし…
スペースが広いとたくさん走らなきゃいけないし、いくらパスを繋いでも得点にはならないし…
当たり前なんだけど、そのひとつひとつがサッカーなんですよね、笑。

ただ、気づいたことは「シンプル」だから、いろんな考え方ができて逆に「奥深さがある」のかなと…
ユースBで、「サッカーの全体像」について、いろんな人の話や考えを聞けて本当に面白かった!
3.「リレーション」の良さ、難しさ
最初に書いたオープンマインドに繋がるところはあるけれど、少し整理して書きたいと思います。
ところで…
「リレーション」ってわかりますか?
改めて調べてみると、ビジネス界隈で使われるフレーズのようです。

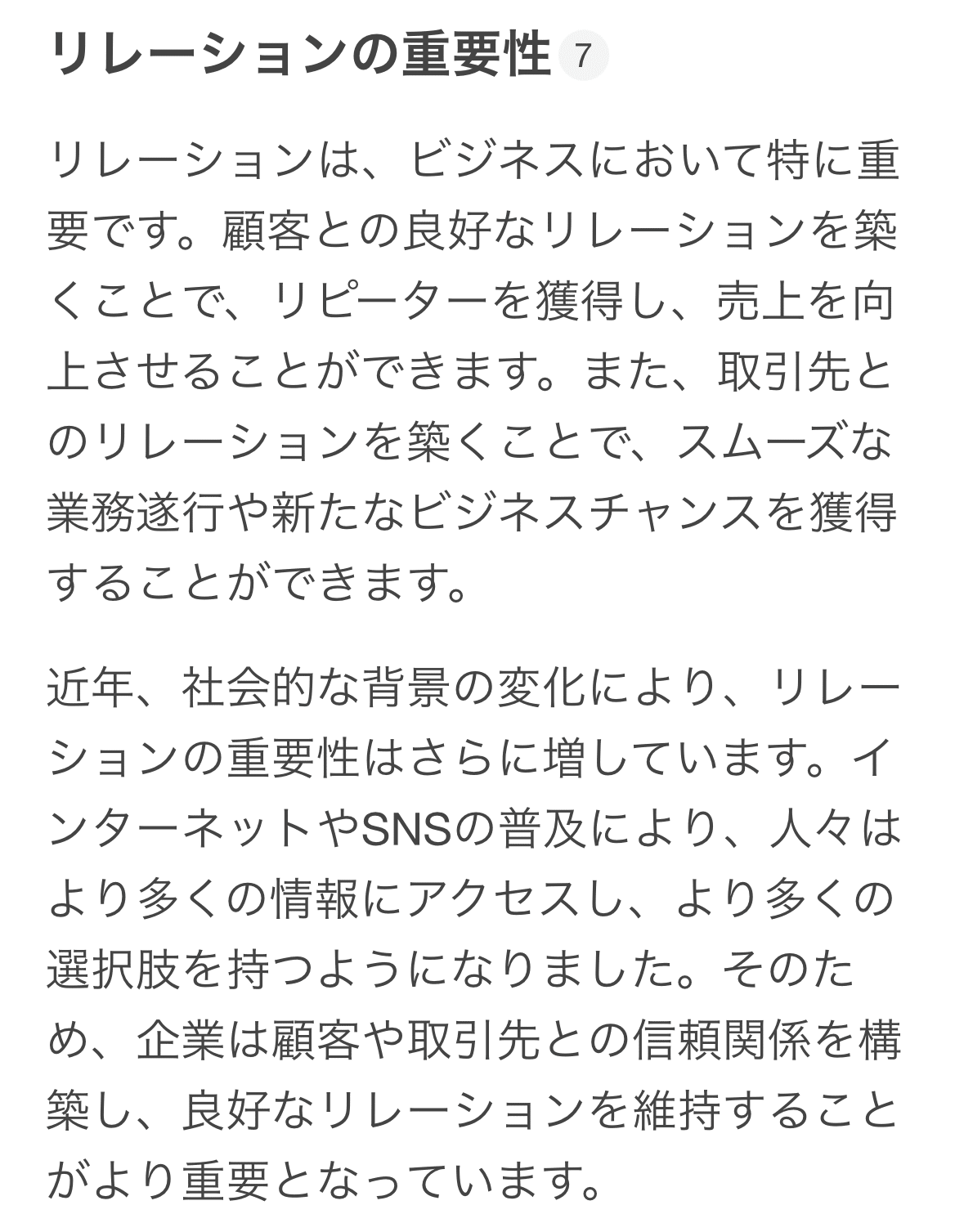

直訳すると「関係」や「つながり」と出てきます。
サッカーにおける「リレーション」…私なりの解釈は、「指導者同士の繋がり」また「トレーニングのつながり」かなと思ってます。
あってますかね?笑。
今回、ユースBでは指導実践を合計で4回やらせてもらいました。
その全てが2〜3人組で行い、役割やトレーニングを決めていきました。
その時に感じた良さは、「自分にない視点が得られること」でした。
具体的には、ルールの設定やキーファクターの整理の仕方、オーガナイズのサイズや意図、選手の人数やゴールの設定などなど…
挙げるときりがないのですが「なるほど!」「面白い!」と感じるものが沢山ありました。
一方で、難しさは、「イメージの共有」ですね。
あれだけ打ち合わせしたのに、全然違う感じになっていたり、ここでこれ積み上げて欲しい、または積み上げなきゃいけなかったのかと思ったりしました。

ただ、トレセンや選抜チームの活動をしていると、この「リレーション」のありがたみを感じます。
とても1人じゃなさあー伝えきれないことや伝え漏れがあっても、きちんと役割分担していれば仲間がフォローしてくれる。
そういった意味では、ユースBで学んだことは今後に、いや進行形でかなり役に立っていると感じています。
4.最後は「質の追求」になる
ユースBのライセンスは、2年前までA級U15、A級U12という名前でライセンス講習会が行われていました。
要するに「育成年代に特化したライセンス」であるということ
ユースBは「サッカーの全体像を抑えつつ、より個人の部分にフォーカスした指導が必要」ということ
すなわち「質の追求」になるということ
ひと言に「質」といっても様々で、ボール扱いや体の動かし方など目に見える「実行」の部分、また目に見えない「判断」の部分、そして「認知」の部分と分けられます。
指導実践のなかで、個人のチャレンジとしてこういった部分にもアプローチしてみようと考えてやってみましたが、なかなか難しかったです。
全体的に見ながら、でも個人の部分にも目を向けてと…
よく虫の目、鳥の目、魚の目といいますが、まさにそんな感じです。

どれかひとつずつならいいのですが、瞬間的に切り替えていくのは、まだまだ訓練や練習が必要です…苦笑。
上記の「サッカーはシンプルだから難しい」に繋がりますが、シンプルが故に最後は個人の「質の問題(追求)」になっていくのだと感じました。
本当にユースB、面白かった!!ご興味がある方、是非、受講してみてください!!
ではまた!
