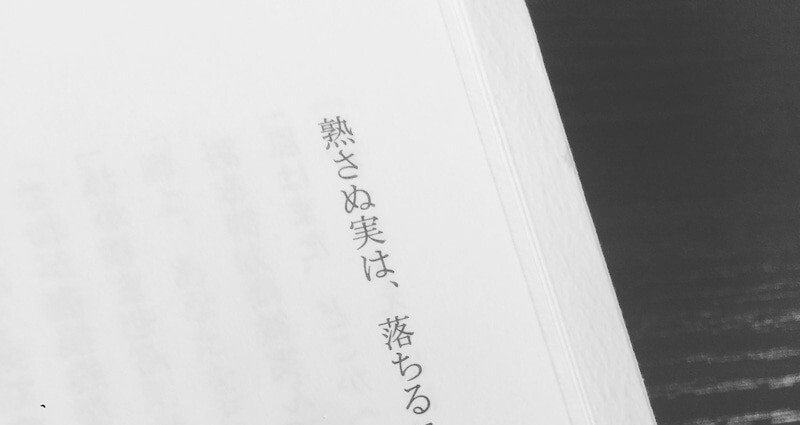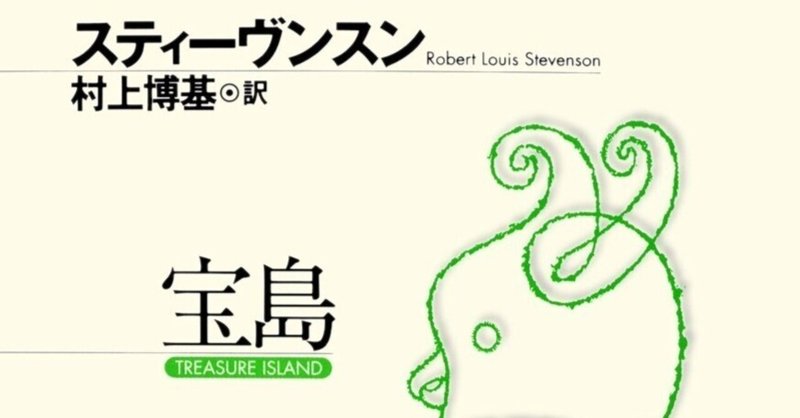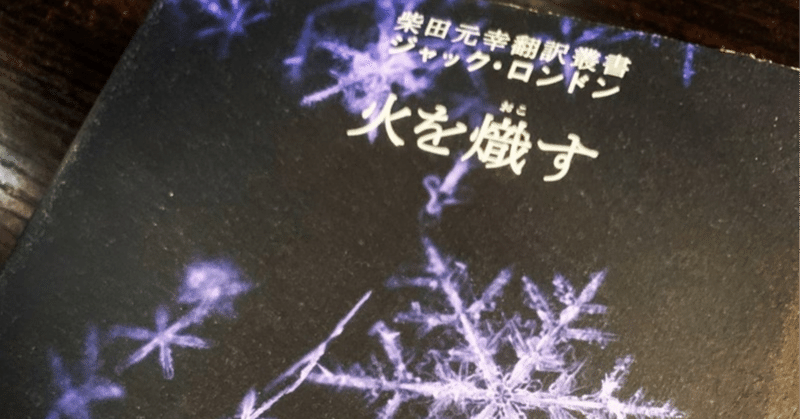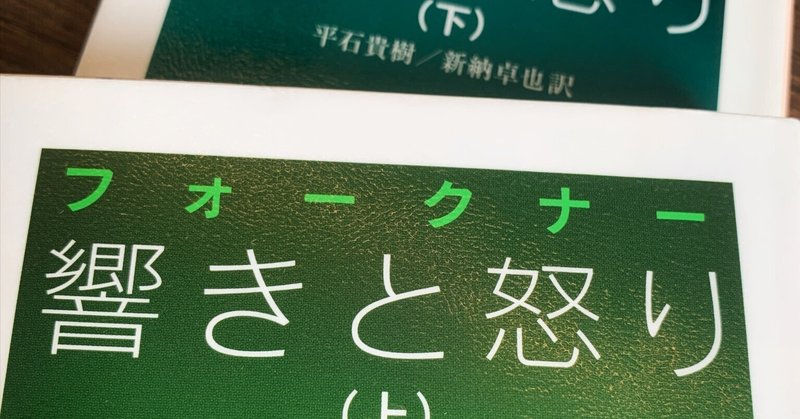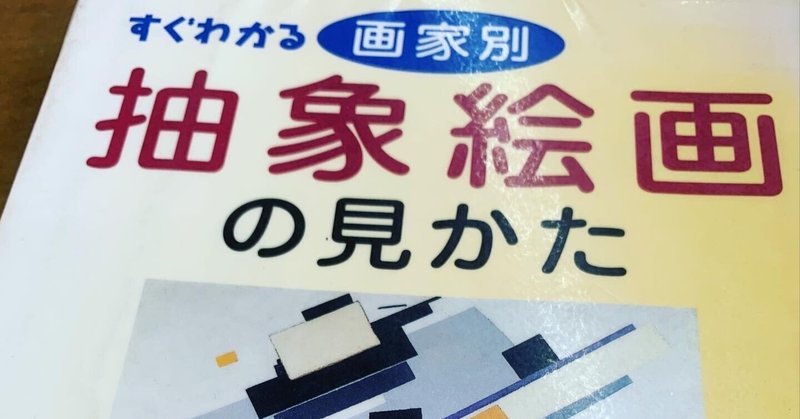#読書メモ
なんど読んでもわかった気にはならないだろうけれど〜ヴァージニア・ウルフ 『ダロウェイ夫人』
ヴァージニア・ウルフ。
このひともフォークナーも使った技法「意識の流れ」を使った作家。
しかし、その難解さ(というか、とっつきにくさというべきか)はフォークナーを凌駕する。
ヴァージニア・ウルフの著作のなかでは本作が一番読みやすい(読みやすいことの功罪は別にして)といわれているようだけれど
わたしにとっては正直なところ、ひたすらにしんどかった。
他の作品を読んでいないので、本作だけで言い
激しく身体感覚に訴える〜ジャック・ロンドン 『火を熾す』
ジャック・ロンドンというと『野生の呼び声』や『白い牙』あたりがよく知られ、読まれているのかな?
でも、短編にもすこぶる魅力的な作品は多い(短編のほうが筆力を発揮できているのではないかと思うほど)。
10年以上昔、スイッチ・パブリッシングから出た柴田元幸氏セレクションの『火を熾す - 柴田元幸 翻訳叢書 ジャック・ロンドン』は
一時期品薄で、プレミア価格までついて(けっこうな、そしてあこぎな)
四大長編に挑む前のウォーミングアップ、基礎体力作りに〜ドストエフスキー 『死の家の記録』
ドストエフスキーはじめ、ロシア文学は名前がどうしてもおぼえにくくて(しかも長かったりして)敬遠しがちなのだけれど、ナボコフきっかけで(とはいえ、彼は自分をロシア文学の作家とはみなしていない)また挑戦している。
好きなひとはいるし(原文で読むことも厭わないひとだって少なくない)シンプルに趣味、楽しみとして読むひともこれまた少なくないのだから、単純に自分の素養のなさ、相性なのかなとは思うのだけれど。
口述筆記のライブ感をギャンブルの疾走感とからめて〜ドストエフスキー 『賭博者』
最近はドストエフスキーをつづけて読んでいる。
ロシア文学は登場人物の名前がおぼえにくくて(長いし)苦手なんだけれども、本作品はそのへんをいくぶんか気遣ってくれているようで、、いや、気の所為だろう。
ギャンブル(ルーレット)という、ライブ感あふれ、疾走感と共ににつむがれるストーリー展開のおかげもあるけれど
冒頭(1/3くらいまでか)の読みにくさ(名前のおぼえにくさとは別に、そうしたものはある)
ひとは絶望とショックからしか学ばない〜ナボコフ 『絶望』
古典文学(厳密な「古典」以外も含まれるけれど)渉猟の旅はつづく。
今回はナボコフの『絶望』。
絶望という言葉は嫌いではない。
というか、好きだ。
なにごとも、すくなくとも新しい何かは絶望からしか生まれないと思っている。
広中平祐氏(数学のノーベル賞ともいわれる「フィールズ賞」受賞の)の名言である
のように。
ナボコフといえば「ロリコン」の語源になった『ロリータ』で知られる、ロシア出身
学校で学んだのはラテン語と、うそをつくことだけだった〜ヘッセ 『車輪の下で』
ヘルマン・ヘッセといえば『車輪の下』。
でもそれは世界的にみると特殊なことのようで、たとえばドイツ本国と比べると日本での同書の売上は10倍(1972年〜82年の10年間の比較)だとか。
読むとわかるけれど、本書には随所に教育制度や学校に対する(学校や教師だけにとどまらず、社会機構もふくめて)批判がみられる。
これはヘッセみずからの体験からくるものでもあり、それだけに痛切に説得力をもって訴えか