
『圭介』 〜1997年 顔が全然タイプじゃない男〜 vol.1 (ゲイ小説)
『モテ』は自信から生まれるのかもしれない。
ロンドンでうっかりミステリアス・アジアン・ビューティ枠(目が細いだけ)にすべりこんで、それなりにモテ人生を満喫していたら、日本に帰国後もそこそこモテるようになっていた。
10代のころは、あんなにパッとしなかったのに。
日本で『中田英寿』が流行っていたのも大きかった。
似てる、ともてはやされることもあった。
相手の部屋に行ったらサッカーのユニフォームが用意されていたこともあった。
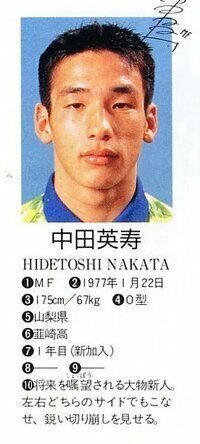
だけど、どんなにモテても、僕の体には10代のころに培われた『非モテ』の血が流れていた。
声をかけられると、どうしたって「本当に自分でいいんだろうか?がっかりされやしないだろうか?」と不安になってしまう。
だから、タイプでない人にも丁寧に対応した。
体を求められば軽々とご提供させていただいた。
そこにユニフォームが用意されていたなら嬉々として着用し「ボールは友達!」とキメ台詞を吐いたかと思えば「違うか!?」なんておどけてみたり、とにかく、サービスがちょっと過剰だった。
そんな僕でも「この人にはサービス不要」と思えるくらい見た目がタイプとは程遠い人に出会った。
真夏の夜の新宿二丁目で。
歳の頃なら30ちょっと。
ナマハゲみたいなギョロリとした目。
平らでやけに横っ広がりな小鼻と大きな鼻の穴。
唇は分厚く、喫煙者でもないのに歯は黄色く、こってりした顔なのに顎髭まで携えている。
なのに、前頭部は見事に禿げ上がっていて額が永遠みたいに広い。
隣の席になった瞬間から背を向けていたのに、その背中をノックされた。
「なに飲んでいるのかな?」
「レッドアイですけど…」
「そうか、あんまりお酒強くないんだね」
ビールをトマトジュースで割ったカクテルを飲む理由は、確かに僕がアルコールに弱いせいだった。
だけど、名も知らぬナマハゲにそんなことを言われ「そうか、あんまり髪の毛ないんだね」と言い返してやりたいくらいイラッとした。
だけど、言い返せなかった。
それどころか、こんな状況下でも「非モテ精神」が発動してしまい、しばらく和やかを気取った会話をした。
「名前、なんていうの?」
「マフミです」
「どういう字?」
カウンターに紙とペンがあったから、僕は『真文』と走り書きした。
「習字やってた?ボールペンなのに筆で書いた時みたい」
「うん」
「やっぱりね。ハネやトメがしっかりしている。俺はケイスケ」
聞いてもいないのに名を告げながら丁寧な字で『圭介』と書いた。
「俺は自分の字の汚さにうんざりして、大人になってからペン習字を始めたタイプ。ダサいでしょ?」
そう言って自虐的に笑った。
「真文君は自分の名前が好き?」
「うん」
「だよね。すごく似合ってる」
「圭介さんは?」
「うーん、響きは平凡だけど、漢字は割と気に入ってる。なんか、ほら、きっちりとしたジャケットかなんかに、ふわっとしたスカートを合わせている人みたいでオシャレでしょ?」
最初は何を言っているのか解らなかったけど、圭介がもう一度自分の名前を
圭
介
と縦書きにしたから解った。
「圭」が上半身、「介」がスカートを履いた下半身に、まあ、見えなくもない。
「変なの」
僕は思わず笑ってしまった。
「だけど、わかってくれるか?この感じ」
「うん、まあ、わかるはわかるけど」
「そっか、よかった、じゃあ、乾杯ね」
友達が、眉をしかめながら僕に視線を送る。
「なに変な男としゃべってんの?全然タイプじゃないでしょう、そんな男」
そういう目をしていた。
それは、確かに、そうだった。
そうだったけど、ひとまず、乾杯をした。
