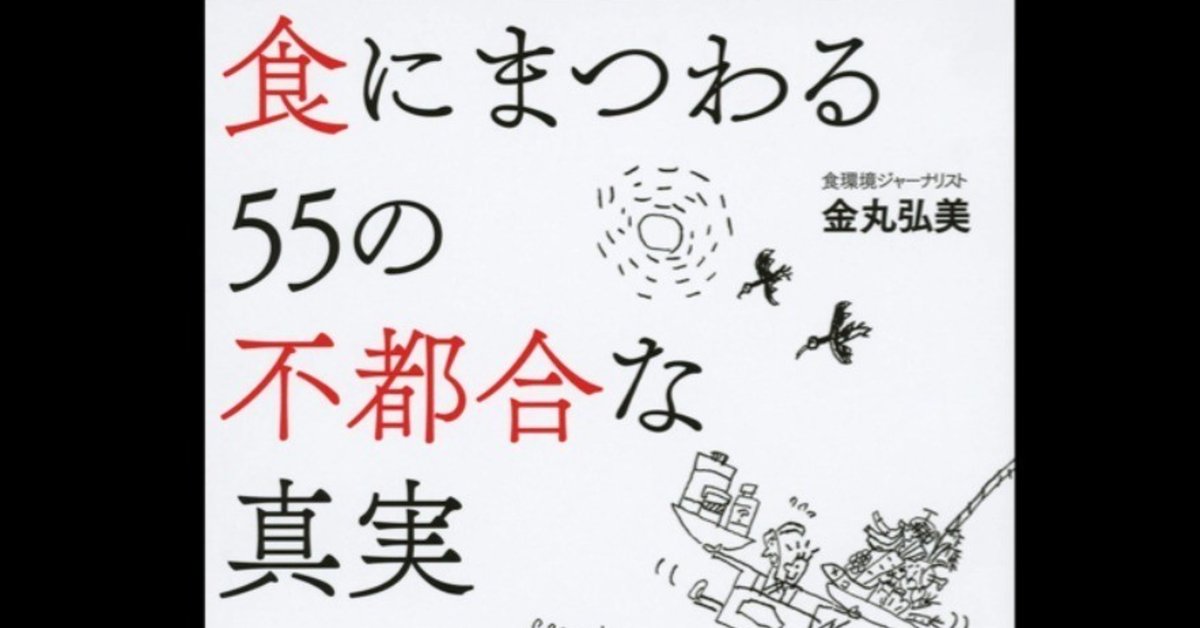
【書評】「不都合」ではすまされない 評者:小口達也

本当は怖い食の話
飽食の時代、ネット上にもメディアにも、グルメ情報が氾濫する。さながら“一億総美食家”時代の様相だ。飽食の果ての膨大な浪費。まだ食べられるのに捨てられてしまうもの(食品ロス)が年間646万tに上るそうだ。毎日10tトラック1770台分を捨てていることになる。世界で飢餓に苦しむ人々に向けた食糧援助量の2倍にも相当するのだと。
一方、日本国内の農地も、農業従事者も、年々減っている。1960年に606万戸あった農家が近年は215万5000戸までに激減、その担い手の老齢化も著しく、農業従事者の61%までが65歳以上だという。因みに、イギリスは7%、フランスは4%とか。日本の耕地面積は1経営あたり2.8㌶。アメリカ169.6㌶、イギリス92.3㌶、フランス58.7㌶、ドイツ58.6㌶と比ぶべくもない。日本の農地444万4000㌶では、全国民に必要なカロリーの38%しか生産できないというのである。
水産業も事情は似たりよったり。漁業者は2008年の11万5000人から年々減少し、2017年には7万9000人にまで減った。漁獲量も430万4000tで、ピーク時の3分の1にまで落ちている。
そんな実状を背景に、非常に心細い数字が本書に並んでくる。日本人がよく食べる牛肉の自給率は38%、ただし、豚・牛・鶏の飼料の自給率が27%なので、これを勘案すると実質的自給率は8%にまで下がってしまう。同様に、豚肉7%、鶏肉13%という具合だ。料理・食卓に不可欠な塩の自給率12%、小麦同じく12%、大豆7%、四面海なる海洋国であるはずのこの日本にあって、魚介類の自給率さえも56%と半分をやっと超えるに過ぎない。日本人の大好物エビまでもが86%は輸入品。さらには、これだけは「日本文化」と思しき日本そば、これも、そば自体はもちろん、具や汁などの原材料まで含めて3分の2までが実は“舶来食品”なのだと。
さて、省みて“グルメ全盛”、われわれ日本人の食生活は果たして豊なのであろうか、健全なのであろうか。世界情勢は今混沌としている。一寸先は闇である。天変地異の不安も常に付きまとう。人間が生物として生命をつなぐための根本である「食」、これをことごとく海外に依存している日本の現実。
そのうえ、小学生から大人まで肥満が問題視されるかと思えば、若い女性は痩せすぎが心配されている。食を取り巻く環境には、有害物質が氾濫している。遺伝子組み換え作物のような怪しげ、危なげなものも枚挙に暇がない。食物アレルギーを持つ子も100人に5人近くいるなど、環境や食が主因をなすと思われる、さまざまな問題が顕在化している。生活習慣病の蔓延も、今や深刻な社会問題である。糖尿病の予備軍は1000万人にも上っている。国民医療費も膨らむばかりだ。著者の指摘で、出てくる、出てくる、その数「55」の不都合。
嘆いてばかりじゃ始まらない
さりとて、著者の金丸弘美氏はアジテーター(扇動者)では決してない。いたずらに危機を喧伝し、扇情を意図しているわけではまったくないのだ。同時に、ペシミスト(悲観論者)とも程遠い。この人には希望がある、理想がある。目標がある。アイデアがある。情熱がある。行動がある。
長年、全国の農村、山村、漁村、地方都市をくまなく歩き、日本中行かないところはないくらいの人物である。行く先々で現場に溶け込み、地域の声に耳を傾け、あるときはジャーナリストとしてその声を読者に届け、あるときはアドバイザーとして、また、コーディネーターとして、サポーターとして、自らも関与し、提言し、実践し、協働し、数々の成果を上げてきた。衰退の一途をたどる農業だが、最近になってほんのわずかずつではあるが、外部の世界から農業を志して参入してくる人々が目に付くようになってきた状況を、著者は本書の中でもとても喜ぶ。
本書には、「不都合」だけではなく、「食」や「農」に対する著者の理念や所見も顔をのぞかせる。例えば、近年の―それは窮余の策ではあろうが―農業大型化、集約化といった方向に、必ずしも手放しで賛成はしていない。それよりも農業(1次産業)に、農産物の加工(2次産業)、さらには、例えば観光、教育、販売・営業、サービス(3次産業)などまったく次元の違うものを融合させ、相乗効果によって新たな価値を創出する、まさにフュージョン(fusion)の発想を重んじている。そして、付加価値の高いものを生産し、国際競争力もおのずと高めるというわけだ。そんな農業の「第6次産業化」なども著者はかねて推進してきたところである。
食の不都合は社会の不都合
「食」は生きることの根幹である。「食」の不都合、それはとりもなおさず、「生」の不都合だ。「生」の不都合を生み出すのは「社会」の不都合に他ならない。評者は「食」の現実を著者から知らされるに及び、「食」の不都合は「経済システム」の不都合であり、「社会」の不都合であるというところに思いが至るのである。
国土のあちこちが焦土と化した第二次大戦の敗戦から雄雄しくも立ち直り、世界が瞠目する高度経済成長を達成し、たちまち世界有数の経済大国に上り詰めたこの国、ただ、その驚異的な驀進のさなか、大事な何かを置き忘れてきた。そんな気がしてならない。
元来、「豊かさ」「幸福」、こんな形而上学的領域に入り込みそうなテーマのハンドリングを、経済学も最も苦手とした。それゆえ、価格が付き、変量として扱える価値のみをひたすら追求した帰結がこれだったのではないのか。21世紀、あの高度成長の夢も果て、低迷する日本、“宴のあと”に目指すべきものは一体、何なのか。それに応えられるような経済システム、社会的目標がいよいよ希求されなければならないときなのではないか。
「食」を軸とするテーマを著者が追い始めてからもう長い。常に前向きに、精力的に、フットワークを活かし、汗を流し、五感で感じ取り、一つ一つ堅実に回答をつかんでいく金丸弘美氏、そんな著者の姿と著書に接するたび、都会の暖房のきいた部屋の中で茫漠とした思いをめぐらせている、怠惰で横着な自分につい面映さを覚えてしまうのである。
評者:・小口達也【会員番号43】
(一社)東京23区研究所理事・研究員。アイノバ(株)取締役・チーフエディター。リサーチャー,エディター&ライターの、二刀流ならぬ“三刀流”、二束の草鞋ならぬ“三足の草鞋”生活を送る。都市問題研究のシンクタンク研究員、大学の客員研究員からフリー、出版社嘱託などを経て現職。東京23区からスタートし、全国いたるところの問題にチャレンジ。
