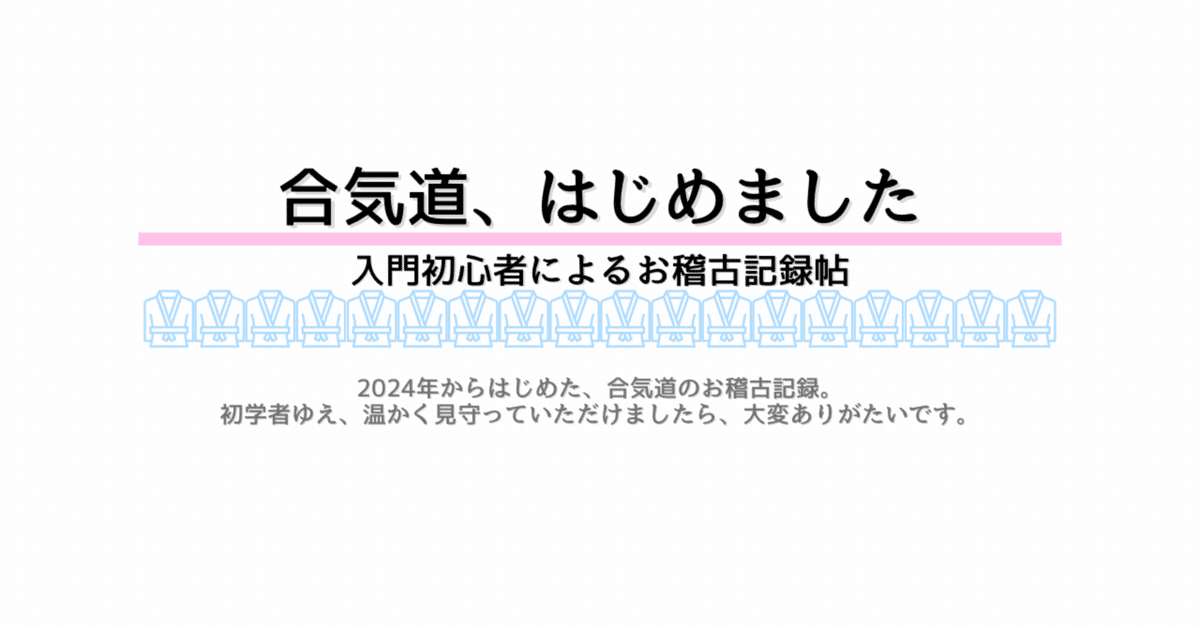
合気道 お稽古録 013、014
今回は2回分のお稽古を、まとめて記録しておこうと思う。
まず、013。
指導員のNさんにお世話になる。
昇段級の審査の日が近いため、審査内容を踏まえた稽古内容だった。
合気道は、試合はないが審査はある。
審査では、多田先生がおっしゃる名前の技を、型通りに行う。
わたしは、合気道のお稽古を始めて、ようやく半年ほど経ったくらいのレベルなので、技の名前を一聴して、その名の通りに体を動かすことが、難しい場合が多々ある。
今回、入門して初めての審査を受けるので、その課題をいくつかの技でクリアしておく必要がある。
審査日まで、数回お稽古があるので、技の名前と体の動きをピタッと一致させておくことと、多田先生がいつもおっしゃるように「のびのびと」技を行っていきたい。
<稽古内容>
準備体操
呼吸操練
取り舟
呼吸投げ 6種
後ろ両手取り 入り身投げ
後ろ両手取り 四方投げ 表裏
後ろ両手取り 小手返し
座技 一教 表裏
気の感応
座技呼吸法
===
つづいて、014のお稽古録。
この日の指導員はAさん、多田先生もお見えになられた。
013で教わったのとは別の呼吸投げを、多田先生からご指導いただく。
「腕を持たれる、のではないよ。
腕を持たせる、のだよ。」
多田先生は、よくこのような表現をされる。
これは、武道の基本中の基本である「後手に回らない」ということと併せて「先の先をいく」ということを、お伝えになっている。
ほかには、
「投げ技のときは、相手を投げようとしないこと。
相手と同化して、相手を放つような、やさしく導くような、そんなふうにして、技をやるんだよ。」
ということも、多田先生はよくおっしゃる。
技の名前に「投げ」と付いていると、人間はやっぱり「投げる技なんだな」と無意識に思うもの。
合気道の「投げ」と付く技で、わたしが今まで教わったものの中では、「投げる」という感じは薄いかもしれない。
柔道の背負い投げは、テレビなどで目にしたことのある方も多いと思うが、合気道の投げ技は、ああいった感じではない(今のところわたしが教わったものに限って、だけれど)。
投げる、ではなく、放つ、あるいは、導く。
勝ち負けがない合気道特有の感覚かもしれない。
対立しない。
比較したり、相対化しない。
同化する。
この辺りのキーワードは、今自分が生活している範囲で耳にするのは、合気道のお稽古のときだけ。
物心二元論のものの考え方が、定着しているせいかもしれない。
相反する価値観を日常生活に持てていることは、とても幸運なことなのかもしれない。
もう一点、今回のお稽古で改めて感じたことは、多田先生のお稽古の、何とも言えない祝福感。
この場でお稽古することを寿ぐような多田先生の佇まいは、周りに集う人たちを、ほんとうに心地よくしてくれる。
だからみんな、多田先生とお稽古したいし、多田先生に会いたくなるのかもしれない。
<稽古内容>
準備体操
呼吸操練
取り舟
受け身 前・後ろ
呼吸投げ 4種
気の感応
座技呼吸法
